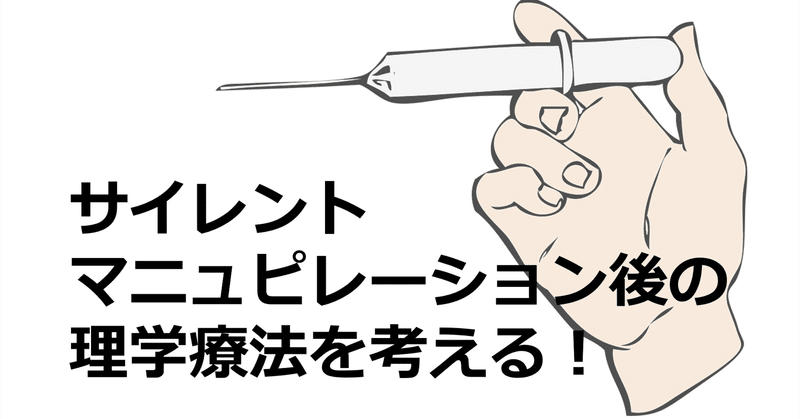
サイレントマニュピレーション後の理学療法を考える!
凍結肩は肩関節の疼痛(運動時痛・夜間痛)や運動制限を伴う疾患です。主に中高年(40~60歳)に多く発症し、男性よりも女性に多く見られます。肩関節可動域では屈曲・外旋・結帯動作が制限されることが多いです。

凍結肩の定義は”原因不明な一次性特発性拘縮肩で、肩関節屈曲100°以下、外旋10°以下、結帯動作L5以下”とされています。

しかし、凍結肩は可動域制限以外にも多彩な症状があり、原因も不明であるため、かの有名なCodmanも凍結肩を「difficult to define, difficult to treat and difficult to explain:定義するのも、治療するのも、説明するのも難しい」と表現しているほどです。

ですが、凍結肩を発症した大多数の患者は1~3年以内に機能的に回復することが示されており、自然治癒する疾患として考えられています。

一方で長期的には、症状や肩関節の可動域制限が見られることも珍しくないとも報告されています。発症後平均44ヵ月で50%に疼痛や可動域制限が残存していると報告もされています。
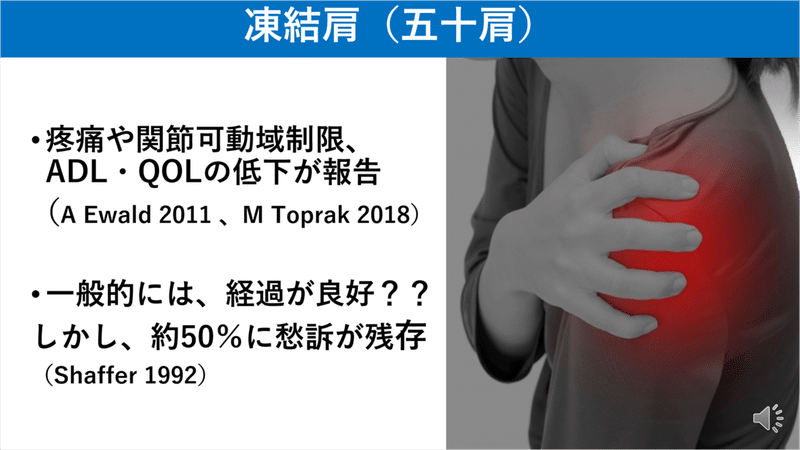
ここで少し、肩関節周囲炎の病期・病態を考えてみましょう!肩関節周囲炎の病期には三段階あります。病期から考えると、瘢痕組織が形成され、可動域制限が出現する「拘縮期」が凍結肩が生じる段階と考えられます。

病態としては、主に関与している細胞は線維芽細胞と筋線維芽細胞です。これらの細胞は、高密度のIII型コラーゲンを産生します。コラーゲンというと鍋に入れる「プルプル」のものをイメージするかもしれませんが、解剖学的には全く逆の組織になり、コラーゲンは「硬くて伸びない組織」です。

コラーゲンが関節包に過剰に生産されると関節内容積が減少したり、腱板疎部、上・下肩甲上腕靱帯、および烏口上腕靱帯の硬さも出現し、関節可動域制限に繋がります。

このコラーゲンの生産される量や炎症や疼痛の強度、不動期間などが人それぞれ異なるため、自然治癒する場合と症状が残存する場合があるのではないかと考えています。
一般的に凍結肩の介入は保存療法ですが、どうしても可動域制限や症状が残存する場合もあります。その場合、手術が行われる場合もありますが、最近では”サイレントマニュピレーション”が着目されています。

今回の記事では、最近着目されているサイレントマニュピレーションについて記載し、私の学会発表スライドも加えて記載していきたいと思います!
1.サイレントマニュピレーションとは(SMP)
ここから先は

週刊!リハマガ! ~整形リハビリの考え方~
マガジン名を変更し、内容もリニューアルしています!リニューアルした記事は値上げしますので、早めの登録がおすすめです! このマガジンでは運…
ありがとうございます(#^.^#)
