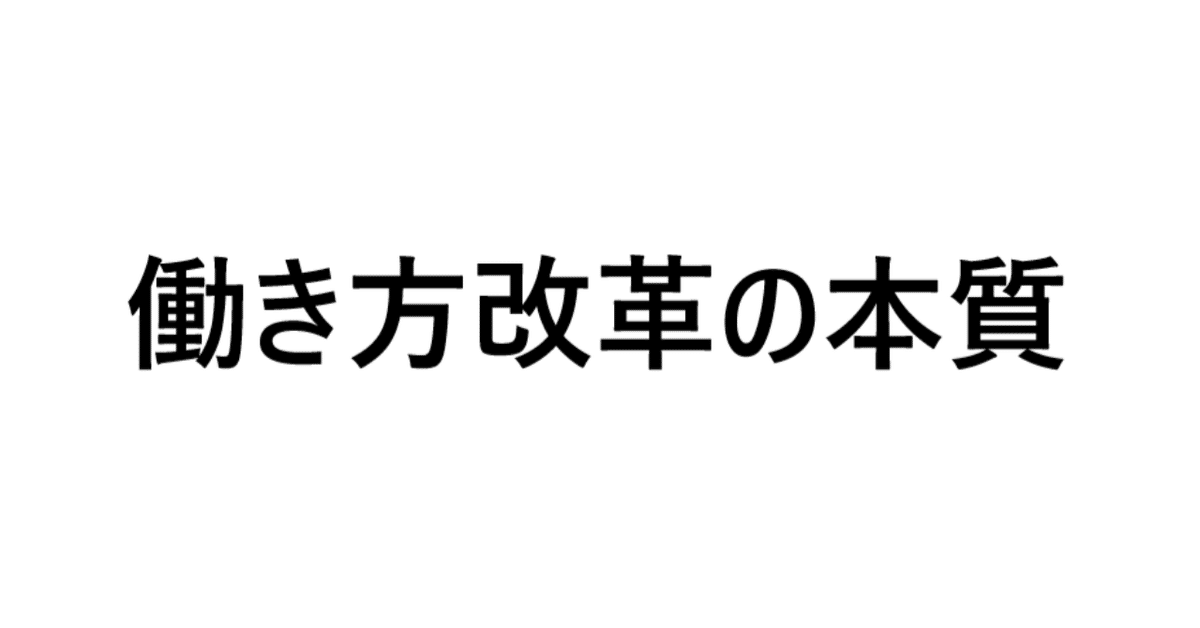
働き方改革は社長の度胸試しである
組織論を勉強していたら、改革らしい働き方改革をしている企業はごくわずかで、できていないのは結局は社長の度胸が足りないだけなんだろうなという結論に達したので、その結論に至った考察を書いていこうと思います。A4で11枚相当と長めなので、通勤電車の中で読むなら降りる駅を逃さないようにご注意ください。
【問題提起】マネジメント機能不全な職場
みなさんの職場では、従業員の負荷に偏りありますか。個々の能力の違いで業務時間に差がついてしまうのはある程度仕方ないことなのですが、課している業務量や責任が給料テーブルとまったく連動することなく偏っているというのは、たぶん大企業あるあるだろうなと思います。同一の給料テーブルの従業員の責任が等価になるよう管理するのは、使役する上での大前提のはずなのに、まったくできていない。いや、やろうとしていない。大変なのはわかるけども、やらなければいけない。
愚痴っぽくなってしまいますが私の場合、現職では裁量も責任も大きいのに時給制で、それならばマネジメントがしっかりしているべきなのですが、まったく機能していません。時給制であることは求人を見た時点から承知していましたが、想像をはるかに超える辻褄の合わない実態に驚愕しています。案の定、成績がいいけども超多忙で私より給料が低い20代の人が散見される。私は被害者じゃありませんが、ひどすぎて黙っていられないのでこんな長文を書き始めてしまいました。
転職から3か月くらい経ったころ「これは何かおかしいぞ」と思い、マネジメントや組織論についての本を読んで勉強し始めました。そのうちの1つ、本間浩輔氏の「残業の9割はいらない」が私の疑念にざっくりと刺さりました。本間氏はヤフーの役員さんで、人事制度改革に取り組んでいらっしゃいます。ヤフーの週休3日制の導入はネットニュースで話題になりましたね。本間氏は、多くの職場でマネジメントが仕組み・運用のどちらの面でも機能していないこと、そのマネジメントは成果主義を実現するものでなければいけないことの2点を強く述べています。
この記事は本書から学べたことを整理し考察していく読書感想文みたいなものではありますが、それなりにシンプルな終着点に達することができたので、ぜひ末端の会社員から部長や社長、役員まで読んでいただきたいです。
【原因1】マネージャーがやりがちなマネジメントの過ち
さて、マネジメント機能不全の根本原因を考えるには、まずマネジメントのあるべき姿を理解するところから。どんな会社でも業務というのは複数発生するものですので、それぞれの業務を従業員に割り振るにあたって、マネージャーが丁寧にひとつひとつの業務の性質を理解しなければいけません。その際に基準として便利なのが手順書を設けるべき業務かどうかです。
(a) 予め決められた手順に従って忠実に実行する
(b) 決まった手順はなく状況に応じて臨機応変に行動をとる
よりマネージャーの立場で言い換えれば、(a)業務を与えるべきものか、(b)責任と権限を与えるべきものかの違いです。
例えば生産工場のラインで一定作業を黙々と繰り返すような業務は(a)ですね。オフィスワークであっても、取引伝票を管理表に入力するというのもこれです。手順書にないことをしてはいけないし、手順どおりにできない状況になったら自分で処置せず上司に報告・相談するというのも徹底されています。このような業務はかっちりと確立した業務手順が存在するので、基本的には誰がやっても同じ時間で同じ成果が出るようにできています。
一方で(b)は、例えば新しい機能をもつ製品を目指す開発や、新しい顧客獲得のために商品をアピールしにいく営業、生産中の新しいトラブルに対処する品質管理なんかがそうです。「新しい」がキーワードであり、この類の業務は前例がほとんど存在しないのが常のため手順を作るようなパターンワークにできません。どのタイミングで何をどうするかなどは、業務を課された当人が自分の頭を使って決めたほうがよい。担当者の経験、知識、好奇心などによって選択する手段が変わるため、人によって同じ時間をかけても異なる成果が出る、あるいは同一の成果でもかかる時間が異なることが特徴です。
ここまで業務の特徴が整理されたら、マネジメントが気を付ければよいことが見えてきます。なお、ここで使うワードは本間氏の本の引用ではなく私の造語です。
(a)の場合「管理型業務」
✔手順のないことをやらせてはいけない。
✔業務にあてる時間を管理すればよい。
(b)の場合「委任型業務」
✔スコープを明確にして伝えなければいけない。(スコープとは、品質・予算・納期の3点セットの意味)
✔具体的な手段や時間配分は委任し、過度に干渉してはいけない。
✔成果を評価しなければいけない。
(a)管理型業務の場合は特定の人だけが忙しくなることはなく、チームや部門といった組織全体で残業が発生するはず。残業が一部の人に偏るという場合は管理が行き届かない(b)委任型業務で発生します。残業が偏る職場の管理職たちは、何を間違えてしまっているのでしょうか。ひとつずつの注意点を見ていきましょう。
✔スコープを明確にして伝えなければいけない。
何か業務を部下に依頼するとき、そのスコープが不明瞭になっていませんか。どんな完成イメージを期待しているのか、どれだけリソースを費やしてよいのか、いつまでにできればよいのか。この品質・予算・納期の3点セットとそれらの優先順位が疎かになっている依頼は、イメージと違う成果物が出てきてやり直しになる、想定以上のリソースが使われて他の業務に支障が出てしまう、期日に遅れて水の泡になる、などの問題を引き連れてきやすいものです。
例えばミーティングを開くということひとつをとっても、その目的を招待者に伝えていないケースは多い。そのようなミーティングのあとは「結局結論が出なかった」「自分が出席しなくても進んだことだった」などとがっかりするものです。どんな結論を目指しているのか、どのようにそこへたどり着きたいかが予め整理されていれば、招くべき人員に過不足がなくなり、意見が堂々巡りするようなことが減ります。そもそも会議ってだいたい費用対効果悪いですよね。
✔具体的な手段や時間配分は委任し、過度に干渉してはいけない。
思いついたことをすぐその場で口頭で従業員に投げるということが常態化しているのはよくありません。その人は元々課されていた業務について自分なりに計画して進めているし、それを推奨されている。よほどの緊急性がない限り委任型業務の人の時間を奪うような場合は、それが自分の部下であっても事前にアポイントをとっておかなければいけません。集中してデスクに向かっている人に「ちょっといい?」と声をかけるのはよく見る光景ですが、アウトです。手段と時間については管理を委任しているのですから。
同じ観点でもうひとつ指摘しておくと、組織の中で2階層以上離れた人の間で直接業務のやりとりがあってもいけません。2人の間にいる中間管理職は自分の部下の業務采配を委任されているので、それを無断で崩されるようなことがあってはいけないからです。部長にとって「おれの部署なんだからおれの自由にしていい」のはそのとおりですが、相手は人間です。「計画が狂う」と言われないために作法は守りましょう。これもマネジメントの基本中の基本なのですが。
✔成果を評価しなければいけない。
委任型業務は成果(=アウトカム)でしか正確に働きぶりを評価できないのに、投入した時間(=インプット)に対し報酬が出るという仕組みがあるのはおかしなことです。すでに述べたとおり人によって時間当たりの成果物の価値が変わるので、委任型業務に対して勤務時間を評価すると、能力の低い人が残業をして多く給料をもらい能力の高い人は定時に帰って少ない給料をもらうという、不公平な状況が出来上がります。
しかしこの矛盾についてはマネージャーばかり責められない部分があります。それはマネージャーより上位に存在する社長や本社が作った仕組みが矛盾を押し付けているからです。多くの大企業では、業務の性質ではなく年齢や勤続年数に従った階級で給料システムを切り分けています。そのため、「委任型だけど時給制」という矛盾した組合せが発生するのです。

この構造の結果様々なところで制度と実情がミスマッチし、毎日残業まみれの人と定時までこっそり暇をつぶす人が混在する不平等な職場が出来上がります。その他具体的な事例を列挙してみますので、みなさんの職場で思い当るところがないか気にしてみてください。
■委任型業務の部下をもつ人たちのおかしな挙動
✔優秀と認める若い人に大きな成果を期待した。でも組合員なので権限をこれ以上広げられない(=委任しきれない)
✔自分が外出する日、部下の勤務時間を把握するために出退勤のタイミングで社用電話で連絡させる(=インプットを評価しようとする)
✔部下の報告は口頭で聞けば十分。報告書は読まないから書かせない(=アウトプットの証明を求めない)
■従業員たちのモラルハザード
✔出勤さえしていれば勤務時間は申告どおりになるので休憩を多めにとる
✔業務は効率化せず、むしろ複雑化したほうが得である
✔業務時間が稼げるのでどんな会議でも出席する。そこで発言は必要ない
✔業務が少なくても、ゆっくり進めて毎日少しだけ残業し、忙しいふりをする
✔業務の優先づけは、重要かどうかではなく簡単かどうかだ
✔成果は評価されないし、誰にも読まれないので、報告書を作らなくなる
✔年度の途中で年間目標を達成したが、出勤しないと給料が出ないのでただ毎日暇をつぶしている
✔成果を上げても給料は増えないし成果を出さなくても減給されない。だったらクビにならない最低ラインを目指そう
いや、私がこうしているわけではありませんよ。むしろ成果は形に残したい人なので報告書は他の誰よりも詳しく書いています。残念ながらほとんど読まれないけど。
【原因2】会社が犯しているマネジメントの過ち
さきほどの「アウトプットを評価」に関わってくるのですが、マネジメント不全の原因をもう少し掘り下げてみます。この委任型業務に時給制という仕組み自体は何十年も昔からのものですから、こういったミスマッチやモラルハザードは以前からある程度は起きていたはずです。しかしこれだけ話題になっているのはここ最近の15年ほど。何か時代とともに急激に変化した事象があるはずです。いくつか可能性を挙げることができ実態はそれらが複雑に絡み合っていることでしょうが、私が思うに確実に一因として効いたのではと思うところがあります。それは製造業の海外展開です。
今となっては日本の貿易収支はほぼトントンですが、私が20年以上前の小・中学のときに授業で学んだのは、日本は製造業で貿易黒字を達成している国だということ。エネルギーやモノの資源を輸入し、製品に加工して輸出するというやつです。経済成長は郊外の工業団地で働く人たちによって支えられてきました。しかしここ近年で、いや私がこの社会の授業を受けているころにはすでに様子が変わり始めていたはずですが、企業は中国、インド、ベトナムなどアジアに子会社を作り、そこへ工場を移してきました。もちろんコスト抑制のためであり、人件費、輸送費、関税を小さくすることができます。この引っ越しによって生産については効率化を達成することができましたが、日本ではすっかり製造・加工することがなくなってしまいました。一方で技術面の差別化を強いられるグローバルな競争激化によって営業や開発のほうが大事になり、日本法人はそちらにリソースを割いています。グループ会社としては製造業でも、その中の日本法人だけを見るとほぼ頭脳ワーク中心の会社なのです。
さて、ここで既出の2種類の業務タイプを思い出してください。忘れてしまった方は読み返してください。昔に比べて今、どの業務タイプが増え、または減ったでしょうか。そうです、管理型業務が減って、委任型業務が増えたのですね。それにもかかわらず、会社の仕組みを何も変えてこなかった。

その何十年も変えてこなかった仕組みというのは、もちろん明文化されていない社内文化にも根付いてしまっているのですが、ちゃんと文書として定められているものがあります。就業規則です。
従業員が10名以上いる企業は就業規則というものを作って運用することが労働基準法第89条で決まっています。法文は大事な順に書かれているので、作られる就業規則は大原則である第1条の理念に従っていなければいけない。労働時間を定めた第32条や残業を可能にする第36条は有名ですが、最も大事な第1条は意外と知られていないので引用しておきます。
労働基準法 第1条
労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
要は人権の尊重であり、この理念は使役者を戒めるもの。よって就業規則には不当な従業員の扱いをしないために必要なルールを書くことになります。しかし残念なことに、はるか昔に作られた就業規則は従業員の行動について規範を設けそこから逸脱する者が現れないようにする、まるで聖書や軍規のような文書に仕上がっていることがほとんどです。例えば勤務時間は9-18時であるとか、帰属意識を持つべしだとか。規範のとおりに従業員が動いてくれれば、会社は労働基準法に違反することがないという目論見であり、「会社は正しく従業員を扱える」という暗黙の前提の上に成り立っています。おや、何かおかしいですね。使役者を戒めるはずの法律が、使役者に労働者を取り締まらせる構図になっている。もしや世の中の就業規則って間違いだらけなのでは。
規範設計にもとづく組織については別の投稿で詳しく述べますが、これは性悪説に基づいて作られたもので「ルールにないことはやってはいけない」ということです。かつて産業を支えていた主役である生産ラインの従業員たちをマネジメントする上で、再現性、効率、安全確保などの観点では規範から逸脱されないようにする方法は有効に機能します。
反面、ルールにないことを認めるのはすべて例外扱いです。業務タイプがすっかり様変わりした現在では完全にミスマッチになってしまいました。委任型業務の従業員たちは、この例外扱いのために申請と承認というプロセスを駆使しなければまともに仕事ができないということが起きます。例を挙げればたくさん出てきます。
■いちいち申請や申告が必要
✔上司は必要性を認識しているのに、出張前に申請が必要だ
✔上司は必要性を認識しているのに、ものの購入に申請が必要だ
✔通勤ラッシュを避けたいだけなのに、定時以外に出社しようとするといちいち申告が必要だ
✔出張の成果を仕事に応用しているのが明らかなのに、出張報告書を提出させる
✔複数の人で利用したので不正しようがないのに、経費精算の承認プロセスがやたら長い
■リモートワークが許されない
✔在宅勤務は、育児や介護が理由でないとできない
✔集中したいから静かなワーキングスペースで仕事したいのに出社しなければいけない
✔出張中はみなし8時間勤務なので、ホテルで夜仕事をしても損
■例外の扱い方が実情に即していない
✔出張で移動含め12時間かかり帰宅したが、みなし8時間勤務だ。(裁判所判例では移動を勤務とみなさないが、近年のコンプライアンス常識に照らし合わせてどうか)
✔介護や育児は毎日のことなのに、週に数日しか在宅勤務が許されない
■新しいテクノロジーを勝手に使うことが許されず不便を強いられる
✔PCやそのOSが選べない。支給されたラップトップは大きくて重い
✔社内の非同期連絡手段がEメールしかない
✔社用スマホはセキュリティがかかりすぎていてロック解除すら面倒臭い
✔スケジュールを3か所に入力している。社内にシェアするためにイントラ、自分で使いやすくするためにOutlook, 外出がある場合は個人スマホ。どれも同期されない。させてくれない
■無駄を強いられる
✔すでに学校や前職で学んだ内容なのに、会社が認めた研修を受けないと習得したことにならない(逆に研修を受けると、理解していなくても習得したことになる)
✔やろうと思えば誰でも情報漏えいできるくらいセキュリティ管理はザルなのに、インターネットのアクセス制限だけは厳しくて自社のウェブサイトすら開けない
✔業務がなければ待機を命じられる
おっと、いくらすべてが私の実体験ではないといえ日頃のストレスがやや溢れてしまった感。でも一部は少し補足してでも主張したい。
まず何事も承認ばかりなのは勝手に会社の金で遊ばれないためなのでしょう。近年は聞かなくなりましたが「カラ出張」なんてワードがあって、出張と見せかけたただの慰安旅行が起きてしまったことがある組織では神経質になるのもわからないでもない。しかし成果主義さえ根付いてしまえば予算管理すら委ねることができ、余裕ぶっこいて遊んでくることまで含めて評価することができます。これも時代が可能にしてくれたものですが、明らかな不正をすればすぐクビになるくらいには近年はスマホ普及や内部告発システム充実のおかげで相互監視社会が成立しているので、不正が発生する確率は低いので上が下を一方的に監視する方法はもう古い。
Eメールも本当に時代遅れだと思います。誤爆は頻発するし、一方的に送りつけられるし、やたらファイル添付してトラフィックが増えるし、なりすましができて偽口座を使った詐欺が横行しています。今の大学生以下くらいだとLINE, Twitter, Instagramしか使ったことないなんてことが珍しくない時代。そんな若い人向けにEメールの書き方講座みたいな教室が存在するそうで、不便なものを学ばせるなんてなんとお粗末な。せめてSlackかGaroonのようなビジネス向けメッセンジャーはすべての組織に導入してほしいものですが、その存在すら知られてないのはどうしてなのでしょうね。そうそう、今の10-20代はキーボードよりフリックで入力するほうが早いので、文字を打つことが多い業務ならばスマホでやらせたほうが効率いいですよ。
ここまで、マネジメントが機能していない原因が古い就業規則という仕組みにあるということを述べました。「昭和の体質」「古い仕組み」といった抽象的なワードを使った企業批判が飛び交い始めて久しいですが、どういうところが古いのか、なぜ今の時代に合わないのかという詳しい分析や考察はあまり見かけないので書いてみました。
【解決】働き方改革は社長の度胸試しである
サブヘッドに書いた通り、ここからは特に悩める社長たちに読んでほしいところです。委任型業務の人に管理型業務を前提としたルールを適用している矛盾が問題だと理解できたところで、解決策の話に移りましょう。早速2つを書きます。
(a) 委任型を維持して、インプットではなくアウトカムを評価する
(b) インプット評価を維持して、委任型を管理・把握型に転換する
そう、どちらかに統一しろということです。文にすると簡単そうですが、どちらもやるとなるとそれなりに大変です。いずれにしてもマネージャーたちに求められる課題がありますが、本来やって当然のことですので、やらせましょう。ひとつずつ説明します。
(a) 委任型を維持して、インプットではなくアウトカムを評価する
業務タイプを委任型に維持したまま、インプットである業務時間ではなくアウトカムである成果物を評価してそれにもとづく報酬を出す仕組みに変更する方法。評価と報酬のシステムを、組合員と管理職のようなランクで切り分けるのではなく、マネジメント手法の違いで切り分けるのです。既出の表でいうと、組合員の中に時給制と年俸制の2パターンを用意して列を増やすということ。もっとベタな言い方をしてしまえば、裁量労働制を導入せよということ。「委任」は「裁量を与えること」ですから、何もおかしいことではない。

この場合、マネージャーたちは今まで意識してこなかった「成果を評価する」ことが課題となります。どの企業でも考課のために従業員と一緒に年間の目標を作っていることでしょう。委任型業務の場合に大事なのは、ここに書くべきことはまさに目標であって手段ではありません。何回顧客を訪問するかとか、何件開発試験をまわすみたいな手段や時間に干渉してはいけないので、それは書かない。どれだけビジネスをとってくるか、どこまで製品の機能を引き上げるかなど各々の役割の終着点だけでいいのです。もちろん裁量労働であっても勤務時間が違法なことにならないようにケアすることは欠かせませんので、給料に関係がないからといって記録しないことがないように。
企業側は、社員の「アウトカム(成果)」で評価すると言いつつ、実際には時間などの「インプット」で評価する傾向が強いのです
本間浩輔「残業の9割はいらない」
究極的には、管理職だとか本社だとかは従業員の評価さえ適切にできれば他の管理機能を一切持たなくてもいいということでもある。もちろんその評価の公平さや正確さを確保するのは難しいのですが、やろうとしないのは怠慢。
勤務条件や給料体系という仕組みを変更することになるので、会社の根幹に関する書類を大幅に書き換える必要があります。まさに「社長が決めること」「社長の理念をアップデートする」ことです。
(2) インプット評価を維持して、委任型を管理型に転換する
もう一方の解決案(2)ですが、これは(1)の逆です。インプットである勤務時間で人を評価し報酬を払うことは変えませんが、その代わり業務タイプを管理型に変更します。もともと古くから運用されている就業規則は管理型業務を管理するために最適化されています。従業員をこれまでと同じ仕組み上で、ただし正確に使役するのです。

(1)の場合はマネージャーに加えて社長が大仕事を抱えることになりますが、この(2)の場合ではマネージャーにだけ負荷がかかってきます。社長としては責任を中間管理職にぶん投げることができるのでこちらの選択をするほうが気楽ですが、根底になっている思想は変えないのでやはりこれも働き方「改革」とはいえません。むしろ間違いなく効率悪化で利益率は落ちるでしょう。
そもそもなぜ営業や開発が委任型業務になっていたかと振り返ってみれば、ひとつひとつの業務の性質と量が異なるためいちいちマネジメントしきれないという事情があるからでした。それをしろというのですから、マネージャーにかかる負荷は相当なものになります。
具体的に何をすればいいか考えるために、管理型業務で大事なポイントである「手順のないことをやらせてはいけない」を意識します。ということで、まずは今まで担当者に委任してきた手段と時間に裁量を与える方法をやめて、業務は徹底的にマニュアル化し、その業務に標準作業時間を設定します。これらができれば管理型業務への転換ができます。
たとえば、ある新規顧客候補を訪問して自社サービスを取り入れてもらうチャンスがないかをヒアリングしてくる営業の仕事があったとします。まずは業務を標準時間を定めやすい単位になるまで分解します。この営業の場合はプレゼン資料作成、ヒアリング項目作成、移動、打ち合わせ時間、報告書作成、経費精算といったところでしょうか。そして次にプレゼン資料やヒアリング項目を作るという業務のマニュアル化です。過不足ない情報を入力しやすく、見返した時にも読みやすいテンプレートをかっちり作って、その際必要な自社情報はいつでもどこでも取り出しやすいようにクラウドストレージ上で整理整頓しておき、完成させるのに要する時間が人によってぶれることがないようにします。そしてこの資料作成という単一業務の標準時間を定めましょう。移動や打合せは時間を調べるだけですね。報告書もテンプレートを作って、やはり完成から配信までに要する標準時間を定めます。経費精算の申請も意外と時間をとられるものですので標準時間を定めましょう。これで予想される所要時間の合計が算出できて、今回営業の業務をやってくれる従業員にかかる負荷が数値になって可視化されます。各社員の判断で勝手に追加業務が発生することを許すならば、それがマネージャーに必ず通知される仕組みも必要です。これらの負荷が部下たちの中で偏ることがないよう采配していくのがマネージャーの仕事です。一例を紹介するこの段落だけでもやたら長くなったのは、それだけこのマネジメント方法におけるマネージャーの仕事が多いということです。
私は年俸制の前職から時給制の現職に転職するときに、このような管理型業務になるものだと思ってきたので、実態が前職以上に委任度の高い業務である現実に驚いています。前職では時給制の従業員に過剰な負荷がかからないようにするために丁寧な業務采配がなされていたのを見てきたし、私もそういう采配を意識したことがあるし、必要なことを当然のようにしているだけに見えたからです。この管理があれば、業務が溢れそうかどうかが常に可視化できるので、その都度無駄な業務が発生していないか見直すとか、どうしても必要な業務が多いのだとしたら人員配置を見直すとか上層部へ人員増強を願い出るための根拠として使うことができます。というか、マネージャーってこれが仕事ですよね。
プレイヤーとして経験の長い人がその中でリーダーシップを発揮したり顧問役になったりしてランクが上がっていくのはいいのですが、リーダーシップとマネジメントはまったく別物です。ついでにいうと大方針を決定する役割をもつディレクターも別物です。マネジメントを経験していない人が何の訓練もなしに突然こういうことをできるようにはなりません。営業や開発に成績優秀なスーパーマンがいたとして、その人がマネージャーとして適任かは別問題。できるようになるというのは、能力だけではなく可処分時間の問題もあります。こういったマネジメントはとても大変なので、プレイヤーとしての実務をもつ人が兼任するのはかなり難易度が高いことでもあります。純粋なマネージャーというのはヒト、モノ、カネの、中でも特にヒトのリソース采配に専念する人であって、営業戦略を考えたり、実験データを見て開発担当に助言したり、顧客訪問の出張に出かけるようなことを、自ら積極的にしないものです。管理職はいっぱいいるのに管理できる人が1人もいない組織は、そりゃコストが肥大化して潰れるわけですよ。
プレイヤーとマネージャーは役割分担であって、マネージャーがプレイヤーの上位互換である必要はまったくない。チームスポーツを見ればわかるでしょう。選手は必ずしも監督として相応しくはないし、逆も然りです。マネージャーの給料が高いのは能力が高いからではなく、できる人材が希少だから。「上司を使う」というフレーズを聞いたことがあるかもしれませんが、それは正確には「マネージャーにマネジメントを依頼する」ということです。
ここまで(2)の方法について長々とマネージャーのやるべきことばかりを書いてきましたが、それまで委任型で業務をさせてもらっていた末端プレイヤーたちも働き方の変更を強いられます。管理型では手順にないことを勝手にしてはいけなくなるので、特に研究開発に従事している人にとっては不便なこととなります。こういう仕事には想定外や失敗がつきものです。実験している最中に「条件を変更したほうがよさそうだ」「予想以上に手間取った」ということが頻発します。しかし管理型業務では予め決めたことしかできず、かつ予め想定された時間から大きく超過してやってはいけないので、思いついたことをその場ですぐ試すということができません。まずは「こういう理由でうまくいかなかった」という報告書と「こうすると改善するはずだ」という次の計画書や企画書を書いて提出する必要があります。こんなペースでは技術競争に負けるでしょう。しかし怠れば、ブラックな職場が作られていきます。
この(2)の業務タイプの変更とそれにともなう現場の変化はあまり理想的な姿とはいえないのがわかってきたでしょう。そうするとやはり(1)のようにアウトプットを評価する仕組みの導入が望ましく、重い腰を上げるのは社長か社員か、すなわち改革か転職かという極端でありながら妥当な終着点になるのです。
社長にとっては、これまで「従業員は放っておくとサボるものである」という疑いや恐怖の前提に立った性悪説に基づくルール作りで管理型業務を統率する方法をとってきたので、信頼の前提に立った委任型業務に任せる「従業員に任せておいたほうがいい成果が出る」という性善説に切り替えるのは怖いはず。しかし性悪説ルールを敷いている現時点のデメリットに気づきましょう。性悪説では会社と従業員の間には疑う側と疑われる側という敵対関係が成り立ちます。そうすると互いを警戒しあうのでそのケアに双方にコストがかかってきます。会社側は深い階層でできた一方通行の監視システムである巨大な組織図で成る布陣で構え、従業員側は肥大化して金だけかかる労働組合という布陣で構えるという冷戦が起きています。性善説であればこんなものはきれいさっぱり必要なくなります。
恐れは恐れを生むし、信頼は信頼を育てるという最も基本的な心理に行き着くというわけだ。
フレデリック・ラルー「ティール組織」
まとめに入りましょう。
働き方改革というのは会社が従業員とどんな信頼関係を目指すかという思想から考え直すものです。ペーパーレス推進とか育児世帯の優遇というのはただの小手先の改善活動であって、そんなものを改革だと言ってはいけません。信頼関係や性善説なんて夢物語だと思った人、成功事例は調べればたくさん出てきます。もはや社長の度胸が試されているだけです。大きい会社であるほど、従業員の業務は多岐にわたります。それなのにすべてをたったひとつのルールの上で運用するなんてことは、合理的なはずがありません。自社の中で、その部門にどのルールを適用するべきか、よく考えて使い分けてください。
もたもたしていると、「良心に基づいて仕事しているのに、いつも監視され疑われている」ことを不満に感じる従業員の中から、度胸のある順に逃げていきます。そして規範に順応することしかできず、前例のないことが一切できない人たちだけが残っていき、ますますルールを変えられなくなるでしょう。
さて、末端従業員の私はどうしようかな。
■本マガジンの今後の投稿予定
2. 会社は司祭のいない宗教団体だった
3. 個人は企業より強いという新しい常識
*一部誤植と体裁を修正 2019年1月22日
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
