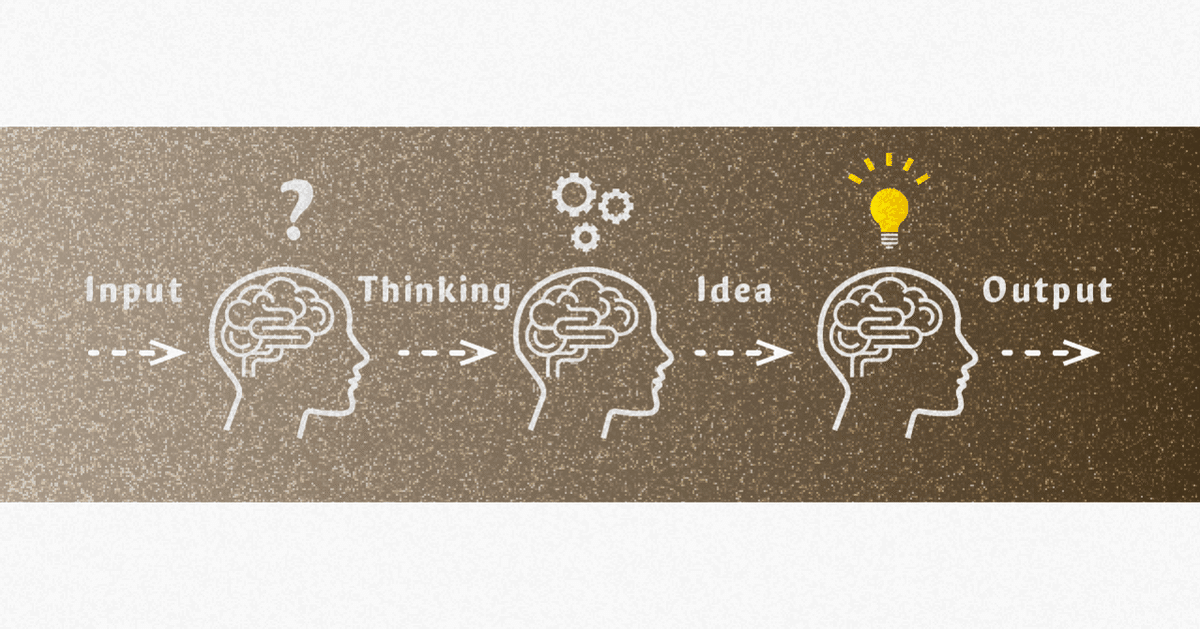
本の棚 #7 『空気を読む脳』
『空気を読む脳』
中野信子
脳科学とはすごいものだ。
人(動物)がどう考えどう行動するか
それらを分析して
再現可能なものにする。
脳みそがどう反応するかは
本能的なレベルにあるから
抗えない。
抗うつもりもないが。
科学の力を誰かにとって
都合よく利用することは
果たして幸せなんだろうか。
科学することで
社会は
発展して
人は便利に、豊かになっている…
ように見える。
持続可能かどうかは
だれにもわからない。
−−−−−−−−−−−−−−
自分の選んだ答えを正解にする力が重要
これまでの教育の賜物だろうか
どこかに唯一無二の正解○が
あると考えている。
知ってるんでしょ?
教えてよ、先生、先輩。
えっ?答えがないの?
じゃあ…どうすればいいの?
こんなやりとりを仕事の中で
日々繰り広げている。
実際は答えなんてない。
答えだったようなものも
時代の流れによって
よく変わる。
そのあたりを理解して
問題の本質をつかみ
そのときの最適解をもって
成果を出し、正解にする。
解の方程式は…もうない。
歯車である部分と個人である部分をうまく折り合いをつけながら、それを抱えて生きていくのが人生だ、と割り切る方法
もう歯車であることは放棄してら自分は自分というシステムとしてやっていくんだという挑戦的な戦略を取る方法
ただいま上のパターンで
生きている。
歯車であることを自覚し
組織に貢献する。
それは全く悪いことではない
と思っている。
でもどこかで飽きるとも思う。
それが1年後か5年後か
はたまた10年後かもしれない。
その人の努力や工夫に焦点を当てて褒めていこう
模範解答のようなものに○を
つけるのはつまらない
努力や工夫に焦点を当てるとは
つまり
その人が物事に向き合う姿勢を
よくみることだ。
覚えることではなく
よく考えて自分なりに
アウトプットする。
模範解答と違ってもいい。
その答えが100%間違いだ
なんて、私は言えない。
脳の進化の歴史をたどれば、人間は合理的に考えることのできる知性を発達させることで繁栄もしてきましたが、その合理性を適度に抑えることでーつまり、適度に鈍感であり、忘れっぽく、愚かであり続けることによってー集団として協調行動をとることが可能になりました。
適度に鈍感…のくだりが
みそである。
この「弱み」とも考えられる
人の特性が
削られずに残っていることが
これが不可欠であることを
証明している。
細やかな気遣いができて
一度覚えたら忘れない
同じ過ちを繰り返さない
それはそれは苦しいだろう。
人の不完全さこそが尊さだ
そんなニュアンスのことばを
煉獄さんも言ってた気がする。
サポート頂いた分は全て書籍代として本屋さんに還元します!
