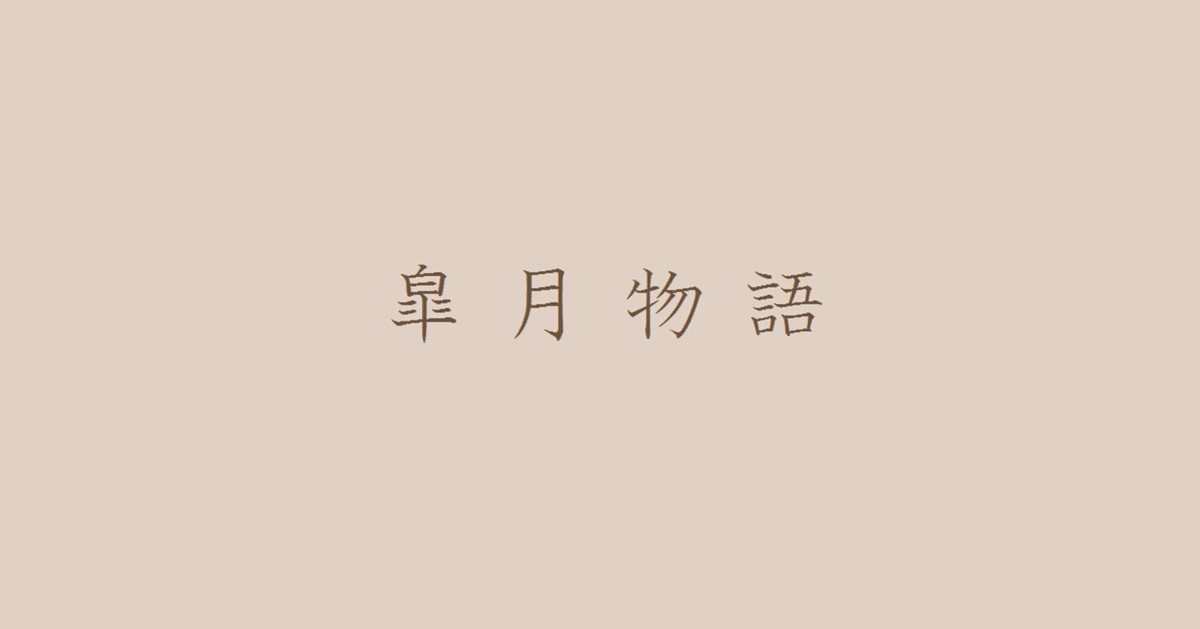
『羅生門』と『雪国』 (皐月物語 53)
6年4組では前回の社会の授業で幕末の単元が終わったので、今日はそのテストが行われた。担任の前島先生はテストの制限時間を30分に設定している。5年生までの担任の北川先生は授業時間の45分を全て使って問題を解かせていたので、誰よりも早く問題を解き終えていた藤城皐月はいつも30分以上時間を余らせていた。テストが終わるまでの間、何もすることがなくなってしまうので、退屈を通り越して苦痛だった。
だが6年の担任の前島先生は時間内に解き終われば答案を提出をさせてくれる。しかもその場で採点をしてすぐに答案を返してくれ、その上余った時間は自由に読書をしていていいという。
皐月はこのシステムをとても気に入っている。カラーテストなんて100点満点が取れて当たり前だと思っていたので、自分がクラスの中でどのくらい勉強ができる方なのかがわからなくてつまらないと思っていた。だが前島先生のやり方なら解く早さでおおよその順位がわかり、皐月にはこれが面白かった。初めて前島式のテストを受けた時はクラスで一位を取ってやろうと張り切っていたが、中学受験組の栗林真理や二橋絵梨花にまるで歯が立たず、天狗の鼻を折られた。
今日は暗記テストだからガンガンに解いて真理を出し抜いてやろうと思っていた。1学期までの経験だと、暗記中心のテストならある程度勝負になっていた。しかし今回はどういうわけか真理がバカみたいに早く終わらせたので、またしても勝てなかった。それでも真理が先生に採点をしてもらっている時には皐月はテストを終わらせることができたので、大差をつけられたわけではなかった。次こそはと闘志を燃やして席を立つと、真理がべっかんこうをして挑発してきた。憎めないくらいかわいい顔をしていたので、ニヤニヤしながら皐月が先生に答案を渡すと、すぐ後に月花博紀がやって来た。
「栗林さんってあんなキャラだったっけ?」
博紀が小声で皐月の耳元で囁いた。博紀は真理のことを見ていたようだ。
「まあ、あれがあいつの本来の姿なんだよな。学校ではいつもスカしてるけど」
「俺、あんな栗林さん初めて見た」
「ご機嫌なんだろ。何かいいことでもあったんじゃね」
皐月のテストは満点だった。採点の終わった答案用紙をスキャンして、点数を入力してテストを手渡されると、皐月と博紀は先生から私語を慎むよう注意された。
「お前のせいで怒られたじゃないか」
「話しかけてきたのは博紀だろ」
「声がでかいんだよ、皐月は」
皐月が席に戻ろうとした時、博紀がまた先生に叱られていた。ざまあみろと思いながら席に着こうとしたら、絵梨花が解き終わって立ちあがった。
「今日は遅いじゃん」
「藤城さんたちが早過ぎるんだよ」
絵梨花は皐月みたいにムキになって早く終わらせようとはしないが、それでもいつも皐月よりも解き終わるのが早い。真理は皐月みたいに早解きにこだわっているので、いつもは2番目に早い絵梨花だが、今日みたいな暗記モノだと皐月が勝てることもある。絵梨花に勝てた皐月は嬉しくて表情が緩んでいたが、絵梨花は何とも思っていないような普段通りの落ち着いた顔をしていた。
皐月は席に戻ると机の中から読書用の本を取りだした。それは図書館で借りた日本の世界遺産のガイド本で、熊野古道の大きな写真が見られるものだ。その本には皐月の知っている知識しか載っていなかったが、プロの撮影した写真は美しかった。
2学期の初日に筒井美耶から実家の十津川村の話を聞かされ、興味を持ってネットで少し調べていたので、ぼんやりとした熊野の知識が頭の中ですでに整理されてまとまっていた。ページ数の少ないガイドブックではありきたりな情報しか掲載されていなかったので、皐月はすぐに飽きてしまった。
(熊野古道じゃなくて修験道の本を借りればよかったかな……でもそんな本、小学校の図書館に置いてあるわけないか)
あの時、神谷秀真と美耶と三人で話した、修験道の女人禁制の話は面白かった。知識はネットで調べたから知っているが、美耶の十津川での体験談をもっと聞きたかった。松井晴香と花岡聡の諍いがあったことで皐月は美耶と話すきっかけが作れなくて、夏休みの話の続きをずっと聞けずにいた。その後、秀真に教えてもらった十津川村の玉置神社のことも興味深かった。美耶は玉置神社のことを知っているのだろうか?
皐月は身体を絵梨花の方に向け、絵梨花の読んでいる本を見た。それはハードカバーの本で、紙面の上部にイラストが描かれているものだった。本文の漢字にはルビが振られている。絵梨花にしては少し幼稚な感じに思えたので、後で何を読んでいるのか聞いてみようと思った。
右を向くと岩原比呂志はまだ問題を解いている。比呂志なら鉄道関係の本を読むだろう。皐月の後ろで比呂志の隣の席の吉口千由紀もまだ問題を解いている。千由紀はいつも川端康成の文庫本を読んでいるので、今日もそうだろう。
テストが始まって20分も経つと解き終わった子も増えてきた。先生の前に児童が列を作って並ぶようになり、教室内も少しざわついてくる。千由紀と比呂志も解き終わって席を立ったので、皐月は隣の席の絵梨花に何の本を読んでいるのか聞いてみた。絵梨花はまだ問題を解いている子に配慮して、黙って本を手渡してくれた。
その本は少年少女日本文学館シリーズの『トロッコ・鼻』だった。芥川龍之介の作品を集めたもののようだ。
「どの話を読んでたの?」
「今読んでいるのは『羅生門』。読むのは何度目になるかな……」
少し顔を近づけなければ聞き取りにくいくらいの小声だ。
「二橋さんって何回も同じ話を読むの?」
「読むよ。だって回を重ねるごとに理解が深まって面白くなるから。藤城さんは一度読んで終わり?」
「小説はほとんど読まないから何も言えないけれど、確かに漫画は何度も繰り返して読むかな。台詞とか覚えちゃうよ」
「小説も漫画も同じだよ」
千由紀が席に戻って来て、机の中から文庫本を取りだした。ブックカバーがされているので、今日は川端康成の何の本なのかわからない。
「芥川龍之介って知ってるけど、読んだことないな……教科書に出てきたことあったっけ?」
「教科書には載っていないみたいだよ。戦前の小説は言葉が難しくて表現も古いから、最近の小学校では習わないって塾の先生が言ってた」
皐月は絵梨花に手渡された本の最初に乗っている『羅生門』の冒頭を読み始めた。イラストだと思っていたものは頭注の挿絵で、平安京のどの位置に羅生門があったかとか、揉烏帽子の絵と共にどんな材料で作られたかまで説明されていた。本文はすべての漢字にルビが振られているだけでなく、本文中の語句に用語解説も書かれていた。これなら知らない漢字や言葉に詰まったり、飛ばし読みをしなくて読み進められる。
「おれ、漢字超得意だから、難しい漢字がいっぱい載ってる小説って面白そう。蟋蟀とか、ルビがなくても余裕で読めるんだけど……あれっ? ここではコオロギじゃなくてキリギリスって読ませるのか。……でもやっぱり読めない字も多いな……薪の料(たきぎのしろ)とか。薪なら読めるけど料なんて読めねーよ。意味は材料の料なんだろうけどさ……」
「昔の文学作品って表外読みが多いからね」
皐月が夢中になって『羅生門』を読んでいると、珍しく千由紀が皐月たちの話に入ってきた。千由紀から話の輪に入ってくることは本当に稀で、今の席順になるまで見たことがなかった。
「吉口さん、表外読みって何?」
「常用漢字表に載っていない読み方のこと。時々クイズ番組で出てくるよ。小学校で習う難読漢字ってことで、インテリ芸能人でも結構読めなかったりする」
「吉口さんは読めるの?」
「漢字だけ単体で出されると難しいけど、小説の中だったら前後のつながりで大体読めるよ。でも薪の料は読めないな……」
話を聞いていると千由紀の漢字力のレベルの高さがわかり、皐月はさっき漢字が得意だと言ったことが恥ずかしくなってきた。
皐月は漢字が好きで、独学で漢検2級を取っていた。すべての常用漢字をマスターしていることになり、高校卒業・大学・一般レベルの知識をすでに知っていることが自慢だ。しかし皐月は千由紀の言う表外読みは知らなかった。漢検2級を取ったことは皐月にとって隠しておきたい努力だったので、友達にも話したことがなかった。千由紀には自分のプライドを守るためにも漢検のことは話せない。
「吉口さんは何の本を読んでるの?」
「川端康成の『雪国』」
「あ~、あのトンネルを抜けると雪国だったってやつ?」
「ちょっと違う。国境の長いトンネルを抜けると雪国であった、だよ」
「ああ、そうなんだ。で、吉口さんも二橋さんみたいに同じ本を何回も読んだりするの?」
「なにもかもってわけじゃないけど、好きな本なら何度でも繰り返して読むかな」
「じゃあ『雪国』は何回目?」
「ん……よくわからない。途中から読んだりやめたりしてるし、適当な読み方をしてるから……」
「『雪国』って面白いの?」
「そうね……クズ男とキチガイ女のすっごく胸糞悪い話なんだけど、それを美しく表現しているところが川端の凄いところなんだよね。文章に惹かれて何回も読んじゃう」
千由紀の口の悪い『雪国』評が面白い。それでいて川端康成への愛を感じる。
「クズ男とキチガイ女の胸糞悪い話ってのがいいね。俺も『雪国』読んでみようかな。ところで二橋さんの読んでる『羅生門』も面白いの?」
「勉強のつもりで芥川龍之介の小説を読むようになったんだけど、勉強なんて忘れちゃうくらい面白かったよ。『羅生門』は平安京を舞台にしたお話なんだけど、社会の授業で習ったような華やかな平安京じゃなくて、治安が悪く荒んだ状況になっていたのが新鮮な驚きだった。あと人が極限状態に置かれた時にどうするか、生きるってことは大変なんだなってことを考えさせられたかな。よかったら藤城さんも読んでみる?」
絵梨花はよくできた読書感想文に書かれているような『羅生門』評をした。でも千由紀の話ほどの面白味はない。
「『羅生門』も胸糞悪い話?」
「切羽詰まった人間を描いた小説だから、胸糞悪い話に決まってるじゃない」
絵梨花も面白い。最近いい感じに素を出すようになってきた。
「本当? じゃあ俺も芥川読んでみようかな」
「読むんだったら皐月は絵梨花ちゃんから本を借りた方がいいよ。吉口さんみたいに文庫本で読んでも皐月じゃ全然意味わかんないから」
真理も話に加わってきた。いきなり挑発するようなことを言ってくる。
「なんだよ、俺じゃあ全然意味がわからないって」
「だって『羅生門』って高校の教科書に載ってる小説だよ。小学生じゃ無理だって」
「大丈夫だよ。俺、漢検2級持ってるから。もう大学受験の漢字だって読めるからね。それにわからんことはネットで調べればいいだろ」
真理に煽られて、つい秘密にしていたことを喋ってしまった。
「皐月、漢検の勉強してたんだ。……全然知らなかった」
「2級ってすごいね。藤城さんは漢字博士だね」
「やめろよ、漢字博士とか。恥ずかしいわ……」
絵梨花の言葉に他意はないと思うが、最近の絵梨花はもう優等生ではなく、よく喋る利発な女の子だ。そう考えると皐月はからかわれているような気がしてきた。真理にはこっそり勉強をしてきたことがバレてしまったし、千由紀には表外読みを知らずに漢字博士はないだろうと思われているに違いない。皐月はこの班になってからまるで格好がつかず、いつも自分のことを褒めてくれていた美耶のことを懐かしく思った。
秀真と比呂志が採点が終わって席に戻ってきた。大半の児童が解き終わるか採点の列に並んでいている。教室はさらにザワザワしてきたが、理科や社会のカラーテストの時はみんな早く解き終わるのでいつもこんな感じになる。あまり騒がしいと先生に怒られるが、少しくらいの私語は大目に見られていた。
ざわめきに促され、まだテストに向き合っていた子たちも未解答のある答案用紙を持って採点の列に並んだ。これで単元テストは終わる。あとは残り時間で先生がテストの解説をしてくれる。即座にテストの復習をすることで学習効果が高まるということらしい。授業時間内に採点と返却、解説を終わらせるのが前島先生のやり方だ。6年4組の児童たちはこのやり方を気に入っている。
授業が終わったので皐月は真理に何の本を読んでいたのか聞いてみた。真理は小説は読んでいなくて、植物学者・稲垣栄洋の『はずれ者が進化をつくる 生き物をめぐる個性の秘密』というノンフィクションを読んでいた。この作者の文章は中学受験で頻出だということで塾から読むように指示されているという。
「真理っていつも塾から読めって言われた本を読んでるの?」
「まあ受験生だし割り切ってるよ、そのへんは」
「この前貸してくれた『100%ガールズ』(吉野万理子著)も塾の課題図書?」
「違う。あれは私が読みたくて買った本」
「そっか……。あの本は面白かったよ」
真理が受験勉強から外れたことをしているのが皐月には嬉しかった。
「塾から奨められた本なんて読んでて面白い?」
「読んでみればそれなりに面白いよ。この本だってまあまあ面白いかな。でも好きじゃないところも多々ある」
「へぇ~、どんなとこ?」
「私、植物じゃないし。植物の話として読めば面白いけど、それを人に当てはめようとすると、道徳臭くてキモい。なんか読者を慰めようとする意図があるみたいなんだけど、私にはそれがちょっと息苦しいな」
「なるほど……」
真理に本を借りて、目次と序文をさっと読んでみた。
「俺はちゃんと読んでいないから偉そうなことは言えないけど、個性とか、らしさとか、進化とか、エグい言葉のオンパレードだな。確かにキモい。でもちょっと面白そうな気もする」
「じゃあ読む? 貸してあげるよ」
「いや、今はいい。芥川龍之介を読んでから考えるわ」
「ふ~ん。私はてっきり『雪国』を読むのかと思った」
皐月はさっと周囲に気を配り、千由紀が近くにいないことを確認した。
「『雪国』はね……読んだことはないけど、内容は少しだけ知ってるんだ。芸者の描かれ方が気に入らないって和泉(皐月の母の師匠)が言ってた。だからちょっと読むのに抵抗があって……」
「それって男目線の偏見みたいなの?」
「俺もよくわかんないんだけど、多分そんなとこじゃないかな」
「そういうことだったら私が読んでみたいかも、『雪国』」
「えっ、なんで? 読んでも気分が悪くなるだけだろ?」
「読んで吉口さんみたいに辛辣なことを言ってやりたい」
「さっきの話、聞いてたのか」
皐月が自分の後ろの席の千由紀の方を向いていると、前の席の真理が皐月の背後になってしまうので、真理が皐月のことを見ていることに気付かなかった。
「吉口さんってノーベル文学賞作家を相手にボロクソ言ってたよね。聞いてて気持ちよかったな……」
「でもちゃんと褒めてたけどな。文章表現が美しいって」
「私も塾の推薦本なんか読むのやめて、面白そうな小説を読もうかな……」
「そうすればいいじゃん。どうせ読めって言われた本を読んでも、その本から入試問題が出るわけじゃないんだろ?」
「まあ、そうだね……学校にいる時くらいはそうしようかな」
稲荷小学校では毎朝10分間の読書タイムがある。毎日の積み重ねなので気付けば案外たくさんの本を読めている。それに前島先生のクラスだと各教科の単元テストの余り時間でも本を読めるので、本好きには恵まれたクラスだ。
千由紀が席に戻ってきたので、真理から千由紀に話しかけた。皐月はこの二人が話しているのを初めて見る。
「吉口さん、私も『雪国』読んでみようかなって思ったの。難しくて意味がわからないことがあったら教えてもらえないかな」
「そんな……私が栗林さんに教えられることなんてあるかな……」
「私、文学のこと疎いから頼りになってもらえたら嬉しいんだけど、ダメかな?」
「じゃあ、あまり力になれないかもしれないけど、私で良かったら……」
「ありがとう!」
皐月の席を挟んで真理と千由紀が仲良くなった。二人とも不器用で、特に千由紀は真理よりも人見知りに見えたので、そんな二人が友達になる瞬間を見られたのは皐月にとって僥倖だった。まだ表情が硬い千由紀だが、嬉しそうな顔が可愛らしい。千由紀の大きな一重瞼の瞳は吸い込まれるような魅力があり、真理の前なのに、皐月は千由紀にドキドキしてしまった。
最後まで読んでくれてありがとう。この記事を気に入ってもらえたら嬉しい。
