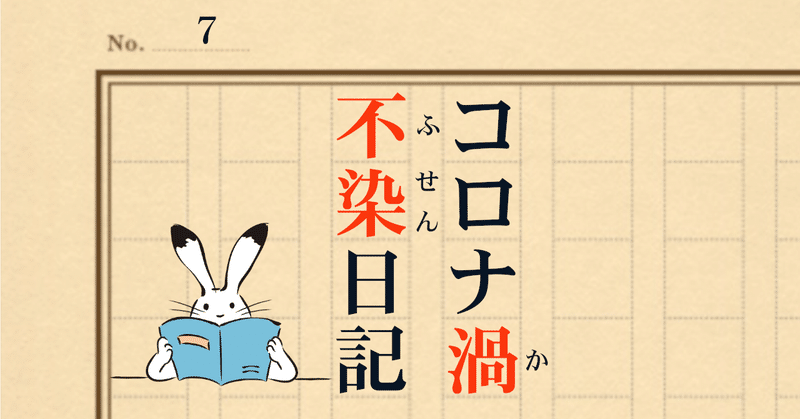
コロナ渦不染日記 #7
四月二十七日(月)
○一日中、なんとも言いがたい天気。明るくとも寒く、曇ればなお寒い。午後からは雨が降りだす。
○在宅仕事はダレぎみ。身が入らないことはなはだしい。それでもやるべきことはこなしているが、それ以上のことはなかなかしがたいのは、新人だからか、在宅ゆえの疲れがでているせいか。
○終業三十分前から、こっそり『ゴルゴ13』を読む。初期のクライマックスのひとつである、「最後の間諜 -虫[インセクト]-」につながる連作(「ゴルゴin砂嵐」、「ベイルートVIA」)はすばらしい。
特に「ベイルートVIA」では、それまでのエピソードで出てきた東西陣営それぞれの諜報機関の大物が一堂に会し、「第二次世界大戦の後始末」の総括といった趣がある。思うに、最初期のゴルゴは、「戦後」を描くマンガだった。ゴルゴは戦中-戦後世代のニヒリズムを体現する若き人物の造形であったのだ。だからこそ、「最後の間諜 -虫-」でゴルゴが対決する「敵」は、第二次世界大戦の生み出した「巨大な怪物」であった。そして、それは当時さいとうプロで脚本家として頭角を現しつつあり、同作の脚本を担当した小池一雄、すなわち、のちの小池一夫氏の提示した世界観だったのではないだろうか。「巨大化しすぎて内部に矛盾をかかえ、身動きのとりづらくなった大組織と、それに対峙する個人」という図式は、『子連れ狼』をはじめとする、小池氏脚本によるマンガ作品の定番である。
○夕方から背中が痛くなる。就業中の姿勢が固定されているからだろう。
○夜、テレビドラマ『からくり事件帖』を見る。山田風太郎の傑作『警視庁草紙』の映像化である。
特に、「最後の牢奉行」は涙なしには見られない。明治七年、すでに役目を解かれてなお、かつての伝馬町牢獄に身を置く「最後の牢奉行」、第十七代石出帯刀をめぐる物語は、最後、伝馬町牢獄を襲った延焼に際して、彼がその権限もないのに独断で囚人を解き放し、燃える牢獄の中庭で腹を切る。これは、『からくり事件帖』全体——つまりは『警視庁草紙』全体……あるいは山田風太郎の小説世界全体を貫く、以下のテーゼを強く示すものである。
「人は死なないから生きているのではない。生きるべくして、あるいは死ぬべくして生きるのであり、そうした理由がなければ、人は生きているとはいえない」

四月二十八日(火)
○埼玉県が公立高校の休校を五月末まで延長したことを受け、全国自治体で公立学校の休校延長が検討されているようだ。
昼には、休校を九月まで延長し、諸外国が採用している、九月新学期開始に日本も足並みをそろえるべきである、と主張し、署名を募る学生が複数いるのだ、というニュースがあった。
夜には、五月六日でこの災禍が収束するとは思えない、という各自治体の意見が述べられた上で、東京都知事が九月新学期制の導入もありうるというようなことを述べていた。
もちろん、そうなるには多くの試行錯誤が必要になるに違いない。現場の混乱もひとかたならぬものであろう。だが、そうなってしまうのもまた一つの世界のかたちであろうと思う。
かつて、ぼくは世界が変わる日がくればいいと思っていた。もっというと、世界が燃えあがる日がくればいいと思っていた。世界が燃えあがれば、死なないから生きているというだけの日々が終わるのではないかと思っていたのだ。それから数十年が経ち、世界は燃えあがらなかった。しかし、変わる日は来たように思われる。いや、本当は、世界は変わり続けていたのだ。ぼくだけが、自分と世界は変わらないのだと思いこんでいただけだったのだろう。
○アメリカ国防総省が、2004年と2015年に空軍が遭遇した未確認飛行物体の映像を公開し、これを受け、日本の国防総省も記者会見の場で、未確認飛行物体遭遇時の心構えを述べたという。愉快。
○夜、vic cisono氏による、「リチャード・コネルの『最も危険なゲーム The Most Dangerous Game』」を読む。
「最も危険なゲームThe Most Dangerous Game」は、究極の狩りを志向する富豪の島に流れ着いた、こちらも高名なハンターが、命がけの狩り/サバイバルに挑むという話。いわゆる「マンハントもの」の元祖ともいわれている。大傑作『深夜プラス1』で知られるギャビン・ライアルに同名の長編があるが、それはこの作品の本歌取りであろうし、松田優作主演の映画『最も危険な遊戯』(と、そこからはじまる「遊戯シリーズ」)もこの作品が源流とみる。
しかも、このタイトルが素晴らしいのは、「Game」が「ゲーム」「遊戯」であることは間違いないが、それと同時に、「獲物」の意味もあるというところだ。つまり、「最も危険」なのは、「人狩りというゲーム」である(主人公からの視点)と同時に、「命がけで対峙せねばならない獲物=強敵」である(相手からの視点)ということだ。そして、後者があざやかに印象づけられたその瞬間、主人公と相手の視点/主客が逆転することまでも、このタイトルは示唆している。もちろん、vic isono氏の訳文もそのことを踏まえた上で構成されているだろうから、ラストの切れ味の良さは野獣の牙のごとしである。これこそ「最も危険な獲物」なり。
四月二十九日(水)
○休日。普段の始業時間まで寝る。
○風涼しくも、好天なれば、近所の公園から子どもの声が聞こえてくる。
○フリマアプリで、転売を目的に買い占められたとおぼしいドライイーストが売られているという。外出自粛で暇をもてあまし、D.I.Y.に興味を向けた人々がパンを作るようになり、そのことで小麦粉やドライイーストが普段以上に小売店で買われるようになったのを受けてのことか。
やはりこのときがきたかと思う。これはまったくヤミの市場の再現である。つまり、七十五年前と、やはり人間の本質においてなにもかわるところはなかったのだ。
需要が供給を生み、供給が価値を得るのだとすれば、需要を察知し供給をコントロールする場を作るというドライイーストをぶちこむことで、価値はなん倍にもふくれあがるということだ。これは科学であり、知恵である。そして、科学や知恵に善悪はない。善悪は、それを行う人間の、あるいは彼を眺めている別の人間のなかに生まれるものである。

四月三十日(木)
○終業後、郵便受けを確認すると、ケイト・ウィルヘルム『鳥の歌いまは絶え』が届いている。
ケイト・ウィルヘルムは、ジェイムズ・ティプトリー・Jrやアーシェラ・K・ル=グウィンといっしょに語られることの多い、フェミニスティックなニュアンスのある女性SF作家である。ティプトリーより若く、ル=グウィンと同期で、つまりは七〇年代的な、いわゆる「ニューウェーブ」の人である。だからというのでもなかろうが、ティプトリーよりはル=グウィンに近い、リアリスティックな未来像がある。同時に、ティプトリーがプロパーなSFに託した寓話性も持ち合わせているように受け取る。
『鳥の歌いまは絶え』は、出生率減少を背景に、クローンによる人口増加をもくろんだ社会がどのように変容していくかを、三世代にわたって描く大河SFということである。発表は一九七六年というから、ロックの流行やヒッピームーブメントといった、カウンターカルチャー勃興の時代を写したリアリスティックな内容であろう。ここ五年くらい、個人的にこういうSFに興味がある。自分が足をつけて生きていかざるをえない「時代」というやつに、興味がわいてきたのかもしれない。遅れてやってきたニューウェーブといえなくもないが、なに、時代とはつねに自分のなかにあるのだ。
なお、『鳥の歌いまは絶え』の原題は『Where Late the Sweet Birds Sang』という。直訳すれば「すてきな鳥が歌ってからずいぶん経った頃」となるところを、「鳥の歌いまは絶え」と訳したのは、かの浅倉久志氏であった、という逸話が巻末に載っている。すばらしい。
○夜、岬へ行く。イナバさんの買い出しに付き合う。
○今日で四月が終わる。
二〇二〇年春は激動の春であった……などというつもりはない。いつだって激動の春であり、激動の年であるのだ。それを「今年こそは」「今月こそは」「今回こそは」と思うのは、生き物の感覚の限界である。生き物の感覚は、その精神の活動するところ、感覚器官の集合体である、肉体の限界をこえることができない。すなわち、肉体(とそこに接続される延長物)の感覚できる範囲を超えて感覚することは出来ないし、肉体(とそこに接続される延長物)の変化(劣化)をまぬかれえない。そして、記憶もまた変質し、劣化する。だけど、そうした限界のなかで、ぼくもあなたも生きている。だから、激動の春は、それはそれとして正しい。
月やあらぬ 春や昔の春ならぬ
わが身ひとつはもとの身にして
(月は、春は、昔とは違うものになってしまったというのか。
ぼくは、相変わらずぼくでしかないというのに)
——『伊勢物語』より。
(現代語訳は引用者)
参考・引用文献
イラスト
「ダ鳥獣戯画」(https://chojugiga.com/)
いただきましたサポートは、サークル活動の資金にさせていただきます。
