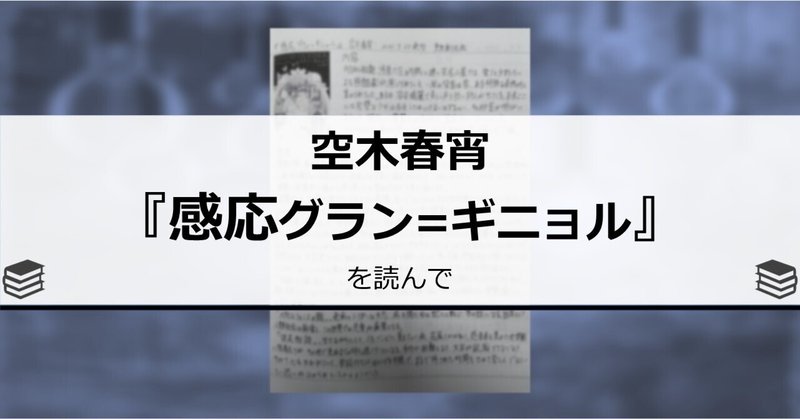
空木春宵『感応グラン=ギニョル』を読んで
『感応グラン=ギニョル』空木春宵 2021.7.29 発行 東京創元社
内容
昭和初期、浅草六区の片隅に建つ芝居小屋では、夜ごと少女たちによる残酷劇が演じられている。一座の役者は皆、ある特殊な条件のもと集められていた。ある日、容姿端麗で美しい声を持つ新人がやってくる。本来ここには完璧な少女は存在してはいけないはずなのに。その秘密が明らかになるとき、彼女の〈復讐〉が始まる。(「感応グラン=ギニョル」)。
分かち合えない痛みや苦しみを抱えて生きる孤独な魂を描く全5編。
感情と共有、痛みを描いた短編集。グラン・ギニョル=残酷劇。
※「グラン・ギニョル」とは大きな指人形という意味ですが、上演される舞台は人形劇ではなく役者たちの芝居で構成されていました。猟奇・残酷劇を得意としたため「グラン・ギニョル的」とはそうした演劇あるいはセンスを指す言葉となりました。
「きれいはきたない、きたないはきれい」を根幹に退廃的で痛みを伴う美しさを雰囲気ある文章で描くSF小説。
「感応グラン=ギニョル」
表題作は、欠損を抱えた少女たちの劇場。夜ごと、どこかが欠けてる特殊な少女たちによるグランギニョルが演じられていた。
浅草の片隅の方で怖いもの見たさで来る観客たち。演じるのは、鼻がない女の子、身体が傷だらけの女の子、身体的な痛みと、目が見えない女の子、どこか一つ欠けてる女の子たちによるグランギニョルが行われてるときに、主演者に新人の女の子が入ってくる。
その子はどこも欠けていない、綺麗な人形さんみたいな子。ただその子は心がない女の子。
あらすじを読んだだけで、ぞわぞわしました。どこか欠けてる女の子たちに対して可哀想だとか、可哀想だけど彼女たちがやっているものを観たいという、怖い反面、興味本位で覗いてみたくなるなります。
「わたし達を憐れむな」と言って表現するものは何なのか、ドキドキしながら読みました。
「地獄を縫い取る」
エンパスと呼ばれる精神感応装置で、他者の体験をネット共有できる時代。業を背負うAIとあぶりだされる醜さ。
自分の内側に地獄を縫い取り、復讐を誓うジェーンの姿が凄惨でした。
「メタモルフォシスの龍」
発病のトリガーは失恋。病を得た女は蛇へと転じ、男は蛙になる。そして女は愛した男を喰らわずにはいられなくなる。結果として人類社会は崩壊し、この世界では恋愛が厳禁とされる。恋に破れ共同体を出たテルミは、愛した男を喰らうために街に出る。
蛇女のルイと同居する中で、テルミは自らが持つ、宿命を向き合うことになります。テルミは苦悩の果てに、蛇でもなければ蛙でもない、龍として生きることを選択します。
生々しく胸が痛かったです。
「徒花物語」
生きながらにして、人をゾンビに変えていく病、花屍(かばね)。感染者を集めた女学園に隔離され、その地で死までの時を過ごすことになる。歩行が困難となり、文字が認識できなくなり、やがて心も失われていく。
学校内だけはいつでも平穏で、まるで残された時間をせめて楽しんでほしいという思いが込められているかのようでした。
「Rampo Sicks」
美醜の尺度が絶えず評価され、美しいものたちが差別を受ける世界。
「美は善、醜は悪」。人間がよく陥りがちな認知の歪みについて考察した内容。
「感応グラン=ギニョル」の後日譚であり、閉ざされた世界の中で、人間の醜さを描いた物語になっています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
