
【小説】ある日、飼い猫が喋りだした
冷夏だった今年の夏の勢いそのままに、今年の冬は例年より冷える気がする。
私の腕の中では、ダウンジャケットを着た娘の紗季が、よく眠っている。二人で繰り出した冬のグレーの空は、太陽を覆い隠しているのに、こうして路上に出てみると、なんとも日差しが眩しいから不思議なものだ。
今日はこれから、娘と新しい猫を買うためにペットショップに向かっている。駅に向かうこの通りは、すきっぷ通りという名前がついているのだが、今日は決してスキップしたくなるような陽気ではない。
こういう徒歩での移動って、昔からほんのり退屈だ。
とはいえ、話相手になりそうな娘はとうに寝てしまっているので、話し相手もおらず、道すがらぼんやりと昔のことを思い出していた。
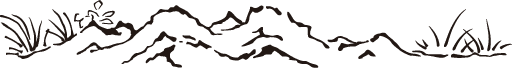
私が小学生の頃、学校から帰ると母さんはいつもパートで出掛けており、放課後の殆どの時間を自宅で独り過ごした。昭和風の表現で言うと、鍵っ子という感じ。
独り。というのには、少し語弊があるかな。
正しくは、家にいたのは、一人と一匹。
私が小学校に入ってまもなく、母さんはどこからか、家に猫を連れてきた。母さんはいつも、事前の相談や匂わせとかが無い人だった。いつも突然なにかをひとりで決めて、さらっとやりとげる。
いつだったか、母さんに当時の経緯を聞いてみたところ、どうやら、当時私があまり学校に馴染んでおらず、放課後も友達と遊んだりすることなく、まっすぐ一人で帰宅。そのまま家でも、ずっと部屋で一人ぼっちでいるのを可哀想だと思ったらしい。本人としては、べつにに辛くもなかったのだけれど。
大人となった今では、小学校に入りたての頃の記憶は、もうおぼろげにしか残っていないけれど、確かに暗い子だった気がする。それでも孤独さを感じたことはなかったし、大人になった今でも友達の数はそんなに多くない。
連れてきた猫には、母さんが名前をつけた。
そこら辺にいる猫と、あまり代わり映えのしない名前の、「ミケ」と。
確か私も色々と案を出したけれど、全部却下されて随分すねたのを覚えている。そもそもミケは、三毛猫の柄をしていない白猫なのに、ミケっていうのは、どういうことなのかと。
そういえばなんでこの名前にしたのか、母さんに聞いたことはなかったな。まあ母さんのことだから、特別な理由なんて特にないのかもしれないけれど。
そんなある日の夜、居間で母さんと過ごしていると、ミケが突然、炬燵の上に昇ってしまったことがあった。
夕食はとっくに済ませていたので、炬燵の上に乗っているのは、みかんの入ったお皿ぐらい。だからお皿をひっくり返したりといった騒動は殆どなかった。
でもその時の私はまだ子供。
それはもうかなり驚いて、キャーって叫んだのを覚えている。
そうしたら、なんと、炬燵の上のミケが突然、喋ったのだ。
『ごめんにゃー』
そこからはもう大変!
私はさっき叫んだ以上に、ものすごく驚いて、ミケに色々話しかけた。挨拶やら、好きなものとか、私のこととか、それはもういっぱい。
けれども結局、その夜はさっきの一言以外は全然喋ってくれずじまい。猫じゃらしをぶんぶん振っても、いつもは喜ぶ頭なでなでをサービス満点でしてあげても、ゴロゴロと喉を鳴らすばかりだ。しまいには最終兵器のちゅ~るまで持ち出したのに、つれない態度だ。
私は母さんにも、
「なんでミケはもう喋ってくれないの?」
って問い詰めた。
すると母さんは、優しく笑いながら、
「不思議だねぇ」
と、あまり真面目には、とりあってくれなかった。
猫が喋ったという我が家の大事件の最中、さも当然かのように驚いていない母さんが不思議だったのを、子供心に覚えている。
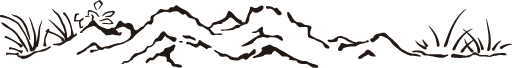
母が心配する程度に、私に友達は少なかったけれど、それでもクラスには数人だけ仲の良い子がいた。その中でも葵ちゃんとは特に仲が良くて、給食も机をくっつけて、一緒に食べていたくらいだ。
猫が喋った事件があった数日後、私は葵ちゃんに猫が喋ったことを自慢した。
「うちの猫。しゃべるんだよ!」
「えーっ。そんなことあるわけないよー」
クラスの中でも、少しだけ落ち着いた雰囲気を持つ葵ちゃんは、私の話をすぐさま否定した。
「じゃあ、今日の放課後、うちのミケに会いにきて!」
最初にミケが喋ったあと、実はその後も何度か、ミケは喋ることがあった。
喋る時は決まって、母さんと私が炬燵に座っている時で、その時のミケは炬燵の上や、絨毯の上でごろごろ寝ながら、突然、喋りかけてくれた。
その喋る内容はすごく簡単で、「眠いよー」とか、「ごちそうさま」みたいな独り言。
逆に私が学校から帰って、「ただいまー」って挨拶しても、返事が返ってきたことは一度もなかった。そういう時に喋ってくれればいいのに。
学校で葵ちゃんに話した数日後、本当に葵ちゃんは家まで遊びにきてくれることになった。やっぱり友達は持つべきだね。
お友達を、家に招待したのは葵ちゃんが初めて。
放課後は、母さんはパートでいつもいないから、二人きり。
ミケは人に物怖じしない猫で、葵ちゃんが頭をなでても、素直に喉を鳴らしている。
それから、私と葵ちゃんのふたりで、ミケに色々話掛けたのだけれど、待てど暮らせど、ミケはまったく喋ってくれない。もしかしたら、炬燵の上に乗せないと喋ってくれないのかと、子供心に思いつき、無理矢理ミケを炬燵の上に乗せてみたりしたけれど、ミケはせいぜい、にゃーと鳴くぐらい。
結局、その日は夕方になるまで遊んだけど、ミケは一言も喋ってくれなかった。
帰り際。
葵ちゃんが、まじめな顔をしたかと思うと、突然怒られた。
「ひとみちゃん! 嘘はついたらいけないんだよ。」
「嘘じゃないもん!喋るんだもん!」
たまらず私も言い返した。だって嘘はついてない。ミケは・・・本当に喋るのだ。
─────小学生の口喧嘩は平行線。
確かに今日はミケは喋らなかったけど、昨日の夜も喋ったし、
結局、その日は喧嘩別れになってしまったけれど、翌朝、学校で葵ちゃんも謝ってくれたので、仲直りができた。よかった。
でもなんか以前より、ぎくしゃくした雰囲気、っていうのかな、以前より距離が離れてしまった気がした。私もまだ少し意地になってたところがあると思う。ミケは本当は喋るんだ。
そんなことがあって、家でも暗い表情をしていたら、すぐに母さんに気づかれた。
やはり母というのは、自分の子供に対しては、鋭い生き物らしい。私の方も子供だったから、感情を隠すなんてことは、まるで考えてもいないので、悩んでるのがバレるのも早い。
「なにか悩みでもあるの?」
「実はね・・」
そこからはもう泣きながら、ミケが喋るって葵ちゃんに自慢してしまったこと、葵ちゃんを家に連れてきたけどミケが喋らなかったこと、葵ちゃんと喧嘩したこと、仲直りしたこと、ぜんぶぜんぶ母さんに話した。
泣くだけ泣いて、しゃべり尽くした頃、母さんはいつものように優しい顔で。
「そうね・・だったら、また葵ちゃんをお家に呼んだらどうかな? 何度か来てれば、ミケもそのうちきっと喋ると思うな。」
「えっ。うん・・そうだね。また葵ちゃんを誘ってみる!」
「たとえば、明日とかなら母さんもお家にいるから、美味しいお菓子も出せるよ。」
母さんの言う「おいしいお菓子」は、決まって手作りバタークッキー。
あれは美味しいから葵ちゃんも喜ぶに違いない。
私は気持ちもすっかり軽くなって、そのまま自室に戻り、日課である日記を書いて就寝することにした。描き込んだイラストは、もちろん、クッキーとミケだ。
日記を書いている時、隣室から母の声が少し漏れ聞こえてくる。当時、公団住宅住まいだった我が家は、かなりの安普請。特に静かな夜であれば、隣の部屋の話声には、簡単に気がつく。
母さんは、どうやらどこかに電話を掛けているようだった。親しい人には使わない、ビジネス口調のトーンで話している。珍しいな、夜中に電話するなんて。
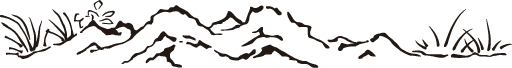
翌朝、爽やかに目覚めた私は、すっきりした気分で小学校に行き、そのままの勢いで葵ちゃんに話しかけた。
「おはよう。葵ちゃん。」
「おはよー」
「早速なんだけど、今日またウチに遊びに来ない? 母さんも言ってたんだけど、ミケも遊んでるうちに、そのうち気まぐれに話してくれるかも!って。」
「う、うん。じゃあミケちゃんのことはべつにして、一緒に遊ぼう。」
良かった。
こないだの件で、ウチに来るのが嫌になってないかと心配してたのだけれど、なんだか気にしすぎだったみたい。
その日の放課後、自宅で遊ぶため、友達の葵ちゃんと一緒に帰宅した。
珍しく母さんが家にいて、ミケと一緒に玄関まできて、笑顔で出迎えてくれた。うれしい。
私の部屋に入り、葵ちゃんと取り留めのない話をしていると、突然、母さんに呼ばれた。
「ごめんね。母さん、今クッキー焼いてて目が離せないんだけど、実はトイレの掃除をするのを忘れていたの。ちゃちゃっとでいいから、掃除しておいて。」
「えー。今あそんでるのにー。」
「もし葵ちゃんがトイレ借りて、中が汚かったら、また嫌われちゃうかもしれないでしょ。ねっ、おねがい?」
「はーい。」
いきなりのお使いに、いささか機嫌を悪くしながらも、しぶしぶトイレ掃除を始めた。そもそもトイレ掃除は、おうちの中では数少ない私の役目だった。
うーん、そんなに汚れてない気がするけど。
外から話し声が聴こえる。どうやら母さんと葵ちゃんが何か話しているようだ。
トイレの中からは話している内容は聴こえない。何を話しているのかな?
トイレ掃除はほどなく終わった。自分がちょっと掃除をサボっていたとはいえ、友達が遊びに来てる時にやらせることなくない? とは思ったけど、悪いのは自分なのでひとまず我慢。
「ごめんね。母さん、突然掃除しろって言い出すんだから。」
部屋に戻った私は、ミケの背中をなでている葵ちゃんに言った。
「ううん。それよりね、ミケ、喋ったよ!」
「えっ!? ほんとに?」
「うん。」
そうか、それでさっき私がトイレ掃除してる時、母さんと話している声が聴こえてきたのか。
「それで、ミケはなんて喋ったの?」
「それはね・・」
葵ちゃんによると、どうやらミケは、「こんにちは」と簡単な挨拶をしてくれただけらしい。
それでもミケは喋った。喋ったんだ。うれしい。うれしい。
これで私も嘘つきだって言われなくて済む。それも少しほっとする。
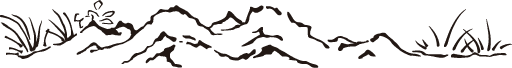
ペットショップがあるらしい場所には、おそらくあと数分で到着する。
私も大人になった今、葵ちゃんとは今でも時々連絡を取り合っている。たまにご飯を食べにいったり、映画を観にいったりする、仲の良い友だちだ。小学生の頃からの友達なんて、いまとなっては葵ちゃんぐらいだ。
会うと今でも時々、小学生の頃の話をする。
中でも定番なのは、何を隠そう、ミケと・・私の母さんの話だ。
結局、ミケが葵ちゃんに喋った日、私がトイレ掃除に行っている最中。母さんは葵ちゃんにネタばらしをしていた。
母さんが、実はミケのふりをして、声真似をしているだけだと。
そして、そのことは私には秘密にしていて欲しいと、母さんは葵ちゃんにこっそりお願いしていたのだ。その為の時間稼ぎ、その為の突然のトイレ掃除だった。
その後、中学受験を控えた小学6年の頃には、そんなからくりにも、とっくに気がついていた私だけど、それを改めて母さんに言うこともなかった。
母さんもなんとなく、バレてしまったことに気がついていたに違いない。人の心の機微には敏い人だ。いつしか、ミケは炬燵の上に昇っても、なにも喋らなくなっていた。
実は昨日も、私は葵ちゃんとスタバの一角で、当時の思い出話に花を咲かせている。葵ちゃんは子供の頃からの夢だった、キャラクターデザイナーとしての道を歩み始めたばかりだ。
彼女は大人になってからも時々、私の家に遊びに来て、母さんと一緒に笑うのだ。
「あんた、あの頃、完全にミケが喋るって、信じ切ってたわよね。」
「そこは、素直で可愛かった。って言ってよ。」
「素直は兎も角。可愛いってとこは、判断に困るわ(笑)」
私を産む前、売れない劇団員をしていたという母さんは、ちょっとした演技は勿論、声優業までかじっていたらしい。当然、普段と違う声で猫の声をあてる程度のことは、造作もないことだったらしい。
とはいえ、隣りにいてそれに気づかなかった私の、ぽんこつ加減も相当なものだったのは・・まあ否定できない。自立した今でも、その片鱗は残ってるし。
あの日、私からの告白を聞いてすぐ、仕事をわざわざ休んでまで、些細な私への嘘につきあってくれて、葵ちゃんという、親友も得るきっかけまで作ってくれた母さんには、感謝の言葉しかない。
自分も娘を持った今になって、ようやく当時の母の気持ちが少しわかるようになった。手作りのクッキーも、ミケのお喋りも、ささやかな嘘も、すべて私のことだけを考えての行動だった。
残念なことに、ミケは去年の末に亡くなってしまった。ここ1年は、毎週のように注射をうちに動物病院に連れていったりと、私も色々と頑張ってはいたのだが、寿命だけはどうしようもない。
私の子供も来年には幼稚園に入る年になる、そろそろいいか、と夫とも相談して、春には新しく猫を飼うことに決めた。娘には悪いが、もう名前は決まっている。ふふ、母の特権だ。
さあ。
今から私、猫に声をあてる練習はじめて、間に合うかな?

俺はねぇ、饅頭が怖いんだ!俺は本当はねぇ、情けねぇ人間なんだ。みなが好きな饅頭が恐くて、見ただけで心の臓が震えだすんだよ──── ごめんごめん、いま饅頭が喉につっけぇて苦しいんだ。本当は、俺は「一盃のサポート」が怖えぇんだ。
