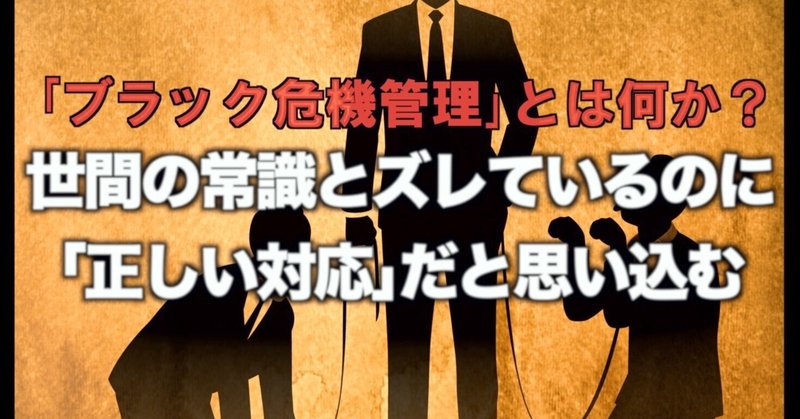
「ブラック危機管理」とは何か?
自分たちは「正しい」と信じる”独りよがりな危機管理”
このマガジンのタイトルは「ブラック危機管理」です。
と言われたところで「なんのこっちゃ」と首を傾げる人も多いことでしょう。
「ブラック危機管理」というのは、報道対策アドバイザーとしてこれまで多くの企業不祥事などの対応にあたってきた私が提唱をしている「日本企業の構造的な問題」を指しています。では、どのような「組織の病」なのかというと、ざっくりと説明するとこうなります。
経営幹部らが議論を重ねて「これがベストな選択だろう」と判断を下しておこなっている危機管理が、社会や消費者から見るとまったく逆で、「この会社、とんでもないブラック企業じゃん」とドン引きされる原因になってしまう。
つまり、厳しい言い方をさせていただくと、ご本人たちは「正しい」と信じてやっていることが、他人から見るととんでもない悪手になってしまう“独りよがりな危機管理”のことです。
ブラック企業の中にいすぎると「感覚」が麻痺する
これをなぜ私が「ブラック危機管理」などと呼んでいるのかというと、「ブラック企業」と構造的に近いものがあるからです。
これまで私は取材やコンサルで、世間的に「ブラック企業」と叩かれるような企業の内情を見る機会がよくありました。部下を自殺に追い込んだ上司などにも実際に会ってヒアリングをしたこともあります。
そこで感じたのは、世間の見方と組織内部の感覚に絶望的なまでのギャップがあるというケースが少ないということでした。
世間もブラック企業だと捉えて、働いている人たちもブラック企業だと感じているという自他共に認めるブラック企業もありますが、実は当事者はそこまで自分たちの会社を「ブラック」だと思っていないケースもかなりあるのです。
「厳しいところもあるけれど、現場の自主性にかなり任せてくれる」「確かに残業も多いけれど、別に強制されているわけでもないし自由でやりがいがある」ーー。そんな風に多くの社員が思っていたところ、ある日、突然、自殺者やメンタルを壊した社員が会社を訴えることなどが発覚して、一般の社員は「ああ、うちはブラックなんだ」と自覚をするということが実はよくあるのです。明らかに間違っているのに「ズレてますよ」の一言が言えない。ブラック企業という組織の中に長くい続けることで環境に適応して、世間の感覚が麻痺してしまうのです。
ブラック企業と同じ「世間とズレる」という組織の病
ただ、これはしょうがありません。会社であろうが学校であろうが軍隊であろうが、閉鎖された組織の中だけで生きていると、人はどうしてもそこで起きていることが「当たり前」だと感じてしうものです。
例えば、新人に対するパワハラや社内イジメのようなことが蔓延していたとしても、それが何年も継続していれば、「オレも新入社員の時はやられたなあ」という中堅社員ばかりなので、誰もこれを「異常」なことだと指摘しません。新人たちも「ああ、先輩や上司も問題視していないってことは、この会社ではこれが常識なんだ、早く慣れなくちゃ」と疑問や不安を押し殺して、パワハラや社内イジメを受け入れていきます。
つまり、「ブラック企業」というのは、本人たちが良かれと思って続けている社内カルチャーやシゴキが、世間の常識と大きくズレているにも関わらず、それに対して誰も「ズレてますよ」と言うことができずに組織全体の感覚が狂ってしまっている状況なのです。
これは実は危機管理に失敗して大炎上をしているような企業にも当てはまります。
小林製薬「紅麹パニック」はブラック危機管理の典型
経営幹部らは「危機」に対して、「こうすれば収束するはずだ」「これで鎮火できる」という感じで良かれと思ってさまざまな対応をしますが、世間の常識と大きくズレているということが多々あります。しかし、それを誰も「ズレてますよ」と言うことができません。「専務が主張しているのだからしょうがない」「社長がそう決めたら誰も逆らえない」など、世の中的にはどうでもいい「社内の論理」に従って、“独りよがりな危機管理”に沈黙をしてしまうのです。
かくして、世間が「なんでこんなに対応がヤバいの?」と呆れるような「悪手」がつくり出されるというわけです。これが当事者たちは「正しい」と信じながら目も当てられない酷い対応をする「ブラック危機管理」の基本的な考え方です。
こういう「組織の病」を原因とする炎上企業を、仕事柄これまで嫌となるほど目の当たりにしてきました。この病がやっかいなのは、規模や業種が関係ないことです。
日本人なら誰もが知る名門企業や大企業から、創業間もないベンチャーまで「組織」であれば「ブラック危機管理」に陥ってしまう危険性があります。
そのわかりやすい例が小林製薬です。2024年3月時点、日本中を震撼させている「紅麹パニック」をここまで拡大をさせてしまったのは、社会の一般常識とズレた「ブラック危機管理」もあるかと思います。そのあたりについては、ダイヤモンドオンラインで以下のように記事にしていますので、よければご覧ください。
このマガジンでは、このような形であらゆる企業が陥る恐れがある「ブラック危機管理」の事例を紹介していくとともに、この「組織の病」を克服するにはどのような対策が必要なのかということを、実体験を踏まえてお話をさせていただきたいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
