
完全オンラインインターンを開催して、令和の新しいかたちが見えてきた
はじめに
こんにちは!採用担当の我如古です。
フルリモートワーク生活も早、丸2ヶ月になります。
私は3月半ばより採用チームにジョインしたのですが、挨拶もそこそこに画面越しの新しい同僚とコミュニケーションを取りながら業務に勤しむ日々です。
そんな「はたらく」の大変革のさなかで生まれた採用施策が”完全オンラインの2DAYSインターンシップ”。
社員も学生も全員在宅で開催した満足度100%(※)のインターン運営の舞台裏を書いてみたいと思います。
(※開催後アンケート結果)
集合型インターンから完全オンライン型インターンへ
緊急事態宣言が発令された4月初週。
「辞めるか、別の方法を考えるか、そろそろ決断したい。」
「いや、今だからこそやろう。オンライン前提のプログラムに切り替えて実施しよう。」
関係者会議にて、当社としても前例のない完全オンライン型インターン企画を進めることが決まりました。
それまでは、当社では2021年度の新卒採用選考を合格した学生のため、入社後に行う具体的な仕事レベルの経験や、現場社員、同期との交流の場を提供する機会として、進めていたオフラインの集合型インターンの準備。
3月末ごろには、新型コロナウイルスの猛威が深刻化しはじめ、様々なイベントが中止や延期を余儀なくされる中、当然、我々の集合型インターンの実施も難しいのでは…。という空気が漂っていました。ですが、せっかく学生も期待してくれている、中止にはしたくない、という思いが強く、逆にオンラインだからこそやれることを0ベースで考えてみるのもありか、と方向転換することを決めました。
完全オンラインでぶつかった壁
今回のインターンで大事にしようと掲げていたことは、同期との交流、社員との交流、リアルな仕事体験、それを実現するために、いくつかの課題を解決する必要がありました。
1.参加者同士のコミュニケーション
オンラインでのインターンに適切なプログラムは何か?オンラインでやるとなると、当然ですが物理的に隣に人がいない。みんな1人で、画面越し。集合型のように、同期や社員とのかかわりの中で刺激を受けたり、助け合ったりする機会を提供するには?という点が課題でした。
画面の向こうの学生達が、「いっしょに仕事した」という体験を得てもらうために、いつのまにかぽつんと置いてかれるようなことがないように、仲間と協業する体験の得られるグループワークを採用しました。
2.全体進行のコントロール
集合型であれば、参加者1人1人の目をみながら説明をしたり、学生側の聞き逃しやわからないことに関しても、その場で近くの社員に尋ねることができたりと、全体の足並みをそろえることができます。
しかしながらオンラインでは、全員が説明内容を理解しているか?次のスケジュールを把握しているか?これらを一望して確かめることは難しく、個々人の瞬間的な見逃した、聞き逃した、に対応することができません。
そのため、オンライン開催にあたっては以下の事を意識的に行いました。
【1】重要なアナウンスはテキストでも同時配信
→「聞こえなかった」「その場で理解できなかった」部分についての後からの見直しをカバーできた。
【2】投影スライドにはポイントや画像のみではなく、話している内容も文章で記載
→「接続不良で音声が途切れてわからなかった」を回避。
【3】開催日前に、主要連絡先/URL接続先/イベントのタイムテーブル概要を記載したPDF資料を事前配布
→なんらかの理由で離脱してしまった際にすぐに戻ってこれるよう、先の予定を把握できるように配慮。
3.適切なインターバル
そして何よりこの2日間、学生側も社員側も、約16時間もの間PCの前に張り付いて画面を見ていていなければなりません。
PC内で起こるイベント自体を飽きさせない、魅力的なものにすることもさることながら、ここにいる約40名全員の体力、気力、集中力を保つことがオンライン最大の課題だったかもしれません。
そこでインターン全体のプログラムは、人間の集中力の波といわれている15分の間隔で設計し、集中力の持続時間の限界といわれる90分に1回の間隔で大きめの休憩やコンテンツ切り替えを行うようにしました。
こうすることでイベントとして適度なメリハリをつけられたことは、最後まで離脱者のいない長時間オンラインイベントをやり遂げる上での1つの鍵だったかもしれません。
しかしながらやはり、長時間のテレワークはここ数か月のテレワーク生活で慣れている社員でさえも眼、腰に負担が来ます…
この点については事後アンケートや日報を見ても、体力的な疲労を訴える声は多く、ある程度"強制的にPC画面から離れる"小休憩をいれた方がよいかもしれないと、次回への課題となりました。
そのほか.集合型に遜色しない熱量をつくり出せるか?
やはり画面ごしだと、「場の雰囲気をつくる」という点では、ハイコンテクストな身振り手振りや表情を使えないので難しいと感じました。
そこに関しては、投影資料、BGM、言葉選びの1つ1つで緩急をつけて場のテンションを変えていくことを意図的にやることで、学生を巻き込んだ雰囲気づくりをすることができました。
オンラインインターン運営の鍵はツール活用
今回のオンラインインターンでは、以下のツールをフル活用して実施しました。
・Zoom(会議室)
・Google Spread Sheet(作業ツール)
・Slack(連絡手段)
■ Zoom
グループワークにはZoomの「ブレイクアウトルーム」機能が大変役立ちました。

ホストが学生を事前に割り当てておいた11のブレイクアウトルームにワンクリックで振り分けます。
だれがどこにいるのかは一目で把握できますし、タイムコントロールもしやすく最適な方法でした。
またあらかじめメンター社員には「共同ホスト」権限を持たせておくことで、メンターは各グルーブのブレイクアウトルームを自由に出入りし、見回りすることができます。
■ Google Spread Sheet
グループワークにはGoogle Spread Sheetを利用しました。
学生達はワークシートを共同編集しながらディスカッションを進めます。

レビューの時間になったら、レビュアー社員が担当チームのブレイクアウトルームに入室し、同じ画面をみながら企画のレビューを実施します。
■ Slack
インターン中における運営連絡、コミュニケーションツールはSlackを利用しました。
目的に応じた専用チャンネルをあらかじめ用意することで、Slackに慣れない学生達を適切に誘導することができました。
また、いつ・誰に・どこでコミュニケーションを取ればいいのかを明確にしておくことで、テキストベースのコミュニケーションルートを混乱させないメリットもあったかと思います。
#all_announce
全体への連絡用チャンネルです。
@channelメンションを付けることで、アナウンスが確実にアナウンスがいきわたります。
#daily_report
2日間、学生達には日報を投稿してもらいました。
個性豊かな日報に対し、チームメンバーや社員からにぎやかなコメントやリアクションが付きます。気付きや学びをシェアしてもらうため、共有チャンネルへの投稿にしました。
また1日目の終わりにはあだ名で呼び合っているなど、学生同士がものすごいスピードで仲を深めていくそのコミュニケーションスキルには感心させられました。
#team_a1 ~ d2
学生チームごとのチャンネルを作成。
メンターやレビュアーも参加し、メンターに向けたワーク中のタスケテ連絡や、レビュアーへの課題提出や議事録共有はこのチャンネルで行ってもらいます。
これ以外に社員用プライベートチャンネルも作成して、運営関係者はリアルタイムに社内連携をとっていました。実際に立ち回るオフラインとは違い、常にPC画面を確認できる状態のため、Slackでの連携は非常にスピーディでスムーズでした。
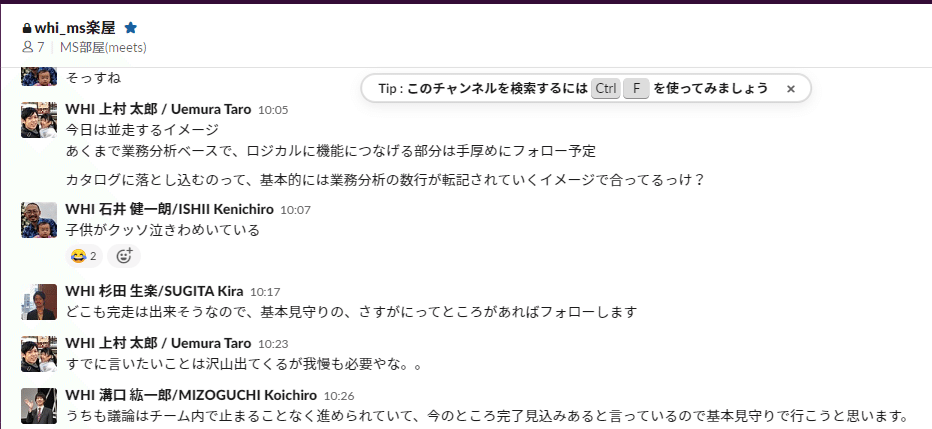
インターン当日の様子
■ Zoom会場へ集合

参加者側の音声環境チェックを兼ねて、JazzのBGMがかかるZoom会場。
参加者総勢33名が続々と集まってきます。
まずはじめにZoomの画面表示切替やリアクション機能などを試用し、簡単にZoomの操作方法を確認しました。
■オンラインインターン開幕!
ついにインターンが開幕です。
Works Humen Intelligenceの1社員として、
”若手に最高難度の仕事を”
入社0年目の君たちに、今もっとも難度が高い問題解決を任せたい。
Works Human Intelligenceのフィールドで、「はたらく」を体感しよう。
はじめに、本インターン『ZERO CAMP』に込められた思いがメッセージとして伝えられます。
そしてこの2日間、学生が取り組むプロジェクトは、新製品の企画。
チームで新製品企画を立案し、当社の現場エンジニア社員によるレビューを突破するというミッションを突破してもらいます。

また、オンラインインターン中は、学生と並走してワークの進捗状況を確認・サポートをするために、各プロジェクトチームに1人ずつ「メンター」として担当社員がつき、先輩としてディスカッションのパートナーをつとめました。
そして、メンターとは異なる社員が、「レビュアー」として、各チームが作成するアウトプット(企画書)を、現場視点でレビューし、フィードバックを行います。
このインターンの企画にあたり声をかけた現場社員の人たちは、ノリノリで協力してくれました。
いずれも当社開発の第一線で活躍するキレキレのエース級社員たち。
たとえオンラインであろうとも、安定感のあるコーチングスキルを発揮してくれる布陣です。
■ アイスブレイク
2日間のプロジェクトをともにするチーム分けを発表、自己紹介後、
グループワークへの導入としてアイスブレイクで行ったのは『NASAゲーム』です。

宇宙船の故障で、母艦から320km離れた月面に不時着した宇宙飛行士のインターン生達。かろうじて破損を逃れた15品のアイテムを利用して、生きて母艦にたどり着くというミッションです。
まずは個人ワークで15品の優先順位を考えた後、チームごとにワークシートを画面共有で表示しながら、アイテムの重要度を話し合い最終的に1~15位の順位をつけます。
実はこのテストにはNASAによる模範解答がありました。NASAの回答と自分たちのチームの回答が比べてどのように違うのか、誤差を答え合わせ。なんと、誤差16点という高成績を叩き出すチームも!

▲回答報告をする様子、スタンプも活発に活用されています。
実はこのゲーム、最も重要なことは、個の力を集結して組織の意思決定をする力。
多くの学生が、個人で考えたときよりもチームで出した答えの方が高い点数でした。個人よりも、チームで出すアウトプットの方が素晴らしいものがつくれる。そんなことを学んでほしいということを話すと、学生達は大きくうなずいてくれました。
■ 本編:本番課題に取り組む
課題内容は残念ながら非公開です。
しかし、Works Human Intelligenceが求める「はたらくを楽しむ」を実現するための問題解決に挑む課題です。
今ある正解を求める課題ではなく、前例のない状態から本質的な問題を掴み出し、誰もを納得させられるメリットがあるソリューションを生み出す製品企画となっています。
(ワークスHIの企業理念の中のValueでいうと、”Solve(本質を追求し問題を解決する)”、”Know Our Customers(お客様の価値を創造する)”を意識したものですね)
学生達はこの2日間で2回、チームで考えたアウトプットに対する現場社員からのレビューを受けます。
現場のマネージャー層による厳しくも適格なフィードバックを得ながら、学生達も負けじと思考を深め、製品企画書をブラッシュアップしていきました。
■ 成果発表
2日目の終わり。
2部屋に分かれ、同時進行で全チームが企画書の発表会を行いました。
各チームの熱いプレゼン、そしてプレゼン後にはチームのSlack上で声を掛け合いお互いをたたえ合う姿は、この2日間でオンライン上にもかかわらずチームメンバーが強い絆で結ばれたことを思わせてくれます。
最後に最優秀チームが発表され、レビュアーからの総評プレゼンテーションを経て、怒涛の2日間のオンラインインターンは無事に幕を閉じました。
■ オンライン懇親会
インターン終了後は、Zoom会場にてオンライン懇親会を行いました。
2日間を終えた達成感とともに、同期や社員とリラックスした様子で談笑したり、課題について社員からフィードバックを求めたり、賑やかな日曜の夜となりました。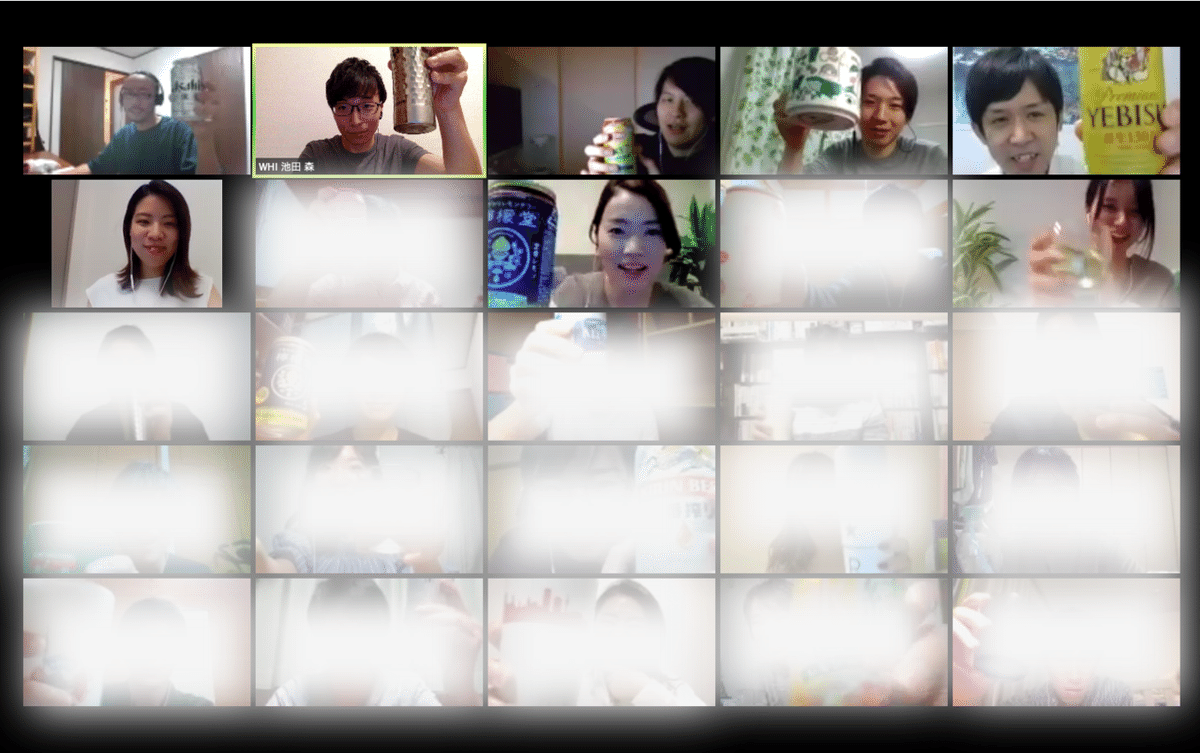
参加した学生の声
・初めはオンラインでのインターンのイメージがなかなかつかず、ディスカッションや発表などをきちんと行えるのかとても不安でしたが、オンラインだからこそ自分から自発的に意見を発信しようという意識が強まりオフラインと変わらないくらい議論ができました。(慶應義塾大学・4年)
・レビューの精度が高く、思考の抜け漏れを網羅できるような鋭いものが飛んできて、成長のためになった。(名古屋大学・4年)
・オンライン上でも実際の業務に類似したものを体験させていただくことができて良かったです。(関西学院大学・4年)
・とても良いメンバーで、学生同士で楽しめる時間が多く確保されていたのが嬉しかったです。(秋田県立大学・4年)
・この状況下で、オンラインでもこのようにインターンを経験できる機会を与えてくださりありがとうございました。(国際基督教大学・4年)
オンラインでインターンをやってみて感じたメリット・課題
■メリット
1.学生の参加機会の地域格差を埋めることができる
今回インターンをオンラインで開催したことで、秋田や北海道、九州など様々な地域の学生が追加コストかけずに参加してもらうことができました。
数百km離れた地域に住む学生同士が1チームでグループワークを行うなど、テレワークの特性を存分に生かした要素だったと思います。
2.連絡がしやすい
特に運営側の社員メンバーにおいて、横連携が取りやすいと感じました。
オフラインでは各メンバーが常にそれぞれの位置に散らばり動いていたり、また参加者に向かって何かアナウンスをしている時は当然、スマホを確認することもできないため裏で何かハプニングが起こっても把握できません。
オンラインでは一見、対面での阿吽の呼吸がとりづらいなどコミュニケーション上のデメリットが想像されますが、全員がPC画面という同じインターフェース上に集まっているオンラインでは、Slackなどでの連絡もすぐに気づくことができます。
口頭で全体にプレゼンテーションをしながら、手元ではSlackで裏方連絡を取り合うなども可能なため、連絡はむしろ取りやすいとすら感じました。
3.タイムコントロールのしやすさ
移動時間や隙間時間によって合間にロスされるアイドルタイムが少ないオンラインでは、かなり正確にタイムコントロールをすることができます。
またブレークアウトセッションなどをホスト権限で取り仕切ることのできるWeb会議は、そのツールの強制力を持って全体の行動の足並みをそろえることができるため、その点もコントロールのしやすさといえると思います。
4.「はたらく」の多様性を体現
今回インターンを運営したメンバーの半分は、小さな子どもを育てるパパママ。
真剣なレビュー中に後ろから赤ちゃんの泣き声が聞こえてくるなんてほっこりハプニングもありつつ、オフィスに拘束されないテレワークを垣間見ることは学生にとっても新鮮に映ったようで、多様化する働き方そのものをお見せすることができた機会だったかなと思います。
そして学生自身もまた、身をもって「リモートワーク」という働き方を経験。
リモートネイティブ世代ともいえる彼らにとって、この体験はどんな影響を与えたでしょうか。
■デメリット
1.長時間のテレワークによる体力的な疲労(眼・腰・頭)
学生からの事後アンケートでは1番多い意見でした。
これは上記でも書いたように強制的に休憩をいれることで軽減したいです。
「明日は午後にみんなでラジオ体操でもする?」なんてシュールな意見も出たのですが、実行ならず。
2.ハイコンテクストなコミュニケーション
事後アンケートでも2番目に多い意見でした。
特に学生同士の初対面のインターンのような場合、相手の反応が見えにくい画面越しのコミュニケーションには多少なりとストレスが伴います。
限られた時間の中で、アイスブレイクや本編以外でのコミュニケーションを通していかに信頼関係を築きやすくしてあげるかが肝だと感じました。
最後に
今回、初めて完全オンラインでインターンを実施してみましたが、結果的にオフラインに引けを取らない熱量の高いインターンシップを実現することができました。
(事後アンケートでは、「良かった」の声が100%!)
そして、これからは企業イベントも、双方の体験が生み出すメリットとデメリットを理解したうえで、目的や内容に応じてオンラインとオフラインの両方を使い分けることができる、そんなアフターコロナ時代の働き方を確信した2日間でした。
以上が弊社で実践した完全オンラインインターンの振り返り。
学生のファーストキャリアが「たのしい」ものになるよう、これからも積極的にインターン始め様々な機会を提供してまいります。
\ワークスHIの採用サイトはこちら/
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
