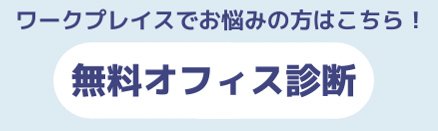出社義務を理由に、働くことを諦めてほしくない。全社フルリモートに切り替えたことで、見えたものとは
「働きたい思いのある人を、働き方で応援したい」という強い気持ちで働き方改革を進めている株式会社ノヴィータさま。試行錯誤の末、現在は全社フルリモートで業務を推進しています。会社と社員の間で、お互いに期待することのすり合わせを定期的に行う代わりに、時間や場所などが柔軟で自由に働けるあり方「リベラルワーク」を提案されています。
同社が辿った軌跡と、フルリモートのリアルについて、代表の三好さまにお話を伺いました。
株式会社ノヴィータ
設立:2006年
事業内容:WEBマーケティング支援、コンテンツ企画制作、人材サービス等
オフィス:東京都港区南青山2-7-23-301
フルリモートは「柔軟な働き方を提供したい」という想いから。みんなが働きやすい環境を目指し、重ねた試行錯誤
コロナ前から「柔軟な働き方」を実現するため、様々な取り組みをされていたノヴィータさま。まずはその働き方の歴史を振り返ります。
■設立~2016年:出社が基本の勤務形態
・客先常駐や週3日勤務などはあるものの、フルリモート勤務の人はいなかった
・2016年、代表・三好さまが出産。当事者として育児と仕事の両立のあり方に悩み、柔軟に働ける就労環境の必要性を痛感した。子連れ出社に端を発し、柔軟な働き方を模索し始める



■2017年:初のフルリモートメンバー誕生
・地方転居を機に、1名のメンバーがフルリモートに転向
・面談や顧客対応など、フルリモートでは対応できない業務が明らかに
■2018年~2019年:豊岡と会津にオフィスを開設
・採用フローのオンライン化を開始。入社時からフルリモート勤務する地方メンバーの事例も
・情報をフォローする側、される側の認識差が生まれやすく、連携のハードルに
・この時点で全体の3割ほどがリモート勤務に移行
・ただ、本社の出社率はまだ高く、チェアを総入れ替えするなどオフィス環境も重要視

■2020年~現在:全社フルリモートへ
・コロナの感染拡大を受け、いち早く在宅勤務を推奨。ハード面の体制は整っていたので、期間限定でフルリモートにチャレンジ
・チャレンジ当初挙がった懸念の解消が見込め、かつ生産性の低下がみられなかったことから半年後に全社フルリモートへの完全移行。オフィスも思い切って1/4程度まで縮小
・機器や什器などを、従業員の希望に合わせて各自宅へ配送
・現在も全社フルリモートを推進中


メンバーのライフスタイルの変化や社会情勢に合わせて、柔軟に働き方を工夫してきたという同社。現在も、必要に応じてオフィスも利用しながら、無理なくフルリモートで業務を進められているそうです。
全社フルリモートへの移行は、思いがけないことの連続。良いことがたくさんあった一方で、課題も浮き彫りに
リモートワークで感じたメリット・デメリットや、課題解決に向けた取り組みについて、代表の三好さまに伺いました。
── 現在は全社的に原則フルリモートワークだそうですが、具体的にどのようなメリットがあるのか教えてください!
三好さま:まず単純なところでいうと、感染症に罹患するリスクが低くなることですね。メンバーの安心感にも繋がっていると思います。それから、通勤時間が削減されたのも良いですね。「通勤ストレスから解放されて嬉しい」という声をよく聞きます。
あとは、業務における「待ち」の時間を有効活用できるようになりました。ちょっとしたスキマ時間に家事を進めたり、家族と話をしたり。「オン」の時間の中に「オフ」の時間を生むことができます。休憩の取り方などは各人の自己管理に任せていますが、今のところ問題はなく、むしろ在宅勤務をするようになってから生産性が上がりました。また、「家族や子どもに仕事を身近に感じてもらえる」と喜んでいる方もいます。ミーティングの様子を家族に見せたり、仕事に取り組む雰囲気を共有することで、仕事への理解と興味を深めてもらえたら嬉しいですよね。
働き続けるための選択肢が増えたことも、大きなメリットだと思います。病気や怪我、育児や介護などにより、長時間の外出が難しくなるという状況は、誰にでも起こり得ることです。そんな時に「在宅でも勤務できる」という選択肢があるだけで、働くことを阻害する要因が一つ減ります。会社としても大切な人材を失わずに済みますし、双方にとって良いことだと思います。
課題に直面してもマイナスに捉えず、積極的にフォローしたい。「時間や場所にとらわれない働き方」は、自分たちで実現していくもの
── リモートワークを始めて、良いことが沢山あったのですね!逆にデメリットと感じた点はありますか?
三好さま:やはりコミュニケーションの質の低下や、会話量の減少は課題になりました。特に、業務に直接関係のない「雑談」は、なかなか積極的にできないメンバーもいるようでした。こうした状況が続いてしまうと、例えば「体調が悪い」「プライベートが大変そう」など、オフィスにいる時には察することができたものに気づけなくなってしまう、と思いました。物理的に顔を合わせなくなったからこそ、「最近どう?」というラフなコミュニケーションの大切さを痛感しましたね。
最近入社したメンバーの中には、対面で他メンバーに会ったことがほとんど無い人もいます。会わないことが心理的な壁になったり、気持ちの不調に繋がってはいけない、と思っています。
リモートだと察することができず、自分から言ってもらえないと気づけないので、会社と社員、上司と部下などにおいて、何かあれば言ってもらえるような信頼関係も大事です。オンラインでもコミュニケーションを活性化するため、工夫を重ねています。

── コミュニケーション促進のために、例えばどんなことをされているのですか?
三好さま:「よもやま会」という、オンラインで雑談する会を催しています。お昼の時間などにオンラインで集まって、ざっくばらんに話ができる場として活用されています。「平成生まれの会」「ママ同士の会」など、参加テーマを決めて、より集まりやすくすることもありますよ。「平成生まれの会」は特に、一人暮らしなどだとさらに話す機会が減ってしまう若手のメンバーに対し、社内の人ともっと会話しやすくするきっかけになればと思い、開催しました。やはり、若手メンバーの方が遠慮などもあって「雑談しづらい」「オンラインで声を発しづらい」という傾向が強かったように思えるので、「よもやま会」を通じて話しやすい相手が増えていったら良いなと思います。
また、コロナを機に、週1で朝会を行うようになりました。普段他のメンバーの仕事が見えづらい分、丁寧に情報をインプットし、全体の理解を深めてもらっています。情報のアップデートだけでなく、意見を募ったり議論をしたりと、相互的なやりとりも増えてきました。それから、月に一度、LT大会(Lighting Talk大会)というショートプレゼンの場も設けています。日々の業務での気付き、目標と経過などを発表してもらっています。LT大会はコロナ前から行っていたのですが、フルリモートになってからは、インプットできる機会やコミュニケーションできる機会としての活用を模索するべく、別途とっているアンケートをもとに小さい改善を繰り返しています。
共有の場として一番大規模なものは、年に2回の総会です。コロナ前は会場を借りて集まっていましたが、今はオンラインで行っています。上期・下期の総括や、今後の方向性など、改めて全員で同じ方向を向くための大事な会です。
日々の業務では、チャットだけでなく音声通話ツールも積極的に使い、雰囲気の伝わるコミュニケーションを心がけています。音声での会話は「ついでの雑談」もしやすいですし。そして役員やマネージャーを中心に、「いつでも話しかけていいよ」というメッセージを日頃から発信することで、コミュニケーションのハードルを下げています。在宅交流手当を新設したりなど、喚起の甲斐もあってか、最近はオンラインでも気軽に雑談している場面や、業務外の遊びの誘い(夜に一緒にゲームしませんか?など)をしあう場面も見るようになりました。
在宅勤務では、他のメンバーと空間を共有していない分、放っておくと気持ちの距離ができてしまい、自然なコミュニケーションがしづらくなりますよね。それを防ぐために、出社を促している会社もあると思います。オンラインでこの問題を解決するのは容易ではありませんが、当社は積極的にチャレンジをしています。「リモートワークで得られる柔軟さ」を諦める理由にはしたくないからです。まだまだ課題はありますが、今後もフォローを徹底し、より快適に仕事ができる環境をつくっていきたいと思います。
多様な働き方を選択できる「リベラルワーク」を目指してきたノヴィータさま。フルリモートのおかげで地方の採用も増え、今では全国に社員がいます。中には介護や転居といった理由で、仕方なく前職を離職してしまった方もいるそうです。「そういう理由で仕事を辞めてしまう方を減らしたい」「むしろ辞める理由にならないよう、会社の制度を変えていきたい」とのこと。
代表の三好さまは、「フルリモートは自己管理や積極性が求められるため、合わないと感じる方も一定数いると思います。ただ、やり方次第で工夫ができることも経験でわかってきたので、どんなサポートをすれば働きやすくなるか、今後も考えていきたいです」と話していました。

さらなるご成長を楽しみにしています。この度はありがとうございました。
(執筆:呂 翔華、写真:ノヴィータさまご提供)
👇ワークプレイスに関するご相談は、こちらをクリック!