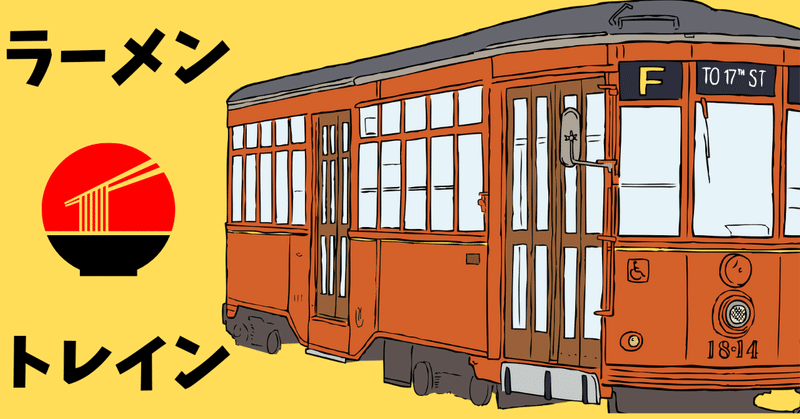
【アジカンSSのお時間③】ラーメントレイン
数年ぶりに地元へと帰ってきた。
都内の大学を卒業し、そのまま東京で就職したこともあって、なかなか戻ってくる機会がなかった。たまたま実家近くへの出張が入り、おれは久しぶりに地元の温泉にでも浸かろうと、市内を走る路面電車の停留場へと向かった。
十一月にもなれば、日が暮れるとすっかり冷え込んで、吐く息も白い。かじかむ手を温めようと両手を擦り合わせながら停留場に着くと、すでに電車が到着していた。一両編成のオレンジ色の車体を見ると、地元に帰ってきたんだなぁという懐かしさが溢れてくる。
が、その見慣れたはずの車体にある違和感を覚えた。電車後方のドア横に赤提灯がぶら下がっているのだ。
「ラーメン?」
灯りがともった赤提灯はラーメンの屋台を想起させる。とはいえ、鉄道会社のフェアか何かの飾りだろうと思い、そのまま電車へと乗り込んだ。
「いらっしゃいませぇ!」
乗車すると活気ある声が車内に響き、目の前に広がる光景におれは目を疑った。
コの字型のカウンターが車内の真ん中に設置されていて、もくもくと白い湯気が立つほどのお湯が寸胴に沸き、湯切り用のテボが置いてあった。重ねられたどんぶり。セットされた具材やタレやスープの並び。カウンターには卓上調味料。どこからどう見ても、ラーメン屋のようだった。
「お好きな席にどうぞ。まもなく出発の時刻です。あっ、お冷はセルフでお願いしますね」
カウンターの中にいるタオルを頭に巻いた男は、ブロックのチャーシューを厚めに切っている。
前方の運転席には、運転士が座っているので路面電車なことは間違いないはずだが、信じられない光景だった。
座席に座ると、カウンターの高さに合わせて設計されていることがすぐにわかった。ドアが閉まり、運転士の車内アナウンスを合図に、ゆっくりと電車は出発した。
とりあえず、お冷をコップに注いで一口飲み、落ち着くことにした。
「あのぉ、これは何かの催しですか?」
もしかしたら、一種の観光列車のようなもので、おれが知らないうちにこういうスタイルの電車が地元に浸透しているのかと考えた。
「お客さん、うちはここで営業している、正真正銘のラーメン屋ですよ……冷やかしのお冷じゃないんだ。文句があるなら……あれ? ひょっとして、一条か?」
突然、自分の苗字を呼ばれたもので驚いて、男の顔をよく見てみる。
「えっ、百田監督じゃないですか! ご無沙汰しています!」
「おぉ、立派になったなぁ。髪も伸びたんじゃないか?」
その男はおれが高校時代の野球部の監督だった。厳しさの中にもユーモアのある監督で人気があった。高校卒業以来の思わぬ再会に、さっきまでのぎこちない雰囲気も和んでほっとする。監督の笑顔は相変わらずだけど、くっきりと刻まれた深い皺からは月日の経過を感じた。
「それにしても、びっくりしました」
「あぁ、指導者は引退してな。昔からの趣味が高じて、ラーメン屋を開いたんだ。セカンドライフってやつだな」
風の噂で監督が野球部の監督を勇退したことは知っていたが、まさかラーメン屋をオープンしていたとは知らなかった。
「でも、路面電車に店を開いちゃうとは」
「本当は屋台のラーメン屋を開きたかったんだが、許可が下りなくてな。それでも、なんとか店をオープンできないものかって探していたところに、路面電車の一両オーナーの話が舞い込んできてな。特大ホームランの幸運だったよ」
腕を組み、いかにもラーメン屋の店主という佇まいの監督が感慨深げに経緯を語ってくれた。
「それにロメンとラーメンって、なんか似ているだろ」
「ちょっと無理ありませんか?」おれは苦笑する。
「まぁ、とにかくだ。終点に着くまで、食べていってくれよ。おれの特製醤油ラーメンを」
監督は木箱から麺を一玉とりだすとテボに入れて、沸騰したお湯に投入した。さっき切っていたチャーシューがバーナーで炙られ、香ばしい匂いに食欲を刺激される。お湯で温めていたどんぶりに醤油ダレと油が入れられ、スープが注がれる。茹で上がった麺はしっかりと湯切りされ、どんぶりに移されると、手際よく具材が盛りつけられていく。
「特製醤油ラーメン、お待ちどおさま!」
監督のこだわりが詰まったラーメンが、おれの目の前に着丼した。
「いやぁ、見た目も最高ですね。いただきます!」
まずはスープを一口すすってみた。醤油感の強いスープだが、その奥には鶏ガラや魚介の旨味も感じられる。
「う、美味いです、このスープ。なんていうかキレがありますね」
電車はちょうど信号待ちで停車しているところだった。外はもうすっかり夜になっていて、車や自転車のライトが点灯している。
「教え子に褒められるのは作りがいがあるねぇ。キレといえば、一条の投げる球もキレがあったよなぁ」
「よしてくださいよ、監督。昔の話です」
おれは高校時代、野球部の投手でエースだった。
直球のキレと変化球の緩急でバッターを押さえる投球スタイルを持ち味としていた。
ふと街の景色を見ようと後ろを振り返ってみると、車窓には街並みではなく、高校の野球場のブルペンで投球練習を繰り返すおれの姿が映っていた。
こんな頃もあったなぁ、と懐かしんでいるうちに電車は次の停留場に到着した。
「いらっしゃいませぇ!」
「もしかして監督に一条? なんでここに? ってか、なんでラーメン屋?」
なんと二つ目の停留場から乗車してきたのは、高校の野球部でおれの球を受けてくれていた捕手の二川だった。
県内に住む二川も久しぶりに地元に帰省していて、終点にある温泉に行くところだったらしい。なんとも不思議な夜だ。
ラーメン屋の成り立ちやお互いの近況を話しているうちに、二川の特製醤油ラーメンも着丼した。
「スープも美味いですけど、この麺も抜群ですねぇ。もしかして、自家製麺とかですか?」
箸上げした麺をフーフーしながら、二川が言った。
「よくわかったなぁ。さすが主将だよ。毎朝、自分で製麺しているんだ」
「この麺がよくスープを持ち上げてくれますし、麺自体も腰があるっていうか」
二川が豪快にズズズッと麺をすする。
「腰といえば、二川も腰があったよなぁ。捕球の構え方もどっしりとしていたし、豪快なバッティングも腰が入っていた」
監督が車窓を眺めると同時に、おれたちも後ろを振り返ると、車窓にはホームベースの後ろでキャッチャーミットをどっしりと構える二川の姿が映し出されている。公式戦で場外ホームランを打ったこともあったよなぁと思っていると、そのシーンも続けて車窓に流れたから驚いた。
「今となっちゃ、腰よりも腹がでちゃいましたよ」
二川がぽこんと膨らんだお腹をさすりながら笑っていると、電車は次の停留場へと到着した。
「いらっしゃいませぇ!」
「一条に二川、それに監督まで! 久しぶりぃ」
次に乗車してきたのは、これまた野球部で一緒だった内野手の四木だった。
地元に住んでいる四木もなんと温泉に行くところだという。
三人で喋っているうちに、四木の特製醤油ラーメンも着丼した。
「海苔と麺って、一緒に食べると最高ですよねぇ」
醤油スープに浸した海苔を麺に巻くようにして、四木が麺をすする。
「四木はチームのムードメーカーだったよなぁ。ノリがいいっていうか」
「そうでしたっけ? いつもこんな調子なんで。おっ、このメンマ、グローブみたい」
きれいに盛りつけられた茶色のメンマは確かにグローブのようにも見える。
「セカンドの守備範囲も広かったよなぁ」監督が懐かしそうに思いだす。
「よしてくださいよ。なんかラーメンが熱々のせいか、水がうまいっすねぇ」
四木の照れ隠しに笑いながら、三人で後ろを振り返って車窓を眺めると、センターへと抜けると思われた強い打球に四木が飛びついて捕球し、アウトにしたファインプレーが流れた。
電車はS字カーブをギギギギッと曲がり、次の停留場へと到着した。
「いらっしゃいませぇ!」
「みんな、監督、どうして?」
次に乗ってきたのは、同じく野球部で外野手だった七瀬だった。
七瀬もまた久しぶりの地元らしく、温泉に行くところらしい。話しているうちに、七瀬の特製醤油ラーメンも着丼した。
「おれは煮卵からいこうかなぁ」
和やかに予期せぬ再会を楽しみながら、よく浸かった煮卵を七瀬が箸で口に入れようとしたときだった。
箸からすべり落ちた煮卵が、スープの中へとぽとりと落ちたのは。
慌てた七瀬はレンゲを床に落としてしまい、車内にカランカランとレンゲの転がる音が響き渡った。
「そういえば、最後の夏の試合も七瀬が落としたっけな、レフトフライ」
二川がふと思いだしたように語りだした。車内が静まり返る。かじったチャーシューの焦げた部分もなんだかやたら苦く感じた。
「慌てる必要はないんだ。あのときだって、慌てる必要はなかったんだよ」
二川が新しいレンゲを七瀬に渡しながら、語気を強める。
「ちょうど太陽とボールが重なったんだよ。もう過ぎたことだろ?」
七瀬は落としたレンゲを拾うと、煮卵を箸でつかみ、口へと放り込んだ。
「その後の送球はどうなんだよ? 慌てたせいでホームベースから送球が逸れて、それで逆転されて……おれたちの夏が終わったんだろ」
二川がお冷を一息に飲み干し、空になったコップをカウンターに強く置いた。
「よそうぜ、せっかくの再会なのにさ」
車内に流れる険悪な空気を感じとった四木が二人の間に割って入った。
「そういう四木だって、エラーして決勝点のランナーを出塁させただろ」
二川がお冷を注ぎながら、その矛先を四木に向ける。
「はぁ? そういう二川だって満塁のチャンスで凡退したよな。あそこで点をとれていれば、流れはだいぶ変わっていたはずさ!」
「なんだとぉ!」
「もうやめようよ、なぁ!」
車窓に流れる最後の試合の悔しいハイライトを見て、おれは悲しい気持ちになり叫んだ。ほろほろと崩れていくチャーシューのように、楽しい時間も崩れていくようだった。
監督はじっと黙ったまま、おれたちのやりとりを見ていた。
「あのとき、実はおれさ、指先にマメができてたんだ。最後の送球が逸れたのはそのせいかもしれない」
七瀬がチャーシューを噛みしめながら、あの日のことを打ち明けた。
「お前、そんな大事なこと今更いうなよ! 試合中にいえよ!」
二川がほうれん草を食べるのを見ながら『報・連・相』という言葉が頭をよぎる。
「みんなで勝ちたかったんだよ! 最後まで戦って勝ちたかったんだ。ごめん……」
七瀬が最後の麺をすすり終え、すすり泣く。
「おれだってさ、悔しかったよ。エースとして、初回に三失点したのは大きかった」
残ったスープにコショウを振りながら、おれはずっと考えないようにしていた辛い記憶を口にした。
「お前がいたから、チームは決勝戦まで勝ち上がれたんだ。攻めることはないよ」
三年間バッテリーを組んできた二川が最後に残った煮卵を食べながら、おれをかばった。
「なら、七瀬だって同じじゃないか? 七瀬の守備や強肩に救われた試合だって、たくさんあった」
おれもほうれん草を食べながら、二川に本音をぶつけた。
そこで、ずっと静観していた監督がついに口を開いた。
「お前たちは本当によくやったよ。あの最後の試合、おれは自信を持ってメンバーを決めて、試合に送り出したんだ。誰が欠けてもだめだった。ラーメンだってそうだ、スープや麺だけじゃだめなんだ。必要な具材が揃ってこそ、ベストな一杯が完成するんだ。三年間の集大成をお前たちに託そうと思った。そう、おれが決めたんだ。お前たちは最高のメンバーだよ」
スープをレンゲで掬って飲みながら、おれはとても救われた心温まる気持ちになった。
「だから、胸を張っていい。ぐるぐると変なことは考えないでいい」
そう言うと、スライスしたなるとをおれたちに見せて、監督はむしゃむしゃと食べた。
四人して同時に笑うと、なんだかとても気が楽になったから不思議だ。
「確かに、七瀬の強肩には何度も助けられたよ。お前の気持ちも考えないで悪かった」
二川はどっしりと構えると七瀬に頭を下げて謝った。
「二川がチームをまとめてくれたから、三年間やってこれたんだぜ」
四木がすぐに二川をカバーする。
「ピンチを背負ったときの四木の掛け声には、いつも肩の力を抜いて投げれた。ありがとう」
おれも直球で四木に感謝を伝えた。
「一条が投げていると、守りにもリズムが生まれて試合が締まったよ」
七瀬の言葉の送球は、おれの心のど真ん中へと届いた。
「ありがとうございましたぁ!」
特製醤油ラーメンを食べ終えると、四人で監督に挨拶をした。
運転士のアナウンスが聞こえてくる。電車が終点へと到着したようだった。
「とても心に沁みる一杯でした。おいくらですか?」
電車のドアが開き、おれは運賃箱の前で監督に尋ねた。
「なーに、ここは奢らせてくれ」
「監督……ご馳走様です!」
ラーメンどんぶりのように器のでかい監督の気持ちを、おれたちは有り難く受け取ることにした。
電車を降りると、三人は肩を組んで温泉へと歩きだしていた。
真っ白いユニフォーム姿が三つ、夜の闇に浮かび上がっていて、おれは駆け足で後を追いかけた。
文章や物語ならではの、エンターテインメントに挑戦しています! 読んだ方をとにかくワクワクさせる言葉や、表現を探しています!

