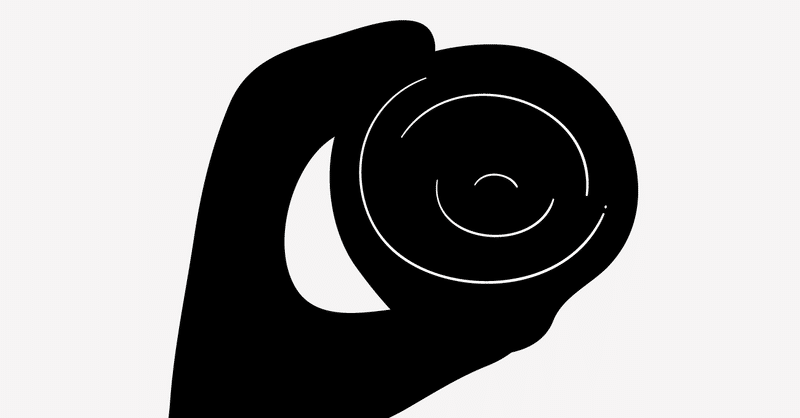
Photo by
hamahouse
記憶に残したい物語がある地酒・北九州の「猿喰1757」
最近晩酌のお酒をビールからオーガニックワイン(赤)、そこから日本酒に変えた。
持病の腰痛に冷えは悪影響で、それならばとオーガニックワインに変えたけど、胃弱な自分にはちょっと重たくて。
他にいいお酒は無いかな〜と思っていた頃、出かけた先のお店で飲んだ熱燗がピタリと来た。
ビールやワインだとグイグイいってしまうけど、日本酒はチビチビ楽しめるのがいい。

それ以来晩酌はもっぱら日本酒。
説明表示を見て「ふむふむ、これは北陸の白山の水で作られたのか(行ったことないけど)」などと旅行気分で読むのも楽しみである。

そんな折、先日立ち寄った産地直売所で出会ったお酒が「猿喰1757」。
我が町、北九州のお酒。
北九州の地酒として知られる「天心」の蔵元「溝上酒造株式会社」が造っている日本酒で、溝上酒造は門司のある人たちに依頼されて造ったとある。
お酒のラベルには、この猿喰1757の物語が書かれていた。

門司猿喰産酒造米
吟の里100%
特別純米酒 猿喰(さるはみ)1757
宝暦七年、飢饉に苦しむ民を救うため、大里村の庄屋・石原宗祐は庄屋を辞し、弟の柳井智達と共に猿喰湾の干拓に着手しました。
宗祐は現在の17億円に相当する私財を投じ、2年に及ぶ難工事の末に、約33ヘクタールの「猿喰新田」を干拓しました。さらに溜め池と「汐抜き穴」も造成し、着工から16年を経て、ようやく新田から米が獲れるようになりました。
以来門司では飢饉で死者を出さなかったと伝えられており、完成から二百数十年を経た今も、新田は豊かな実りに恵まれています。
宗祐翁の偉業を語り継ぎ、新田が継承発展される事を願って、かつて人々の命を救った田園で酒造米を育て、日本酒を醸しました。
江戸時代の飢饉を救い、新田開拓に尽くした庄屋の子孫ら地元有志による発案でこのお酒は生まれたらしい。
1732年の享保の大飢饉によって、大里村の死者は100人超。
庄屋をやめて私財を投げうった石原宗祐を駆り立てたものとは。
大人になってから本州から北九州にやってきた自分は、北九州のことを知っているようで知らないことが多い。
ありがたくいただきます。
猿喰の関連リンク
買ったお店「海と大地」(産直市場のお酒コーナーにありました)
猿喰の通販サイト
猿喰が飲めるお店
猿喰新田について
猿喰新田の場所
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
