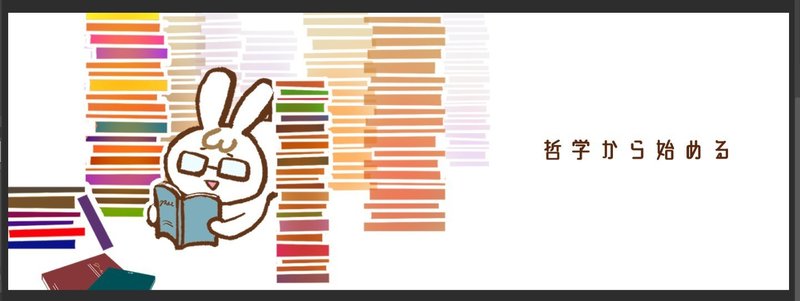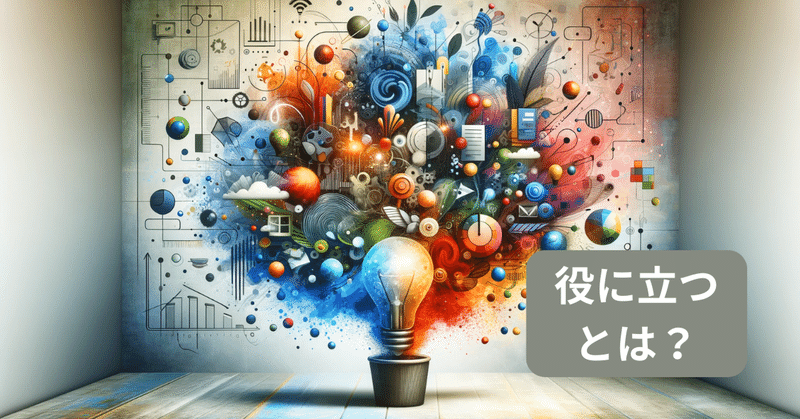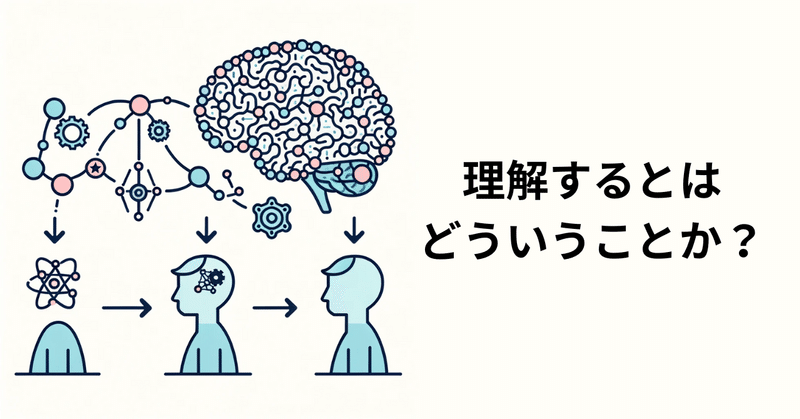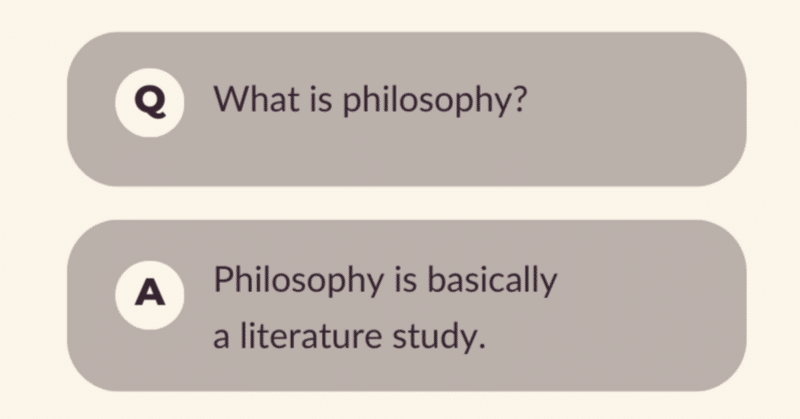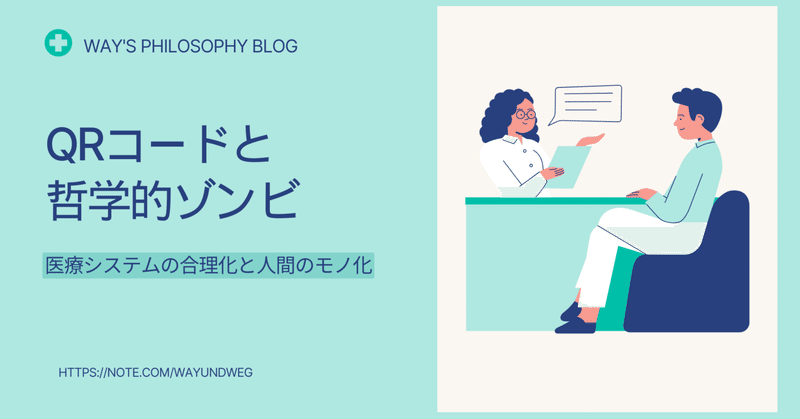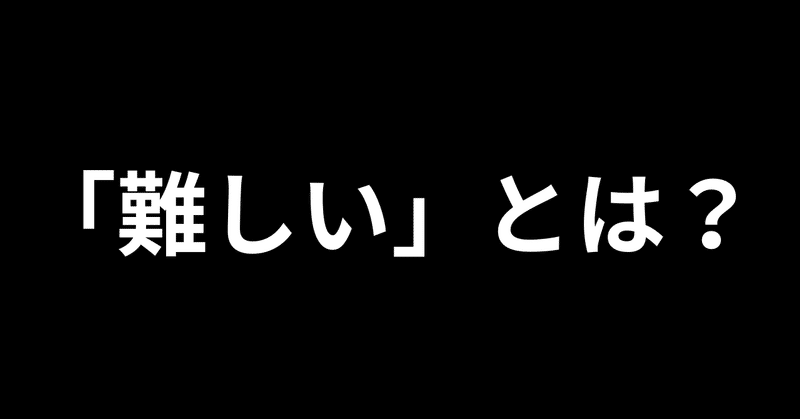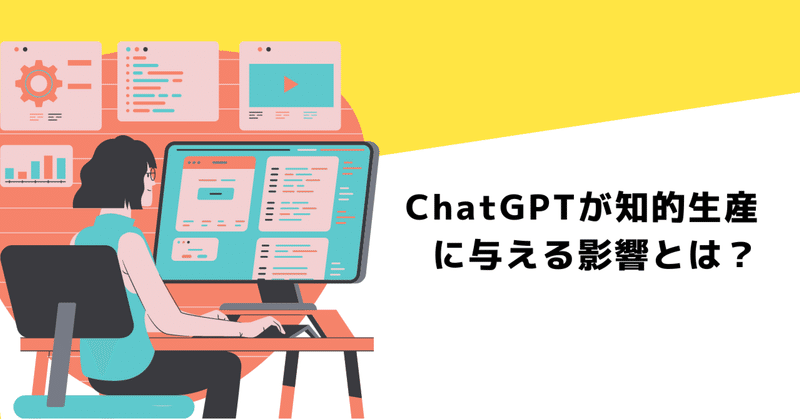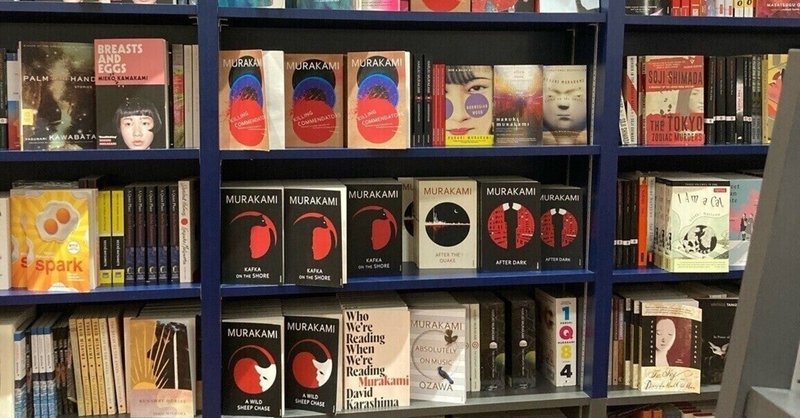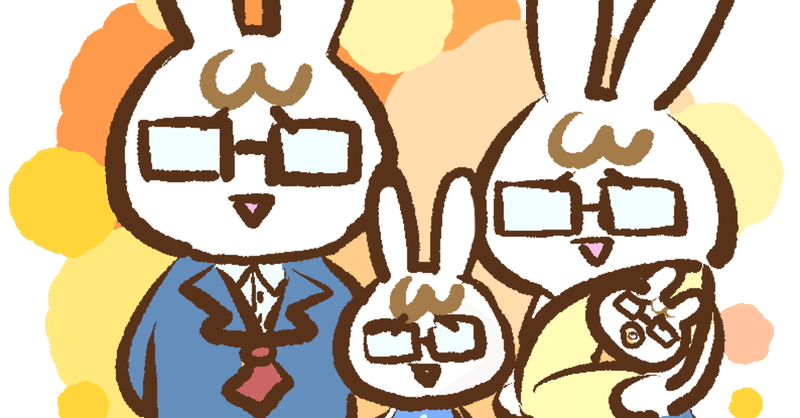#哲学

哲学って何?難しい?その概要と学ぶ意味を哲学科卒が解説 | 哲学ラジオ
本シリーズは哲学科卒の私うぇいが、哲学っぽい話題をざっくり解説する音声コンテンツです。今回は「哲学とは何か」について話しました。 ▼使用文献 〇自分で考えること(啓蒙とは何か) イマヌエル・カント『永遠平和のために/啓蒙とは何か 他3編』中山元訳、光文社古典新訳文庫、2006年 https://amzn.to/4bVBMQe 〇哲学は毒でもあり薬でもあるということ プラトン『パイドロス』藤澤令夫訳、岩波文庫、1967年 https://amzn.to/3VIPtwn 高橋哲哉『デリダ──脱構築と正義』講談社学術文庫、2015年 https://amzn.to/45rPQyl ▼関連文献 千葉雅也・納富信留他『哲学史入門I──古代ギリシアからルネサンスまで』NHK出版新書、2024年 https://amzn.to/3KJ5CLP ピーター・ギブソン『1冊で学位 哲学──大学で学ぶ知識がこの1冊で身につく』上野正道・屋代菜海訳、2022年 https://amzn.to/3yV6tX5 岩田靖夫『ヨーロッパ思想入門』岩波ジュニア新書、2003年 https://amzn.to/3Xn7wcw 信原幸弘編『ワードマップ心の哲学──新時代の心の科学をめぐる哲学の問い』新曜社、2017年 https://amzn.to/3xFxKfw 鈴木生郎・秋葉剛史他『ワードマップ現代形而上学──分析哲学が問う、人・因果・存在の謎』新曜社、2014年 https://amzn.to/4b4H6QE 植村玄輝・八重樫徹・吉川孝編『ワードマップ 現代現象学──経験から始める哲学入門』新曜社、2017年 https://amzn.to/3QkTELI ※本リンクはAmazonアソシエイトプログラムの一環として設置されており、これらのリンク経由での購入により筆者に収益が発生します。 ▼欲しいものリスト(支援オナシャス) https://x.gd/GqyMQ 〇個人的激おすすめサービス:Amazonオーディブル https://amzn.to/45gafGM ▼SNS 〇note:うぇい@哲学 https://note.com/wayundweg/ 〇X:うぇい@オススメ書籍紹介 https://x.com/wayundweg 〇YouTube:【哲学】うぇいちゃんねる Way Channel https://www.youtube.com/channel/UCf81tQ5gTlhfwkoLuWWquhw