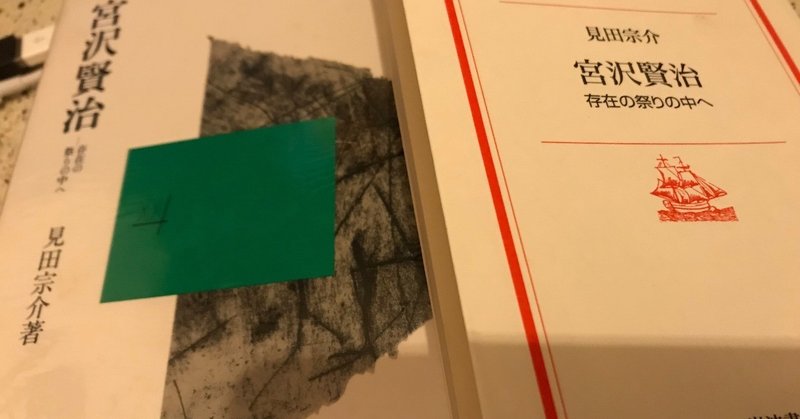
りんごの芯へ沈み込む凹みは中なのか外なのかー読書メモ:見田宗介著『宮沢賢治 存在の祭りの中へ』
目に見える光景よりもスマホの画面を「通して」みる世界の方がリアルという経験
多摩の夜は暗い。
深夜の京王線に揺られながら、ふと窓の外に目を向けても、ここがどこだか識別できるような視覚情報は飛び込んでこない。ただ暗く、まばらな電灯たちが同じ方向に、同じ速度で飛び去る。
それを見ていると、こちらが動いているのか、あちらが動いているのか、分からなくなりそうだ。
乗り慣れた路線である。昼間であれば、外の景色を見れば、どの駅とどの駅の間を走行中かすぐに分かるというのに。不意に「乗り過ごしているのではないか?!」という不安に取り憑かれる。慌てて窓の外を見る。しかし、そこには相変わらず、闇夜「が」流れていくだけである。
そんなときはスマホでGoogle Mapを開くに限る。GPSの人工衛星のおかげで、私はわたしが今どこを移動中か、すぐに知ることができる。
肉眼に飛び込んでは飛び去る車窓の闇夜の瞬きよりも、むしろスマホ画面の中のGoogle Mapに示された小さな青い丸印の方が、より確固とした「リアル」に感じられる。闇夜に目は無力であり、目の「ぬし」である私も無力である。
数千年前のGoogle Map
古の旅人も、茫漠として不安定な足元の地上や海面よりも、毎夜毎夜同じパターンで光り始める夜空の星々の方にこそ、より確固とした、正確で、安定した、信じるに足る、約束を違わない世界を、つまり人が安心してその「中」に確かに存在していると感じられる親しい場所という感じを、覚えることができたのかもしれない。
天上にこそ本来の、約束されたあるべき世界があり、地上はそこからこぼれ落ちた不完全で不安な場所である。といった感じ。そうした観念を支える感覚レベルの経験は、おそらく夜空の星々が描くパターンのあまりの正確さによるのだろう。
りんごの芯へ沈み込む凹みは中なのか外なのか
見田宗介氏に『宮沢賢治』というタイトルの著書がある。
夜を走り抜ける電車に揺られていると、「りんごの中を走る汽車」という賢治の詩から始まる同書のことを思い出す。
「りんごのなかをはしつてゐる」
内と外、内部と外部、表と裏。あるいは私と他者。
人間と動物。
私と、ごく親しい死者。
私の「いまここ」と、もう個々の名前もわからなくなった祖先たちが生きたそのときその場所。
饒舌なコトバと、無言。
それらの区別がなくなり、同時にどちらでもありうるし、どちらにでも転じ得るような中間状態。あるいはまさにそうした区別を再開しようとしている瞬間。
りんご、というのは「それ自身の深奥の内部に向かって一気に誘い込むような、本質的な孔をもつ球体である」と、見田氏は書く(p.5)。
この「りんご」のように、宮沢賢治が書いたものには、区別がゆらぐ瞬間がよく登場する。いつもはしっかりと区別され、互いに通行することも、コミュニケートすることもままならないような境界。そこにつかの間、通路が開き、こちらとあちらが行き来できるようになる。こちらがあちらになり、あちらがこちらになる。『注文の多い料理店』も『銀河鉄道の夜』も、この手のお話だ。
しっかりしたものと区別されている間だけ、かろうじて私も「しっかりしたもの」になる
区別がゆらぎ、境界がひらく。そしてまた、通路は閉じる。
「こちらの私」というものも、この区別、いくつもの区別の後から、かろうじてその輪郭が区切りだされるものである。
私と他者との関係、私とモノとの関係、私と動物の関係、私と私以外の何かとの関係。
ここでいう関係は、もともと居る私と他者とが、後から出会い取り結ぶ関係ではない。この関係とは、私と他者を「同じであるが違うもの」として 区別する「こと」である。
そうした関係がたくさん、無数に寄り集まった場所が「わたし」なのである。
私は他者である。私は他者たちである。
私は他者たちのコトバが、互いに矛盾し、調停することなど到底不可能なコトバたちが、むちゃくちゃに撚り集まって束になったものである。
その束のより集まり方、捩れ方が、あの他者でもこの他者でもない、他者一般とも違う、「私という他者」の個別性を区切りだす。
私は多数の相容れない意味の間の矛盾に引き裂かれつつ、矛盾を引き受けさせられるところで「ひとつ」である。
にんげんの身をつつんでいることばのカプセルは、このように自我のとりでであると同時に、またわたしたちの牢獄でもある。人間は体験することのすべてを、その育てられた社会の説明様式で概念化してしまうことで、じぶんたちの生きる「世界」をつくりあげている。本当の<世界>は、この「世界」の外に、真に未知なるものとして無限にひろがっているのに、「世界」に少しでも風穴があくと、わたしたちはそれを必死に<がいねん化する>ことによって、今ある「わたし」を自衛するのだ。p.191
関係の中で区別され続けること、区別が「安定的に」再生産され続ける時にだけ、かろうじてその安定した姿を知覚できる代物。それが「私」である。
私ははじめから最後まで矛盾に引き裂かれながら、矛盾を矛盾として「見る」ことができる。いや、見ざるを得ない。
この矛盾に気づいてしまい、事あるごとにそれを思い知らされる「受け身」の主体が、わたしたちひとりひとりの「わたし」がたったひとりのほかではない「私」の個別性であるということなのである。
おわりに
スマホどころか、VRにAIにと、「わたし」を拡張するメディアはますます感覚器官と、神経の中枢に直接絡みついてくる。
そのとき「わたし」たちは、いったい複数の意味の「矛盾」に引き裂かれる苦悶を、耐え抜くことができるのだろうか。
あるいは、例えば、Google Mapの便利でスマートな地図。そこに表示された「地名」という文字列を、これを祖先たちの声の残響として聞き取ることができる耳のようなものを、VRは育てることができるのであれば…。
おわり
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 いただいたサポートは、次なる読書のため、文献の購入にあてさせていただきます。
