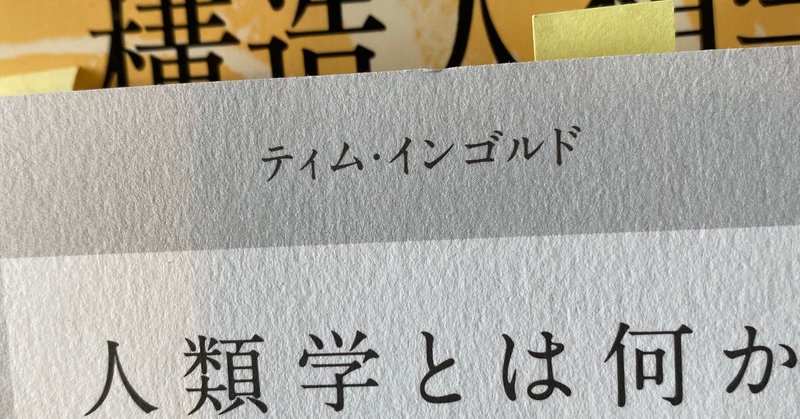
関係論的存在論はダイナミック(動き)である ―文化人類学がおもしろい(2)
科学が行う区別
前のnoteで人類学の「存在論的転回」について書いた。このあたりの話は個人的にとても面白いと思うので、続けてみる。
「自然」対「人間」であるとか、「客観」対「主観」であるとか、近代の科学が知の出発点に設定した大区分がある。
こうした区分はそれ自体として「ある」ものではなくて、「人間」が「行っている」ことである、というのが関係的存在論の考え方であった。
人間が区別をする。近代の大区分も、そうした人間が行う区別のやり方のひとつのパターンである。
科学にとって人間というのは一方で自然環境の内部に属する物質的過程であり、同時に他方で言語的で主観的、つまり意味の網の目を生きる過程でもある。
自然でありながら人間的意味でもある二重の存在が人間である。
その人間が行わずに居られない「区別する」営為が動いている。
科学が依拠する大区分もまた、人間と無関係に、厳然としてはじめからそこにあるのではなく、あくまでもある環境、ある世界の中で実際に生きるひとりひとりの人間が「行っていること」である。
人間が変われば、人間が生きる環境が変われば、この大区分をするやり方も変わる。
部族の人々、「他者」たちが行う区別
こうした根源的な「区別すること」を含めて「人間」の営みを対象とし、記述するのが人類学である。
レヴィ=ストロースの『神話論理』全4巻(日本語では全5巻)など、まさにこの「区別すること」の営みを神話的思考として描き出したものである。
人類学はこの「人間」を、共同主観的な意味の世界に属する「人格」として扱うことと、自然の一部として動く「有機体」として扱うことを共に自らに課してきた。
人間を「社会・文化」と「自然」に分けること。
この大分割を行いながら、その上でなお分割されたはずの両極の両方でありうるという、両義的で引き裂かれつつひとつに絡まった人間の存在を考えるというのは、人類学にとって大変な難問だったのである。
ティム・インゴルドはその著書『人類学とは何か』で次のように書く。
人間存在は「生の網目」と生態学者が呼ぶような他の有機体と関わるいのちの有機体であると同時に、社会関係の網目の中で他者と関わる人間でもある。この二つのシステムにどのように同時に参与しているのかを示そうとした。(『人類学とは何か』p.109)
社会関係をもつことと、有機体であることは、人間存在の二つの面なのではなく、同じ一つのものだと、当該=環境=内=有機体は、世界=内=存在である(『人類学とは何か』p.110)
人間存在は、有機体つまり自然科学の対象である客観的ものでもあると同時に、他者との社会関係のなかで意味を生きる主観的なものでもある。
どちらが「本当か」ではなくて、どちらも人間の存在なのである。
私たち人間は「社会生活の実践的な仕事のなかで、互いの精神と身体をつくっている」のである。
この考え方を可能にしたのは「単なる社会の派生物としてではなく社会生活のなりたちそのもの」としての「関係」に焦点を当てる思考への、思考の形の変化であるとインゴルドは書く。
ここから先は
¥ 180
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 いただいたサポートは、次なる読書のため、文献の購入にあてさせていただきます。
