
梶間和歌プロフィール小説~「及ばぬ高き姿」をねがひて~ 【第3章】
第1章からお読みください。
第1章 女であるということ
第2章 正しさのむなしさ
第3章 本当に美しいもの
第4章 この世ならざる美を追って

第3章 本当に美しいもの

詩を売り始めて3年目の冬、スランプになった。
人に頼まれれば即興の詩はいくらでも詠める。
ただ、普段書き溜めておく“作品としての詩”がまったく出てこなくなった。
それは、「路上詩人ではなく詩人」というアイデンティティに関わる一大事。
作品の生み出せない詩人なんて、“路上詩人”と同じになってしまう。

とはいえ、焦っても仕方ない。出てこないものは出てこないのだから。
アウトプットできないならばインプットすべし。
中高と、学校で国語の勉強をほぼしてこなかった私には、きっと基礎教養みたいなものが足りていない。
これまで感性頼みで続けてきた仕事を一度見直しなさい、という詩の神様のお達しなのかもしれないな。
いわゆる“良い文学”とされているものに改めて触れてみよう。
小学時代に読まなかったものや、読んでも良さのわからなかったものが、きっとあるはずだから。
そう考え、近所の図書館の近代文学コーナーで川端康成や夏目漱石を片っ端から読んでいった。

その隣の棚に、若山牧水の全歌集があった。
「短歌なんて読んだこともないわ」
好奇心から手に取りパラパラめくってみると、想像していたほど堅苦しいものではなさそうな気配が感じられた。
白鳥はかなしからずや空の青海のあをにも染まずただよふ
「へえ! こんな事詠んでもいいんだ。
短歌って五七五七七なんて定型で、窮屈だと思っていたけど。逆に、定型があるからこそやりやすいということなのかな。
私の詩も、そのつもりはなくても七五調になっていたわけだし、そういうものなのかしら」

牧水の全歌集を読み、同じ棚の与謝野晶子に驚き、北原白秋を読むころには、私自身短歌を詠み始めていた。
初めの感覚どおり、定型があるからこそ詠みたいものがすらすら湧いてくる。それを定型に当てはめてゆく。
なるほど、日本語だとそれが自然な営みであるらしい。
夢中になった。新しいおもちゃを与えられた子どもさながら。楽しいと感じる暇もないくらいだった。
どうやら短歌は古典文法で詠むものらしい、ということで、近代短歌を読みあさる傍ら古典文法も独学し始めた。
こんな事を詠もうと考え、それを古典文法に置き換えてゆき、定型に収めてゆく。
できる。できた! その感覚がまた次の作品アイディアを呼び寄せる。
気づけば詩のスランプなどとうに抜けていたものの、私の意識は短歌一色に染まっていた。もう、制約のない詩の世界には戻れないかもしれない。
そんな生活を半年続けたころ。
何をきっかけにその本をつかんだのだっただろう。
玉の緒よ絶えなば絶えねながらへば忍ぶることの弱りもぞする
恋ひ恋ひてそなたになびく煙あらばいひし契りの果てとながめよ

ひととおり古典文法を学んだはずだった。学び、使いこなせるようになったはずだったのに。
その前に立ちはだかったのは、式子内親王という、平安末期から鎌倉初期にかけて生きた女性の和歌だった。

何だ……これは。古典文法はきちんと勉強したのに、意味がわからない。
この本の著者は、式子内親王のこの歌が良いだの、この歌には余情があるだのないだの、この歌は歌境が浅いだ深いだの言っている。
けれども私には歌の意味を追うので精いっぱい。歌境の違いなどまったくわからない。
どうして?
何なの?
この人にはわかっていて、私にはわからないその差は何?
この、和歌というものは、いったい何なの??
しかし
それでも確かにわかること。
……これは、美しい。

半年間夢中で学んだ知識のまったく通用しないものを前に、私は愕然として。
そして、悟った。
「私には、この歌がわからない。
ただ、この歌がわからないのはこの歌がつまらないからではない。
私が馬鹿だからだ」

半年間の勉強の仕方も短歌の詠み方も、完全に間違っていた。そう悟った。
牧水も晶子も白秋も、古典の言葉のネイティブではない。
明治時代なりいつなり、その当時の言葉で発想したものを、古典の言葉に置き換えて、短歌にしたわけだ。
それを真似た私も、現代の言葉で発想したものを古典の言葉に置き換え、短歌にする、という事をしていた。
それは、翻訳だ。
日本語で発想して英語に訳した言葉がネイティブとの会話で不自然響くことは、嫌というほど経験済み。
英語ネイティブと自然な会話がしたければ、英語で発想して英語で発話しなければいけない。
たとえ変な言い回しになっても、失敗しても苦笑されても、それを根気強く続けること。
同じ事を、私は、和歌でしなければいけない。
翻訳短歌なんてしているかぎり、私にはこの歌のような美しい歌など詠めない。きっと、一生。
現代に、古典の言葉のネイティブはいない。
ただ、ネイティブだった人やネイティブに近かった人たちの遺したたくさんの歌がある。
それも、現代ではそれらが活字で読める!
これらの歌と対話しよう。
これらの歌の発想の源泉を学び、詠んだ彼らと同じ意識で歌を詠もう。
“私が詠みたいと思うもの”など歌にしている場合ではない。
彼らと同じ意識で歌に向かい、彼らと同じ発想で歌を発想し、翻訳ではないネイティブの言葉で私の短歌を詠まなければ!

すぐに古本の『式子内親王全歌集』と『新古今和歌集』を購入した。収入は相変わらずなので、その他は図書館頼み。
その借りる本の数も一気に増えた。毎回10冊借り、2週間後に10冊返してまた10冊借りる。
『源氏物語』や『新古今和歌集』関連の図書ばかりだ。歌詠みに『源氏物語』は必須だとすぐにわかったから。
右も左もわからない。ただあの日の衝撃と直感だけを頼りに、体当たりで和歌と対話する生活が、こうして始まった。
26歳の夏のことだった。

梶間和歌プロフィール小説 ~「及ばぬ高き姿」をねがひて~
第1章 女であるということ
第2章 正しさのむなしさ
第3章 本当に美しいもの
第4章 この世ならざる美を追って
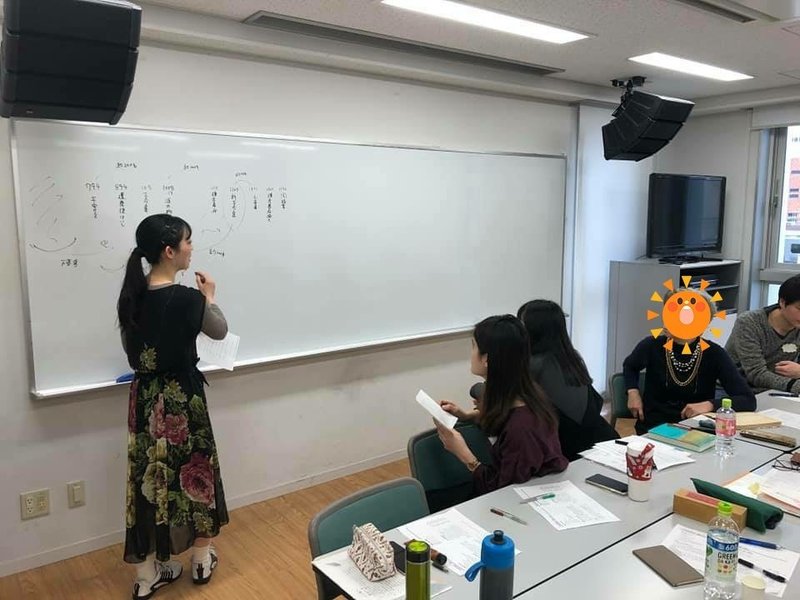
応援ありがとうございます。頂いたサポートは、書籍代等、より充実した創作や勉強のために使わせていただきます!
