
#5 小学校社会科が取り扱う『学習内容』を問う
こんにちは。高杉です。
日本人に「和の心」を取り戻すというスローガンのもと
『和だちプロジェクト』の代表として活動しています。
前回は、『社会科を通して身につけたい力』についてお話をしました。
今回は、
『小学校社会科が取り扱う内容』について
お話をしていきます。
よろしくお願いします。


社会科を通して、
どのような資質・能力をはぐくもうとしているのでしょうか?
『小学校学習指導要領(平成29年告示)解説 社会編』には、
このような力をはぐくむことを目指していると書かれています。
「見方・考え方」「課題解決の学習活動」という
社会科で重視すべき学習過程を通して、
「公民としての資質・能力の基礎」という究極目標が
総括的に描かれています。
(1)は、「知識・技能」
(2)は、「思考力・判断力・表現力等」
(3)は、「学びに向かう力・人間性」
についての目標が示されています。
「公民的資質」とは、
簡単に言うと社会の中で生きる人間としての資質です。
人が社会の中で生きていれば、必ず問題に直面します。
そうした問題を解決するためにはどうすればよいのかを考えながら、
情報を活用しつつ、解決していける土台づくりをしていくという
考え方です。
では、
「公民的資質」の基礎を養うため、
どのような内容構成になっているのでしょうか。

1)『第3学年』では何を学ぶか?

(1)身近な地域や市区町村の学習 【地理~市区町村~】
社会科のスタートカリキュラムともいえる第3学年の第1単元です。
子供と共に身近な地域である「学区」を歩きます。
上り坂や下り坂を歩きながら、土地の起伏を体験します。
農地、住宅地、商業地などを歩きながら、
人々がどのように土地を利用しているのかを実感します。
今まで見過ごしていたものやことを、
社会科学習で地域を調べることによって再発見し、
その意味や役割を理解します。
このような実体験が、
その後の写真や地図、資料を見るときの考えるもとになります。
(2)地域の生産や販売の仕事 【政治~生産と消費~】
『販売』の仕事であれば、
実際に地域のスーパーマーケットやコンビニエンスストアなどへ
見学に行って、お店の様子を調べ、
そこから販売のための工夫や努力について考えていきます。
導入では、自分の家ではどのような買い物をしているのか、
自分の家の献立を調べ、その食材はどこで買ったのか、
併せて何を買っているのか、
その品物はどこで作られているのかも調べます。
また、食材などがどこでとられて運ばれてきたのかを調べ、
他地域・外国とのつながりを考えます。
(3)地域の安全を守る(警察・消防)仕事 【政治~防災~】
『地域の安全を守る』仕事では、
関係機関や地域の人々と協力して防災にあたっていることが重点です。
例えば、『消防』であれば、消火活動に際しては、
交通整理などで警察と、傷病者の搬送に関しては病院と、
火災の拡大を防ぐためには電気やガスなどの供給事業者と協力しています。
また、火災による被害拡大を防ぐために放送局などで
情報を発信してもらったりもします。(公助)
また、地域の消防団員は本業がある仕事を持ちながら、
火災があった際には消火にもあたったり、消防官。
消防士たちの消防活動を支援・補助したりしています。
自治体などの地域の防災活動にも大きく関わっています。(共助)
地域の安全のために、汗を流す大人の姿に子供たちは感動し、
地域への愛情を深めます。
(4)市の様子の移り変わり 【歴史~町の変化~】
『時間の経過』を捉えるために、
交通(鉄道や道路の整備)や公共施設、土地利用や人口、
生活の道具など市の様子の移り変わりを概観できるような資料から
考えていきます。
(※)『地図帳』の活用
第3学年の学習内容の『生産や販売の仕事』で
国内の他地域や外国との関連について学習内容において、
これまでは掛け図などで対応していましたが、
その不備を補うために新しく第3学年から
『地図帳』を利用しての学習が始まりました。
2)『第4学年』では何を学ぶか?

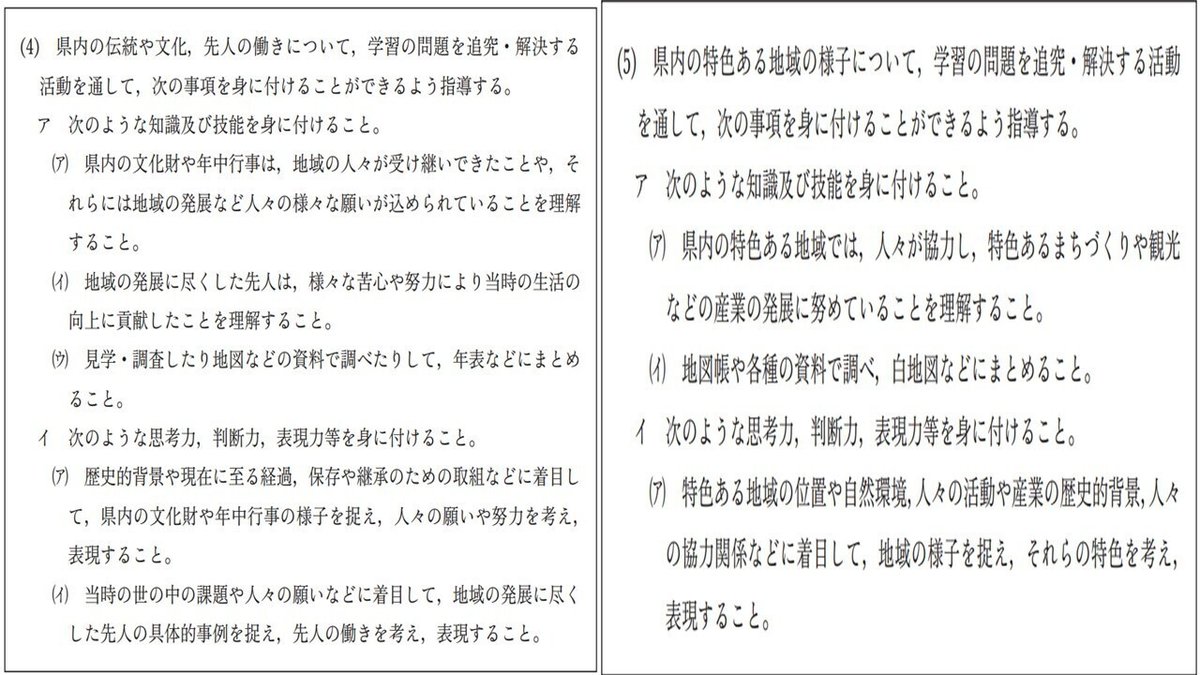
(1)自分たちの県と47都道府県の学習 【地理~都道府県~】
第4学年の第1単元では、「自分たちの県」について学習します。
都道府県の名所や特産品を地図帳で調べたり、
日本地図の地形図から地形の特色を視点に都道府県を調べたりします。
また、「47都道府県」の位置と名称をゲームや調べ学習を通して
学んでいきます。
国語科と関連して漢字配当表が改訂され、
特別な感じの読み方として、
茨城、愛媛、大分、大阪、鹿児島、神奈川、
滋賀、岐阜、鳥取、富山、奈良、宮城を学習します。
(2)人々の健康や生活環境を支える(電気・ガス/水道・ごみ)
仕事 【政治~インフラ~】
新学習指導要領の目玉の一つである「選択・判断」し、
社会に参加・参画ができるように位置づけられました。
東日本大震災以降、
新しい生活様式のもとくらしの電気への依存度はますます高まっており、「エネルギー問題」は私たちのくらしを支える大きな問題で
重要度は増しています。
電気は目に見えないため、
子どもたちにとっては抽象度の高いものになりますが、
くらしのさまざまな場面で活用されており、恩恵は十分の受けています。
また、災害から時間は経ちましたが、
日本中に原子力発電所は存在しており、災害大国日本では、
原子力災害のことは想定しておかなければならない問題です。
エネルギー供給だけでなく、産業や地域経済ともかかわる複雑な問題
ですが、未来を創る子どもたちにこそ考えてもらいたい主題です。
(3)自然災害から人々を守る活動 【政治~防災~】
今回の学習指導要領では、
すべての学年に「防災」に関する学習が入っていますが、
このうち4年生は、
直接くらしに関わる身近な地域での自然災害にどのように対処するか?
というきわめて大切なものです。
自治体の関連部署(県庁の防災課、消防、警察など)や公共図書館、
博物館や郷土資料館で地域の災害について調べたり、
災害の起きた地や防災関連施設の見学や調査活動、
ゲストを招いての聞き取り調査などの体験的な活動を位置づけたりします。
想定されるさまざまな災害、
それに対する「防災・減災」の対策をハザードマップや避難所HUGなどを
通して調べ、
どうすることがよいのか、
どうなることがよいのかを「選択・判断」する学習場面を設定します。
(4)県内の文化財や年中行事の学習 【歴史~先人の働き~】
「先人の働き」については、
『開発・教育・文化・産業など』と合わせて『医療』が加わり、
これらについて貢献のあった人も取り上げることになりました。
できるだけ子供たちが身近に感じ、具体的に学べるように、
見学、聞き取り、調査活動、体験活動など、学習活動を工夫する必要が
あります。
地域の博物館、郷土資料館、記念館、公共図書館などの見学も
位置付けていきます。
(5)県内の特色ある地域の学習 【歴史~伝統工芸~】
県内の特色のある地域の様子を知る学習は、
子どもたちが自身がくらす都道府県に愛着をもったり、
地域の一員としての自覚をもったりするきっかけになる重要な学習です。
「地場産業の盛んな地域」「国際交流に取り組んでいる地域」
「自然環境(地形・気候など)や伝統的な文化を保護・活用している地域」から、地域の良さ、人々の前向きさを共感的にとらえられるようにします。
「伝統工芸」は、
陶磁器、塗り物、織物、和紙、人形、筆といったものが
取り上げられてきましたが、
現在では、芸術的色彩が強まり工芸になったり、
観光資源の一つとして体験と併せて提供されたりと形を変えてきています。
各地でその土地特有の産業としておこり、発展し、現在があります。
この過程や取り組み、人々について調べながら、未来に向けてどうなっていくことがよいのかを考えていきます。
3)『第5学年』では何を学ぶか?
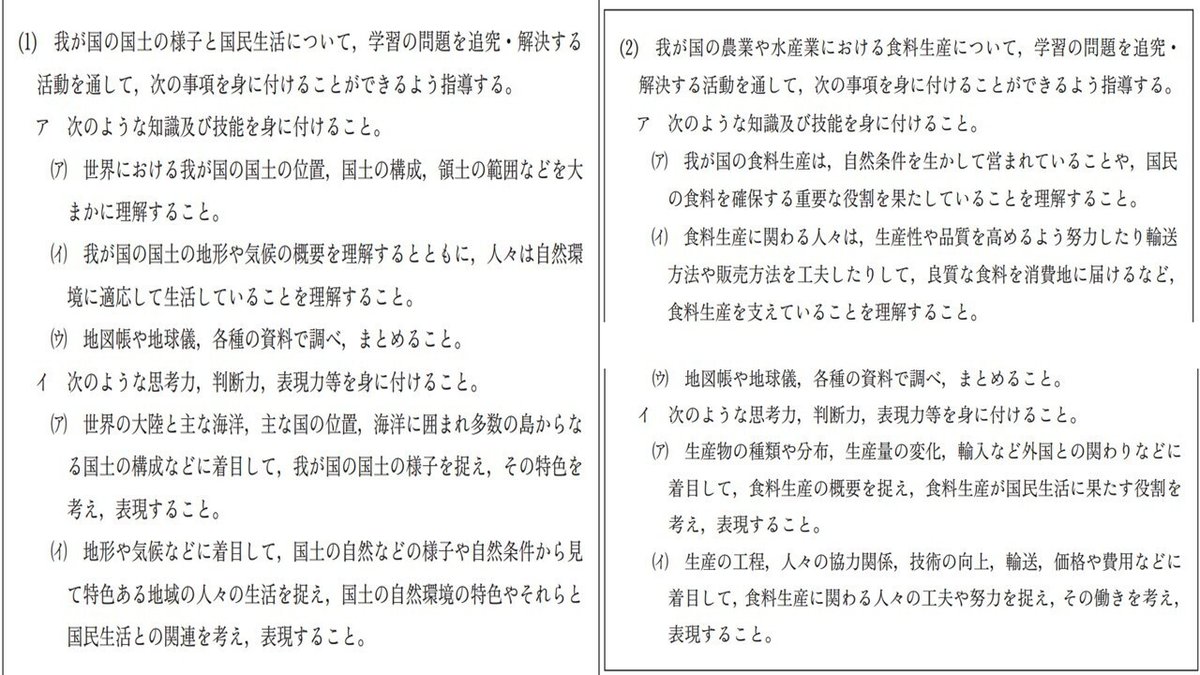


(1)日本国と世界との位置関係 【地理~国家~】
「日本の位置」の学習は、第5学年の学習の基礎になります。
世界の概要について(大陸、海洋、主要国)を
クイズやゲームを通して理解していきます。
また、
この単元を学習するために緯度・経度、『地球儀』の利用、
雨温図の読み取りなども必要になってきます。
地図帳を活用してさまざまな国の緯度や経度を表現したり、
地球儀を使って2地点間の距離を測ったりしてみたりする時間を
確保します。
「領土」に関しても、
竹島、尖閣諸島がわが国固有の領土であるにもかかわらず、
大韓民国、ロシア連邦によって不法に占拠されており、
尖閣諸島についてもわが国固有の領土であることを
伝えていかなければなりません。
(2)食料生産(農業・水産業) 【政治~第一次産業~】
「農業」では、米づくりが中心の学習となっています。
米は歴史・文化を大きく動かしてきた重要な農作物で、
農家の主要な収入源です。
広大な平野で大規模で効率的な米づくりを行う「庄内平野」と
限られた平地で付加価値の高い米づくりを行う「南魚沼」の
特性を把握しながら、地元の米づくりと対比して学ぶことが重要です。
「水産業」では、島国日本は海に面している県が大半で、漁業についても地元の水産業について取り上げることができます。
「食料生産」については、食糧生産に関わる人が、
生産量や品質の向上に向けて努力したり、販売方法を工夫したりして
良質な食料を消費地に届けるなど食糧生産を支えていることや、
食糧自給による安全保障や防災対応、食の安全や品質の保証、
フードマイレージや食品ロスなども視野に入れた学習を考える必要があります。
(3)工業生産(生産・運輸) 【政治~第二次産業~】
「工業」では、自動車工業を中心に学習します。
自動車工業は、
これまでも日本の工業の根幹産業で多くの人がかかわってきており、
新しい技術(生産の工夫や努力)が集約されてきました。
ただ、子どもの生活とは若干距離のある産業のため、
工場見学などの実体験に関わる学習活動も位置付けていきます。
また、
日本の工業は多くの中小工場によって支えられており、
身近な地域の中小工場を取取り上げて展開することも大切です。
さらに、製造の工程、工場相互の協力関係、優れた技術などに着目します。
「貿易」では、運輸の様子や交通網の広がり、
外国とのかかわりなどをとらえ、
地図帳、地球儀、各種資料(統計)を活用して調べることが必要です。
(4)情報活用(放送・新聞/販売や運輸・観光・福祉)
【政治~第三次産業~】
世の中は、情報社会ですが、
情報は抽象的な概念で目に見えず、捉えにくいものです。
情報単元では、
「情報を発信する産業」と「情報を活用して発展する産業」
2つの内容を含みます。
子供が情報を必要とする場面を考え、天気予報に着目し、
新聞社や放送局のニュース番組の中での気象情報の発信のされ方、
気象情報を活用して顧客の求めるものを発注し提供する小売業に
ついて学びます。
『販売』の仕事では、
販売情報を収集・分析して商品の入荷量や販売数を予測したり、
これには運輸業が結びついています。運輸業の倉庫管理と配送の仕組みが
結びついていて、インターネットを利用した通信販売などの新しいサービスが提供されています。
これらの学習を通じて、
情報化の進む社会の良さや課題について
自分の考えを持つようにすることが重要です。
情報化は、良い面ばかりではありません。
報道被害やプライバシーの侵害を起こすことがあります。
情報は扱い方を間違えると生命の安全を脅かしたり、
金銭的な被害を被ったりするなど、
情報化の負の側面についてもとらえさせておかなければなりません。
「情報を発信する産業」「情報を活用する産業」とともに、
国民として社会参加する際に、情報を利活用することも学習するべきです。
マスメディアなどのメディア情報から虚偽を見抜き、
社会参加する際の意思決定に役立てられるようにしたり、
SNSなどを活用するといった「情報リテラシー」の獲得についても
考えていく必要があります。
(5)自然環境の保護(災害・林業・公害) 【政治~防災~】
この単元の学習の主要な内容は、
「①日本の国土の保全(自然環境と災害)」「②森林の働き」
「③公害防止から環境問題の対策」です。
我が国は、「災害大国日本」です。
毎年各地で自然災害が起きていますし、
過去にさかのぼれば全国どこでも被災の事実が見いだせるでしょう。
「公害」については、
大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、地盤沈下、悪臭など
取り上げる範囲が示されています。
また、
四大公害病が扱われ、高度経済成長前後に各地でも公害事件が
起こっており、その対策を様々に講じてきました。
公害事件は、社会問題の典型例です。
自社の利益のみを求め、
他者をないがしろにして展開したきわめて残念な事件ですが、
裁判も起こされており事実などがはっきりとしていることが多いのです。
公害の事件の事例から多くのことを学ぶことができます。
4)『第6学年』では何を学ぶか?


(1)日本国の政治の働き(日本国憲法) 【政治~国政・地方自治~】
今回の学習指導要領の改訂から、政治単元が第1単元となったことで、
現在のくらしの中の問題を、年間を通じて追究していくような
課題解決学習が行いやすくなりました。
子供がくらしている身近な社会の中で起きている問題に関心を持ち、
さらに社会で起きている諸問題についても問題意識を高め、
その解決に向けて、調べ、考えていけるようにしていきたいです。
そのために、
まずは、日本国憲法の内容から国政の仕組み、
地域の政治と展開していきます。
子育て支援・災害復興・高齢者問題などどこの地域であっても
課題となっているようなものについて取り上げ、身近な地域の問題として
学習が進められるようにしていきます。
(2)我が国の歴史学習 【歴史~国史~】
今回の学習指導要領改訂にあたっては、
「歴史を学ぶ意味を考え、表現すること」とあります。
また、
「当時の世界との関わりにも目を向け、
我が国の歴史を広い視野から捉えられるように配慮すること」とあり、
日本だけではなく、世界との関わりについて扱うように求められています。
歴史学習は、子どもの生活との接点が見出しづらいため、
生活と結びついた学習問題を設定することが難しく、
ともすると、教員が教科書本文を説明する講義調の授業に
なってしまいます。
そのため、
示された資料をもとにつくりだした学習問題から、
子どもの問題意識をもとに展開していく歴史学習にしていく必要があります。
歴史を学ぶ意義や有用性が実感できるような学習を構成することが求められています。
(3)世界の中での日本の役割 【地理~日本と世界のつながり~】
国際単元の学習は、
我が国とつながりが深い国々について、
経済や文化などの面でのつながりを視点に取り上げていきますが、
「スポーツや文化などを通して他国と交流し、
異なる文化や習慣を尊重し合う」ことが加わりました。
世界の人々と共に生きていくために大切なことや、
今後、我が国が国際社会において果たすべき役割などを多角的に考えたり、選択・判断したりできるようにしていきます。
国際協力の学習では、
世界で活躍している日本人について取り上げられています。
環境問題、貧困、飢餓の問題、平和維持などの
世界が抱えている問題に立ち向かっている日本人の姿に学びながら、
これからの世界のために何ができるのかを考えられるようにしていきます。
5)『日本人の良さやひたむきさ』から学ぶ

日本人の親からは、私たちは日本の国籍を持つ日本人になります。
まだ日本という国の様式を身につけていない、まっさらな日本人です。
そんな私たちは、
親のしつけ、友達とのかかわり、
そして、学校での教育を通じて、少しずつ日本人になっていきます。
社会科は、「日本人の良さやひたむきさ」を学ぶ教科です。
人々の工夫、努力、先人の苦心、課題解決、
そのような日本人のよさを、社会のために、
ひたむきな生き方のために、努力してきた姿を学ぶ教科です。
明治維新や先の大戦を経て、我が国の生活様式はすっかり西洋化しました。
しかし、
それでもなお古来の伝統・文化が日常生活の中に数多く残っている、
世界でも稀有な国です。
たとえ、時代遅れと言われようとも、
我が国は、手放そうとも手放せない、
失ってしまっては取り返すことができない
大切なものがたくさん息づいているのです。
日本人の生きた教材を目の当たりにできる―。
だからこそ、結果として子供たちの心が育つのです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
日本には、綿連として受け継がれてきた「よさ」がある。
少しでもよりよい社会を創ることができるように努力してきた先人の知恵や働きを知ることで、何が我が国の社会で正しいとされているのかを学ぶ。
このような日本人のよさを共感しあうことを通じて、
その子も将来、私たちと同じように社会の形成者の一人となり、
日本のよさを受け継いでくれる存在になる。
そのために、
必要なことを学ぶことが「社会科の本質」である。
と僕は思います。
日本人が2683年以上紡いできた「和の国づくり」とは何か?
なぜ大切なのか?
どのように受け継いで、つないでいくのか?
を学ぶことを通して伝えていきたいのです。
日本に生まれた日本人が、
日本に生まれたことを幸せに感じ、
日本に生まれた子供達が、
日本に生まれたことを誇りに感じる。
そんな想いを社会科を通して育みたいのです。
一緒に、日本国を楽しく学んでいきましょう!
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
