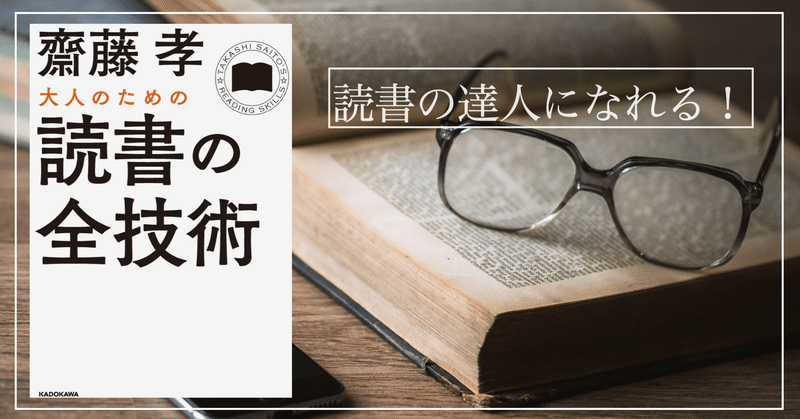
”絶対に挫折しない”読書術、伝えます|【大人のための読書の全技術】
どーも!
わーさんです!
さっそくですが、#2021年に読んだ本の紹介 をしていきます。
・・・
・・・
『大人のための読書の全技術』
齋藤 孝 (著)
著者説明
齋藤 孝(さいとう たかし)
・1960年生まれ
・日本の教育学者、著述家。学位は教育学修士(東京大学・1988年)。
・明治大学文学部教授。
引用元:Wikipedia
その他著書
・数学的思考ができる人に世界はこう見えている ガチ文系のための「読む数学」
・頭のよさはノートで決まる
・大人のための書く全技術
・・・
本書の概要
・大事なポイントだけを抽出できる。
・本との向き合い方もわかる。
読んだ感想をTwitterに投稿しました!
#2021年に読んだ本の紹介 #03
— わーさん@【学び×読書】の伝道師 (@W_notenoter11) January 16, 2021
『大人のための読書の全技術』
齋藤 孝
総評:「A」
理由:
・大事なポイントだけを抽出できる
・本との向き合い方もわかる
商品はこちら↓https://t.co/XVdXcplldx#ビジネス本 #読書 #本 #読了 pic.twitter.com/Q7bGnwndk5
重要なポイントを「大きく3つ」にわけて、お伝えしていきます!
・・・
■本を読む理由
本書では『社会を生き抜くための「思考力」』と述べています。
現代であれば、多くの情報がインターネットやSNSを通じて獲得することが可能になった時代です。
しかし、その情報というのは持続力がありません。
芸能人の誰かが
・結婚した
・離婚した
・熱愛報道だ!
・スキャンダルだ!
という情報がネット上で踊ったところで、数日後、早ければ翌日にはそのネタというものの価値がなくなっていることがほとんどです。
つまり、ネットに溢れている情報の価値というのはそれほど高くないのです。
それに比べて、本の価値、知識の価値というのはとてつもなく大きなモノです。
実際、本を書いた著者に会うことができるかどうかすらわかりません。
ましてや、もうすでに亡くなっている方もいます。
『FACTFULNESS』の著者のハンス・ロスリングさんはすでに亡くなっています。
自身の最後の仕事として、本の制作に取り組みました。
その方が残した知識を一冊数千円から手にできるのであれば、とても安いと感じませんか?
これが「本を読むべき理由」の大きな点だと感じました。
・・・
プラスして「思考力」の部分を紐解いていくと、上記でも例を出しましたが、芸能人が何かした話題を深堀りしたところで社会に通用する思考力は身に付かないです。
スキャンダルを起こした芸能人の行動に対して、「私は気をつけよう」くらいしか学ぶことができないため、浅はかな思考しか身に付かないです。
それを、友人などとコミュニケーションしたところで、次に生かせるだけの価値は残すことも身につけることも難しいです。
・・・
本であれば、一冊読むだけで自分が知らなかった知識に触れることができます。
その知識を自分なりに解釈、咀嚼をして、再構築していくことによって思考力が高まっていきます。
このことを本書では「垂直次元の思考」と言っています。
この、垂直次元の思考を鍛える意味でも、読書というのはとても大切なモノなのです。
・・・
■本の速読術
本の速読術と言っても、眼球を早く動かして見るようなモノではありません。
個人的にも信じていないですし、実際、無理です。
また、本を読む速さは「遺伝によって、ある程度決まっている」とメンタリストのDaiGoさんも動画で言っていますので、そちらの方が信憑性が高いです。
・・・
ここで紹介する速読術というのは、一言で言えば「ムダな部分を捨てる」ということになります。
必要のない部分を読まない。
これが大事になってきます。
本1冊あたりの重要な要素が書いてある部分というのは、約10%くらいです。
あとの約90%くらいは、同じことが書いてあったり、重要な部分につなぐためのモノだったりします。
もちろん、小説は違ったりします。
ただ、ビジネス書などはこのような感じです。
そのため、最初から最後まで読む必要はないのです。
これが、早く読むための心構えになります。
・・・
では、実際に早く読む秘訣を2点紹介します。
1.多くの本を読む
ひとつ目が、結局なところ「多くの本を読むしかない」です。
ただ、理由は明快で「約10%を探す」ためです。
多くの本を読めば、それだけ予備知識が蓄えられます。
それにより、ムダだと思うところは知っているから読まなくてもいいのです。
そうするためにも、多くの本を読む必要があります。
しかし、それができてしまえば、どんどんと予備知識が増えていきますので、読む量を重ねる度に読みやすくなります。
これは私の経験ですが、同じジャンル、専門性のある本を5冊くらい読めば、大体の全体像が見えてきます。
あとは、その本が述べたいことを見つけるだけでいいのです。
2.ピックアップする
「ピックアップ」することも「多くの本を読むこと」に関連していますが、意識の問題が大事になってきます。
ピックアップする上で大切なのが「目的意識」を持つことです。
「この本をいつまでに読み終わらせる」
「誰かに伝える」
この意識が基本要素となります。
本を買ったとしても、「時間がある時に読めばいいかな」って思ってしまって、いつの間にか本棚や普段触れない場所に移動されていないですか?
そうなるのも目的意識がないことが原因です。
自分で買った本の読む期限を決めてしまうことで、必然的に時間を生み出そうとします。
プラスして、「誰かに伝えないといけない状況を作り出す」ことによって、より時間を確保しないといけない気持ちになります。
その気持ちが大切なのです。
ピックアップする時に、一番大切なのが「目次」です。
目次には、その本で読んで欲しい部分がわかりやすく書いてあります。
目次を熟読することによって、必要な部分がわかり、
読む時間を短くすることができます。
それだけ、目次をしっかり読むことが大事なのです。
・・・
ピックアップをする際、本書では「本を買ったらすぐに喫茶店に入って20分くらいで読むところをまとめなさい」と述べています。
買った直後が一番気持ちも高まっているので、その時に読みたい部分を決めておけば、次の日に大事な部分を読むことができます。
このような工夫をしながら、本を読むことが大切です。
・・・
■実際の本の読み進め方
ここでは、私のオリジナルなやり方も交えながら説明していきます。
できれば、本を用意してもらうと理解しやすいかも知れないです。
要素としては、
・「はじめに」の部分を熟読
・「終わりに」の部分を熟読
・目次を熟読
・その本で気になるところから読む
わけると、この4点が重要です。
簡単にですが、説明していきます。
・・・
1.「はじめに」の部分を熟読
「はじめに」の部分には、著者が読んで欲しい部分が含まれています。そこからキーワードを探すのが重要です。
購入を検討する際、立ち読みなどであなたが「ビビッと」くる要素が「はじめに」の部分にあれば、買って間違いないかなと考えます。
2.「終わりに」の部分を熟読
「終わりに」の部分は、全体を通じての感想や、今後に向けた想いが書いてあります。
ここからもキーワードとなる言葉を抜き取ることが大切です。
人によっては、こちらから読んだ方が感覚を掴める場合もありますので、それはあなたにおまかせをします。
3.目次を熟読
「はじめに」と「終わりに」の部分を読んだら、
ある程度のキーワードが見えてくるはずです。
キーワードは大体5〜6個くらいで十分です。
そのキーワードが、その本の伝えたい内容です。
キーワードが書いてある部分に線を引いていきます。
なければ、似たような言葉でも大丈夫です。
そのから、探して読んでいく感じです。
4.その本で気になるところから読む
目次に線をつけたら、
気になるところから読んでください。
最初から読む必要はありません。
本の構成的に
「過去-現在-未来」の順でできていることが多いです。
過去の部分については、多くの書籍で述べている場合がほとんどですので、読み飛ばしても問題ないことが多いです。
その本が伝えたい、現在や未来のことを中心に触れてから、過去に戻るものひとつの読み方です。
私の読み方としては、大体、1章は読みません。
真ん中あたりから読んで、
最後に1章を読んだり、読まなかったりします。
まずは、気になる部分から読み始めることが大事です。
・・・
■まとめ
本書は過去に本の読み方で、
挫折してしまった方におすすめです。
読むべきところを理解すれば、
全部読む必要がないこともわかります。
たくさんの本を読みたいと思っている方でしたら、一度本書を読んでみることをおすすめします。
サポートすると、それがnoteユーザーのためになります✨ サポートよろしくお願いします🔥
