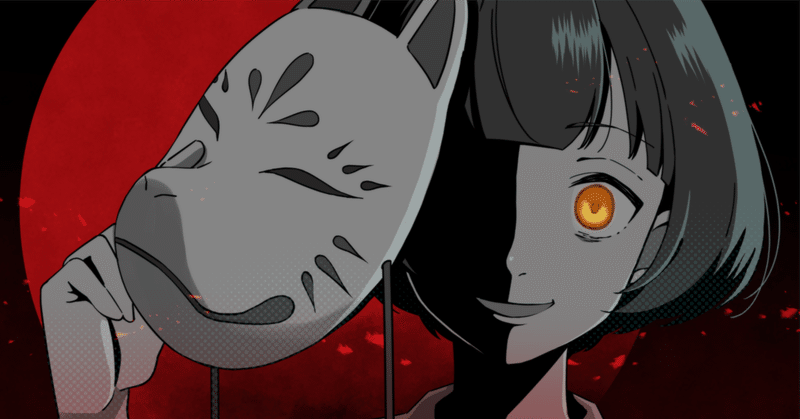
小説 さいかい 1章〜1
授業終わりのチャイムが耳に鳴り響いている.どうやらまた妹を探す夢を見ていたらしい.毎回探してるだけで夢に妹は登場すらしないし,顔もわからない.なのに存在していると思う自分に毎回驚いている.
証拠を探すため,親に聞いたり,アルバムを調べたりしたけれど,妹がいたことを証明するものはなにもない.当然,このことを周りには言えない.
目を開けるとクラス全員が起立して自分を見ていた.働かない頭をフル稼働させて,状況を理解しようとすると後ろから友達の匠に声をかけられた.
「隼人,早く起きろよ.先生にキレられるぞ」
今は6時間目の歴史の授業,担当の石崎先生は全員が席を立ち挨拶をするまで授業を終わらせてくれないタイプの人だ.どうやら授業がいつの間にか終わってしまっていたらしい.
周りから早くしろという圧を感じ,慌てて席を立つ.それに合わせて,日直の掛け声がクラス内に響き,休み時間に移った.
昨日見たテレビとか,この後ゲームをしようとか他愛もない話が飛び交っている.なんとかクラスのみんなには許してもらえたみたいだ.こんな些細なことがいじめの原因になったりするので気をつけないといけない.
「金田,帰りの会が終わったら職員室にきなさい」
先生から声をかけられてしまった.みんなには許されても先生からは許されなかったらしい.
「わかりました」
眠ってしまった自分が悪いので,言い返すこともできずに渋々従うことにする.
「あ〜あ,石崎の説教は長くなるぞぉ.まぁ,どんまい」
とてつもないニンマリとした顔をした匠に声をかけられた.
「うるさいな.少しはこっちの身にもなってくれよ」
匠の絶対に心配してないであろう心配に少し苛立ちながらも何か言い返せるはずもないのでとりあえず愚痴だけはこぼしておく.
「まぁ大したことは言われないって,そいえば今日も図書館行くのか?」
「そのつもり」
「そうか.一年前から図書館入り浸ってるけど,いつから本好きになったんだ?」
「いつの間にか」
あまり深堀りしてほしくないので適当に流す.
「ふーん,今度面白い話があったら教えてくれよ」
「うん,わかったよ」
控えめに言っても匠はいいやつだ.言い方は少し雑ではあるけれど,中学生で図書館に入り浸っている全くタイプの違う自分を理解しようとして,声もかけてくれる.
こういう時はありがとうと一言言うべきだし,言いたい気持ちもあるけど,何処か少し気恥ずかしい.それだけの理由でうまく言葉返せず,昔から何も変わっていない自分が嫌になった.
帰りの会が終わったので,職員室のドアを開けて石崎先生を探す.
「失礼します」
石崎先生の席は窓際の席で入り口からかなり遠い.周りの先生の目が少し気になりはしたが,早く図書館に行きたいのでさっさと石崎先生のところへ向かった
「来たか,金田.最近よく居眠りしてるけど,夜はちゃんと寝てるのか?あれこれ言うことはできないけど,お前たちは中学生なんだから授業も程々にちゃんとやれよ」
石崎先生も少し,説教臭いところはあるけれど,なんだかんだ自分たちのことを考えてくれることが多い.いい先生である.
「はい,気をつけます」
心配してくれるのはありがたいが,正直なところ,自分にはいい迷惑だ.
「そういえば,昨日図書館で本を読んでるところを見たけど,民謡とかに興味があるのか?」
どうやら,資料を調べているのを見られていたらしい.
「少し,自分が住んでる県の言い伝えとかに興味があって」
嘘を言ってはいない.ただ,あまり触れてほしく無いので適度に濁した.
「そうか,大体言い伝えってのは起こった出来事が曲解されて成り立つパターンが多い.この辺だと竹馬山がよく言い伝えの場所になってるな.例えば,雨乞い巫女,後は狐化かしとかがあった気がするな」
「そんな話があるんですか!なんで知ってるんですか⁉どこで調べれば出てきますか⁉」
思っても見なかったタイミングでいい情報を知ることができたせいで,前のめりになって聞いてしまった.
「すごい興味あるんだな.読んだ場所だけど,メディアクローバーってところ知ってるか?図書館と喫茶店が一緒になったとこなんだけど,車で大体30分くらいかかったから自転車なら1時間かからないくらいかな.県内で一番大きい図書館だからネットで簡単に調べれるぞ」
「そうなんですね.今度行ってみます」
1時間も自転車を漕ぐのは気が重いけど,それで少しでも夢の情報が手に入るなら行ってみる価値はあると思った.
夢ではいつも妹を探して森の中をさまよい続けている.行ったことも無ければ写真で見たこともない.そして,毎回縄紐が並んでいる道を通り抜けるタイミングで目が覚める.これがもうかれこ1年は続いている.
こんなことが何度も続くと魔法みたいな何かが関わっていると疑ってしまう.だからこそ調べたい.
調べて安心したい.
妹なんていなくて,ただ偶然が何度も,何度も起こっているだけだと…
「本当ならほどほどにしろと言いたいところだけど,勉強ってなると怒るに怒れないんだよな.とにかく,好きなことに一生懸命なのはいいけど,体には気をつけろよ」
「はい,これからは気をつけます」
今日の予定では学校の図書館に行くつもりだったけれど,今々,先生と話した手前,とても行きづらい.仕方がないので,今日は諦めて家に帰ることにした.
「よし,もう行っていいぞ」
先生からの許しも得たので会釈をして,扉に向かった.
「ほんとに石崎先生ってお節介焼きだよね」
「確かに,私はちょっと苦手かも」
周りにいた先生たちがコソコソ話している声を聞いてしまった.やっぱり石崎先生みたいな人でも誰かに嫌われたりするのかと知り少し,嫌な気分になる.
「失礼しました」
これ以上聞きたくないのでさっさと職員室から出た.
僕は縄紐が並んだ道を通り過ぎ,奥へ奥へと進んでいる.走っている道はどんどん固くなっていき,野草が少しずつ生え始めた.
そのまま,ただひたすら真っすぐ突き進むと開けた草原に行き当たった.よく見るとこの草原はクローバーの群生地らしく,そこら中がクローバーで覆われている.雲間の隙間から光が差し込み,目の前の丘が光り輝いた.すると突然きれいな女の人が現れ,電球を回すみたいに優雅手を振った.その周りにはたくさんの四葉のクローバーが咲いていた.
「隼人起きてる?ご飯できたよ」
母さんに呼ばれ目が冷めた.まだ少しうつらうつらしているけれど,あまりの驚きに頭は早くも稼働する.
夢の内容が変わった.というより続きがあった.あの女の人が自分の妹なのかと思う.しかし,すこしだけ違和感があった.妹というよりは姉みたいな気がしたからだ.とにかく図書館で調べればなにかヒントがあるかもしれないので,忘れない内にメモしておく.
「隼人,早く起きな!」
母さんに急かされ,慌てて部屋から出た.扉を閉めようとすると隣の部屋のドアノブにぶつかった.この部屋のドアは自分の部屋のドアと直角の場所にあるせいで,ドアを開けようとするとよく肘をぶつける.母さんは俗に言う断捨離できないタイプの人間でこの部屋は完全に彼女の物置と化している.
妹が本当にいるならここが妹の部屋になっているのだろうと思いながら階段を降りた.
テーブルには目玉焼きと白米が並んでいる.
父さんも母さんもすでに食べ終えたらしく,食器を洗う音と車のエンジン音が聞こえてきた.とりあえず,早めに自分も家を出たいので箸に手をつけた.
ネットで調べたところメディアクローバーは県庁の前の道路を挟んだ場所にある.元々は県内で一番大きい県立図書館だったけれど,少し前に改修されてきれいになっただけではなく,有名なコーヒーショップが併設されたみたいだ.この店の人気は凄まじく,中学生や高校生が勉強会という名目で利用しているらしい.個人的には図書館は静かで自分の席の隣に誰もいない中,あの古い紙の鼻につくような匂いを楽しみながら調べ物をするのが好きだけれど,メディアクローバーではそれはできなさそうなので少し残念だ.
「母さん,今日って暇?」
「ごめん,今日はパートがあるから忙しいのよ.なにか用事でもあった?」
「いや,ちょっとメディアクローバーに行きたかっただけ」
先生も言っていたみたいに自転車で行くには少し骨が折れそうなので,母さんに送っていてもらいたかったけど,それも厳しいみたいだ.
「バス使ったら?迎えなら行けそうだし,お金は出すよ」
「分かった.じゃあ迎えだけお願い.」
「はーい,じゃあ4時位に迎えに行くね」
とりあえず,バスの時刻をネットで調べることにし,昼食代とバス代を受け取った.
メディアクローバーは思っていた以上に活気にあふれていた.同い年くらいの男子たちが仲良さげに勉強して,小さい女の子とその母親が本を読だりしている.あまり得意な雰囲気ではないけれど,これはこれでいいと思う.
「やっぱり,来たか」
後ろから声をかけられ驚きながら振り返ると,そこには石崎先生がいた.
「昨日,あんなこと言ったから絶対来ると思ってたよ.場所わかるか?案内するよ」
この人はどこまでお節介を焼けば気が済むのかと少し呆れたが,案内をしてくれるみたいなので従うことにした.
先生に案内されながら奥へ進むと今までいた人の数が嘘のように減っていき,太陽の光の差し込みづらく,少し薄暗い本棚に行き着いた.本棚のラベルには民謡と書いてあり,本も開いていないのにあの鼻につくような香りが漂い始めた.どうやら相当古い本がたくさん置いてあるのだろう.
本は著者名順に並んでいたものの,どれが目当てのものか全くわからない.
「確か,この辺だったかな」
先生に言われた棚を見ると,「伝説の地,竹馬山」という題名の本があった.発行されたのは1960年で著者は詰草士郎といういかにも偽名のような名前だった.
「じゃああそこのテーブルでも使ったらどうだ?俺は別で探すものがあるから,後でまたそっちに行くよ.何かしら教えられることもあるかもしれないしな」
そう言って先生は窓際のテーブルを指さした.
「はい,ありがとうございました」
正直なところ,まだいるのかとも思ったけど,自分では分からないこともあるかもしれないのでありがたく先生を使わせてもらうことにして本を開いた.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
