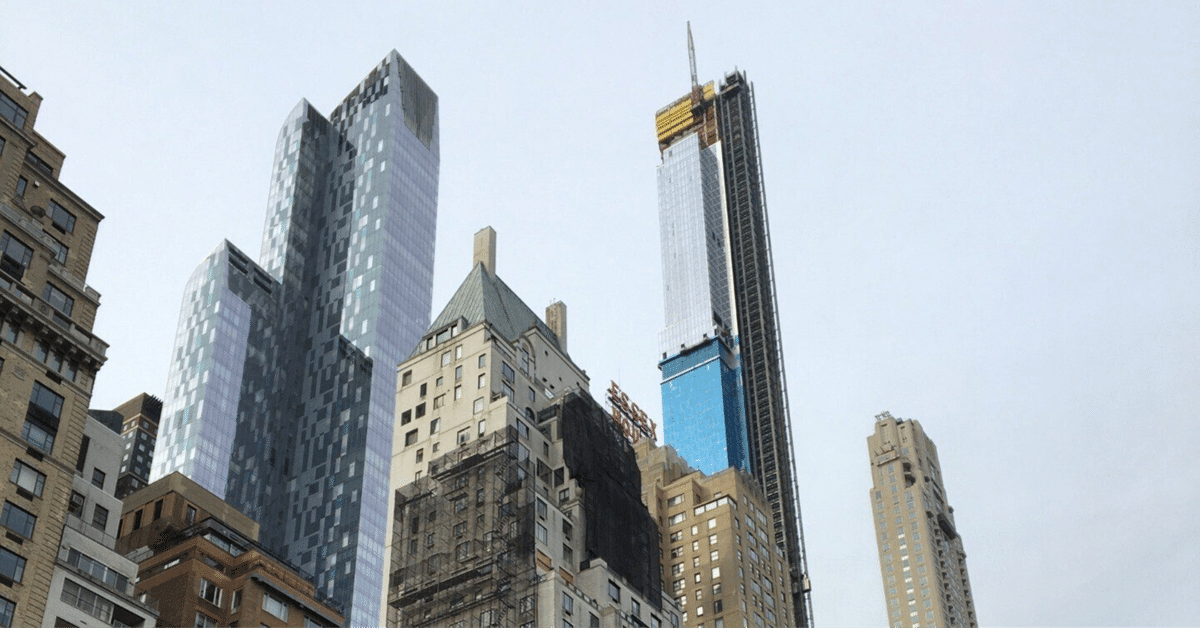
マネジメント[エッセンシャル版] Part2【読書記録#10-2】
ドラッカーの読書記録の続きを書いていく。
https://www.amazon.co.jp/マネジメント-エッセンシャル版-基本と原則-ピーター・F・ドラッカー/dp/4478410232
前回の読書記録はこちら。
Part1は「マネジメントとは」について書かれた章だったが、Part2は、マネジメントの具体的な方法論の話だ。
マネージャーは組織のアウトプットに責任を持つべき存在
まず、マネージャーの仕事には、2つの役割があるという。
①第一の役割は、部分の和よりも大きな全体、すなわち投入した資源の総和よりも大きなものを生み出す生産体を創造することである。
②第二の役割は、そのあらゆる決定と行動において、ただちに必要とされているものと遠い将来に必要とされるものを調和させていくことである。
ただ、人員を「管理する」という存在ではなく、組織のアウトプットに主眼を置いて、長期的な成長も見ながら決断してく存在なのだ。この辺の捉え方は、以前に読んだ『high output manegement』と同じ考え方だ。
アウトプットに主眼を置くと、組織を構成する人員との関係性が最優先事項でないことがわかる。
事実、うまくいっている組織には、必ず一人は、手をとって助けもせず、人づきあいもよくないボスがいる。この種のボスは、とっつきにくく気難しく、わがままなくせに、しばしば誰よりも多くの人を育てる。好かれている者よりも尊敬を集める。一流の仕事を要求し、自らにも要求する。基準を高く定め、それを守ることを期待する。何が正しいかだけを考え、誰が正しいかを考えない。真摯さよりも知的な能力を評価したりはしない。
意思決定するかどうか、そして行動するかどうか
次に、マネージャーが行うべき意思決定について。
まず、どんな時に意思決定が必要かについて、明快な原則が述べられている。
何もしないと事態が悪化するのであれば、意思決定を行わなければならない。
…「何もしなければどうなるか」との問いに対して、「うまくいく」との答えが出るときには手をつけてはならない。多少頭痛の種ではあるが、たいした問題ではないときも手をつけてはならない。
しかし、多くの問題は中間にある。…そのようなとこには、行動したときのコストと行動しないときのコストとを比較する。…
①行動によって得られるものが、コストやリスクよりも大きいときには行動する。
②行動するかしないかいずれかにする。二股をかけたり妥協したりしてはならない。
意思決定しない、を決めることも非常に重要なのだ。また、意思決定とは、行動するか/しないかの2択である、という点も単純である。しかし、ここは、現実においてはそうすることが非常に難しい点であると思う。
さらに意思決定には行動が伴わないと意味がない。だからこそ、行動に関わる人たちを適切に意思決定に巻き込んでいくことについても述べられたいた。
したがって、意思決定の実行を効果的なものにするには、決定を実行するうえでなんらかの行動起こすべき者、逆に言えば決定の実行を妨げることのできる者全員を、決定前の論議のなかに責任持たせて参画させておかなければならない。
「伝える」と「伝わる」は違う
次のコミュニケーションに関する言及も面白かった。受け手が情報を受け取って始めて、コミュニケーションが成立したと言えるのだ。
コミュニケーションを成立させるものは、受け手である。コミュニケーションの内容を発する者、コミュニケーターではない。彼は発するだけである。聞く者がいなければ、コミュニケーションは成立しない。
コミュニケーションと情報は別物である。ただし依存関係にある。コミュニケーションは知覚の対象であり、情報は論理の対象である。…
しかし情報は、コミュニケーションを前提とする。情報とは記号である。情報の受け手が記号の意味を知らされなければ、情報は使われるどころか受け取られることもない。情報の送り手と受け手の間に、あらかじめなんらかの了解、コミュニケーションが存在しなければならない。
重要なのは、大きく物事を捉え、リスクを取ることを前提に行動すること
これは自戒をかなり込めた知見なのだが、マネジメント層にとっての意思決定は、できる限り物事を大きく捉えて判断しなければならない。人間はどうしても、細かいところの正確性を積み上げたくなるような傾向ががある気がしているが、それは意思決定にとっては必要ないのである。
正確な測定が困難であり、幅をもってしか評価できないという情報こそ重要である。…大ざっぱな数字のほうが、かえって本当の姿を伝える。一見根拠があるかのごとき細かな数字こそ不正確であることを知らなければならない。
そのように細かな数字を突き詰める行動は、「リスクを最小化したい」という願いから来ているような気がする。しかしながら、経営判断とはリスクを伴うことなのである。
企業活動からリスクをなくそうとしても無駄である。現在の資源を未来の期待に投入することには、必然的にリスクが伴う。まさに経済的な進歩とは、リスクを負う能力の増大であると定義できる。
本のタイトルにある通り、本当にマネジメントのエッセンスが詰まった本だ。マネジメント経験をもっと積んで読んだら、また新しい発見がありそうだから、しばらくしたら、また読み直したいな。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
