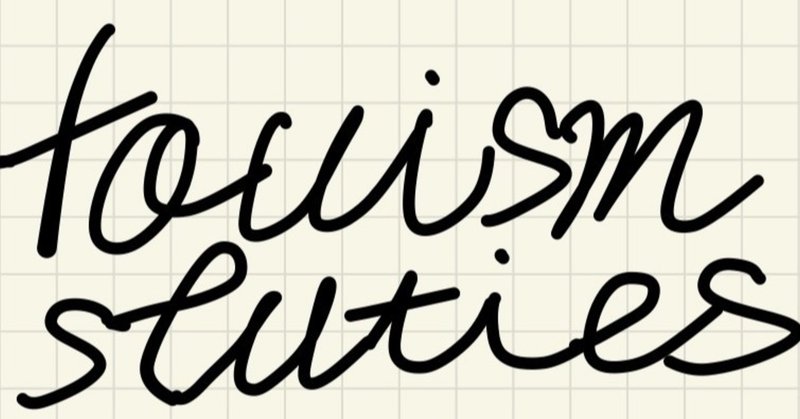
観光学ってなんやかんや人間についての学問かなと
筆記体ってどう書いていいか分からないから、テキトーに書いちゃいますよね・・・
さて、今日は、「観光学」について思ったことを書きたいと思います。
観光学って、結局「人間」についての学問だよなぁ、ということ。
いまや、多くは観光に行かないもしれませんが、だからといって観光業も観光学も衰退するわけではないと思います。もしかすらば、今以上に、観光業と観光学における研究が進むかもしれません。
観光はもはや人々の生活とは切っても切れない存在となったのではと思います。
j.アーリが、観光が終焉を迎える、つまり何が観光で、何が観光でないかの判断がつかなくなるほど、観光が人間の生活に浸透していると指摘しているくらいです。
観光が社会に中に組み込まれる、換言すれば、観光が社会化しているのです。社会は、人間が営為を成す場所。社会無くして、「人間」という社会的生物は生きることが出来ません。
観光学は、幅広く「観光」について学ぶ学問であると私は認識しています。観光を促進することはもちろん、観光が持つ悪影響にも関心を向け、そしてそもそも「観光」とはなにかを問うことも、いやそればかりかもしれません(笑)。
観光は、オルテガ・イ・ガセットのいう「大衆社会」のように、大衆化した現象の一例です。大衆化すれば当然、カオスとも言える状況が生まれます。今のコロナ関係の状況も、そのカオスの一つ。頼れば頼るほど、それに頼れなくなった時のダメージが多いけれども、今更それ以外の道がないという人もいます。
人間のニーズに合うように多様化する観光は、まさに大衆化社会の証、近代社会の証だと思います。
国によって、「観光」の持つ本質が違うところが興味深い点でもあります。しかしながら観光はどの国においても、産業としての力を備えている。
やはり「観光」は、もはや人間が手放すことの出来ない、一種の麻薬のようなものなのかもしれません。
裏を返せば、人間はその「観光」と向き合っていかなければならないのだと思います。情報化社会がもたらした、情報の高速伝達は、他地域への興味や関心を生じさせます。生まれた土地のみを知り、その地で死んでいくような時代ではもうないのだと思います。
ある意味で「観光」は、人間の無際限の欲望を満たそうとする心象の表れかもしれませんし、可能体として身体性を備えた人間の活動の当然の帰結とも言えるかもしれません。
自分を超える。自分には不可能なことを可能にする。自分にはできなかった体験をする。自分ではない他者の経験をする。自分が知らないものに直に触れる。そして自分ではない何者かになる。
自分という有機体の可能性を最大限に引き出し、「他」に触れようとすること、「他」を識ろうとすることが、「グランドツアー」から、「旅」、そして「観光」へとつながる道を切り開居っていたのでしょうか。
色々書きましたが、「観光学」は終局「人間」について学ぶ学問だと思います。他の学問も大体はそうだとは思いますが。
他分野にまたがり、学際的な研究が避けられないからこそ、余計に「人間」とその「活動」への研究に必然的にかかわって来るのではないでしょうか?
と
今日も大学生は惟っている。
サポートするお金があるのなら、本当に必要としている人に贈ってくだせぇ。
