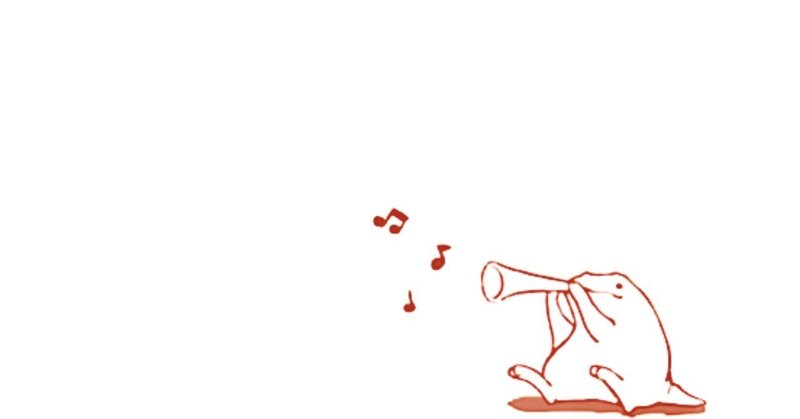
もしも将来音楽が荒廃していくとしたら1
音楽と人の社会の連動
もしも将来、音楽というものが荒廃していくとしたら、そのときは、人間社会そのものが荒廃してってる、ということになってると思います。
そのくらい人間社会と運命をともにしているのが音楽で、そもそも人間がいなければ音楽を奏でる人もなく、音楽は人間の長い歴史の営みに寄り添って発展してもしてきました。音楽は人の内面を通して初めて世に生まれてくるのだし、だから、音楽の豊かさや深さはそのまま人の豊かさや深さでもあるのだと思います。
その音楽と人間社会のきってもきれなさって、なんなんだろう?と考えました。こういうことを思い煩いはじめて、もう何十年も経ちます。なんでそんなことを考えるかというと、私が、音楽伝達師の末端、どこにでもあるような音楽教室を営んでいるからです。
小さな音楽教室の小さな発見
私は20代の頃、ピアノ教室を営みながら、何を教えていいのかわからなくなったのです。というか、正直に言うと最初っからわかりませんでした。一応生徒にピアノのテキストを買って渡してそれに沿ってレッスンをしていきます。でも、私には肝心のことがわかっていませんでした。音楽ってなに?何の役に立つの?ってこと。「私は音楽の何を伝えたいの?」ってことを患い始めると、それが言い当てられないから表面的なことしかやっていない自分に失望するばかり。生徒にも申し訳ない。なにかはわからないけど音楽大事、というのは自分の中にあったんです。だから音楽を続けました。でも、楽譜の読み方を教えるとか、ショパンの歌心を伝えるとか、なんか、それ、本質的なテーマからすると 枝葉の部分じゃないですか。そういうのがいけないというんじゃなくて、もしもっと幹がしっかりと捉えられていれば、同じことをするにしても、なにか質的にちがってくるんじゃないか・・・・・・
それから、レッスンをすればするほどわからなくなるのが、人。だって人ってあまりに一人ひとり違っていて、なんか、マニュアルが積み上がってかない。教えれば教えるほど沼に落ち込むのも、自分に音楽をすることへの確信が具体的になかった、いや、あるのにそれが何かわからなかった、からでした。こんなんでピアノ教えていていいのかしら、と。
楽しくレッスンする方法とか、コンクール目指して音楽と人間形成みたいな華やかなレッスンのレクチャーなんかを横目に、どうしてもそんなふうにうまくいかない自分に焦りや劣等感も抱えながら、そういうのに対してこれじゃない感もあったりして、とてもやりにくい人生前半でした。
ただ、答えなんかでなくても、それ、を考え続けたことは、私は良かったんだと思います。そうして今がある。そうするうち、あ、そうか、とおもったのが、この文章の冒頭に書いた
”もし音楽が荒廃することがあったら、そのときは人間も荒廃していくんだろう”
ということだったのです。
結局音楽っていうのがなにか、ということは言い当てられない。言い当てられるはずがない。人生後半になって、というか、手当たり次第にいろいろ模索した前半、音楽に対するイメージは深める事ができたことで、むしろ、「これが音楽だ!」なんて言ってしまってはなにか大事なものをとりおとすだろう、ということに気づいてきました。
でも、そうか、と。音楽が豊かである限り、人も豊かなんだ、ということに思い至ったのです。だから、音楽が痩せていかない、ってことのために生きてってもいいんじゃないかなって。
小さな音楽教室ミンネジンガーを目指す
はるか昔、ルネッサンスの時代、フランスではトルヴァトゥールやドイツではミンネジンガーと呼ばれていた教養深い放浪者たちにとって、音楽は修辞学や数学と同じように必須の学問でした。アルテス・リベラーレス(現代語に訳すとリベラル・アーツ)自由七科と呼ばれる学問体系の中に音楽が組み込まれていたからです。自由七科は人が自由を獲得するために学ぶ学問でした。自由七科を学んだトルヴァトゥールやミンネジンガーは、旅を続けながら、音楽を伝えていった、そうやって、西洋の音楽は耕されていったのでした。学ぶことで自由になる、という考え方は、私はとても好きです。
現代の日本では残念ながら、学校での音楽の授業は端へ端へと追いやられています。そして、たとえ音楽大学で学んだとしても、技術は技術、理論は理論で、肝心なその間にある音楽を掴むことは難しい。それは、そもそも、音楽というものの本質的なものの体現としての基礎がまだ根付いていないからです。学校での扱いもその結果なのだと思います。そうして、私が、音楽を伝える仕事を始めたとき、あんなに心もとなかったのも、そうした社会的背景もあったのです。
私はどこにでもあるような音楽教室の講師です。でも、だからこその役目ってあるし、そこに希望を見出すこともできるんではないかって、思います。トルヴァトゥールやミンネジンガーは国の隅々にまで歩いていって歌を歌い楽器をかき鳴らしました。音楽教室は街の隅々にあります。そして、学校のようにこの年令にこれをしなければいけない、というような縛りもないので、学ぶ人も伝える人の手を借りながら自由に自分のペースで音楽を学ぶことができます。つまりじっくりと熟成をかけることができるのです。
サン・サーンス「白鳥」を紐解く
だれでも参加できるワークショップを企画しました。
受講料3500円
毎回、馴染みの曲をえらんで、
音楽的感覚養う方法としてのutena drawingを体験していただきながら
音楽を身近に感じていただけるように
工夫しています。
メンバーシップ|「感覚をひきだすはじまりのワーク」コース
メンバーシップには4っつのコースがありますが、
ちょっと、どんなもの?と覗いてみたい方には
600円の「感覚をひきだすはじまりのワーク」コースをお勧めしています。
初回は無料なので、一月覗いてみてはいかがでしょうか?
面白そうだったら、継続してやってみてください。
ほぼ毎週一回、10〜15分の動画「日々の基礎」をあげています。
百均のスケッチブックとクレヨンかクーピーを準備して
一緒に音楽を描きながら、音楽と自分の感覚の触れ合う場所をたのしんでみてください。
この動画には、utena music fieldの音楽プロセス体験メソッドにとって
基本となる要素を詰が詰めこまれています。
通して、また繰り返してやってみることで、
「音から音のあいだ」へ、意識が向いていく手助けになると思います。
そのほか、ホームページやnoteからの記事の案内や
ワークショップのご案内もいちはやく届きます。
愛媛の片田舎でがんばってます。いつかまた、東京やどこかの街でワークショップできる日のために、とっておきます。その日が楽しみです!
