
【睡眠薬の種類と作用②】
Umito / カラダ・コンサルティングの山本健太です!
理学療法士の資格を持って地域で予防の活動に取り組んでいます!
・睡眠について最低限知っておいてほしい情報
・睡眠習慣を見直す情報 を発信します!
前回は睡眠導入剤の種類と作用について、特にベンゾジアゼピン系薬剤についてお話ししました。今回は、前回の続きで残り2種類の作用についてお伝えします!
メラトニン受容体作動薬
質の高いに眠りに必須なメラトニンホルモンは、そのほとんどが夜間に分泌され、副交感神経の活動を促し、深部体温の低下や血圧の低下など眠りに備える働きを担います。神経系の発達のため、1歳から3歳頃までの分泌量が最も高く、思春期以降低下していき70歳を超えるとピーク時の1/10以下にまで低下します。年齢を重ねるにつれて眠れなくなる要因の1つとなっています。
そんなメラトニンと似たような構造で、メラトニンの受容体と結合させようとするのが、このメラトニン受容体作動薬です。メラトニンの受容体には、MT1とMT2の2種類があり、MT2が主に概日リズムの調整に必要とされています。視交叉上核においてこのこれらの受容体と結合するとメラトニンと同様の反応が起こることになります。比較的安全性の高い薬剤と考えられており、中止時の再発や離脱症状の出現率は低いとする報告が多いです。
この薬の服用で改善がみられる場合、メラトニンが不足してしまうような生活習慣がなかったどうかも検討が必要です。
オレキシン受容体拮抗薬
オレキシンは睡眠と覚醒の制御に重要なホルモンと考えられており、覚醒を促す働きを担っています。オレキシンが視床下部の結節乳頭核に作用することでヒスタミンの分泌を促し、覚醒作用をもたらします。そんなオレキシンの働きを阻害することで入眠させるのがオレキシン受容体拮抗薬です。

オレキシンの受容体であるOX1R・OX2Rの両者に対して抑制的に働くことでオレキシンによる覚醒作用を阻害して、本来のGABAニューロンによる覚醒に対する抑制性の働きを強調するものです。
ストレス負荷においてオレキシン産生神経が活性化するとの報告があり、ストレス反応とオレキシンによる過剰覚醒状態の関連性があると考えられている。このオレキシン受容体拮抗薬で不眠の改善が得られた場合には日常でのストレス反応に目を向けていくことが重要となってきます。
参考文献:明日からの臨床に役立つ睡眠薬の基礎知識.高江洲義和.睡眠口腔医学,April 2016.
日々の眠りをサポートする
”リカバリーウェア“の取り扱い始めました!!
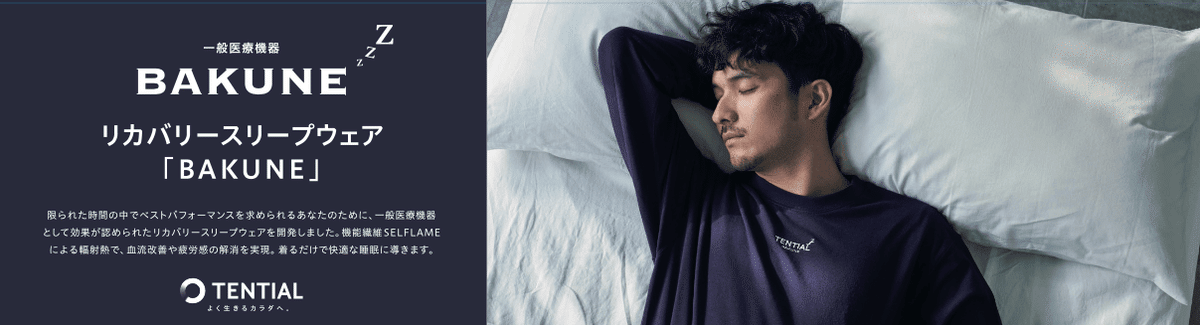
▼販売サイトはこちら▼
https://kencoco.com/shops/umito
▼睡眠について個別の相談はこちらから▼
睡眠習慣コンサル&良眠ピラティスワーク
登録で無料特典(睡眠プチ講座動画・睡眠習慣チェック)
自律神経にまつわる情報満載のオープンチャット
"自律神経の知識箱"はこちらから!
https://x.gd/PiE0p
