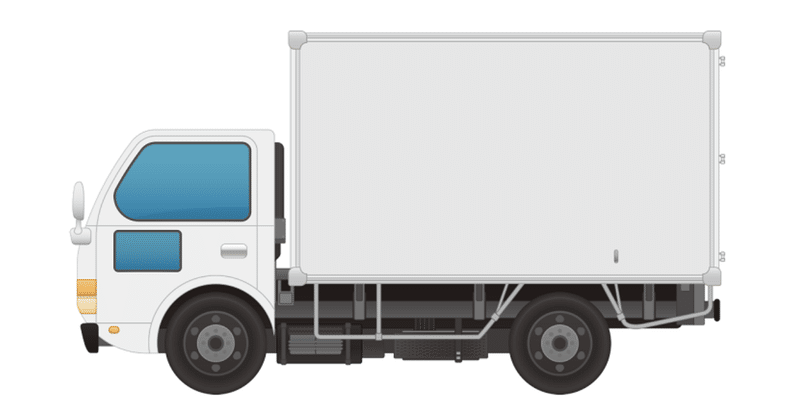
あおり屋
トラックから降りると、ものの5分も経たずに額から汗がしたたり落ちた。首にかけたタオルで俺は額の汗を拭いた。
俺と優也は1トンの保冷車の荷台から食用肉をいくつも下ろし、台車で運んで納品場所である業務用冷蔵庫に品物を納めた。
ここは千葉県のショッピングモール内にある特設会場。明日から土日の2日間で『肉フェス』の開催だ。毎年恒例のイベントで関東のフードフェスタの中でも人気が高い。
俺の勤務する福島県の食肉卸業者は、この『肉フェス』で使用される食用肉を卸している。俺と部下の優也は、今朝早朝、福島を出て午前中に東京のホテルやレストランに食用肉を納品し、昼過ぎに最後の納品場所であるこの千葉の会場にやってきた。
俺は会場の担当者に納品伝票を渡した。
「全部、冷蔵庫さ納品しました。今年から福島牛まで注文いただき、本当にありがとうございます」
「いやいや、なんの。おたくのお肉やわらかくておいしいと評判でね。そこで今年は福島牛を目玉にさせていただいたというわけです」
「感謝いたします」
納品伝票の控えを受け取ると、俺と優也は深々頭を下げた。
担当者が壁際にある段ボール箱を指さした。
「ごくろうさん。あっ、そうだ。まだ冷えてないけど良かったらあそこから好きなもの1本持っていって」
ペットボトルの飲料だった。
「ありがとうございます。トラックの荷台で冷やせっから大丈夫です。どこかのサービスエリアで運転席に持ってきて飲ませていただきますんで」
俺は緑のラベルのお茶を、優也はエナジードリンクを取って、お礼を言った。優也がトラックの荷台の扉を開け、台車をしまい、いただいたペットボトル2本を保冷用のトレーに乗せて、扉をロックした。
2人はトラックに乗り込んだ。俺がハンドルを握り、常磐自動車道を福島に向かった。茨城県に入り、守谷サービスエリアでトイレ休憩をすることになった。サービスエリアの出口方向に頭を向けて車を停め、俺たちはトイレで用を足した。優也が、お先です、と言ってトイレをあとにした。トイレを出ると、俺は自動販売機前でポケットから携帯を取り出し、営業所に現在の位置を報告した。営業所の事務員からは、きょうは猛暑なので熱中症に気をつけてくださいと、ねぎらいの言葉をもらった。首筋に汗が流れる。携帯をポケットにしまうと、自動販売機のお茶が目に入った。ペットボトルのお茶を買い、俺は運転席に戻った。
「さあ、早く帰って、おらほもビール飲むべっちゃ」
「元太さん、いいっすねえ! 早く帰りましょう」
「んだなぁ。タラタラ走ってっと、あおり運転食らうかもしんねえし。最近、多いかんな」
高速道路に戻ると、車は空いていた。眼前にはとても長い直線道路が見える。
助手席に座る優也がドリンクホルダーに置いてあるペットポトルのエナジードリンクを取り、ふたを開けるところを、俺は左側の視界でかろうじてとらえた。
あっ、俺もお茶もらったんだった。忘れて、自販機で買ってきたべ。まあいいか。あれは家で飲むべ。
俺は心の中でつぶやいた。
優也は飲み口をくちびるに放り込み、ボトルを高々と上げ喉を鳴らした。
「ああ、うんめぇぁ」
優也はそれをドリンクホルダーに戻すと、今度は、となりのドリンクホルダーに置いてあるお茶のペットポトルを取り、ふたを開けて、ハンドルを握る俺の左手にお茶を近づけてきた。
「はい、元太さん。気を付けて」
「おお、サンキュー」
俺はそれを取り、左手だけを動かして口に運んだ。
「おお、ひゃっこいなぁ」
ごくごく飲み、ドリンクホルダーにお茶を置くと、優也がふたをしてくれた。
俺は3車線の中央を走行していた。右のドアミラーに目を向けると、うしろから追い越し車線を猛スピードで走ってくる車に気がついた。みるみる俺のトラックに迫ってくる。車は車高が低いスポーツカータイプのクーペだった。
うしろの車が一定の距離を保ちながら、ヘッドライトを瞬間的にハイビームで点灯させてきた。
「なんだ。うしろのスポーツカー、パッシングしてきたべ」
「えっ! あおり運転か! とうとう来たか」
「でもよ。あおり運転って、隣の車線じゃなくて、真うしろにピタッとくっつくべ。なんだろうな。あっ、そうか。荷台が保冷庫だと真後ろにいたんじゃ見えねえから追い越し車線走ってんでねえべか」
「んだ。この車は真後ろが見えないっすよね」
右側からスポーツカーが近寄ってきた。車の鼻先が並び、同じスピードで並走する。
プァー! プァー!
クラクションまで鳴らされた。イラっとする。俺はちらっと右に目を動かした。こちらの運転席が高いからか、スポーツカーの運転手の姿は隠れて見えない。
そのうちに、スポーツカーはスピードを上げて追い抜き、トラックの前に入ってきた。俺はブレーキを軽く踏む。ハンドルを持つ手に力を込めた。スポーツカーが少し減速し、ハザードランプをつけてきた。
「あおり運転だ! コノヤロー! 元太さん、気を付けて!」
優也が叫んだ。
俺は細心の注意を払いながら、減速する。ハンドルを握る手が汗ばんだ。
優也がこちらを向いた。
「元太さん、あおり運転でも大丈夫っすよ。おれが携帯で録画撮るから」
「お、おお。よろしく頼んだや。この車にドライブレコーダーなんぞ付いてねえから」
「ところで、元太さんは喧嘩強いのっしゃ?やたらガタイがいいべや」
「まあな。ラグビーやってたかんな。だから2、3発殴られても立ってられるべ。そこから反撃すっと、相手はおどろくんだべ」
「そりゃあ、心強い。しかも相手が先に殴ってくるんなら正当防衛っすよ。卑劣なあおり運転野郎を逆にボコボコにしてやりましょう!」
しかし、前のスポーツカーは止まることなく走り去っていった。
俺は手の汗をシャツに擦りつけた。
「なんだったんだべ、今の」
「バックミラー見たら、ごっつそうな元太さんだったから諦めたんでねえの」
優也はお茶に手を伸ばし、今度は先に俺に渡してくれた。
若いころの喧嘩で勝った場面を思い返す。アクセルをグッと踏み込んだ。
高速道路は空いていた。
ラジオの音が耳に入る。
≪常磐道下り線、守谷サービスエリアを過ぎた付近からわずかに渋滞≫
「おお、ラッキー! 渋滞に巻き込まれずに済んだな、優也!」
「元太さん、早く帰ってビール飲みましょう!」
俺は中央の車線をスイスイ走り、帰途を急いだ。
しばらくすると、右のドアミラーに小さく黒い点が写っているのを確認した。黒い点はみるみる大きくなり、ベンツだとわかった。ベンツが徐々に接近すると、今度もハイビームを点灯させ、パッシングされた。
またかよ。なんなんだべ。
「今度はベンツだ! またパッシングされたっぺ」
「もう日本中、あおり運転だらけっすね。でも元太さんがいるから安心っす。こうなったら、あおり運転のドライバーの性根叩き直してやるべ!」
黒のベンツが横に並んだ。ウインドゥがスモークガラスで何も見えない。
「こりゃあやばい。ヤクザかもしんね。殴られても平気だども、さすがに刃物でも持たれたらやべえ」
「元太さん、大丈夫っす。俺が携帯で録画撮れば、さすがに刃物は持たねえっしょ」
プーーーーーーーーーーー!
クラクションを鳴らしながら、並走するベンツのウインドゥがスーッと下りた。右ハンドルの車を運転している男は角刈りで黒いサングラスをかけていた。ビシッとスーツを着込んだその男はハンドルに手を置いたまま、ちらちらこちらを向いてはなにか必死にしゃべっているが、まったく聞こえない。
先ほどのスポーツカーとは違って、さすがに今度はビビってきた。
ウインドウがスーッと上がりながら、ベンツは加速した。すかさずハザードランプを点灯させ、このトラックの前に車線変更をしてきた。ベンツの運転席の窓から腕が出て手を下に向けてきた。
車を停めろって言ってんのか。
優也がまた叫んだ。
「今度こそあおり運転だ! しっかり録画してやる!」
ハザードを点けたままベンツは減速し、一番左の路側帯へと車線を変更してきた。
誘導されるまま、俺はハザードランプを点けて、路側帯へ寄せて行った。
お互いの車がハザードを点けたまま路側帯で停車した。
ベンツの運転席のドアが開く。
スーツを着た背の高い男が降りてきて、こちらに歩いてきた。
大きめのサングラスをした男はまるで西部警察の大門刑事だ。
大門なら刑事なのでよいが、この男はヤクザかもしれない。
俺は深く座り直した。
「元太さん、俺、なにかあったらすぐ警察に電話しますから」
「おっ、おう」
優也がズボンのポケットから携帯を取り出す。
ベンツの男が俺の真横まで来て、トラックのウインドウをコツンコツンと叩いた。左手を真横に上げ、うしろを指さしながらなにかを叫んでいる。
うしろに来いと、言ってるようだ。
俺はウインドウを開けなかった。
優也が携帯をこちらに向け、録画をはじめた。
俺は優也に自慢話をした手前、このまま車に閉じこもっているわけにもいかなくなり、意を決した。
「優也、なにかあったら警察に電話してけろ」
「了解! 元太さん、まず相手に殴らせっぺし。そうすれば正当防衛になるべ」
そう言いながら、優也は自分が飲んでいたエナジードリンクを俺に手渡した。俺はそれをごくごくと飲む。ラジオから軽快な曲が流れてきた。Jigsawの『スカイ・ハイ』だ。
俺は深呼吸して、車のドアに手をかけ、外へ出た。
サングラスの男が車のうしろを指さしながら叫んだ。
「おたくのうしろの扉、開いてますよ!」
「えっ!?」
俺は男と車のうしろに回る。
あっ!
荷台の扉が開いていた。
男は、それじゃあ、と言ってベンツに戻っていったようだ。
俺は扉のノブをもち、大きく開け、ステップに足をかけ荷台にのぼった。
中は空き箱やトレーが崩れ散乱していた。どうやら道路にいくつか落としてきたようだ。さらに一番手前に置いておいた台車もない。フェスの担当者からもらったお茶のペットボトルもなくなっていた。
保冷用のファンから冷風が吹き付けてきて、吐く息が白い。俺は膝に力が入らなくなり、その場にへたり込んだ。トレーに腰かけると、尻もおねしょをしたみたいに冷たくなった。
「えっ! 扉開いていたんすか!」
背後から声がした。振り向くと、優也が携帯をポケットにしまいながら、立っていた。
「優也、おめえ空けてたんでねえべか?」
「あっ、サービスエリアでトイレ借りて、そのあと飲もうと思ってたエナジードリンクを取りに荷台を開けました。そのとき荷台の扉を閉めたんですが、取っ手はロックしませんでした。だって、元太さんもお茶を持ってくるだろうと思って。案の定、そのあと元太さんがトイレ終わってお茶を持ってきたじゃないっすか。ってことは、元太さんが締め忘れたのっすか?」
「おい、あのお茶は荷台から持ってきたんでねえ。サービスエリアの自動販売機で買ったもんだ。お茶を荷台に冷やしていたなんて完全に忘れとったべ」
「あれは自販機で買った別のお茶だったのっしゃ? ペットボトルのラベルも緑だから、てっきり、荷台から持ってきたもんだと・・・」
会社に電話すると、別の営業車が落下物を回収してくれるので、おまえたちはこのまま営業所に帰社しろ、との命令が下された。
営業所に到着し、仕事を終えた俺は優也とともに馴染みの居酒屋に入った。
「とりあえず、生ビール2つ。大ジョッキで!」
俺が注文すると、すぐ大ジョッキが運ばれてきた。ジョッキの表面は白く霞んでいた。ジョッキを持つと手がしびれるほど冷たかった。
「カンパーイ!」
2人で冷たいビールを喉に流し込む。俺はジョッキを置いた。
「なんでペットボトル冷やしてたの忘れたんだべ。運転するまえにはちゃんと荷台も確認しねえとダメだな。こんなミスはじめてだ」
俺は肩を落とした。
「元太さん、元気だして。ベンツの男に向かって外に出ていくときはかっこよかったっす」
「おお。そうか」
優也がにこにこしている。
「元太さんを励まします! 今日のお酒が飲めるのは元太さんのおかげです! 元太さん、ありがとー!それイッキイッキ・・・!」
俺は大ジョッキを掲げて椅子から立ち上がり、ジョッキを傾けた。
「よっ! 元太さん最高! これぞ、ラガーマン!」
俺は空のジョッキをテーブルに置いた。
「店員さん! 次は瓶ビール! ラガービールね!」
#あの夏に乾杯 #コンテスト #キリン #PR #ビール #ショートショート #小説 #umaveg #あおり屋 #あおり運転 #キリンラガービール #肉フェス #フードフェス #ドライブレコーダー
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
