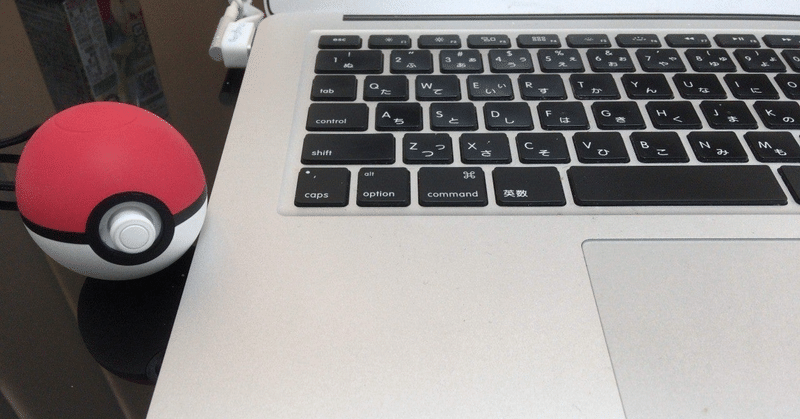
「人文学ならではの悩みと強み」の巻
オープニングトーク
やっぱり日本語はおもしろいと感じることがたくさんあります。
前回、少しだけ言及したことです。
日本語学習経験者の方からの質問はだいたい、
「イ形容詞」とか「ナ形容詞」とか、「マス形」(これはどっかで書いた気がするぞ)とか「ナイ形」とか日本語文法を使うことが多いのですが、日本語学習経験者の人に、国文法と日本語文法は違うんだよ~。と教えると、「え!じゃあ、イ形容詞とか知らないの!?」という話になります。
実際に、自分のまわりの日本人(国文法を学校教育で学んだ人)に「イ形容詞ってわかる?」と聞いてもやっぱりわからないそうです。
英語を教えていた時にも、英語教師として、「助動詞」とか「関係代名詞」とか文法項目を伝えることは少なからずありましたが、「え??なにそれ???」というリアクションを受けることも多く、第二言語としての言語取得の形態は、指導の仕方や学び方にも醍醐味があるなあと感じました。
(元教育者/ポスト教育者としての視点)
人文大学院生としての悩み
さて、最近はというと授業での葛藤があります。
それはなにかというと、授業についていけないということです。
授業についていけないとはどういうことかというと、そもそもアイデアが浮かばないのです。
英語で伝える、ということに関しては、おかげさまでそんなに困ることはないのですが、質問に対して自分の意見が思い浮かばないのです。
人文学というのは、本当にひとそれぞれの意見があり、例えば芸術作品を見たときにどう思うかは十人十色だし、文学作品を読んだあとにどう感じるかも十人十色です。
今、自分が悩んでいるのは、興味のない分野(というと直接的ですが)や知識が圧倒的に不足している分野に関して意見を求められたときのリアクションです。
「ねえ、ハリーポッターの最新作見た?」
「見たよ!」
「どうだった?」
「面白かったよ!」
「面白かったよ!」←この部分をもっともっと広げる必要があるのにもかかわらず、知識がないものに関しては意見が生まれず、ドツボにハマるのです。
「ねえ、谷崎潤一郎の痴人の愛読んだ?」
「読んだよ!」
「どうだった?」
「面白かったよ!」
しかし、大学院生活、(しかもド文系学門)それだけでいいのか!?と自分に言い聞かせています。
例えば、これが
「日本語学習者の音声面でのアプローチについてこの文献では、述べられていますが、それについてどう思いますか?」
「この文献では~ということが述べられていますが、実際には学習者の国籍や母語が大きく影響すると思います。実際に、漢字圏の人と英語圏の人を比べたときに…。また、自分の経験では…。」
というように興味のある分野に関してはかなり強気です。
一方で…(う~ん)
人文大学院に進学する人
人文学問は、少し変わった人が多いです。
ひとつの学問を軸にして、その枝分かれした一つの領域に強い人がたくさんいます。自分の専門分野(学術日本学)に関しては、
歴史・サブカル・神道思想・戦後芸術・児童文学・日中関係
(実際はもうちょっとそれぞれコア)
など、本当にスペシャリストが多くて驚きます。
授業で意見を求められ、困ることはありますが、それよりもほかの人の意見を聞くことでモチベーションを維持できています。
逆に言えば、「言語」の話になると、結構?たまに?話を振ってくれたりするので、その領域の時には「よっしゃ!がんばろ!!」となり、傾聴してくれるコースメイトにとっても「新発見」となるようなきっかけつくりをできたらなあ、なーんて思っています。
まとめ
ということで、明日は早速、意見を求められても
「面白かった!」
という感想文しか提示できない苦手な授業ですが、素敵なコースメイトたちと一緒に学びを深めてきます。
人文学問への進学を考えている人がいれば、自分の分野の知識を身に着けることと同時に、その分野が包括されている学問に興味をもつことが大切かなあと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
