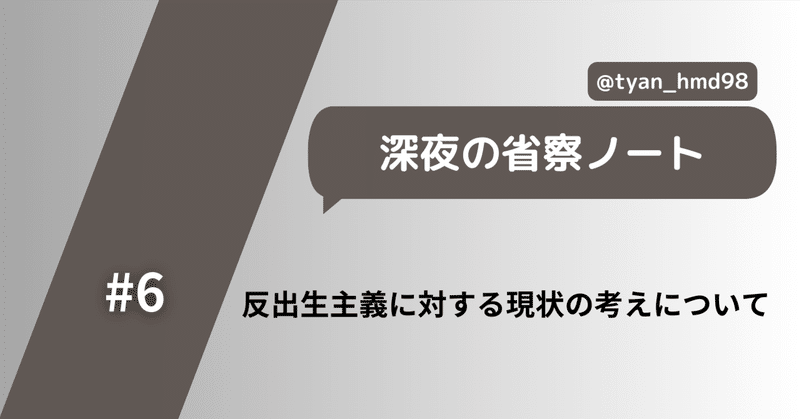
#6 反出生主義に対する現状の考えについて
時おり、私が反出生主義者であるかのような前提で話をされることがある。(恐ろしいことに)もう3年前のことになるが、反出生主義をテーマに卒業論文を執筆したことが始まりだ。
仮にも当時、私が地理学のゼミ、あるいは歴史学のゼミ等に所属していた学生であれば、社会人になってからもここまで卒論のネタがこすられ続けることもなかっただろうとも思う。私は同期の卒論テーマをことごとく忘れているというのに。
哲学的、倫理学的な学術論文にはどうしても、単純な事実、実証・実験の類が指し示す結果の羅列、また純粋な学問的探究心の結実だけには留まらない、当人の思想上の都合が反映されることしばしばである。
実際のところ3年前の、また現在の私自身に、出生という営為に対する疑心暗鬼が無かったと言えば、それは嘘になるだろう。これまでの幾千のポスト(ツイート)のどこか端々に、何か反出生的な含みを持たせていなかったかと聞かれれば、おそらくこれも嘘になる。何か思想上のこだわり、偏りとも言えるものがあるテーマでなければ確かに、2万字以上の打ち込みが最低条件とされる卒論の骨子には採択できない。
しかし私は、反出生主義者ではない。
正しくは、この主義は誰しも掲げることができないものと考えている。
このことについてはこれまで、具体的な説明を避けてきたように思う。もとより、日常的な会話の中で、当人に関わる倫理的態度の深い部分を論議する機会はそうそうやってこない。飲み会の席でいきなり、世界中で当たり前に行われている営為に対してその是非にまつわる議論を展開しようとする者に、次回の飲み会の席はおそらく用意されないだろう。
しかし私の立場について誤った解釈をされ続けるのは本意ではない。大抵この話題で自身へと向けられる視線は、優しくて懐疑的なもの、通常には嘲笑を伴ったものであるからだ。
私自身のためにも、現状の反出生主義に対する考え方をまとめておきたい。
Ⅰ. 反出生主義であるかの判断基準
まずはじめに、反出生主義者であるかどうかを判断するための基準を考えてみたい。それはいたってシンプルで、「子どもを産むべきではない」という文言を設定したときに、その主語が自分自身の中でどこまでの広がり、段階をもつものかどうかを考えてみるとよい。
子どもを産むべきではない…とは思わない
”私は”子どもを産むべきではない
”経済的/精神的余裕がない者は”子どもを産むべきではない
”自分一人で子育てができない障害者は"子供を産むべきではない
”子が苦しむ紛争地においては誰も”子どもを産むべきではない
”世界中のいかなる人間も”子どもを産むべきではない
最下行は紛れもない反出生主義の主張である。主義すなわちイデオロギーとは、その思想を社会普遍的なテーゼに押し上げようとする動機付けを伴う。もし仮に世界中の全ての人間に対して(当然に親兄弟や友人も含めて)、あらゆる不幸の元凶である出生は禁止されるべき、と主張する場合には、反出生主義の標榜者としての自覚と覚悟を持つ必要に迫られる。
しかし私の場合は、主語はせいぜい「”私は”子どもを産むべきではない」に留まっている。そしてこれはただのチャイルドフリーな態度であり、普遍的な広がりを伴う主義の標榜には至っていない。
早い話なら以上で説明は十分である。ところがなかなか、これだけでは納得してもらえない場合も想定できる。
そうはいったところで、卒論のテーマにまで設定して書いておいて、そのうえ何かと厭世的な内容の投稿ばかりしている者の説明など信ずるに値しないと、(相当な杞憂であるかもしれないが)訴追されるところまで考えておかなければならない。
Ⅱ. 反出生主義に至らないでいる理由
私が出生という営為に対して全く懐疑的でないということはない。でなければ、そもそもチャイルドフリーという態度にすら至らないはずである。これは正しい。
少なくとも、子どもすなわち一人の他者を、当人の意思確認を伴わずに(不幸や苦痛を避け得ない世界に)実在させることについては、原初的な暴力行為であるという考え方は私の中に確かにある。
しかしそれが、「主義」として顕実されないのには、出生にまつわる権利そして社会的な実相について、私自身が以下の信条を持っているからだ。
子どもを産むことは歴史的・社会的に認められている自由人の権利であること(本邦であれば憲法13条の幸福追求権が最も近しい)
自由人の権利は何人によっても侵害されるべきでないこと、仮に侵害されなければならない場合、その行使者は社会契約上に位置付けられた権力主体であるべきということ(つまるところは法治主義)
出生による人口の再生産によって維持、発展される文化および文明によって、現在そして未来の自分自身の生活水準が保たれていること
出生はその本質的な生理的欲求性と共に社会的に担保された権利であり、またその結果として存在する多くの他者によって自分という存在そのものも担保されている。前者は法治国家の市民であれば当然に尊重しなければならないものであり、また後者には文明社会に生きる私たちに付帯する事実が描かれている。
冒頭で「反出生主義は誰しも掲げることができない」としたが、これは以上の理由から導出される提言である。社会に生き、また社会によって生かされている以上、その構成員たる市民が反出生主義を標榜することは、自己矛盾の危険性を大いにはらんでいる。
他者の権利を侵害する場合には自分の権利が侵害される可能性を覚悟しなければならないし、また他者によって支えられる社会を否定する場合には、その恩恵に預かる現在の生活を全て放棄する覚悟が必要である。これらの覚悟なしに反出生主義を掲げることは理屈上できないのである。
(R6.2.17追記:以上の論理で言えば、欧州で度々ニュースとなる過激な環境活動家の例が想起される。彼らは例えば石油資源の利用を批判しながら、自らは石油製品の恩恵に、知らずの内に十分与っていることについては言及しない。)
Ⅲ. 出生を抱え続ける社会の責任
ただそうした中でも、何か出生に対する懐疑が消えるわけではない。
自分自身の将来の不安解消(それは孤独や介護といった諸問題)のためという理由で子どもを産むことには違和感を覚えるし、虐待によって子どもが殺されてしまえば、彼らの親に出生の権利は余りにもそぐわないとも思う。子どもの自殺が報道されれば、彼らが生きることを諦めてしまったその瞬間に至るまでに、「生まれてこない方が幸せだった」と、ひとり絶望した夜があったのかもしれないと思いを馳せたりもする。
出生がもたらす当人の実在と、それによって引き起こされる悲劇は決してなくなることがない。以上に列挙したような過酷な実例だけでなく、相対的に幸せな存在であるように振る舞う我々の足元にも、各々の地獄が広がっている。それらの不幸の発端は子を産む我々の、権利によって担保され、社会の維持発展のために必要な営為として見過ごされている、いたって単純な欲求とエゴの結実であることは明白だ。
それでも出生の輪廻から抜け出すことのできない私たちは、せめて出生の暴力性については十分に理解しておく必要がある。そしてその暴力に真っ先に晒される子どもたちについては、大人が積極的に守ってあげなければならない。
小説「かがみの弧城」では、学校に行けなくなってしまった主人公・こころへ、「大丈夫だから、大人になって」と、かつて自分も学校へ行けなかったフリースクールの喜多嶋先生が内で語りかける場面がある。
私たちは同じように、子どもたちへ「大丈夫」と声を掛けることができるだろうか。あるいは相手が子どもであるか否かに関わらず、人が生まれ実在することで抱えざるを得ない悲しみに対して、真摯に向き合うことができるだろうか。
以下にこれまで掲載していなかった、卒論原文の末端を引用してテキストを閉じる。
最後に反出生主義についての見解をまとめておきたい。ベネターの反出生主義を通して我々は、確かに人生には多くの害悪が取り巻いていること、このような世界に新たな存在者を招く(出生させる)ことはやめるべきであるということを理解した。しかしながら、ベネターの主張の何とも歯がゆく面白いところは、これだけ論理的に反出生主義を主張しながらも、その実行が現実的でないことをベネター本人が認めている点にある。
存在者は自らの幸福のために、また社会はその文明の維持向上のために、実に肯定的に新たな存在者を増やし続け、おそらくこの営みは地球が何らかの内的、あるいは外的要因によって生物が住めなくなるまで、あるいは人類が種としての限界を迎えるまで続けられることだろう。その過程において、我々は多くの犠牲を払いながらも着実に、存在することの快楽の程度を高めてきたと言える。人生を豊かにする文化、生活を便利にする発明、人間の安
全保障の要である人権思想などがその例である。人類が存在し続けることは、確かにそれによって生まれる苦痛を保持し続けながらも、同時に多くの快楽も(苦痛による人生の損失を埋め合わせるためとはいえ)生み出してきたのだ。それらは存在することによる害悪を少しでも軽減するための偉大な発明であると言えるのではないだろうか。
では我々は一人としてこの世に生まれてくるべきではないと(原理的に)唱えている反出生主義を、「非現実的で非倫理的な見解」として棄却すべきかと言えば決してそうではない。反出生主義はその逆で、実に現実的で倫理的な思想である。出生主義と言われる我々の営みは、確実に多くの「不幸な存在者」を生み出す可能性を含意する。ベネターが示したような、明らかに十分な子育てができるような状況にない 14 歳の少女を想定したとき、我々は彼女が子どもをもうけないように努めなければならない。すなわち我々は、存在者と非存在者の干渉可能性における非対称性の下で、自らの意志に関係なく生まれてこなければならない子ども達に対して重大な責任を負わなくてはならないのである。生の代替不能性に基づき、充足されるべき出産許容性原理はその一例である。また「死ぬ権利」についても、その意志の純度のような課題はあるが、これもまた生の代替不能性に基づいて、苦しみ続ける他者を無為に生き続けさせることは時として倫理に反し、したがって生死の最終的な判断は本人のそれを最も尊重しなければならないという事実を反映したものである。反出生主義とは、存在することの害悪を我々に認識させ、そして同時に存在の被投性(我々は既に存在してしまっている状態)が将来に渡って継続され続ける限り、その害悪を取り除く努力を怠ってはならないという、実に現実的で倫理的な訴えであると解釈できる。
―存在・非存在の非対称性を巡る議論―
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
