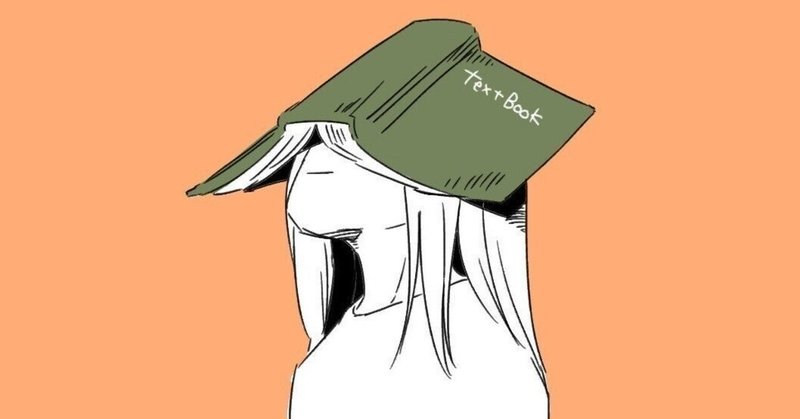
本屋だからこそ生まれる運命的出会いを育てていきたい
自分が働く書店で本を予約した。社割で安く買えるし、貴重な売り上げにもなる。
なんてったって、大ファンのしずる村上さんが自伝(村上純『裸々』KADOKAWA)を発売するというのだ。単独ライブのために東京まで追っかけ、”タフネス”という我に返ると異様なファンネームを嬉々として自称するくらい応援している。確実に手に入れたかった。ドキドキしながら取り寄せの手続きを済ませ、日数を指折りカウントして待ち望んだ。
発売前日、もしかしたら1日早く納品されているのではとわくわくしながら朝の品出しに取り掛かる。さすがに前日から田舎の小さな書店に届くことはなかったが、大型店舗にはすでに納品されているよう。寝る前に、ツイッターのタイムラインをチェックしていると、本棚に陳列されている画像付きツイートが目に留まる。紙の質感や温度感、重みをてのひらに想像して期待はますます膨らんだ。
ところが、納品前日に送られてくるはずの出荷メールがまだ来ていない。一抹の不安が胸をかすめる。送り忘れているだけならいいのだけど。ホームボタンを押し、懸念を振り払い眠りにつく。
迎えた当日。届いたのは本ではなくメールが1通。店頭着は発売日の翌日になるという。
ショックでスマホを落としそうになった。翌日も、翌々日も定休日だ。品出しにときめいてた24時間前の私はどこへやら。途端にごはんを食べる気力すら失せた。手に入ることに変わりはない。作品自体のおもしろさは減りやしない。わかってはいる。
そもそも「発売日にお届けできます」とはどこにも書いていなかった。私が勝手に期待しただけだ。それでも大々的に「発売日に手に入らない可能性あり」と注意喚起してくれてもいいじゃないかと未練がましく思ってしまう。予約したからには、他の本屋で買ったのでキャンセル、なんて不埒なことはできないし。最善を尽くして対応してくださっている現実は、書店員としてきちんと理解している。だけど、だけど、私にとっては「確実に」手に入れたいのと同じくらい、「いち早く」読みたい気持ちは大事だったのだ。
別の本だったらここまで取り乱さなかったかもしれない。作家さんご本人の告知や読書メーターの新刊情報を頼りに、発売日めがけて本屋に行くときはある。それで買えない日もめずらしくないけれど、積読はたくさんあるし、もう少し待てばサイン本が出てくるかもしれない。そうやって、何度だって切り替えてきた。
でも、今回ばかりは簡単に割り切れない。だって、ファンなんだもん。
作家や作品のファンには、新作や続きが気になるという単純な欲求とは別軸の「発売日に手に入れる=ファンとしての本気」的な価値観がある。その等式の前において、お金や理屈はほとんど力を発揮しない。
サイン本が出てきたら?保存用として2冊買えばいいじゃない!となるわけだ(だったら他の店で買って、後日予約した本も買えばいいのだが、金銭感覚を狂わせるのはサインという付加価値)。
他人には「生活ありきなんだから、自分のペースでいい」とちゃんと思っている。それが自分になるとなぜかできない。誰に責められるでもないのに、ほの苦い罪悪感に苛まれるのをどうしようもない。
自分でも面倒くさいなあと呆れるけれど、それをオタクのくだらないメンツと片付けてはいけないと思う。『ハリー・ポッター』シリーズの最新刊の発売日、世界中の人たちがコスプレして待ち望んだ。『鬼滅の刃』最終巻の発売日、書店に行列ができた。「フライングゲット」という言葉が市民権を獲得した。「発売日に自分のものにしたい」欲求は経済を回すひとつの原動力になっているんじゃないか。
その需要に、書店は正直応えきれない。店舗の規模や仕入れの仕組み、出版社の推しなどケースバイケースだが、取次を介している以上スピード感はどうしても落ちる。
一方で、複雑なファンの思いにタイムリーに対応しているのがAmazonだ。当日に届いたとツイッターに投稿した人の多くはAmazonで注文したのではなかろうか。深夜だろうと早朝だろうと欲しいと思ったその時にクリック。早ければその日のうちに届くという。恐るべし瞬発力、Amazon……。
書店の経営・存続が厳しいと叫ばれる背景には、間違いなくAmazonの存在がある。あれもこれも並べたいと棚の前でうんうん唸っている書店員を傍目に、ネットの海に陳列し放題。ベストセラーはもちろん、都会の大型書店じゃなきゃ買えないような学術書もお手の物。速さに劣らず懐もでけえ、Amazon……。
最近では、Amazonの予約数で初版部数が決まるとか。となれば作家さんがAmazonに誘導したくなるのも理の当然。かくいう私だって、noteで本を紹介するときにはAmazonのリンクを貼っている。値段や装丁が一目瞭然。互換性も高いし。信用力、広告力もハンパねえ、Amazon……。
総合すると、Amazon、RPGのラスボス級に強えぇ。
私はネットで買い物をほとんどしないが、浪費癖が発動するのが目に見えているので避けているに過ぎない。生活と折り合いをつけて利用できるなら、抱えている問題が解消されるなら、便利なものは取り入れるに限る。
が、このままだと書店員として収入源がなくなる。それは困る。本屋がなくなるとさみしいとかかなしいとか感傷に至る以前に生死にかかわる。届いた本に傷はひとつもなかった。丁寧に梱包・運搬してくれる方たちには頭が下がる。そういう速さに対抗しうる書店ならではの強みを押し出さねばならない。
「これが欲しい」と目的が明確に決まっているとき、ネットだととても助かる。店内をぐるぐる歩き回らずとも、検索窓に文字を打ち込めば一発で導き出し、クリックひとつで手続き完了。だけど「なんか本が欲しいな」くらいの漠然とした物欲を満たすのには、あまり向いていない気がする。どの商品も情報量が同じで、すべて平積みされている本屋を歩いているような、ぜんぶ太字の教科書を眺めているような散漫な気分になる。
その点、本屋は歩くだけで店の推し具合や売れ筋が肉感的に伝わってくる。同じ本が2列も占めているとか、新刊じゃないのに平積みしているとか、陳列から気合いや情熱が訴えてくる。
書店は返品できるから、手あたり次第仕入れていると思われるかもしれないが、返品すると次の発注時に数を減らされたり、配本してもらえなかったりする。品出し、レジ打ち、経理などの業務に追われながら、補充するか、どこに置くか、一瞬一瞬選択を迫られる。1冊1冊と向き合って、できるだけ多くの本を届けようとしている。だからこそ書店には、運命的瞬間が訪れる。棚挿しされているのに、なんとなく目が合って手に取ってしまった。興味のないジャンルなのに、気づいたらレジまで持っていってしまった。往々にしてそういう作品の中に、今の自分に向けられたとしか思えないことばがあって、救われるような心地がする。
生の本が引き出す"出会い"こそ書店の魅力のひとつだ。
品揃えで個性を出したり、表紙やタイトルを隠して販売したり、トークライブなどのイベントを開催したり、すでに多くの工夫が試みられている。だが、自分の店でもない、入って半年の一非正規社員が思い立ったその日から変えられるのはなんだろう。
私にとってはやっぱり接客だ。デパートの販売員と記者経験を生かせる。
まずは隣のコンビニより、気持ちのよい対応をする。無理に声は掛けない。レジで商品を受け取ったら乱丁がないかチェック、思いやりのある手つきでバーコードを読み込み、心地よい声のトーンで金銭のやりとり、お帰りの際は深々と頭を下げる。それだけでも信頼感を覚えてもらえるようで、お会計を済ませた後、お客様がおすすめを聞いてくださった。後日、紹介した本を買いに来店してくださり、帰り道小躍りするくらい嬉しかった。私も私なりの方法で出会いを生み出している。
電子書籍、活字離れ、ステイホーム、リモート……書店に、特に私のような末端の人間に、残された時間はきっとわずかだ。本屋という営みを守るため、一書店員として何ができるのか。はたまた、しがらみから離れた都村つむぐだからこそアプローチできることは何か。
1冊の本が発売日に届かなかったあの日から、ずっと考えている。
◉村上純『裸々』(KADOKAWA)
いろいろ考えたけど『裸々』を読んでいる間はショックを忘れ、没頭。ショックを吹き飛ばす没入感と牽引力のある作品です。私を夢中にさせるしずるの魅力と作品の感想をまとめた記事もよければぜひ。
頂いたサポートは書籍代に充てさせていただき、今後の発信で還元いたします。
