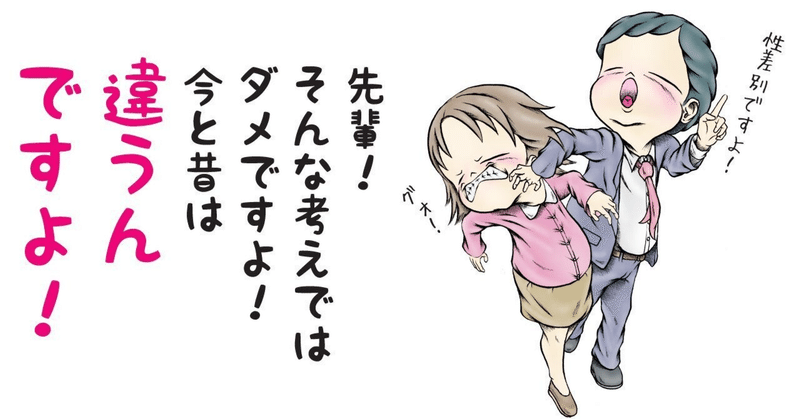
政治講座ⅴ657「流転する世界情勢」
世界第三次大戦の前夜の嵐の前の静けさのようでもある。世界のバランスが崩れ出してきた様相を呈している。どの様な進展が予想されるかは皆目分からない。自国の防衛努力は怠りなくしたいものである。
皇紀2682年12月7日
さいたま市桜区
政治研究者 田村 司
これがプーチンの思惑なのか…!ウクライナ戦争長期化でアメリカに拡がる「陰謀論」のヤバすぎる正体
藤 和彦 - 5 時間前
ロシアで台頭する「武器マフィア」
ロシアがウクライナに侵攻してから11ヶ月が経過した。西側諸国の制裁にもかかわらず、ロシア経済はなんとか持ちこたえているが、その影響はむしろアメリカの方が深刻になっている。
まずはロシアの状況から見ていこう。ロシアの10月の工業生産額は前年比2.6%減にとどまり、9月の3.1%減から改善した。ウクライナでの軍事作戦に新たに動員された部隊の装備などに政府が支出を増加させていることが主な要因とみられている。
しかし、急速に進む経済の軍事化はロシアの政情に暗い影を投げかけている。ロシアで武器を用いた犯罪が急増しているからだ。

急増が懸念されている Photo/gettyimages© 現代ビジネス
ロシア内務省によれば、ウクライナ国境付近のクルスク地方では今年1~10月の銃器、爆発物などを使った武装犯罪は昨年に比べて675%増加した。戦地から遠く離れた首都モスクワでもその傾向は変わらない(前年比203%増)。
長引くウクライナとの戦闘で市民の不満が高まるとともに、武器の入手が容易になったことが関係していると言われている。
ロシア政府は兵員不足を補うために囚人を大量動員しており、「解き放たれたマフィアが今後ロシア社会に大混乱をもたらすのではないか」との懸念も高まっている。
アメリカでも「政治犯罪」急増の懸念
ロシアの政情が不安定化するのは確実な情勢だが、ウクライナを強力に支援する米国では、戦争の影響で「政情の悪化」がより多層的になっている。
元々、銃乱射事件が相次いでいた米国だが、11月上旬に恐ろしい記録が打ち立てられた。複数の犠牲者を出す銃乱射事件が3年連続で600件を突破したのだ。米国では既に4万人近くが銃で死亡しているが、米国人の銃の購入意欲はとどまることを知らない。
今年のクリスマス商戦でも銃は飛ぶように売れているという。

Photo/gettyimages© 現代ビジネス
ハーバード大学によれば、米国で日常的に弾丸を装填した拳銃を携帯している成人の数は2015年から2019年にかけて300万人から600万人に急増している。
社会の分断が懸念される中、「自分の身を守りたい」との意識が高まっていることがその理由だ。
昨年1月の議会襲撃に関与した被告の有罪判決がこのところ相次いでいるが、米ワシントン・ポストが11月上旬に発表した世論調査によれば、88%が「政治的動機による犯罪が今後も増加することを懸念している」と回答した。
「陰謀論」と「秘密結社」に操られるアメリカ
米CBSが同時期に明らかにした世論調査では、79%が「米国はコントロール不能の状態にある」と考えている。そのせいだろうか、米国では公の政治の場でも陰謀論が語られるようになっている。
米民間調査会社ベネンソン・ストラテジー・グループが10月下旬に実施した世論調査によれば、有権者の44%が「連邦政府は秘密結社に操られている」と回答している。
秘密結社は「陰謀論」の基本アイテムだ。米国の代表的な陰謀論サイトQアノンが敵視している秘密結社は、米民主党の政治家やハリウッドスターなどで構成する「デイープ・ステート(影の政府)」だ。
これまで一笑に付されてきた陰謀論がなぜ米国で広がりを見せているのだろうか。
理由は様々だが、筆者は「連邦政府があまりにも巨大化したことにそもそもの原因がある」と考えている。

Photo/gettyimages© 現代ビジネス
米国民にひろがる「生活苦は政府の陰謀」
米国では伝統的に「小さな政府」が好まれてきたが、20世紀後半から連邦政府は肥大化するようになり、この傾向は「テロとの戦い」でさらに助長された。
国民にとって連邦政府は理解不能の存在になったばかりか、安全保障の名の下に生活全般に介入する忌まわしき存在になってしまった。
巨大化した連邦政府を運営しているのは専門家集団だ。
専門家はすべての分野で効率性な統治を目指してきたが、急速に複雑化した行政ニーズに対応することができず、極めて非効率なものになってしまった。
国民は「専門家は優秀だ」と考えているが、その専門家が統治しているのにもかかわらず、日々の生活は悪化するばかりだ。この矛盾した状況に直面した彼らは「専門家が意図的に失敗して私たちを苦しめている」と考えるようになったというわけだ。

Photo/gettyimages© 現代ビジネス
民主主義の議論はこれまで選挙制度など立法府のあり方が中心だったが、政治課題が錯綜し複雑化した現在、立法よりも行政の方がはるかに重要になっている。
だが、行政府のあり方が顧みられることがほとんどなかったため、国民の行政に対する恨み・つらみが陰謀論に投影されているのではないかと思えてならない。
行政に対する不満を募れば募るほど、国民の間で「非常手段に頼るしかない」との思いが強まっていくことだろう。
今年8月に出された世論調査では、米国人の4割以上が「今後10年以内に内戦が起きる」と予測するようになっている。

深刻な危機をもたらしている Photo/gettyimages© 現代ビジネス
すでにアメリカは「内戦状態」
カリフォルニア大学政治学部のバーバラ・ウオルター教授は今年1月、著書「内戦はこうやって始まる」を上梓した。
米国では19世紀後半に南北戦争が起きたが、ウオルター氏が想定している内戦のシナリオは以下の通りだ。
「マイノリテイーとエリートの極左政治家が国を乗っ取ろうとしている」と呼びかける匿名の文書が投稿されると、右派の民兵組織が政府機関へのテロ攻撃を開始する。
その後、これに対抗する形で左派の民兵組織も暴力活動を活発化し、各地でテロ攻撃やゲリラ戦が頻発する。その結果、米国は泥沼の状態と化していくというのだ。
にわかには信じ難い内容だが、陰謀論の広がりはその予兆かもしれない。
行政府のあり方にメスを入れない限り、米国の政情のさらなる悪化は避けられないのではないだろうか。
苦境に陥った「プーチンの将来」…暗殺か、 勇退か、それとも?予測される「4つの可能性」
渡部 悦和,井上 武,佐々木 孝博 - 5 時間前
ウクライナへの軍事侵攻を続ける、ロシアのプーチン大統領。戦況はこう着しており、ロシア国内においても「プーチン離れ」が起きているとの見方もある。これからプーチンはどのような選択をするのか、どのような運命をたどるのか。共著『プーチンの「超限戦」 その全貌と失敗の本質』を刊行した、自衛隊元陸将の渡部悦和氏、井上武氏と、元海将補の佐々木孝博氏が、プーチンの「これから」について語り合う。
噴出し始めたプーチン政権への反発
佐々木 最近私が注目しているのは、プーチン政権を支えてきたパトルシェフ国家安全保障会議書記を中心とする保守強硬派がプーチン大統領に圧力をかけているという報道です。
ロシア研究者の北野幸伯氏によれば、保守強硬派は、「総動員令を出し、一般男性(徴兵期間が一年あるため、完全な素人ではない)を、一〇〇万人単位で、戦場に投入すべきだ。そうすれば、ロシア軍は勝てる」と主張しているそうです。
他方、ロシア国民の七〇%が、ウクライナでの「特別軍事作戦」を支持しています。総動員令を出せば、この支持率は下がり、政権基盤そのものが危うくなります。プーチン大統領としては、保守強硬派の主張を受け入れることはできません。これに彼らは不満であり、プーチン大統領に圧力をかけているとのことです。
その後、この圧力に屈したのか、プーチン大統領は九月二一日に部分的な動員令に署名しました。これを受けてショイグ国防相は軍務経験がある予備役から三〇万人を招集する旨を明言しました。
しかし、公表された動員令には人数に関する記述はなく、独立系メディアによれば一〇〇万人が招集されるとしています。動員令発令後、招集事務所が襲撃を受けたり、国外脱出者が続出したり、招集を逃れるための様々な混乱が生起しています。
当局の思惑どおりの数が招集できるのか、招集した兵が企図どおりに機能してくれるのかなど、不透明な点も多々あります。プーチン政権への反発というものも、この部分動員を機に噴出してきたようです。
これから起こりうる「4つの可能性」
井上 プーチンの特別軍事作戦を盲目的に信じている多数のロシア国民と戦争の実態を承知している保守強硬派とのあいだで、プーチンは身動きが取れなくなっています。ロシア軍はすでに戦意を喪失し、攻撃する装備や兵站も欠乏しています。プーチンは、自業自得とはいえ、厳しい状況にあります。
渡部 プーチンの将来を予測することは難しいのですが、いくつかの可能性を列挙することは可能だと思います。
例えば、(1)大統領職に長期間居座る、(2)後継者を指名し自主的に勇退する、(3)何者かによって強制的に排除され実権を失う、(4)暗殺される。
おふたりはどう思いますか?
井上 (1)のプーチンが長期間大統領職に居座る可能性は低いと思います。たしかにロシア国民の七〇%はプーチンを支持していますが、これは、強力な国内向けの情報戦の成果であり、ロシア軍が敗北している状況をいつまでも隠し通せることはできなくなります。
すでに、モスクワやサンクトペテルブルクなど一八ヶ所の地区区議からプーチンの辞任要求も出はじめています。
可能性が高いのは、(2)の都合の良い後継者を指名し自主的に勇退することだと思いますが、権力を手放した独裁者の末路を考えると、思うようにはいかないものです。
もしプーチンに異変があった場合は……
佐々木 私は(1)、(2)の中間的なことになるのではないかと考えています。四面楚歌の状態に追い込まれつつあるとみられますが、ロシア国内の強力な国民統制の状況から、(3)、(4)は考え難いと思います。
四月から六月にかけて、プーチン大統領の健康不安説を伝える報道が増えていましたが、その後、米CIAのバーンズ長官、英MI6のムーア長官がそれを否定しました。
とくにバーンズ長官は、私が在ロシア防衛駐在官として勤務していた時期と同時期に、在ロシア米国大使を務めていた人物であり、ロシア情勢には詳しい人物です。そのため、バーンズ長官の発言は信頼度が高いものと考えています。
ただし、プーチン大統領はロシアの平均寿命とほぼ同年齢にあるので、年相応の何らかの健康上の不安は抱えている可能性はあります。彼が年相応の健康上の不安を抱えつつも、政務の遂行に問題がなければ、このままの政体が継続すると見積もられます。
しかし、そうでない場合に備え、水面下で影響力を残すカタチで院政的な政体を考えている可能性もあります。
以前から、プーチン大統領に異変があった場合、暫定的に実権はパトルシェフ国家安全保障会議書記に委任されるということが伝えられていました。憲法上では、大統領代行職はミハイル・ミシュスティン首相が就任することにはなりますが、実権をパトルシェフ書記にということのようです。
意外な人物が大統領に就く可能性も?
ロシアの複雑な国家指導体制を熟知し、インテリジェンス組織出身で同分野に大きな影響力を持つ同書記は、プーチン大統領と同じ手法で国家指導することは可能です。プーチン大統領が退いたあと、パトルシェフ書記がその任を引き継ぎ、プーチン大統領が院政を敷く可能性もあると考えられます。
ただし、パトルシェフ書記はプーチン大統領の信頼は非常に厚いものの、メドベージェフ前大統領とは違い、影響力を持ちすぎているマイナス面があるとも言われています。
力を持ちすぎている者に後継を譲ると将来的にプーチン大統領が権力の座から追い落とされるリスクもあるため、パトルシェフ書記自身が大統領に就く可能性は少ないのではないかとの見方もあります。
そこで、その折衷案として浮上しているのがパトルシェフ書記の長男であるドミトリー・パトルシェフ農相に大統領職を移譲し、プーチン・パトルシェフ(父)のタンデム体制で院政を行うといったことも持ち上がっているとのことです。
これは前述の北野氏の指摘ですが、私もその可能性はあるのではないかと考えます。
渡部 いままでも多くの人が予測を外していますので、プーチンが何者かによって強制的に排除され実権を失う場合や、暗殺される場合も排除すべきではないと私は思います。
モンゴルの首都で大規模な反政府デモ 石炭めぐる汚職疑惑で不満爆発
ABEMA TIMES - 40 分前
モンゴルの首都ウランバートルで数千人規模の大規模な反政府デモが発生した。石炭をめぐる汚職が原因とみられている。

で不満爆発© ABEMA TIMES
シンガポールのメディアなどによると、モンゴルの首都ウランバートルで5日、数千人のデモ隊が大統領宮殿を取り囲んだ。15%を超えるインフレによる物価高で国民が生活に苦しむ中、中国に輸出する石炭をめぐり、政府高官に巨額の汚職疑惑が発覚したことで、不満が爆発したとみられている。(ANNニュース)TA会話を始める
キューバ大統領 経済危機で米非難 中露に支援乞う
昨日 16:44
【ニューヨーク=平田雄介】共産党独裁体制のキューバで経済危機が続いている。新型コロナウイルス禍の打撃から回復できず、食料や燃料など生活物資が不足。9月の大型ハリケーンで配電施設が壊れ、電力不足に拍車をかけた。ディアスカネル大統領は11月、支援を求め中国やロシアなど4カ国を歴訪し、1962年からキューバ制裁を続ける米国を非難。自らの責任の回避に努めている。
「配給から鶏肉がなくなり、卵の数が減った。パンの価格は夏から倍増し、政府に対する市民の不満は募っている」。首都ハバナの様子を外交筋はこう語る。
同筋によると、ハバナでは最近、1日4時間の計画停電を実施。地方都市では12~16時間続く突発的な停電が常態化している。こうした状況について、ディアスカネル氏は「米国の妨害によって悪化している」とツイッターに投稿した。
外遊先は、米国主導の国際秩序に不満を抱くロシアや中国、米国からの外交的自立を模索する姿勢が顕著なエルドアン大統領のトルコなど。エルドアン氏は先月23日の首脳会談後の記者会見でディアスカネル氏と調子を合わせ、「両国関係の発展を妨げてきたのは経済制裁だ」と米国を非難し、「両国の貿易額を4倍に増やす」と訴えた。
同月22日のプーチン露大統領との会談では、ディアスカネル氏が「不公平で一方的な制裁を科してくる共通の敵」と米国を非難。ロシアのウクライナ侵略を支持する立場も示した。プーチン氏はキューバの老朽化した発電施設の修理と石油供給を約束したとされる。
石油供給は、最初の訪問地アルジェリアのテブン大統領との同月17日の会談でも議題となり、テブン氏は石油供給に加え、太陽光発電設備を寄付することで合意した。キューバは医薬品やワクチンを供与する。外交筋は「薬と燃料の交換は1970年代から続く両国関係の特徴だ」と話す。
中国の習近平国家主席とは同月25日に会談。ロイター通信によると、習氏は数百億ドル規模とされる債務の見直しに応じ、生活物資やエネルギー危機対策として1億ドルの供与を表明した。中国外務省によると、習氏は「社会主義国家の連帯と協力」を強調したという。
ディアスカネル氏は帰国後、国営テレビのインタビューに「全ての国から支援の約束を取り付けた」と成果を強調した。ただ、経済危機が改善するとの見方は少ない。キューバでは昨年7月に反政府デモが起きたが、その後の裁判でデモ参加者への厳しい判決が相次ぎ、国民は声を上げにくくなっているという。現地外交筋は「ディアスカネル氏は国民の暮らしを犠牲にして強権的な政治体制を維持している」と指摘した。
2023年の中国経済が「三重苦」に直面する背景 ゼロコロナ、不動産不況、輸出減速が波乱要因
財新 Biz&Tech - 昨日 20:00
2023年の中国経済はいくぶん回復する可能性があるが、ゼロコロナ政策、不動産市況の低迷、輸出の減速という「三重苦」に直面する――。大手格付け会社のフィッチ・レーティングスは、来年の中国経済についてそのような見通しを示した。

(写真は上海市松江区政府のウェブサイトより)© 東洋経済オンライン
「現時点で、われわれは2023年の中国の経済成長率を4.5%と予測している。しかし不確実な要素が多いため、この予測には大きな下振れリスクがある」。フィッチの中国担当チーフアナリストを務めるアンドリュー・フェネル氏は、11月24日に同社が主催したオンライン会議でそう指摘した。
同氏によれば、上述の予測は中国政府がゼロコロナ政策を継続することを前提に立てられた。2023年の中国の国内消費は(新型コロナウイルスの感染状況や行動制限の度合いに応じた)政策の影響が避けられず、振れ幅が大きくなる可能性があるという。
消費者は投資より貯蓄を優先
また、フェネル氏は中国人民銀行(中央銀行)の調査データを引用し、「(新型コロナの流行が始まった)2019年末以降、中国の消費者は貯蓄を増やし投資を減らす傾向にある」と指摘した。少なくとも短期的には(新型コロナの流行収束が見通せないため)消費者は楽観的になり得ず、自分の収入と雇用の先行きに強い不安を覚えているとの見立てだ。
不動産市場の低迷に関して、フェネル氏は「(不動産会社に対する融資規制や個人の住宅取得制限などの)引き締め政策の緩和はすでに始まったが、はっきりした市場回復の兆しは見えない。不動産会社の多くは資金不足のため新規投資の余力がなく、2023年も市況の改善は期待しにくい」と予想した。

過去2年余りにわたる輸出の好調は、中国の経済成長の牽引役を果たしてきた。しかしフェネル氏は、「今後数カ月でアメリカやヨーロッパを含む世界規模の景気減速が鮮明になるだろう。その影響を受け、中国の輸出は成長エンジンとして機能しなくなる可能性がある」と警鐘を鳴らした。
(財新記者: 程思煒)※原文の配信は11月25日
参考文献・参考資料
これがプーチンの思惑なのか…!ウクライナ戦争長期化でアメリカに拡がる「陰謀論」のヤバすぎる正体 (msn.com)
苦境に陥った「プーチンの将来」…暗殺か、 勇退か、それとも?予測される「4つの可能性」 (msn.com)
モンゴルの首都で大規模な反政府デモ 石炭めぐる汚職疑惑で不満爆発 (msn.com)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

