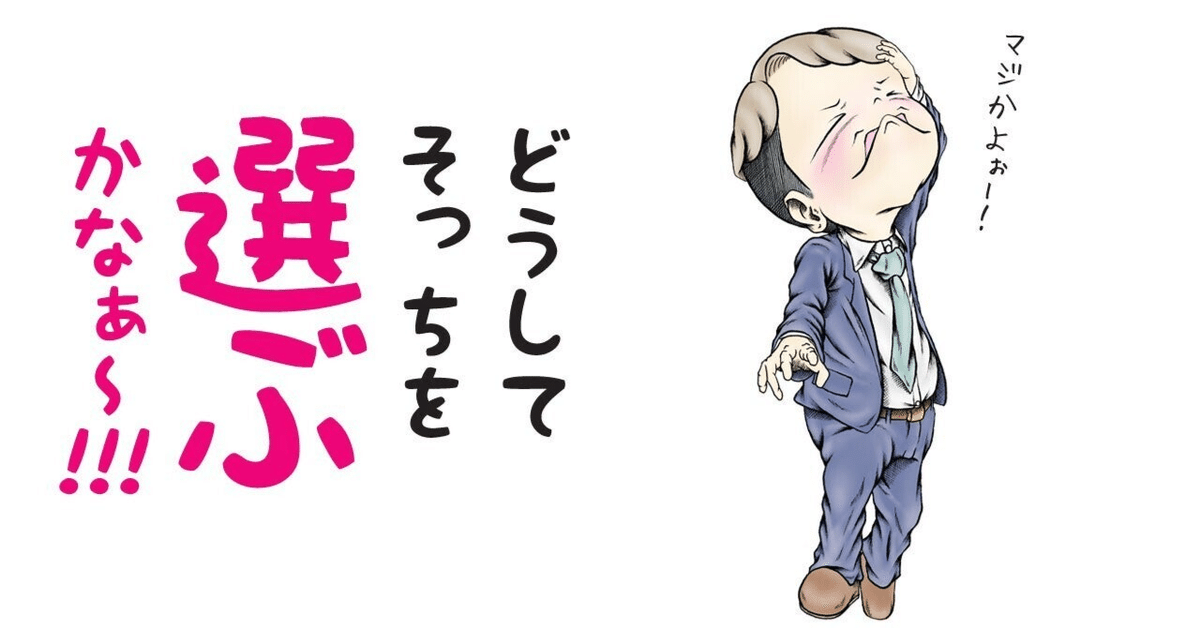
政治講座ⅴ845「外交と内政の失敗、中国は何処に向かう。自暴自棄で戦争か?断末魔の叫びが聞こえる」
習近平氏は外部にも内部にも敵を増やし過ぎた結果が今の事態になっている。「中国の夢」という誇大妄想の帰結である。「中国の夢」は「中華民族の偉大なる復興」と「一帯一路」、二つの部分が構成しているが、戦狼外交で世界に覇権主義をまき散らし、途上国を債務の罠で縛り付けた「一帯一路」は大失敗である。側近は忖度して苦言を呈する者がいない。今や「裸の王様」を揶揄して「全裸主席」と批判されている。報道記事からこのような事態であることが推測される。どんどん悪い方向へ歩みだしている。今般の偵察気球問題は米国の「9・11」テロに相当する程の危機感を米国民に植え付けて心証を悪くした。米国の逆鱗に触れたのである。習近平氏の謝罪がなければ、「遺憾」で済まない程、収まらないほど米国は激怒している。台湾問題は中国の国内問題という抗弁があるが、今回の偵察気球は米国の主権を犯したという抗弁のできない問題であり、米国は決して譲らない。今後の「落とし処(解決策)」の顛末は如何になるのか、乞うご期待。
今の中国は始皇帝の末期を思わせるほど、条件が揃いすぎている。中国の断末魔の叫びが聞こえるようである。
皇紀2683年2月14日
さいたま市桜区
政治研究者 田村 司
組織内の意思疎通に問題か=習氏、気球打ち上げ関知せず―中国
【北京時事】中国から米国に飛来した気球を巡り、米政府高官は9日、「習近平国家主席も関知していなかった」との見立てを明らかにした。昨年10月に中国共産党総書記として3期目に入り、「一強」体制をさらに固めた習氏だが、専門家の間では、組織内の意思疎通が十分でなく、今回の騒動につながったとの見方が出ている。
中国共産党に詳しい神戸大大学院講師で日本国際問題研究所の李昊研究員は「中国では権力が一点に集中する半面、トップに届く情報は限られざるを得ない。大量の情報を全て習氏に報告するわけにもいかず、下の人間にとっての取捨選択は非常に難しい」と指摘する。
政治指導部と軍部の意思疎通を巡っては、2011年、当時の胡錦濤国家主席とゲーツ米国務長官の会談時に行われたステルス戦闘機の試験飛行を、胡氏が事前に把握していなかったというエピソードがある。07年の衛星破壊実験も知らなかった可能性が取り沙汰され、政治による軍の統制が不十分なのではないかという懸念が浮上した。今回の気球の飛行には、サイバーや電子戦を担う軍の戦略支援部隊が関わっていたとみられている。
李氏によると、習政権下では、軍内の対米強硬派が指導部の意向を無視して単独行動を起こす事態は想定しにくい。軍が何らかのデータ収集目的で放った気球の存在が、上層部に周知されていなかったとみられ、そこに「深い思惑」はなかったと李氏は分析する。
一方、別の中国の有識者は「中米関係が改善し、国防予算の割り当てが減る展開を嫌った軍が独自に動いた可能性は残る。ただ、今回の件を把握していなかった習氏が軍の『失態』と見なしていることは間違いない」と話した。
習近平の逆走が止まらない…「肉体労働」を奨励する中国「貧困・失業対策」の時代錯誤な中身
福島 香織 - 6 時間前
「失業対策」にひそむ闇
中国がこのほど失業問題対策として打ち出した「以工代賑」政策が、いろいろと物議をかもしている。
2月1日に、中国国家発展改革委員会が公布した修正「国家以工代賑管理弁法」に「人の手でできることは、出来るだけ機械を使用しない」といった新しい内容が加えられたからだ。
「以工代賑」とは、中央政府によるインフラ工事などで雇用を創出する貧困・失業対策政策で、1984年以降、繰り返し行われ、すでに1750億元以上が投じられている。この政策のガイドラインとして発布された管理弁法は2014年に修正されてのち、今回改めて修正され3月1日から施行されることになった。8章52条からなる。

当局によれば、今回の修正は専門の資金とプロジェクト管理、監督検査などの方面で具体的な要求を盛り込み、新時代の新たな旅路のプロセスにおける以工代賑政策の概念、制度ルール、工程、管理要求をレベルアップして改善したという。
全体として、中央が統括し、省が総合責任を負い、市県郷レベルで実施される。
主に農村部のインフラ建設プロジェクトで、中央が投資計画の基本内容を規定し年度投資計画を省レベルに伝え、定期的に調整し、状況を監視監督する。
プロジェクトごとの資金の範囲、建設領域内で、発展が遅れた地域に資金を振り分け、公益性のあるインフラ建設や産業発展に合致したインフラ建設を行う。目的は民衆を建設労務に参与させ報酬を分配することで、資金の内訳は労務報酬が最大であることが強調されている。
「ニューディール」に似ても似つかない・・・
またプロジェクト実行に当たり、民衆を組織し、技能研修を行うことも要求されている。
以工代賑投資計画の対象となるインフラプロジェクトとは、主に交通、水利、エネルギー、農業農村、地方都市建設、生態環境、災害後復興など。プロジェクト前期の任務としては、まず民衆を組織し、労働技能研修や安全研修をうけさせ、労務報酬を管理、支払うための具体的な要求を明確にする、とした。
また、このプロジェクトで、ニセの労務組織を作るなどして労務報酬をだまし取るような詐欺行為がないよう厳しく管理、総合評価するメカニズムも作る、としている。
米国の1930年代のルーズベルト大統領によるニューディールの一環で取られた失業対策に似ている、と言う人も、日本の技能研修制度に似ているという人もいる。
このプロジェクトは貧困弱者層に対する特殊な救済政策であり、これまでも継続して行われてきた。2022年は500万人の民衆を地元で就業させ、一人当たりの平均増収は8000元を超えた、とされる。
2023年版以工代賑と2014年版との違いは、新たな総合救済モデルを提示している点だ。単に貧困層に労務報酬を出すだけではなく、1.公益性インフラ建設+労務報酬+技能研修+公益性のある管理職ポスト開発をセットにしたモデル、2.産業発展に合致するインフラ建設+労務報酬+技能研修+資産の割引株式化配当をセットにしたモデルによって、管理職に出世したり株式保有の機会もある。
また技能研修を行うことで、プロジェクト終了後も、習得した技術によって新しい仕事を探すことができる。さらに労務報酬が投資全体に占める割合をもともとの15%から30%以上に引き上げた。
だが、26条と28条に含まれる内容が物議をかもしている。

地方組織の「腐敗」と「利権」
26条では、以工代賑プロジェクトは競争入札で事業者を選ばなくてよく、いかなる組織、個人も入札を強要してはならない、とある。
これは建設許可、手続きの簡素化のためもある。
さらに28条では、県レベルの発展開発当局は、以工代賑プロジェクトの事業組織、施工組織が、「人の手でできる部分は機械を使用せず、民衆を労務者として組織し、専門の施工業者チームを用いない」という要求に従うよう指導する、とある。
競争入札を行わない、ということは上層部が事業者を指定するということであり、その決め方には必ず癒着や汚職の問題が起きるだろう、という懸念の声がある。
競争入札しないプロジェクトとは、もともと次のように決められていた。
1.一般に国家安全、国家機密に関わるか危険な災害救援が伴うもの
2.貧困救済資金で行われる以工代振で出稼ぎ農民を雇用する場合
3.施工主が求める技術が特定及び専門性の高い技術である場合
4.施行企業が自ら建設し自ら用いるプロジェクトで施工企業がプロジェクトの要求に合致している場合

しかし、これまでの以工代賑では「複雑な技術などが必要で適宜入札行われるプロジェクト以外は、入札制度を実施しなくてよい」とあり、実際は適宜入札が行われてきた。
入札を一切しなくてよい、となると、おそらくは郷鎮、村の幹部たちのコネによる業者が、貧しい村民を組織し研修し、報酬を管理することになる。
きちんと管理されているかを審査する組織も結局、共産党末端組織となると、従来からある汚職構造の中に落とし込まれることになるだろう。
そもそも、入札しても様々な汚職が起こるのだから、こうしたプロジェクトが地方のレベルの低い共産党末端組織の利権になることは避けられまい。
労働力の「無限採掘」、人民は「消耗品」…習近平が歴史的大逆走!失業対策にひそむ「壮大な思想」の「危なすぎる中身」
福島 香織 - 5 時間前
中国で打ち出された失業対策「国家以工代賑管理弁法」が、物議をかもしている。
なんでも、「人の手でできることは、出来るだけ機械を使用しない」といった内容が加わり、地方の環境改善のためのインフラプロジェクトを実施し、労働者を大量に雇い入れようというのだ。
一見、理にかなった政策にも見えるが、中身をつぶさに検証すれば、役人の汚職をいっそう助長しかねない内容も見えてきた。
さらに、人民を使い捨てとするかのような「歴史的大逆走」の政策になる可能性も懸念されている。

暴走しかねない「労働環境」
2月1日に、中国国家発展改革委員会が公布した修正「国家以工代賑管理弁法」(8章52条)の内容をつづけて、見ていこう。
特に28条では、人の手でできることはできるだけ機械を使用せず、民衆を労務者として組織し、出来るだけ専門の施工チームは使わない、と要求している。これはが地方レベルの共産党末端組織の利権化を助長しかねないが、さらにプロジェクトのクオリティや施工に従事する労務者の安全などに配慮しないということにならなかいか、という見方がある。
当局側は、「工程のクオリティ、安全に影響の出ない前提での話だ。雇用増収作用を発揮するためであり、出来るだけ多くの地元民衆が建設プロジェクト参加できるようにして、地元民衆に多くの労働報酬を支給できるようにするということだ」と説明しているが、これをそのまま信じる人はすくない。
この新版以工代賑についてはルーズベルトのニューディール政政策と比較して論評する声もあるのだが、中国の以工代賑はニューディール政策のように長期的目的のインフラ建設プロジェクトではなく、貧困地域に一時的な雇用を作り出すだけの規模のものであり、しかもニューディール政策のようにフェアな労働基準が盛り込まれていない、という指摘もある。
以工代賑では中央の投資額の30%以上を労務報酬に充てるという基準があるが、機械をできるだけ使わず、熟練の専門施工業者を使わず、地元農民を労働者として組織して建設に従事させよ、ということは、農民を酷使せよ、ということ同じであり、結局のところ動労者の権益保護にはまったくつながっていない。

しかも、この労務報酬の割り当てについては、共産党末端組織が決めるとなると、やはり郷鎮村の幹部たちが多くとり、末端の農民は低賃金で肉体労働を行うことになりはしないか。
もちろん中国の労働法では残業代や最低賃金の規定があるが、それは多くの現場で無視されている。地方のインフラや施設建設の現場では、実は労働者が負傷したり死亡したりする労災事故は非常に多い。
最大の理由は、肉体の酷使を要求されるために、注意が散漫になったり、外国なら機器や安全設備の補助がある環境で行う作業を体一つで行わせたりするからだ。
さらに工事にかかる時間の効率やインフラのクオリティが犠牲になることは間違いない。これはすでに地方で多くみられる豆腐工事とよばれる脆弱な建物やインフラの量産につながりかねないものではないか、ということである。
時代と乖離した儒教思想「養民」
もともと、中国における以工代賑は儒教思想の中にある為政者の「養民」の発想だ。
災害・飢饉などで農村などのコミュニティが崩壊すると、飢えた難民流民が良からぬことをする、それがしばしば社会動乱を引き起こし王朝の転換を引き起こしてきた歴史から、為政者は民を養うことに腐心してきた。
中国史で有名なのは北宋の官僚政治家で文人の范仲淹の以工代賑で、全国的に飢饉が発生したときに、決まりによって国庫の糧食を放出してもとてもそれで救える数ではない飢えた民が各所に現れた。
だが、その緊急時に、杭州の知事であった范仲淹は、あえてドラゴンボートレース(競渡)を開催し、大寺院に対して飢饉のときの工賃は安いからと大土木工事などを行わせた。
中央の監察官は、范仲淹が競渡にふけり、公私の建築工事で民を消耗させている、と批判したが、范仲淹は、競渡の集客で消費が増え商いが盛んになり、寺院工事などで民の雇用が増えた、これぞ以工代賑(仕事でもって救済に代える)だ、と説明した、という。
つまり以工代賑は中国1000年の智慧であり、民の困窮を放置しておくと、社会動乱が起きかねない、という支配者サイドの教訓が根っこにある。

だが今、21世紀で、大卒や高専の若者の失業が問題視され、さらに「躺平主義」(寝そべり主義)が蔓延し、働かないこと、競争しないこと、努力しないことが一種の体制への反抗スタイルになっている状況で、機械や専門知識を使わない肉体労働の雇用を創ったところで果たして、それが失業対策、貧困対策になるだろうか。
たんに地方汚職の温床を一つ増やすだけにならないか。
労働力の「無限採掘」というあぶない発想
そして人民がこの政策に感じるのは、「人鉱」という最近の流行語に象徴されるように、共産党政府が人民を鉱物のように無限に採掘できる消耗品であるとみなしているということだ。
この政策の責任者は、発展改革委員会主席は何立峰。昨年の党大会で政治局メンバーとなり、3月の全人代でおそらくは副首相、劉鶴の後釜に収まり、習近平の経済ブレーンになるお気に入り経済官僚だ。

もし、この新版以工代賑が、何立峰の習近平に対する出世の手土産だとすると、つまり習近平好みの政策を打ち出して見せたということなら、習近平第三期目の経済の行方がどんな感じか、想像できるのではないか。
毛沢東時代回帰どころか、1000年回帰の発想の経済になるかもしれない、ということだ。
何をやってもダメな中国 中国経済、不動産が大暴落 地方政府が背負う借金は約930兆円 「一帯一路」崩壊も時間の問題 カネ貸した国のデフォルト相次ぎ、回収困難に
中国経済は「悪性スパイラル」に陥没した。何しろ、GDP(国内総生産)の約30%を占めた不動産がさっぱりで、大手デベロッパーの倒産が続いている。
中国の地方政府が背負う借金は約7兆ドル(約930兆円)とされる。日本のGDPの1・7倍! 例えば、貴州省の遵義道橋建設集団は昨年末、銀行融資の返済を20年間延長してもらった。
地方政府の融資平台(LGFV)は、当該地方のインフラ建設のためのプロジェクト資金として起債され、利率は8~12%である。高い金利の魅力にひかれて相当消化されたようだ。
ところが、投資家たちは地方政府の債務保証がされていなかったことに気がついて慌てた。高利に釣られて投資した人々は「詐欺だ」と騒ぎ出した。5年ほど前から、欧米の投資家は中国の地方債を避けてきた。
中国では「城投債」(都市投資債)として知られるが、「担保」のはずの土地入札も、民間デベロッパーの応札がなくなり、国有企業への押し売りが横行している。
中国不動産バブル崩壊の代表例が不動産大手「中国恒大集団」である。社債がデフォルト(債務不履行)となって投資家のカネ返せ抗議活動が本社前を囲んだのは2021年からだ。22年1月には同社株が香港株式市場で取引停止となった。
22年7月には夏海鈞最高経営責任者(CEO)が辞任した。ローンの支払い拒否運動が広がり、下請け業者への代金未払いが発生した。恒大の負債総額は1社だけで33兆円。
あまりの巨額負債に潰そうにも潰せず、かといって救済するわけにもいかない。次の共産党の出方を待った。いまのところ、建築を中断したマンションの完成を急がせるために、融資再開を銀行に命じ、ローン支払いボイコット運動の沈静化を図っている。中国全土でマンション価格の値崩れが激しく、中には半額セールもある。
世界中に展開してきた巨大経済圏構想「一帯一路」も、スリランカ、パキスタン、ザンビアなどでデフォルトが相次ぎ、貸したカネの回収が難しくなった。
輸出が好調な理由は、最終組立をベトナムやカンボジア、タイ、スリランカなどへ移転し、「MADE IN CHINA」のラベルを張り替えて高税率を回避しているからだ。一方で中国企業がアジア各国に進出して、国内産業の空洞化も生まれてきている。 (評論家・宮崎正弘)
参考文献・参考資料
組織内の意思疎通に問題か=習氏、気球打ち上げ関知せず―中国 (msn.com)
労働力の「無限採掘」、人民は「消耗品」…習近平が歴史的大逆走!失業対策にひそむ「壮大な思想」の「危なすぎる中身」 (msn.com)
習近平の逆走が止まらない…「肉体労働」を奨励する中国「貧困・失業対策」の時代錯誤な中身 (msn.com)
何をやってもダメな中国 中国経済、不動産が大暴落 地方政府が背負う借金は約930兆円 「一帯一路」崩壊も時間の問題 カネ貸した国のデフォルト相次ぎ、回収困難に (msn.com)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

