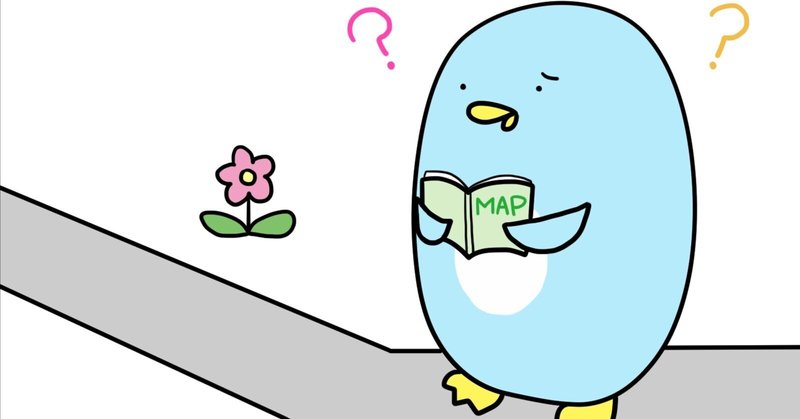
【歴史18】オランダ史備忘録12
オランダ史の学習を深めていきます。
本日は、
①戦後のオランダ政府が経済復興を実現するために
とった方法は賃金と物価の後押しであった。
②政府は賃金抑制は労働者から反発を受けやすいため労働者と雇用者の間で利害調整を行い労使紛争を未然に防ぐ努力をした。これがコーポラティズムである。利益集団を政府・労働者・雇用者の3者に限定し分析するのがネオ・コーポラティズムである。
③1950年頃にあったドレース政権は社会保障など福祉制度の拡充に努めた功績がある。
ベール内閣の閣僚だった1947年には65歳以上を対象とする老齢年金給付のための特別立法を成立させた。1956年は65歳以上の高齢者に毎月給付金が支払われる一般老齢年金法を導入した。
④1970年代に2度起こった石油危機で転機を迎える。石油危機の際には天然ガスの輸出が増大し自国通貨フルデンの為替レートが高騰し労働賃金も上昇した。一方為替レートの上昇がオランダ製品の国産競争力を低下させた。これにより失業者が増加した。
⑤この後は景気低迷と物価上昇が同時に起こるスタグフレーションが起こった。失業率は一時14%になったが政・労・使の協調で不況を打開していった。
⑥1982年のルベルス政権(キリスト教民主同盟)はワッセナー合意で各々の調整をした。続くコック政権(労働党)では労働関連法の改正が行われ労働者1人の労働時間を短縮し雇用を確保するワークシェアリングが普及した。
同一価値労働・同一賃金の原則とフルタイム労働者とパートタイム労働者の待遇面などの格差を是正した点が特筆される。正社員とパート従業員の区別はなくなり同等の労働に対し同じ賃金が支払われるようになる。この雇用改革がオランダモデルである。
⑦オランダの労働者の働き方は3つある。一つ目は週35時間以上で週休2日のフルタイム労働、二つ目は週20時間から34時間で週休3日の大パートタイム労働、三つ目は週19時間以下で週休4日以上のハーフタイム労働である。
⑧1988年からの10年間で約120万人の新規雇用があったが7割以上がパートタイム雇用だった。失業率の低下と経済成長を同時に成し遂げた事はオランダの奇跡と云われている。
その後オランダの雇用・福祉政策は給付型から参加型へと転換している事などを学びました。
■参考文献 『1冊でわかるオランダ史』 水島 治郎 河出書房新社
学習教材(数百円)に使います。
