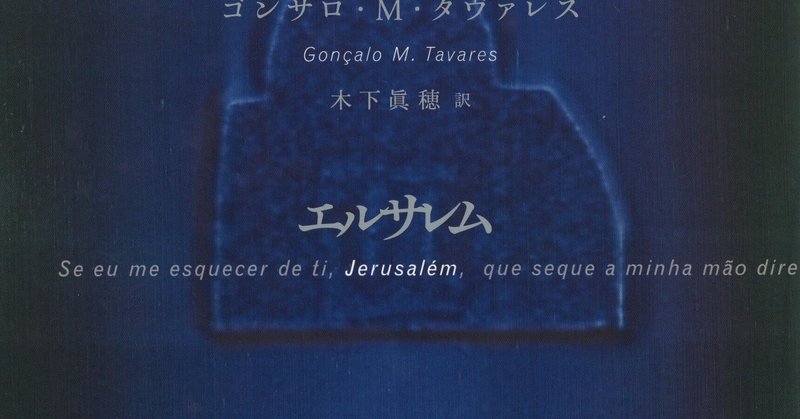
『エルサレム』(ゴンサロ・M・タヴァレス(著)、木下眞穂(訳)、河出書房新社)――訳者(になったつもりで)解説
2021年12月5日に、書評家の豊崎由美さんによる翻訳者向け書評講座を受講しました。今回の講座では、下記の課題書(1)~(3)から一冊を選び、(A)(B)どちらかの形式で書評か解説を書き、当日は、豊崎さんの講評をいただいた上で、参加者全員で合評を行いました。
(1)『エルサレム』(ゴンサロ・M・タヴァレス(著)、木下眞穂(訳)、河出書房新社)
(2)『クイーンズ・ギャンビット』(ウォルター・テヴィス(著)、小澤身和子(訳)、新潮社)
(3)『キャビネット』(キム・オンス(著)、加来順子(訳)、論創社)
(A)書評(800〜1600字、想定媒体を明記)
(B)訳者解説(1600〜3200字)
私は、課題本は(1)の『エルサレム』を、形式は(B)を選びました。
『エルサレム』は、個人的には、課題書の中で一番難解で、かなりチャレンジングな選択をしたと思っていたのですが、ふたを開けてみると、なんと18本の原稿のうち12本が『エルサレム』という人気ぶり! これは少し意外でした。なぜなら、課題書(2)(3)は一読目から「おもしろいな~」とぐいぐい読み進められるのですが、『エルサレム』の一読目は「……。」と感想がうまく言葉にならない感じだったからです。でも、多くの参加者がこの作品を選んだということは、『エルサレム』が難解ながらも多くの人をひきつける魅力にあふれた作品ということなのでしょう。
(B)の「訳者解説」とは、もしも自分が『エルサレム』の翻訳をした訳者で、あとがきで解説を書くとしたら……という設定で書くもので、「訳者(になったつもりで)解説」ということです。なお、今回の文章を書くにあたり、『エルサレム』の翻訳者である木下眞穂さんの「訳者あとがき」を大いに参考にさせていただいたことを、ここに記します(もちろん、以下の文章の文責は私にあります)。以下、講座受講後に修正を加えた私なりの解説文です。
**********************************
一九七〇年生まれの作者ゴンサロ・M・タヴァレスは、現在、著書が約五〇カ国で出版され、国内外で高い評価を受けている、二十一世紀のポルトガル文学を代表する最重要作家の一人である。二〇〇五年(作者三五歳の時)に出版した本書『エルサレム(原題Jerusalém)』は、レール賞、ジョゼ・サラマーゴ文学賞、ポルトガル・テレコム文学賞(現オセアノス賞)とポルトガル語圏で重要な数々の文学賞を受賞し、ポルトガル国内でベストセラーとなった。本作は、タヴァレスの最初の長編群である「王国」をテーマにした四部作の第三作にあたる。この作品群で、タヴァレスは悪のメカニズムの解析を試みたという。本作から垣間見える断片像からも、タヴァレスの構想する暗黒の王国の全体像がいかに深遠で広大なものか、十分にうかがい知ることができる。
物語は、不治の病におかされたミリアが、教会を探そうと夜明け前の町に出る場面から幕を開ける。もうすぐ四十歳になろうとするミリアは、十八歳の時に、統合失調症の治療のために訪れた医院で、精神科医のテオドール・ブスベックと出会い、約二年後、二人は結婚する。その八年後、ミリアの病状の悪化により、テオドールは、ミリアをゲオルグ・ローゼンベルク精神病院に入院させるが、同病院の患者エルンスト・スペングラーとミリアが性的関係を持ったことが発覚し、一方的にミリアと離婚する。そして今、精神病院を数年前に退院したミリアは、一人夜の町をさまよう。時をほぼ同じくして、様々な人々――長年音信不通だったミリアからの電話を受けたエルンスト、劣情にかられ風俗街を目指すテオドール、娼婦のハンナ、銃を所持し危険な欲望をたぎらせる元兵士ヒンネルク・オブスト、夜中に父テオドールの不在に気づいた十二歳の少年カース・ブスベック――も、ミリアがさまよい歩く夜の町に次から次へと出ていく。物語は、各章ごとに様々な登場人物たちに焦点をあて、過去と現在を行きつ戻りつしながら展開する。
テオドールは、精神科医であると同時に、新進気鋭の研究者としても知られている。彼は、歴史上いつどれほどの恐怖が発生したのかを調べ、恐怖と時の関係性をグラフ化することにより、未来を予測できる公式を発見しようとしている。恐怖が発生した現場としてテオドールが対象としているのは、強制収容所や流刑地であり、戦争は除外している。テオドールの研究対象は、「片方(註:=弱者の側)には相手側に死者を生じさせる可能性――もしくは意思――が一つとしてない状況(中略)そして強者の側にはなんら正当な理由もなく、あるいは少なくとも大きな正当性がない恐怖という状態で、弱者の側を破壊しつくした」状況だからだ。そして数十年にわたる研究の末、ひとつの理論を発表する。「〈人民A〉が〈加害者A〉〈被害者A〉となった時、つまり加害・被害の人数が完全な一致を見た時にのみ、歴史は終焉を迎える」という説だ。さらに、この理論を個人にも適用し、「一人の人間が世界に対して送り出し、受け取った善と悪のレベルがゼロになる」時に死が訪れるとする。あらゆる人民、あらゆる個人は、被害者にも加害者にもなりえ、集団の歴史にせよ個人の歴史にせよ、暴力を受ける側と与える側で釣り合いを取りながら進むのだという、この突飛な理論は、発表直後は識者の間で物議をかもしたものの、しばらくすると「少し頭のおかしな人が書いた奇書」として世間から忘れ去られた。
だが、この理論を全く荒唐無稽の理論として無視してよいものだろうか。本書『エルサレム』では、誰もが被害者にも加害者にもなりうる可能性が示唆されているように思われる。例えば、テオドールが実子として引き取った元妻ミリアとエルンストの息子であるカースは、生まれつき脚が不自由で身体的には弱者であるが、老いて視力を失い椅子から自由に身動きの取れない祖母を、背後からたわむれにこぶしで殴りつけるという行為におよぶ。弱者と強者は相対的なもので、もろもろの条件により立場が逆転する可能性がある。テオドールも自らの理論の中で、「『強者』とはすぐ隣にいる者と比較して強いということである」と定義している。また、ミリアが入院していたゲオルグ・ローゼンベルク精神病院では、治療という名のもとに、肉体的にも精神的にも患者の尊厳が踏みにじられている。院長のドクター・ゴンぺルツは、患者それぞれの問題行動のみならず、問題とされる思考を正すことを目指している。狂気と不道徳には関連性があると考え、「狂人とは不道徳な行ないをする者のことであるが、(中略)不道徳な考えを持つ者は、やはり狂人である」と信じている。だが、異常(狂気)と正常、不道徳と道徳を分けるものは、判断する側の恣意であり、テオドールの理論が狂人のたわごととされたように、誰もが判断される側にまわる可能性がある。行動面のみならず思考面すらも管理される治療という名の暴力に、患者たちは深く傷つき、退院後も忘れられない痛みを抱えることになる。
ミリアが精神病院で受けた忘れられない痛みを象徴する「ゲオルグ・ローゼンベルクよ、もしも、わたしがあなたを忘れるなら、わたしの右手はなえるがよい」という言葉は、旧約聖書の詩編一三七編五節「エルサレムよ、もしも、わたしがあなたを忘れるなら、わたしの右手はなえるがよい」がもとになっている。この詩編は、バビロン捕囚にあったユダヤ人が、故郷のエルサレムへの想いを詠んだものである。その後、国を持たない流浪の民となったユダヤ人は、各地で様々な迫害にあいながらも、一九四八年にエルサレムを首都とする(註:日本を含め国際社会の大多数には認められていない)イスラエルを再建するまで、被虐の痛みをともなう望郷の念をこめ、この詩編を口ずさんだ。ユダヤ人が受けた迫害の中で、最も有名かつ凄惨なものは、ナチスドイツによる組織的・国家的なユダヤ人大虐殺(ホロコースト)だろう。優生学の名のもとに、悪名高いアウシュビッツ強制収容所などで約六〇〇万人にもおよぶとされるユダヤ人の命が失われた。この時、ロマ族などの少数民族や精神・身体障害者も劣った人間とみなされ殺害されたが、優劣の判断は言うまでもなく恣意的なものである。本書を通し、旧約聖書の詩編一三七編五節になぞらえたミリアの言葉は、特定の集団や個人の痛みにとどまらず、過去、現在、未来における、あらゆる人々の痛みの象徴として読者の心に刻まれる。
(二六二四字)
**********************************
<講座受講中にいただいたコメント/アドバイスの一部>
・第3段落
テオドールの理論はただでさえ難解なのに、抜粋ではきちんと読者(特に、あとがきを先に読む読者)に伝わらず、小難しいだけの印象を与えてしまうかもしれない。
→確かに、自分の文章を再読してみると、やたら小難しい感じがしました。改善しようと試みたものの、あまり改善されていないかもしれません。
・最後の段落
最後のしめの部分で、もう少し普遍的な方向に持っていくほうがよい。
→この段落、修正前はユダヤ人に焦点を当てた終わり方にしていたのですが、全ての人にあてはまる物語として書き直しました。
講師の豊崎さん、まとめ役のNittaさん、他の参加者のみなさん、密度の濃い学びの時間をありがとうございました!
Nittaさんのブログより↓
版元ドットコムのサイトより↓
#本 #読書 #海外文学 #書評 #豊崎由美 #エルサレム #ゴンサロ・M・タヴァレス #木下眞穂 #河出書房新社 #翻訳
