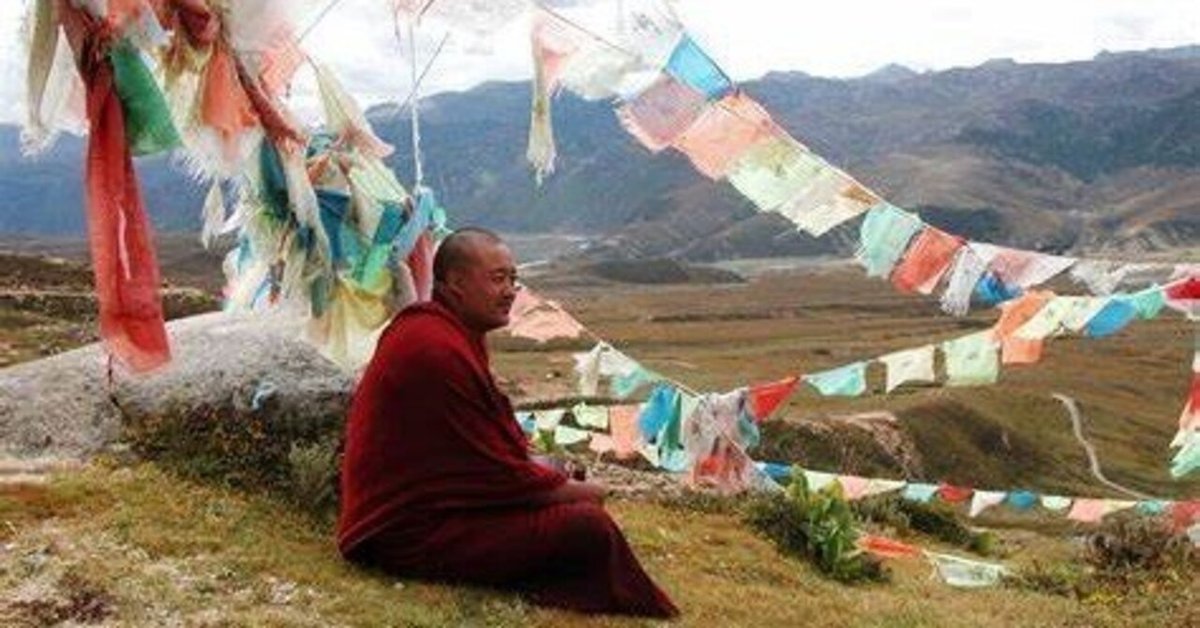
6月11日 高僧生まれ変わりとして育てられ、「やっぱり違った」とハシゴを外された男の話。
チベット特有の文化と言えば「生まれ変わり」の思想だ。有名なところはダライ・ラマとパンチェン・ラマの2人で、この2人は生まれ変わりによって現代までその地位が継承されてきた。
実は生まれ変わりとなるのはダライ・ラマとパンチェン・ラマだけではなく、多くの高僧達も生まれ変わっていくものと信じられている。
高僧がこの世を去ると、すぐに生まれ変わりの子供探しが始まる。チベットではラマ僧侶と住民達の独特なネットワークができているらしく、母親達から出産前に不思議な夢を見たとか、出産前に虹を目撃したとか、そういう話が報告される。それを聞いたラマ僧侶が派遣され、お経を上げ、占いをし、テストを実施し、その結果、生まれてきた赤ちゃんが「生まれ変わり」かどうかが審査される。
こうして生まれ変わりと認定された子供は、子供時代は普通に過ごすが、一定の年齢に達すると僧院に招かれて、修行を受けることになる。
ところが成長すると、「あ、やっぱり違ったわ」……となることが時々あるそうな。高僧の生まれ変わりとして僧院に招かれて、何年も修行に身を捧げたのに、成長してみると、「なんか違うぞ」というときがやってくる。
そうするとその少年は僧院から追放……ということになる。もしかしたら僧院に残れるのかも知れないけど、零落(れいらく)は免れないものとなる。
「違ったわ」と言われてしまう少年もたまったものじゃないだろう。そのために人生を捧げてきたのに、その瞬間、「何にでもない人間」になってしまう。その瞬間、すべてを喪ってしまう。
中尾佐助先生がこの話を本の中で断片的に書いていた。ヒマラヤ探検隊でネパールを訪ねたとき、現地人の荷物運びを雇ったのだが、その中で1人、ちょっと不思議な雰囲気の男がいた。昼食の時、人夫(にんぷ)たちのなかで、1人ぽつんと隅っこで寂しげにしている男がいた。人夫たちの対話に加わらず、人夫たちもその男を仲間に加えようとせず、いつも隅っこで孤独でいる。
彼は嫌われているのだろうか? 中尾先生が気になって人夫に尋ねてみると、その男は「元・活仏(いきぼとけ)」だったのだという。高僧の生まれ変わりとして僧院に招かれたけど、成長して大人になって「やっぱり違った」と言われ、追放になった人なのだという。日本人旅行者の荷物運びをやっているところで、彼が現在どういう地位にいるかは察せられよう。
高僧の生まれ変わりというハシゴを外されて、彼は一般人に転落したのか……というと、そういうわけではないらしい。時々人夫は元・活仏の若者に声をかけるときがあったが、その時は恭しく、丁重に扱っていた。零落したとはいえ、一般人の地位にありながら、一般人からも一目置かれる存在だった。一般人でありながら、その周囲の一般人と同じ地位ではない……という不思議な状態になっていた。
中尾佐助先生はこの不思議な状態を「上方差別」と呼んでいた。差別を受けているが、蔑まれているわけではない。むしろ尊重されている。蔑まれたりしないが、しかし仲間として引き受けられたりはしない。丁重に扱われるが、差別されているという状態。
地位の高い人が平民たちの社会に入っていくと、丁重に扱われるけれど、仲間として引き受けられたりしない。蔑まれたりはしないけれど、コミュニケーションの輪から外されてしまう。地位が高いゆえに孤独を味わう。そう言われてみると、そういう差別はいろんなところで見たことがある。
差別はいつも「下」に向けられるものではなく、時として「上」へ向けられることもある。そういうこともあった……という話として、ここに書いておこう。
高僧の生まれ変わりとして招かれ、人生をかけて修行して、その末、「やっぱり違った」とすべてを喪った彼……。孤独な立場に置かれて、いったいどんな気持ちだったのだろうか……。
もう一つ気になるのは、空位となってしまったその高僧のいるべき地位。もしも「違った」となったとき、誰がその座につくのだろうか。
とらつぐみのnoteはすべて無料で公開しています。 しかし活動を続けていくためには皆様の支援が必要です。どうか支援をお願いします。
