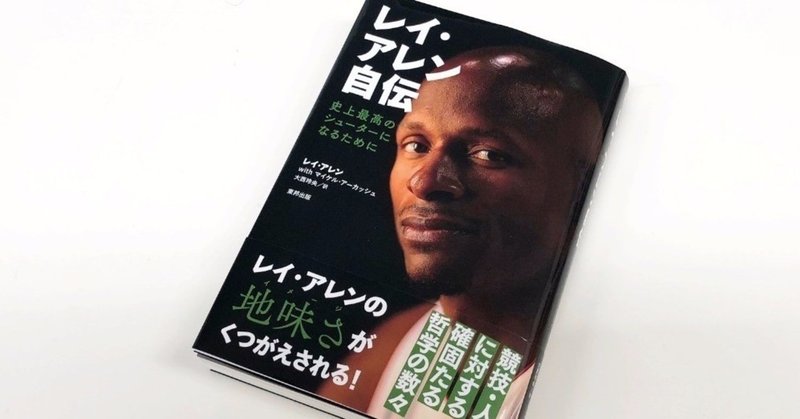
【無料公開】『レイ・アレン自伝 史上最高のシューターになるために』 チャプター2
元NBAの3ポイントキングであるレイ・アレンの人生、競技生活を彼自身の言葉で振り返った自伝『レイ・アレン自伝 史上最高のシューターになるために』(2019年1月7日に弊社より刊行)の2章分を無料で公開中。今回はチャプター2です。
「人生には紆余曲折があり、よい人も悪い人もいる。でも、つねに自分と、自分の進む方向を信じていれば、世界を変えられるような人生を送ることができる。それをいつでも思い出させてくれる物として、この本を使ってほしい」ーーRay Allen
チャプター2 少年よ。南へ行け
子供の頃から、帰属意識を持つことがなかった。
無理もない。父、ウォルター・アレンは金属技術士としてアメリカ空軍に務めており、それは多くの引っ越しをしなければならないことを意味していた。1975年7月20日に生まれた北カリフォルニアからドイツ、オクラホマ、イギリス、南カリフォルニア。そして、1988年にサウスカロライナ州の州都であるコロンビアから約65キロ離れたダルゼルという街にたどり着いた。1990年台半ばにNBA入りした時点で、自分が旅に慣れていたことに驚きはなかった。
そういった人生に、私はとても感謝している。たくさんの人が見ることもできないような場所を数多く訪れ、アメリカ人であることに誇りはありながらも、アメリカだけが正しい考え方と生き方を持っているわけではないということを理解する手助けとなった。イギリス人もドイツ人も、世界中の人々がそれぞれ独自の価値観を持っている。アメリカに住んでいると理解し難いことかもしれないが、世界は決してアメリカ合衆国を中心に回っているわけではないのだ。
本当に美しい場所を訪れることができる一方、このノマドのような生活には当然デメリットもある。それは、自分がとても大切にしているものを手放すような寂しい感覚に陥ることだった。何かに打ち込む意味はあるのか? 引っ越せば、どうせすぐになくなってしまうのだ。
周りの子供たちと仲良くしようと試みて、仲良くなれたとしても2、3年したら次の配属先が決まり、別れがやって来る。アンクル・サム(アメリカ合衆国を意味する架空の人物)というゼネラルマネジャー(GM)に何度も、何度もトレードされたと言ってもいいだろう。彼の指示があれば、また最初からやり直しだ。毎回それはきつかった。
自分が最も外様なんだと感じたのは、サウスカロライナ州に初めて足を踏み入れたときだ。……“サウス”のほうだ。
1860年終盤、合衆国から離反した最初の州だ。それは南北戦争につながった。リー将軍がグラント将軍に降伏してから120年、人々は武器ではなく言葉で戦争を続けていたのだ。
ただでさえ、自分がまったく知らない土地に放り込まれるだけでも厳しかったのに、新学年が始まってから数カ月たっていたということもあった。その数カ月が大きい。仲のいいグループはすでにつくられ、性急だとしても人格の判断もすでにされ始めている。そこにどこか西のほうから転校生がやって来る。馴染めるチャンスなんてほとんどない。
このとき、アレン家の中で新たな土地に慣れることに苦しんだのは私だけではなかった。
中学2年生としての初日、エベニーザー中学校に私を送ってくれた母は、学校がどれだけ寂れて汚い場所であり、さらには墓地の向かいにあることに気付いて涙を流した。
もう少し先まで運転すると、次から次へと農場が現れ、そこから先は森だ。我々が田舎に住んでいるという事実は避けようがなく、ある意味、過去の時代に住んでいるかのようでもあった。決して田舎をバカにしているわけではない。素晴らしい人たちもたくさん住んでいる。しかし、我々にとってはとても厳しい変化で、兵役を務めていたとしても、どんな親でもそうあるように、母は罪悪感を抱いていた。
どれほど劣悪な環境だったかをわかりやすく説明すると、エベニーザー中学の冷水機はパイプが錆びていたため、茶色い水が出てきた。しかし、一日喉が渇ききった状態が嫌なら、それを飲むしかなかったのだ。
それでも、私たち兄弟は文句を言うことがなかった。おそらく、物心ついた頃から我が家はそこまで恵まれていなかったことを知っていたからだろう。住む場所は政府が払ってくれていたが、そのほかの費用はすべて自分たちで工面する必要があった。
もちろん、ダルゼルのほかの家族も同じくらい貧しかったのだが、我が家には真ん中の自分を含めて5人の兄弟がいたので、分け前も当然少なかった。私はいつも穴の空いた靴を履き、シャツは分割で買っていた。時には3歳上の兄のジョンからお下がりをもらうこともあったが、私の成長が早かったこともあり、すぐに着られなくなることがほとんどだった。2週間ごとに食料品が家にあることから、いつが給料日であることがわかった。その食料品も、できる限り日数をもたせるように努力していた。
カリフォルニア時代と同様、生き抜く方法を見つける、それだけ単純なことだった。しかし、カリフォルニア時代に、私はこの貧しさに耐えられず愚かな間違いを犯したことがあった。11か12歳頃のことだ。基地の中にある食料品店に行った私は、リコリス菓子の箱を盗んだのだ。お腹が空いても、母に10セントでもせがんではいけないことはわかっていた。リコリス菓子をジャケットの袖の中に隠し、自分はなんて賢いんだと思いながら店の外に出た。
バカだった。カウンターの後ろにいた店員は、ゲイリー・ペイトンよりも素早く私の前に入ってきた。やがて警察がやって来て、後部座席に押し込まれ署に連れていかれた。
気付けば、窓のない小さな部屋の中で椅子に座っていた。数分がまるで数時間かのように感じられた。死ぬほど怖かった。リコリス菓子なんかのためにだ。
おかしなことに、警察のことは別に怖くなかった。親のほうが怖かったのだ。親と向き合うくらいなら、いっそのこと逮捕されたほうが楽だと思っていた。
まず母は、私が何か問題を起こせば、ベルトをムチ代わりに使うことを躊躇しないような人だった。このときは、多くを語らなくても、その表情だけで怒っていることはすぐにわかった。
「こんなことするなんて信じられないわ。お父さんが帰ってくるのが待ちきれない」
そこが運のいいところだった。父は1年間、韓国に配属されていたので、家にいなかった。考えてみれば、だからこそ私は盗むなんていうリスクを犯したのだろう。1万キロ以上も離れた場所から、いつものようにベルトでたたくことはできないのだから。
しかし、怒鳴ることはできた。当然のことだ。私がやらかしたことで、彼の階級が下がる可能性だってあったのだ。軍の中で階級はすべてだ。
実際は下がらなかったから本当によかった。もし下がっていたら、私は自分を一生許すことができなかっただろう。彼が2カ月後に家に帰ってきた時点で、すべてはもう忘れられていた。しかし、私は人から物を盗ってはいけないということを学んだ。
ほかにも、同じくらい痛みのある学びがあった。
サウスカロライナ時代に、友達が半ズボンを貸してくれると言ってくれたことがあった。学校に行く前の晩に持ってきてくれるという約束だ。それは、私にとってとても重要なことだった。もう何週間も2着のジーンズだけを交互に履いている状態だったから、周りの子たちもそれに気付き、バカにされていた。見せてやるぞ。新しい半ズボンを履いて学校中を歩き回るのだ。そうすれば、もう誰もバカにできない。
その夜、部屋の窓辺に座り、ずっと友達を待っていた。
しかし、彼が現れることはなかった。彼の言い訳がなんだったかはもう覚えていない。唯一覚えているのは、もうちょっとすれば誰にも何も頼らなくてよくなるはずだと考えるようになったことだ。それは両親も含まれていた。とくに父親。貧しい我が家にとって、彼にはもう少しなんとかしてほしいと思う面があった。
早朝5時、朝まで友人と飲んでいた父が家に帰ってくる音で起こされることは、数えきれないほどあった。数時間後、まるでぐっすり寝たかのように仕事に行ける父にはいつも驚かされた。父が飲み屋でお金を使っているということは、私が学校の食堂で食べ物を買うお金がないことを意味していた。
「なんでランチないの?」と、いつもほかの生徒に聞かれた。
「お腹が空いてないんだ」
私はそう答えた。バカにされるよりも嘘をついたほうがいい、と自分は思っていたようだ。ただでさえ2着のジーンズでバカにされていたのだから。
父のためにも言っておくと、父は職場ではとてもリスペクトされた存在で、父の部下は、父から多くを学んでいた。とても賢い人間だったのだが、父は思っていたよりも昇進はできなかった。その時点で、私は「大人になってどんな仕事に就こうと、全力を尽くす」と心に決めた。父の選択に納得のいかないことはあったが、それでも私の父であり、私は父のことを愛していた。
一方、母はそこまで理解がなく、そのツケが回ったことが一度あった。母と父が口論になり、途中から父が少し暴力を振るい始めた。私はふたりのあいだに入ろうとしたものの、当時まだ13歳だったこともあり太刀打ちできなかった。
なぜ母は、父と別れることを選ばなかったのか? 実は、何度か離れることはあったのだ。父は韓国に2度配属されたのだが、いずれも家族で行かなかった。それは、父と母が、少し距離を置けば関係がよくなる、と考えたのではないかと私たち兄弟は推測していた。実際に改善されたのかどうかはまったくわからない。父が帰ってきてからとくに関係が変わった記憶はないし、私が判断することでもない。
母が別れないことには、経済的な状況も大きく関わっていたのだろう。父が夜、何をしていようと、2週間ごとに給料を持って帰ってきていた。養わなければいけない人数が多かっただけに、それは決して軽視できることではなかった。
やらなければいけないことがたくさんあるなかで、母はふたつの仕事をこなす時間をどうにかしてつくっていた。ガソリンスタンドのレジ係と、基地から住人が出ていったあとに家の中を清掃する仕事だ。彼女は隅から隅まで徹底的に清掃した。トイレ、壁、床、コンセントなどをきれいに掃除することから、照明設備の修理などすべてをこなすなか、家族が手伝うこともあった。その稼ぎがあるのとないのとでは、家計に大きな差が出ていたのだ。
1950年代後半にアーカンソー州の田舎で育った母は、ハードワークすることには慣れっこだった。子供の頃も、学校から帰るとすぐさま農場に駆け出し、親と兄弟が綿の収穫をするのを手伝っていた。
カリフォルニアに住んでいた頃、私も庭の芝刈りで稼いだ時期があった。
エドワーズ・エアフォース基地では、毎週木曜日に庭の状態を検査されることもあって、手入れが行き届いていることがとても重要だった。歩道の割れ目から草が生え始めているのを発見すると、違反者として記録されるほどだ。私は近所を歩きながら、どの家が自分たちで芝刈りをし、どの家が人を雇っていたのかを確認した。
当然、基地の中でこの素晴らしい計画を思いついた子供は私だけではなかったので、周りよりも自分が特別であることを主張する必要があった。毎週水曜日の午後、近所を回ってドアをノックする際に言うセリフを、私は何度も細かく練習した。
庭ひとつにつき10ドルという大した金額ではなかったが、30分もあればできるので、暗くなるまでに5軒は回れた。50ドルの稼ぎがあれば、お店でお菓子などを買うには充分だったのだ。
私たち兄弟はサウスカロライナに引っ越すまで、アメリカでも海外でも基地にある学校に通った。そこにはバスケットボールコート、テニスコートなど多くの設備がそろっていた。まるで大学のキャンパスにいるかのようだった。国防総省がすべてを賄っていただけあって、教室や廊下はとてもきれいな場所だった。すべてにおいて最高基準のものを与えられたのだ。最高の教育、最高の教科書、そして何よりも、最高の教師たち。この教師たちは高い報酬と敬意が払われており、生徒たちのことをとても気にかけていた。これから生徒たちが挑んでいく試練への準備をするために、全力を尽くしていた。
エベニーザー中学と、のちに進学した数キロ先にあったヒルクレスト高校とでは、まったく状況が違った。
教師の稼ぎは比べものにならないほど低く、教材も決して充分ではなかった。生徒たちのことを気にかけてはいたが、とくに気にせずに生徒を落第させてしまう教師もいた。そういった子たちが、すぐに手助けを諦めてしまう教師ではなく、信じてサポートしてくれる教師に出会っていたらどうなっていたのだろうか、と私はよく考えることがある。コーチにも同じことが言える。
例として、兄のジョンについて話をしよう。彼は高校3年生のときには州の中でも屈指のランニングバック(アメリカンフットボールのポジション)だった。アメリカ南部では、アメフトが今でも宗教のように崇められている。ジョンの成績はそこまでよくなかったものの、彼自身はとても賢かった。しかし、コーチはジョンの成績がよくなることを待たずに、「あいつは落第で卒業できない」という噂を広め始めたのだ。ジョンはそんなこと知る由もなかった。スカウトは兄について調べるのをやめてしまい、ジョンは大学に進むことができなかった。ちなみに、高校は予定どおりに卒業している。
しかし、エベニーザー中学の教師たちがいろいろな対応に追われていたことも確かだ。私はバスケットボールを長くやっているだけに、汚い言葉はこれでもかというほど聞いてきたわけだが、エベニーザー中学の生徒たちほど、あの4文字(Fワード)の言葉を発する人たちは今でも見たことがない。
そして飲酒、ドラッグ、セックスの問題もあった。まだ中学生なのにだ。中学2年生のときクラスメイトのひとりが妊娠していたのだが、いちばん不思議だったのは、そのことを誰も非日常の出来事だと感じていないように見えたことだ。それがこの頃の様子を物語っていると思う。
新しいカルチャーに馴染むためにも、どれだけ不愉快なことであろうと、私はできるだけ多くを学ぼうと試みた。
例1:アメリカ史。
カリフォルニアで受けた歴史の授業では、エイブラハム・リンカーン、テディ・ルーズベルト、ジョン・ケネディなど、アメリカの過去のリーダーについて学び、当然エベニーザー中学でも同様だと予想していた。しかし、実際はサウスカロライナ州の過去のリーダーについて学んだ。黒人を筆頭に、多くの人がリーダーとは感じられないような人たちだ。
その中にはジョン・C・キャルフーンも含まれていた。1800年代に上院議員や副大統領を務め、さらには奴隷所有者でもあった。教師はその事実を教えず、私はのちに自分でその事実にたどり着いた。それでも、学校の誰かや親に文句を言うことはしなかった。ただでさえ問題は山積みだったのだ。
差別主義という州の過去と現在を恥ずかしく思うどころか、長期にわたって奴隷制度がもたらした苦しみを、教師たちはむしろ美化しているようだった。さすがは、社会の融和を拒み続けたストロム・サーモンド上院議員を、90歳を超えるまで選挙で選び続けた地域なだけある。州議会議事堂には、南部連合国旗が高く掲げられているほどだ。
実は、我々の家から数ブロック離れた場所にも、オークランド・プランテーションと呼ばれる大きな住宅団地が建っていた。壁に打ちつけられた手かせの鎖も含めて、まだ完全なまま残っていた。不気味な場所ではあったのだが、どういう場所なのかをちゃんと理解するうえで、我々はまだ若すぎた。今では、あの鎖のことを考えるだけでゾッとする。2017年のシャーロットビルの事件があって以来、こういった差別を象徴的するものは、何がなんでも取り払うことの大切さを身にしみて感じている。遅くても、やらないよりはマシなのだ。
当時の私にとって、黒人対白人という問題だけではなかった。一部の黒人にも見下されていたのだ。それは新入生だからという理由だけではない。“喋り方”という間違いを犯してしまったのだ。
「おまえ、ホワイトボーイ(白人の蔑称)みたいな喋り方をするな」と、つねに言われていた。
ホワイトボーイ?
これまで聞いたことのない言葉で、私はその言葉に傷つけられ混乱もした。私はこれまで自分が喋ってきたように喋っていただけだ。黒人がどういうふうに喋らないといけないかなど知らなかった。どこに父が配属されていようと、自分や付き合う人を肌の色で区別したことはなかった。我々は、ほかのアメリカ人とともに国に務めていたのだ。白や黒のアメリカ人ではない。
子供は、時にとても残酷であり、私自身もサウスカロライナに知り合いが誰もいなかったから、なんとか馴染もうという想いもあり、周囲からの批判にはとても影響を受けやすい状態になっていた。初めて自分自身の存在を疑い始めたのだ。自分は何かおかしいのだろうか? もっと彼らのように振る舞うべきなのだろうか?
問題は、喋り方の違いだけではなかった。白人の男の子や女の子と友達になるのも問題視されてしまうのだ。たとえその子がすぐ隣に住んでいたとしてもだ。私にはそれが理解できなかった。白人の子供とかくれんぼをすると、自分が白人になってしまうわけではないのに。
カリフォルニアでは、そんなことなどなかった。
ベン・E・キングの1960年代の名曲が流れる、リバー・フェニックスとコーリー・フェルドマン主演の映画『スタンド・バイ・ミー』を覚えているだろうか? エドワーズ基地で知り合った子たちは、黒人も白人もみんな、あの映画の子たちのような関係だった。
お互いの裏庭でキャンプをしたり、川で魚釣りをしたり、基地のレクリエーションセンターでビリヤード、卓球、ビデオゲームなどで遊んだり、親の許可など気にせずにお互いの家に泊まったりしていた。素晴らしい時間だった。誰かの父親の配属先が変わったりすることから、一生この時間が続かないことをみんな理解していたが、まるでずっと続くかのような感覚だった。
しかし、今度のサウスカロライナでは、自分の人種を超えることは許されなかったのだ。自宅で白人の子と遊んだり、バス停で一緒に待っているくらいはバレなかったが、学校のほかの子たちに見られているときは、どちら側につくのか選ぶことを強いられた。とくにそれが顕著だったのが、カフェテリアでのランチタイム。白人は白人と座り、黒人は黒人と座っていた。1988年ではなく、1958年にタイムスリップしたかのようだった。
ほとんどが黒人生徒であるエベニーザー中学での初日、白人の子とすれ違うときに、彼が「ボー(Bo)」と言うのが聞こえた。私は自分のことではないだろうと思い、そのまま歩き続けた。
しかし、実際には私に話しかけており、その後も私のことをそうやって呼ぶ白人の子が多く現れた。当初、私はそれが「Dude(男性同士の呼びかけに使われる言葉)」と呼ばれるようなものだと考え、受け入れてもらえているのだと感じていた。
その考えは甘かった。ボーは「ボーイ(Boy)」の卑語であることがわかった。私はそれを「Nワード」と同じくらいの蔑称だと考えていた。その言葉を発しているのが白人であろうと黒人であろうと関係なかった。黒人はそれを愛情のこもった呼びかけとして使うことがあるのだが、もともとは奴隷の所有者が奴隷を呼ぶときの言葉であるため、使うべきではないと私は感じているのだ。それを父に伝えると、父も基地で誰かにボーと呼ばれたことを教えてくれた。自分だけじゃないのかという安心感は得ることができた。
しかし、ボーと呼ばれ続ける私に選択肢はなかった。唯一あった選択肢は、毎朝バスがエベニーザー中学に到着したときに、黒人側につくのか白人側につくのかというものだった。
私はバスケットボールという3つ目の選択肢を選んだ。誰が来ようと、その人が黄色だろうが緑色だろうが、その人と友達になると決めたのだ。
最初にバスケットボールと恋に落ちたのは8歳のときで、イギリスのベントウォーターズ・ロイヤル・エアフォース基地の近くにある、サックスマンダムという町に住んでいたときだ。
両親は、地域のそれなりに強いセミプロチームでプレーしていた。父はどこからでも左右の手でシュートを決められ、母は冗談抜きに「トラック」という通り名で知られていた。まるでブルドーザーのように人をなぎ倒し、肘打ちすることになんの躊躇もなかった。母、フローラはみんなから「フロー」の愛称で親しまれ、得点とリバウンド能力に優れていた。のちに私が所属したチームの中には、彼女にプレーしてもらいたいと思えるようなところもあった。
観客が彼らを応援するあいだ、私はいつも、スタンドの下で誰かのポケットから落ちた小銭を探すことに夢中だった。数時間で結構稼げたものだ。
ある試合のあと、両親がロッカールームに下がり周りに誰もいないなかで、バスケットボールを拾い、初めて何本かシュートを打ってみた。そして、左側から左手でレイアップ3本、右側から右手で3本、6本連続で成功しないと失敗というドリルを思いついた。大したことないだろう、と私は思った。母と父はいつも楽々とレイアップを決めていたからだ。
しかし、私にとっては違った。失敗したのだ。
思いどおりにならないと、いつもやっていたように私は涙を流し始めた。なぜすべてのシュートを決められないのか理解できなかった。バスケットの高さが3メートル5センチで、自分の背丈はその半分近くでしかないことは考えもしなかった。
その後、イギリス滞在中にボールを手に取ることはなかったのだが、レイアップを外したことが理由ではなかった。ほかのことで忙しかったのと、家の近くに公園やコートがなかったからだ。もう一度バスケットボールをやってみようと思ったのは、およそ2年後。エドワーズで6年生、中学1年生用のリーグに参加したからだ。そして、すぐに自分にはそれなりの才能があることに気付いた。バスケット付近にボールを投げると、入ることのほうが多かったのだ。
しかし、シュートフォームは見られたものではなかった。腕を交差し、ボールをあごの下に引き、バスケットに向かってジャンプしながら両手で放っていた。やばいな。なぜそんなシュートがネットに吸い込まれていたのかは私にもわからない。コーチのひとりであるジェフ・リンチは、この間違ったフォームを直すというチャレンジに挑んでくれた。勇気ある男だ。私がシュートを打つところを撮影してくれ、それを見るのは本当に勉強になった。彼のアドバイスはとてもシンプルなものだった。
まっすぐ上に飛ぶ。肘は中に入れる。片手をボールの下に、もう片方を横に添える。つま先をバスケットに向ける。膝を曲げる。目はつねにリムから離さない。
ジェフには、初めてのNBA観戦に連れていってもらった。1987年3月のことで、ロサンゼルス・レイカーズが当時ファビュラス・フォーラムと知られていたホームアリーナでデトロイト・ピストンズを迎えていた。
コート上で選手たちがウォームアップするのを見ながら、私は両チームの先発センターの身長の高さに驚き続けていた。レイカーズの伝説的選手、カリーム・アブドゥル=ジャバーと、ピストンズのビル・レインビアは、テレビだとここまで大きくは見えていなかったのだ。
ジェフは私に、カリームのサインがもらえれば20ドルやるぞと言ってきた。まるで現実的ではない賭けだ。カリームの有名なスカイフックをブロックできることと同じくらいしかチャンスはなかった。ただでさえシャイであり、ほかの人たちが断られているのを見た私は、聞くことすらしなかった。それにカリームがルーティンの最中であることに気付き、これはきっとNBA選手にとって神聖な時間なのだと判断したのだ。これに関しては正しかった。当時の私は、ゲームのちょっとした細かい点をつかむにはまだ若すぎたが、ただシュートを決めるだけではないということは理解していた。
それもあってか、1980年代を飾ったショータイム時代のレイカーズでいちばん好きな選手は、カリームでもマジック・ジョンソンでもスピーディーなジェームズ・ウォージーでもなかった。私のいちばん好きなレイカーズ選手は、先発メンバーですらなかったのだ。それは195センチの細いガードで、『SportsCenter』のハイライトに出るようなプレーではないが、試合に勝つために必要なことをすべてやってくれる、マイケル・クーパーだった。
ボックスアウト。パスを弾く。ピックを張る。チャージを奪う。
どの試合でも、それがクープだった。
ジェフはもうひとりのコーチ、フィル・プレザントとともに、私に基礎を徹底的にたたき込んでくれた。
左側でのドリブル。
右手でのレイアップ。
バウンズパス。
鋭いカット。
ポンプフェイク。
ゲームにおけるどんな要素でさえも見過ごすことはなかった。基礎を学ぶことに集中しすぎていたせいで、実は今になってもジェフとフィルのどちらがヘッドコーチだったのかはよく覚えていない。どちらにせよ、サウスカロライナへ引っ越すことがわかったとき、友達との別れと同じくらい、あのふたりほど知識を持って熱心に教えてくれるコーチに新しい場所で出会えるのかという不安があった。
当時は、エベニーザー中学にある鎖のネットと砂利のコートが時代遅れに感じていた。今はとても美しいものに見える。
学校が始まる20分ほど前、毎日1、2試合ほどやる時間があった。サウスカロライナのバスケットボールは、カリフォルニアで慣れていたものとはだいぶ違うことを私はすぐに知ることとなった。ポンプフェイク、スクリーン、ゴールへのカットなどを使うのではなく、コートを走り回り身体能力を使うプレーが多かったのだ。押し合い、引っかき合いも多かった。
そして、ケンカだ。大きい子たちは本当に威圧的で、信じられないかもしれないが、すでに生えきったひげを蓄えている奴らもいたため、誰も向かっていこうとはしなかった。注意しなければならなかったのは、サイズの小さい子たちだ。つねに押し回されているだけに、彼らは自分たちがタフであることを証明する必要があった。
始業ベルが鳴るのは8時半で、全員急いで教室へ駆け込む。しかし、私はいつもバスケのことを考えていた。ようやくボールのことがわかってきたように感じていたのだ。
ボールによってはスピンする方向が違う。
打つときは高いアーチを描けるようにする。
ハンドリングを失わないようにドリブルする方法。
ボールに関することならなんだって知ろうと思っていた。試合の中でボールは自分でコントロールできるものだから、これはとても大切なことだった。対戦相手やチームメイトをコントロールすることはできない。ボールはいつだって自分のためにいてくれる。自分がボールのためにいさえすれば……。
時間がたつとともに、私は次から次へと試合に勝つようになり、私がプレーするのを見に来る子たちも現れ始めた。それはとてもうれしいことだったのだが、競争するのが好きだったからだけではない。バスケットボールは、私が「白人の子みたいに喋る」と言われるのをやめさせる術でもあったのだ。
ある日、なぜか私はコートのあらゆる場所からスカイフックを打っていたときがあったのだが、私が6メートルほど離れた場所からスウィッシュで決めるのを、アメフト部のキャプテンと彼の友達がたまたま目撃した。完全に運がよかっただけ。なんというタイミングだろう!
「こいつはうまいな」
そのキャプテンは言った。
大抵の場合、私はほかの子たちと同じスタイルでプレーしていた。速くボールを運んで、クイックショットを打ち、バスケットボールの試合でありながら短距離走に参加しているようなスタイルだ。それでも、カリフォルニアで学んだ基礎は絶対に忘れることはなかった。あれは自分にとっていつまでも役に立つものとなった。
しかし、公園で活躍するだけでは充分ではなかった。もっと意味のある試合で活躍する必要があり、じきにそのチャンスが巡ってきた。
「バスケットボールチームの入部テストを受ける者は、明日の始業前に体育館に来るように」
私はもちろん参加したが、ほかにも多くの子たちが参加し、保証されていることは何もなかった。コーチは我々を3人ずつにグループ分けし、全員に25本のフリースローを打つように指示した。カリフォルニアで学んだとおり、ぐっと膝を曲げ、リムをしっかりと見るようにした。割とフリースローは得意だったのだが、もし調子の悪い日だったらどうしよう? 始まる前から私のバスケットボールキャリアは終わってしまうのだろうか? そんなことを考えてしまった。
幸いなことに、最悪の事態にはならなかった。誰よりも多い25本中23本を決め、コーチが感心していることは目に見えてわかった。同じく入部テストを受けていたケニー(仮名)に関しては、同じことは言えなかった。
「おまえはチームに受からないよ」
ケニーはそう言ってきたが、私は返事をしなかった。むしろ自分のことを何も知らない人がそんなことを言ってきたときは、なんて返事すべきなのだろうか? なぜ彼があれほどネガティブだったのかは見当もつかないが、おそらく自分が受からないという不安があったのかもしれない。
入部テストの数日後、自分がチームに受かったことがわかると、ケニーは再び私を落ち込ませようとしてきた。
「なんの意味もないさ、そんなの。先発できないさ」
私は再び返事をしなかった。
悪い奴ではなかったし、ケニーのようにダメだと言ってくるような奴には、誰しもが人生で2、3人くらいに出会うだろう。問題はそういう発言を真に受けるかどうかだ。
むしろ私は、ケニーがああ発言したこと、そしてそのタイミングに感謝しているくらいだ。彼の言葉は長いあいだ、私の脳裏に焼きついていた。そして、何度も訪れる自分を疑問視する瞬間、その言葉を思い出し前に進んだ。ケニー見てろよ、俺は先発してやる、そしてチームで一番の選手のひとりになってやる! 批判することでモチベーションを上げてくれた初めての人物であり、その後も彼のような存在は多く現れた。
チームに入れたことはとても大きかった。私のことを部外者だと思っていた多くの子たちから、クールだと思ってもらえるようになったのだ。さらに、どこかのグループに所属しているかどうかだけで判断されなくなった。
「あいつはバスケットボールをプレーする、あいつはアスリートだ」と言われるようになり、「あいつは黒人(もしくは白人)とつるんでいる」ではなくなった。
もうひとつよかったことは、試合のある日はウォームアップジャージーを着て学校に行くことを許されたことだ。これによって2本のジーンズ以外に着られる3着目の服を手に入れたのだ。廊下を歩いていると、今まで感じたことのない誇らしい気分になれた。
何人かの子たちは、私がバスケットボールのスキルを持っているだけではなく、何か特別な人間であると思うようになっていた。
ある日の練習前にロッカールームで待機していたとき、私は何を思ったのか錠を開けることができるとみんなに自慢した。嘘つけ、と彼らは信じなかった。見せてやると言いながら私は適当なロッカーに向かい、ダイヤルを2、3回まわし、映画で見るように耳を当てた。すると、信じられないことに、本当に開いてしまった! まるで神様が私に手を貸してくれたかのようだった。
「どうやってやったんだ? もうひとつ開けてくれ」
彼らはそうお願いしてきたが、もちろんやらない。1個で充分だ。あんな幸運に恵まれることはもうなかっただろうから。
不思議に感じるかもしれないが、ピッキングができたことはとても重要だった。あれぐらいの年齢の子供たちは、つねにグループ内で注目される術を探しているからだ。
しかし、バスケットボールに関しては、運に頼る必要がなかった。努力することだけで上達できた。1990年の秋にヒルクレスト高校に進学すると、観客も多くなり、重要度も増した。
自分は、それに立ち向かえる準備ができていることを望んでいた。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【レイ・アレン自伝 目次】

版権の関係上、全文公開できないのが心苦しいばかりですが、この先にはバスケットボールや人生に対する確固たる哲学が詰まっています。書籍内には”あの名シーン”を含む、多数のカラー写真も掲載!
続きをお読みになりたい方、書籍の詳細を知りたい方は↓下記にアクセスしてください。
また、書籍、ならびに本記事をお読みいただいた方からのご意見・ご感想もお待ちしております!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
