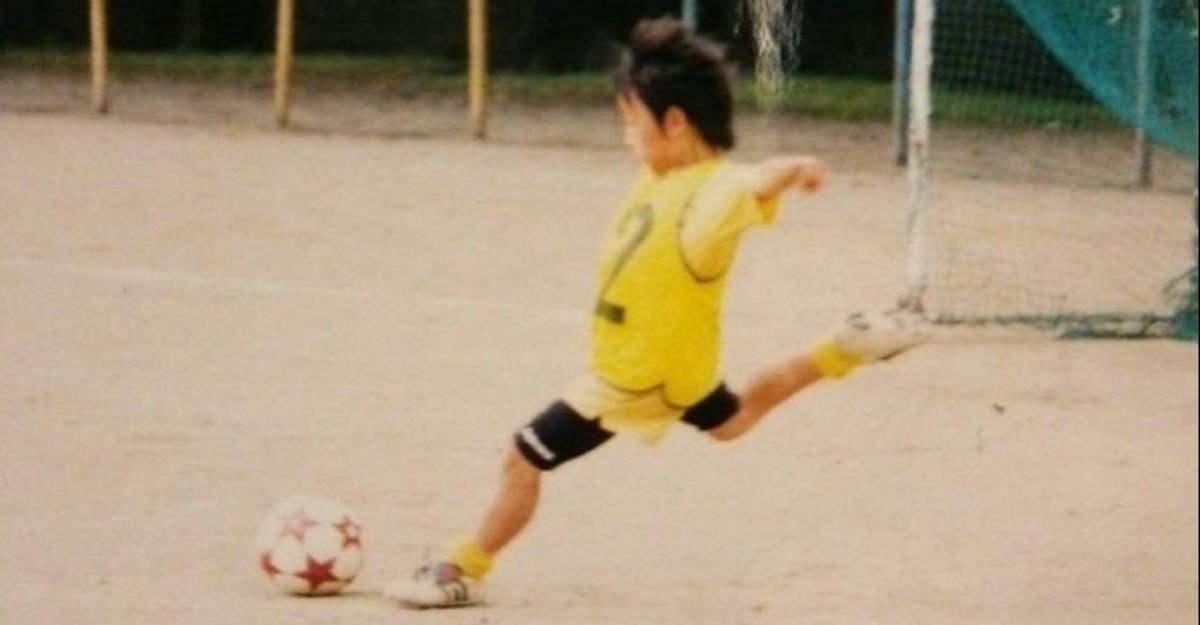
運動のすすめ
2022.6月 追記。
読み返してみると、かなり尖った内容。
あえて、修正せずに、残しておきます。
批判的吟味しながら、読んでみてください。
ある整形外科でリハ助手のアルバイトをはじめた。
理学療法士の資格取得にも興味があった。
スポーツ整形外科もやってますと謳い、院長もあるオリンピック種目のドクターをしているし、いいかもと思い、何となく応募して、合格。
院長は、自分みたいなATを目指している人材、それなりの高いレベルでスポーツをしていた人材が欲しかったらしい。
院長は色んなスポーツ現場では見られない症例やその診察を見学させてくれたり、いろんな話をしてくれるので、ありがたい。
でも、働いてみて感じたことは、、、
ある意味、やっぱりな。。。
リハビリと言っても物理療法のオンパレード。
主な仕事は、、、
☑患者さんを案内、サポートする。
☑物療の機械を患者さんに付けてはずすの繰り返し。
☑たまに、マシーンのレッグエクステンションやレッグプレスの指導をする。(☜運動療法)
これで本当に治るのか。
怪我の種類や主訴にもよるが、完治というより痛みの軽減が目的になっている気がする。
特に腰痛や肩関節痛、下肢痛の怪我には運動療法が欠かせない
物理療法の限界
— tomoki akiyama (@tmk_akym_at) November 20, 2019
腰痛の物理療法=疼痛の軽減・循環改善・鎮痛機構促進による即時効果や短期効果→身体機能が有意に改善するものではない。
★運動療法の準備。
上記は、腰痛に限定的だが、物療は運動療法の準備段階である。

☝引用
運動療法の効果は、科学的にも証明されている。
怪我をする、怪我が慢性化するのは、身体の使い方が悪いから。
☟
物療は組織の修復を促すだけであり、身体の使い方を修正するものではない。
☟
身体を動かすのは、筋肉である。
☟
身体の使い方を修正するのは、筋肉である。
☟
筋肉は収縮=運動することで身体に作用する。
☟
運動療法が必要。
下記は、以前に参加したセミナーのパンフレット☟

Clif Eaton…マンCやプレミアリーグのチームで活動経験がある理学療法士。
この人が訴えていたこと☟
”POLICE”…急性外傷の応急処置の内容
P:protect
OL:optimal loading…適度な負荷
I:icing
C:compression
E:elevation
以前は”RICE”もしくはPRICEであったが、R:restではなく、OL:optimal loadingの重要性が高まっている。
急性外傷であっても、安静にするのではなく、適度に負荷をかけることが、予後成績の向上につながる。
院長も運動療法がリハビリにおいて重要だということは理解しているはず。
では、なぜほとんどのリハビリが物療だけで終わってしまうのか。
個人的には大きく分けて、2つの問題があると思う。
1.人手とお金の問題
☑物療の場合、機械をつけてはずすだけだから、たくさんの患者さんに対応できる。
☑たくさんの患者さんを抱えれば、その分収入も増える。
☑運動療法の場合は、基本マンツーマンのため、今までと同じ時間内で同じ数の患者さんに対応すること難しい。
☑より良いリハビリにするために、リハビリの内容を物療と運動療法にいきなり変えると、料金が変わって患者さんも来なくなったりするかもしれない。
☝これは経営や自治体からの補助金などの問題だから、ここらへんで。
2.運動に対する個々の状況
整形外科に来る患者さんは多くが高齢者。
高齢者になると、ただでさえ、骨密度や筋力が低下するが、病院に来るような人は、さらに低下している。
そのような人が、いきなり運動すると、運動が以下のようなものを引き起こすリスクとなる。
☑悪化
☑他部位を怪我する
これだと、”さあ、運動しよう”と、簡単には言えない。
では、どうすればいいのか?
(答)怪我しなければいい。
☟
怪我を”予め防ぐ。”
☟
”予防”が重要。
大学で勉強し始めたり、トレーナーとして活動し始めてから、"傷害予防"という言葉が、非常に重要ということを感じる。
今までの内容をまとめると、、、
☑怪我をしてから、治すために運動が必要。
☑怪我を予防するためには、運動が必要。
しかし、運動が重要だとわかっていても、運動をしない人は多い。
というのは、人は本気で危機感を感じた時に初めて、危機から回避するために何か行動をする。
例えば、
☑テスト直前の夜になって、”ヤバい、時間ない。”と思って、テスト勉強を始める。
☑監督に怒られて、練習の雰囲気が締まる。
☑失敗したことは、それ以降絶対忘れない。”失敗は成功の元。”
(☝世の中には鈍感で、全く危機感を感じない人もいますが。。。)
しかし、気づいてからでは遅いことも多々ある。
さっき述べたように、高齢者になって運動が出来ないから、怪我のリハビリは物療だけで、慢性化して治らない。
ここで少し見方を変える。
自分はこの夏、アメリカに行って来て、アメリカがスポーツが強い理由の1つを実感した👇
S&Cコーチが常勤。
— tomoki akiyama (@tmk_akym_at) August 24, 2019
限られた資金の中で、公立高校のウエイト場に10以上のラックがある。
ウエイト・strengthの授業を学生全員が受ける。
オフシーズンは、ウエイト中心の体づくり。
体は大きくなるし、スポーツ強いわけだ。#strengthandconditioning pic.twitter.com/5oNN5kL7r8
👇
アメリカは、ウエイトトレーニングを非常に重要視する。
”アスリートに限らず、一般人も。”
というのは、アメリカの公立高校の体育のカリキュラムには、ウエイトトレーニングが入っている。
つまり、高校生のほとんどが、ウエイトトレーニングをする。
その目的は、
☑アスリート…競技パフォーマンスの向上と傷害予防。
☑一般生徒…ウエイトトレーニングを習慣化させて、大人になってもウエイトトレーニングするようにする。
☟
そもそも、、、
ウエイトトレーニングにより筋力を獲得すると、サルコペニアやロコモティブシンドロームになる確率が下がる。
☟
サルコペニアやロコモティブシンドロームなどの運動器疾患になると、寝たきりや要介護状態になる。
☟
寝たきりの生活は、死のリスクである。
また、下記のような言葉を聞いたことがあると思う。
"運動して気分転換しよう。"
"勉強だけではなく、運動もすると学業の成績が上がる。"
運動は、うつ病の予防・改善。
— tomoki akiyama (@tmk_akym_at) July 15, 2019
↓
怪我したら落ち込むのも必然?!
怪我人へのメンタルのケアも必要ですね。 pic.twitter.com/DTyJeQr9wy
①
— tomoki akiyama (@tmk_akym_at) August 4, 2019
うつ病患者に、70~75%HRmax強度の有酸素運動を30min/day、3times/week、16週実施。
→有酸素運動はSSRI(抗うつ薬)よりも症状改善効果がある。また、運動習慣ありの人は、うつ病発症リスクが約3割低い。
②
週3回以上の運動習慣ありの人は、認知症発症リスクが32%減少。#運動習慣最強 pic.twitter.com/2RnQeotFzX
☟
運動は身体だけではなく、精神にも影響を及ぼす。
散歩が大好きなおじいちゃん・おばあちゃん等が元気であるのも、筋力があるのはもちろん、精神的にも元気であるため、長生きできていると考えると納得がいく。
彼らは、"怪我を予め防ぐために、運動を習慣化する"ことができている。
彼らのような人を増やすには、教育段階から運動を習慣化させる環境づくりが必要であり、今後の超高齢化社会になる日本にとって重要なことである。
違う見方から、、、
複数の競技スポーツを若い頃やっておいた方が、怪我をする確率が減る。
「NBAの選手で、高校生の時に単一と複数種目をプレーしていた選手を比較すると、複数種目をプレーしていた選手の方が、怪我をせず長期間プレーできた。」https://t.co/be8mNYbjvD pic.twitter.com/cayIF4IlGG
— tomoki akiyama (@tmk_akym_at) November 4, 2019
☟
それぞれスポーツには、特異的な動作がある。
☟
動作のバリエーションが増える。
☟
怪我の予防につながるというエビデンス。
経済的に様々なスポーツを出来ない子供もいると思う。
そういう子供たちも含め、子供の頃から動作のバリエーションが多くなるような指導が出来るようになりたい。
それが、今後の怪我で競技をドロップアウトする選手が減少し、日本スポーツのレベルの向上にもつながる。
あと、子供には運動を楽しんで継続できるような指導もしたい。
要は、、、
運動しよう。
以上。
p.s.
最近、背中のウエイトを始めるようになった。
選手の時は下肢中心で行っていたが、背中をするようになってから、腰も楽になったし、選手の時からやっていれば、パフォーマンスもアップしたかもと思ったり。。。
今は懸垂が出来ないので、きれいなフォームで懸垂が10回出来るようになることが今の目標。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
