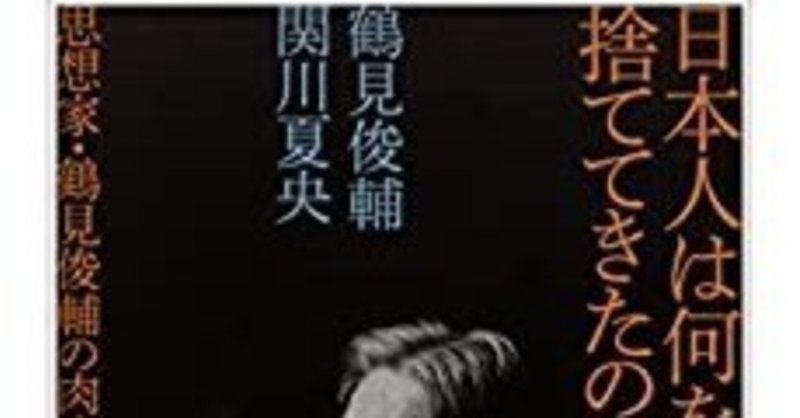
鶴見俊輔「言葉のお守り的使用法について」に関するメモ―パトリオティズムとは?
鶴見俊輔「言葉のお守り的使用法について」は、鶴見のデビュー論文で雑誌『思想の科学』第1巻第1号(先駆社、1946年5月)に掲載されてるが、この論文は国会図書館デジコレの図書館限定配信部分の個人への解禁にともなって自宅で閲覧できるようになった。この論文をあらためて読み直すと、「転向」の問題、プラグマティズムの哲学、言語の問題など鶴見が後年発展させていくテーマがこの時点で登場している。この論文の中で鶴見は「愛国」についても以下のように述べており、興味深いので該当箇所を以下に引用してみたい。
(前略)併し世界の人の幸福を目標とする道義的見地から言つて、今迄の日本の様な意味で国民的情操を維持する事は望ましくない。我々はホッテントットならホッテントットなりに自らの風俗と文化様式に愛着をもち之についてひけ目を感じないやうにしなくては幸福に暮せない。亦人間一般よりも、自分の周囲にゐて共に暮す人々に、より多くの懐しさを感ずる事によつて我々の社会生活は益益愉快になる。この意味での愛国は、人類の共栄を脅すものではない。そしてこの意味での国民的情操は、言葉のお守り的使用を離れて存続し得る。情操生活の一端を担う国民歌謡をとりあげて見よう。(中略)愛馬行進曲、麦と兵隊、露営の歌の如く自然の情の流露する軍歌にはお守り言葉がない。更に、日清、日露の頃から今日に伝へられた古典的な軍歌に於ては、支那事変以後の軍歌に比してお守り言葉の使用が稀である。これは(官製に非ざる)愛国の情の流露がお守り言葉を必要としない一つの証左である。(後略)(筆者により一部を現代仮名遣いにあらためた。)
ここで鶴見は国民歌謡の中に表現されている愛国の情は人類の共栄を脅かすものではないと評している。ここで鶴見は、以下の記事で紹介したようなジョージ・オーウェルの「郷土主義=パトリオティズム」に近いことを述べていると思われる。オーウェルの言うパトリオティズムは国家に迎合するものでなく、抵抗の拠点となるものである。ここで鶴見の言う「お守り言葉を必要としない」「愛国の情」とは、国家からの押しつけでなく人々の間から自生的に発生するパトリオティズムで国家に対して抵抗するものであろう。鶴見は、生涯に自分の住んでいる場所やくらいの中の思想、そこから考えることを追求したが、その方向性や後のオーウェルの評価につながる考えが一番最初の論文にも表れている。
よろしければサポートをよろしくお願いいたします。サポートは、研究や調査を進める際に必要な資料、書籍、論文の購入費用にさせていただきます。
