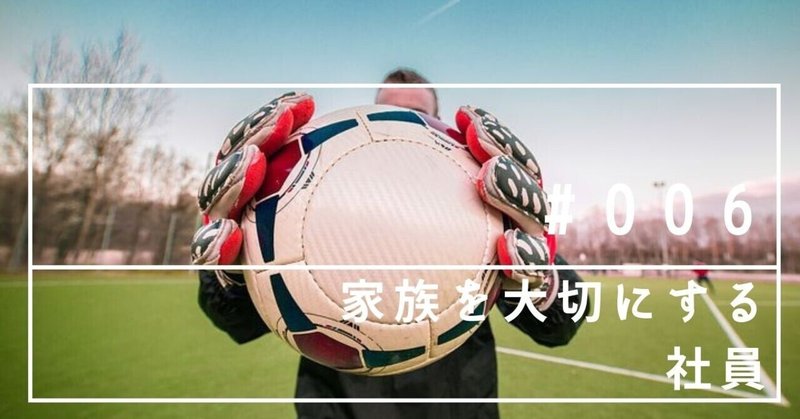
そろそろ会社で幸福の話をしよう #006 「家族を大切にする社員」
はじまり
気になる声を聞いた。それは「幸せとか幸福って言葉、あんまり連発すると、なんかちょっとね。」というものだった。
「なんかちょっとね。」
まさにポイントだと思う。この言葉の背景にあるそれぞれの思い、幸福に対する印象、僕はそれらと向き合いたい。そうすることで、僕と社員の幸福に対する「印象」ギャップを、少しずつ埋めていきたい。
ということで、様々なメンバーに声をかけ、「幸せについて語ること・幸福に対する印象」について聞いてみた。
48歳男性 - 入社15年目(中途入社)Aさん
会社で幸福の話をされたとき、とても大事な話だな、おもしろいな、とは思ったのですが、じゃあ自分が積極的にその話を周りとできるかと言われたら、それは少し難しいなと思いました。
私はまだ下の子どもが小学生ということもあり、日曜日に一緒にサッカークラブに行くのが楽しみになっています。試合の帰りに子どもとサッカーの話をしているときはとても心が安らぐというか、こういうのを幸福と言っていいんじゃないかと考えたことがあります。
ただ、そのことを例えば会社であまりおおっぴらに言うと、「家族第一な人」みたいな感じで見られないかな、という不安もあります。うちの会社は社員の生活を大事にしてくれるとても面倒見のいい会社ですが、だからこそ、仕事は仕事としてきっちりやることが会社への恩返しだとも思っています。家族が安心して過ごせるように、できれば仕事が認められて出世したいですし、給料が少しでも上がるといいな、とも思います。
なので、仕事とプライベートはきっちり分ける人間と思われるためにも、会社で堂々と「家族との時間が幸福!」となんとなく言いにくいという、個人的な気持ちがあります。
幸福な気持ちの共有は大事だけど、仕事とは別の部分にそれ(幸福)があるとなんとなく堂々とは言いにくい。それは言ったらだめという雰囲気ではなく、会社がいい雰囲気だからこそ言いにくい、というのが今の私の幸福に対する印象です。
僕の思い
日曜日に一緒にサッカークラブに行くのが楽しみになっています。試合の帰りに子どもとサッカーの話をしているときはとても心が安らぐというか、こういうのを幸福と言っていいんじゃないかと考えたことがあります。
めちゃくちゃいい。家族との時間に幸せを感じる。とてもいいなと思う。普段のAさんの印象からはあまり想像できないエピソードで、そういう側面もあるんだなと、いい意味で新発見。
Aさんと一緒に働く他のメンバーにも知ってもらいたい。家族を大切にするAさん。子どもとサッカーの話をするAさん。きっと親近感や安心感につながるはずだ。
大それたサポートはできないが、人事として、Aさんが在籍するチームに、日曜当番の順番調整くらいはお願いできると思う。せめて大事な試合と当番が重複しないように。
ただ、そのことを例えば会社であまりおおっぴらに言うと、「家族第一な人」みたいな感じで見られないかな、という不安もあります。
気にし過ぎだと思う。「家族「も」大事にしている」でいいと思う。大丈夫!
仕事は仕事としてきっちりやることが会社への恩返しだとも思っています。
普段きっちりやっているし、サッカークラブに行く時間や家族との時間は、仕事ではなくプライベート時間だと思う。全然大丈夫!
家族が安心して過ごせるように、できれば仕事が認められて出世したいですし、給料が少しでも上がるといいな、とも思います。
家族との時間を大切にし、幸せを感じることでそれがエネルギーになれば最高だと思う。そのエネルギーで、さらに活躍してほしい。出世・昇給につなげてほしい。
仕事とプライベートはきっちり分ける人間と思われるためにも、会社で堂々と「家族との時間が幸福!」となんとなく言いにくいという個人的な気持ちがあります。
もしかして、仕事以外の部分に幸福があることに後ろめたさを感じているのだろうか?
幸福な気持ちの共有は大事だけど、仕事とは別の部分にそれ(幸福)があるとなんとなく堂々とは言いにくい。それは言ったらだめという雰囲気ではなく、会社がいい雰囲気だからこそ言いにくい、というのが今の私の幸福に対する印象です。
やっぱり。でも気持ちは少し分かる。「言いにくい」、ここ特に分かる。
これから、「印象ギャップ」を埋めていくにあたり大切だと感じたこと
「仕事の外にある幸せ」も個人の活力に影響するという意味では、間接的に仕事のパフォーマンスにつながる大事なもの。だから、それを職場で語ることは、悪いことや臆することでは決してなくて、むしろ良いこと。これからの時代の新しい良いこと。この感覚や空気感を、Aさんに対してはもちろん、会社全体に対しても広げていくことが大切だと感じた。
そして、次のメリットについてもきちんと広げていくことが大切だと感じた。
自分の幸せを語ることで、周囲から親近感・信頼感・尊重・協力を得られる可能性があること。ただし可能性を期待しすぎるのはよくない。そして、可能性には普段の自分の職場での状態(頑張りや貢献など)が影響するかもしれない、ということは補足情報として付け加えておきたい。
今回は、とりあえず上記の内容を、印象ギャップを埋める補助線(Tips)として項目立てたいと思う。
他にもなんとなく見えかけた部分があったが、現時点での言語化が難しそうだったので、次回以降に譲りたい。
引き続き、様々なメンバーに声をかけ、幸せについて語ること、幸福に対する印象について聞いてみたいと思う。その中で、実際の声に対応する「印象ギャップを埋める補助線(Tips)」をどんどん整理していきたい。
幸せへの支援を起点に、会社・社員の持続的成長を支えるために。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
