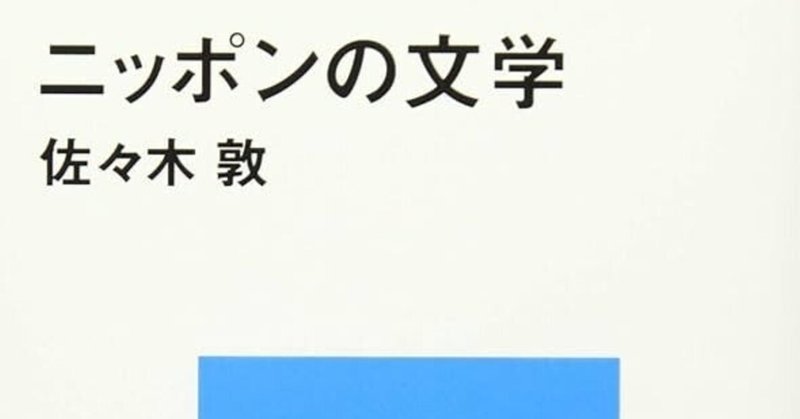
佐々木敦『ニッポンの文学』読書メモ01
佐々木敦『ニッポンの文学』(講談社現代新書)を読んだ際の所感を書いていく。読書メモなので、書きたいことを丁寧に整理しているわけではない。今回は、全体の構成の紹介とプロローグ、第一章まで。
全体の構成
プロローグ 「芥川賞」と「直木賞」
第一章 村上春樹はなぜ「僕」と言うのか?
第二章 「八〇年代」と作家たち
第三章 「英語」から遠く離れて
第四章 かなり偏った「日本ミステリ」の歴史
第五章 さほど偏っていない「日本SF」の歴史
第六章 サブカルチャーと(しての)「文学」
第七章 ポストバブルの「九〇年代」
第八章 「ゼロ年代」─ジャンルの拡散
エピローグ 「文学」はどこにいくのか?
あとがき
全体の構成は上記のようになっている。
最初に、プロローグにて、著者は①「(純)文学」もSFやミステリのような一ジャンルとして扱うこと、②1970年代から2010年代前半までの文学史(小説史)を示すこと、を宣言する。
前半で紹介されるのは、70年代から80年代までの各ジャンルでの小説史(純文学+α/本格・新本格ミステリ/SF)である(第一章~第五章)。
その後、第六章で江藤淳と大塚英志の議論を引用しながら、①70年代後半の時点ですでに(純)文学が「サブカルチャー化」していたこと、②90年代後半ではさらに「サブカル化」したことを指摘する。特に「文学のサブカル化」によって、文学(小説)は、ゲームや漫画といった外部の想像力を取り入れるようになり、文学(小説)の垣根の氷解が決定的となる、という点は重要である。(※用語の定義については後述。)
第七章以降では、第六章での議論を受け、各ジャンルの歴史を合流させたうえで、90年代以降の文学史(小説史)を展開していく。
以上が『ニッポンの文学』の全体の流れである。ここからは順番に、水石(筆者)の私見を取り入れながら、本書の内容を詳述していきたいと思う。
プロローグ 「芥川賞」と「直木賞」
プロローグでは、日本文学振興会が主催する「芥川賞」と「直木賞」という切り口から、著者は①小説が「(純)文学」とそれ以外(=「エンタメ」)に二分されてきたこと、②その区分が制度的なものであること、③制度的な区分でありながら、「(純)文学」は特別であるという信仰をもたらしてきたことを指摘する。
もちろん、こうした区分はこんにちの文学を語るうえで実効的ではない。そこで、著者は「(純)文学」をSFやミステリと同じような小説の一つのジャンルとして見ることを提案した上で、現代文学史の叙述を試みることを宣言する。
……本書にこのような前書きは必要だったのだろうか?、という点が読者として気になった。というのは、私が生まれるずっと以前から、(純)文学の権威というものは失効しており、(純)文学はすでに一つの小説のジャンルに過ぎなかったからである。
第一章 村上春樹はなぜ「僕」と言うのか?
ところで、村上春樹がなぜここまで読まれているのかということを考えるポイントとなるのは、やはり文体です。それ以前にもなかったわけではないのですが、村上春樹と共に「ニッポンの文学」に颯爽と登場してきたのは、何よりも「僕」という一人称です。
第一章で論点となるのは、一人称のことである。「僕」小説の大家といえば、やはり村上春樹である。しかし、それ以前にも庄司薫が「ぼく」という一人称を小説(『赤頭巾ちゃん気をつけて』)に取り入れていたこと、さらに遡っていけば野崎孝・訳の『ライ麦畑でつかまえて』にも「僕」という一人称が採用されている。(ということが言及されている。)
……といっても、大江健三郎『われらの時代』(1959)でも、「僕」という一人称が採用されていたはず。今は手元にないので、後で確認しておきます。
中島梓(栗本薫)と村上春樹
水石にとっても、野崎訳『ライ麦畑』・庄司薫・村上春樹の流れは既知であった。が、面白くなるのはここからである。著者はここで村上春樹と中島梓(栗本薫)の同時代性と文体に注目する。(※中島梓と栗本薫は同一人物)
中島梓の第一評論集『文学の輪郭』と栗本薫の江戸川乱歩賞受賞作『ぼくらの時代』は、村上春樹の『風の歌を聴け』の前年に当たる一九七八年に出ています。村上春樹と中島梓=栗本薫の同時代性については今ではあまり語られませんが、筆者はここには重要な論点が隠されていると思います。それはまさに「ぼく」という一人称の問題、そして「文学」の変質・変容という問題にかかわっています。
『ぼくらの時代』において栗本薫(=中島梓)が、村上春樹の「僕」と同様に、男性の一人称として「ぼく」を使用していること、その同時代性も重要であるのだが、話はそれだけに留まらない。
本書では先ほどの引用文の後、著者は中島梓(=栗本薫)『文学の輪郭』の冒頭を引用する。そこで言及されているのは、夥しい小説が出版されていく中で、文学をどのように峻別するのか、文学の領域をどのように規定するのかということの不可能性であり、すでに「文学の輪郭」というものが溶解しつつある(=「文学のサブカルチャー化」※第六章)という事実である。
『文学の輪郭』に関する議論は、第一章においては単なる脱線でしかないのだが、本書全体からみれば重要な布石となっている。
「あたし」をめぐる系譜~橋本治と新井素子
個人的には、「あたし」という一人称から、橋本治と新井素子を繋いでみせた第一章後半の方が面白かったように思う。
橋本治は1977年に「桃尻娘」でデビュー。男性の作家が女子高校生の文章を仮構しているという点にすごみがあるのだけれども、水石は「桃尻娘」自体を読んだことがない。(『桃尻語訳「枕草子」』なら読んだことがある。)
そして、新井素子も同年に「あたしの中の……」でデビュー。栗本薫『ぼくらの時代』でもそうだったが、タイトルの時点ですでに(当時としては)新しい一人称が盛り込まれている、というのが面白い。(あるいは、著者が目についたものを引っ張り出してきたのかもしれない。)
「人工的に作り上げた一人称」らしい
「僕」や「あたし」といった口語一人称を用いることで、小説に(若年読者にとっての)リアリティを付すことができるようになった。のだけれども、それはあくまでも人工的に作り上げられたものだと、著者は言う。そして、こんな注意書き(?)も。
筆者が強調しておきたいのは、「庄司薫」の「ぼく」や「栗本薫」の「ぼく」や橋本治の「あたし」と同列に、その直後に登場した「村上春樹」の「僕」もまたフィクショナルな存在として扱うべきなのだということです。
ちょっとした年表(第一章)
1958 福田章二「喪失」(『中央公論』11月号)
~~~~
1969 庄司薫「赤頭巾ちゃん気をつけて」(『中央公論』5月号)
~~~~
1977 新井素子「あたしの中の……」(『奇想天外』2月号)
1977 橋本治「桃尻娘」(『小説現代Gen 第3号 '77爽秋』)
1978 栗本薫『ぼくらの時代』講談社
1978 中島梓『文学の輪郭』(単行本)講談社(『ぼくらの時代』と同日)
1979 村上春樹「風の歌を聴け」(『群像』6月号)
この年表をもとにした、補足の年表も入れておく。
1977 新井素子「あたしの中の……」(『奇想天外』2月号)
1977 中上健次『枯木灘』河出書房新社
1977 吉村昭『羆嵐』新潮社
1977 橋本治「桃尻娘」(『小説現代Gen 第3号 '77爽秋』)
1977 宮本輝「螢川」(『文芸展望』1977年10月号)
1978 赤川次郎『三毛猫ホームズの推理』(カッパ・ノベルス)光文社
1978 栗本薫『ぼくらの時代』講談社
1978 中島梓『文学の輪郭』(単行本)講談社(『ぼくらの時代』と同日)
1979 村上春樹「風の歌を聴け」(『群像』6月号)
平素よりサポートを頂き、ありがとうございます。
