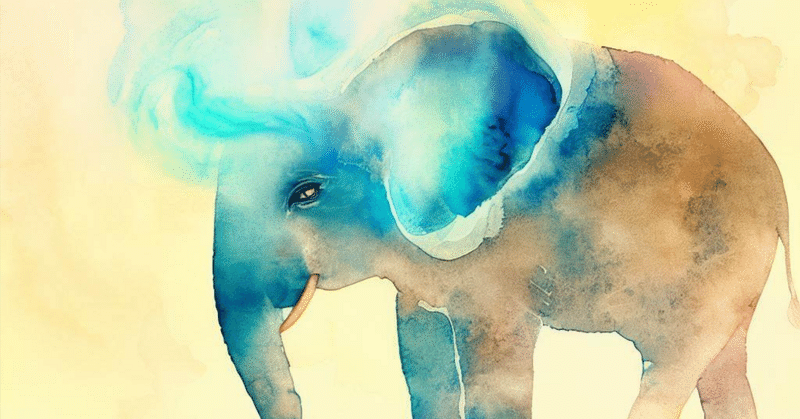
連載【短編小説】「あなたの色彩は、あなたの優しさ、そのものでした」(第一話)
花の色は
うつりにけりな
いたづらに
わが身世にふる
ながめせしまに
小野小町『古今集』より
大切なひとの肩に、そっと手を置くような、柔らかな春の雨に濡れた歩道のアスファルトが、薄墨を含み、色の濃さを増してく。キャップを被っているとはいえ、雨に濡れることも構わず、わたしが持つ灰色の相合傘から離れ、くるくると円舞曲を踊りながらおしゃべりを続ける蜜柑は、人生における不幸を、何一つ知らないように見える。
彼女の心のアルバムを開いたことがあるわけではないから、安易にそう決めつけることは出来ないのだけれど、もう二年近く一緒にいて、彼女の口から、ため息一つ、愚痴一つ、零れ落ちたのをわたしは見たことがない。中には、向日葵のような天性の明るさを持っている人もいるのだろうとは思うのだけれど、もしかしたら蜜柑は、その星のもとに生まれた代表の子なのだろうか。
跳ねる雫のように、絶えず声を弾ませて笑う彼女は当然、このようなわたしの心のうちなど、知る由もない。出会った当初から、わたしに対して、後ろ暗さのようなものは感じているとは思うのだけれど、彼女なりの真綿のような優しさのためか、蜜柑にはこれまで一度も、わたしの影を踏まれたことはなかった。わたしは、そんな彼女に救われていると言えば、確かにそう言えないこともなかった。常に独りで、部屋に閉じ籠っているようなタイプのわたしを、こうして、例え雨の日であろうと、文字通り手を引いて外に連れ出してくれるのは、彼女だけだ。だから蜜柑には、いつも感謝しかない。
わたしたちが目指していた、店内にカフェを兼ねたギャラリーが見えてきた。蜜柑が雛鳥のように、わたしの傘の中に戻ってくる。――そう。蜜柑はいくら遠くに離れて行ってしまったとしても、必ずわたしの元へと帰ってくる。そのことが、わたしにとって何よりも心の寄る辺となっていることを、おそらく彼女は、まだ気づいていない。わたしもまた、その感情をそれ以上、言葉として象ることは避けていた。だって、一度形にしてしまったら、きっと、砂山のように崩れてしまうだけだから。
「あ、いらっしゃい!」
蜜柑の高校時代の美術部の先輩で、美大を出た後、今は現代アーティストとして少しずつ名の知られてきた橘真紅さんが、入り口で笑顔を咲かせて出迎えてくれた。名前の通り、ルージュの口紅が目を引く。
「こんにちは!」
笑顔なら、蜜柑も負けてはいない。
「あの、どうも」
わたしは蜜柑の背中からひょっこり顔だけを出し、真紅さんにあいさつした。真紅さんとは初対面だった。
「あ、真紅さん、この子が琥珀です。三守琥珀」
蜜柑がわたしの背中にそっと手を添える。蜜柑の手は、陽だまりのようにいつも温かい。
「こんにちは。今日は遠いところどうもありがとう。私は橘真紅。名前くらいは聞いたことあると嬉しいんだけど」
「も、もちろん、存じ上げてます。蜜柑の先輩だからって言うのもありましたけど、インスタを見て、一目で大好きになりました。だから、こうしてご本人に会えるなんて、今にも天にも昇りそうです」
にわかのファンながら、憧れの人を前に急にテンションが高まり、早口になる。そんな自分が嫌なのに、いつもそうだ。
真紅さんは大きな口を開け、
「ははは。蜜柑、この子可愛いね」
真紅さんが蜜柑に顔を向ける。蜜柑も笑い声を上げ、
「可愛くて、面白いんですよ」
力説するように、わたしの前でこぶしを握る。やめてよ。恥ずかしい。
「じゃ、そこで受付して。とりあえず一通り観て回ってきてよ」
「はい。ありがとうございます。行こっ、琥珀」
外で丁寧に水滴を払い、折りたたんだ傘を傘立てに立ててから、蜜柑の後に続き、受付に向かう。受付のカウンターで、全身をすっぽりと覆う群青色のレインコートを着た男の人が、大きな手のひらを差し出し、こちらにお名前を、とぼそりとつぶやく。
「うち、書くよ」
蜜柑がキャップを外し、髪を耳に掛けてから、背中を折って名簿の上に屈みこみ、まず自分の名前を書き、続いて、わたしの名前を代筆する。
「ありがとう、ございます。では、ごゆっくりお楽しみください」
男の人が差し向けた手のひらに促され、わたしたちはギャラリーへ足を踏み入れた。
真紅さんの作品は、子どもの頃によく、身近な建物を擬人化して画に描いていた体験がモチーフとなっている。例えば、東京駅をモデルにした代表作『紳士の佇まい』では、ドイツの鉄道技師フランツ・バルツァーの和風建築案が反故となった後、バルツァーに代わり設計者を務めた辰野金吾が採用した、英国建築の流れをくむクイーン・アン様式にちなみ、ステッキ代わりに唐紅の和傘を提げた英国紳士が描かれている。どの作品も、画の奥にモデルとした建築物の歴史を内包させ、観客に見慣れていた建築物の新たな顔や、意外な顔を垣間見させるような仕組みが施されているらしい。批評家からは、「謎解き」としても楽しめると評されていると聞いた。
歴史に疎いわたしには、そこまで深く画を観賞することは出来なかったのだけれど、これが「芸術」と言うものなのかと、今まで触れたことのない世界の扉を開かれたような思いがした。
「蜜柑、これも真紅さんの作品?」
わたしはある作品の前で足を止め、前を行く蜜柑の背中に声を掛けた。蜜柑が振り返り、画を見つめ、
「――うん。そうだと思うけど」
描かれているのは、他の作品と同じように、ある一人の人物なのだけれど、わたしにはどうしても、建築物を擬人化して描いたというよりも、本当の人物をモデルに描いた肖像画のように見えた。
遥か遠くを見つめるような深緑色の瞳が、まず目を引く。それは左目で、右目は、目元にまで垂れ下がる、瞳と同じような色合いの前髪で隠れ、よく見えない。鼻は決して高くはないけれど、顔の中心のパーツとして確かな存在感がある。滲むような緋色で塗られた唇は、下唇が厚く、真一文字に結ばれている。顔の輪郭は、これ以上ないくらい直線と曲線がバランスよく配置されていて、叶うなら、指先でそっと、その輪郭をなぞりたくなるくらい。首は顔の大きさに比べて太く、喉ぼとけも目立つ。右耳には、コバルトブルーの小さなピアスが鈍く光る。
「あら、どうしたの?」
わたしがその画に見惚れていると、真紅さんがヒールの音を響かせてやってきた。
つづく
#短編 #小説 #連載 #小野小町 #古今集 #ギャラリー #アーティスト #円舞曲 #フランツ・バルツァー #東京駅 #辰野金吾 #クイーン・アン様式 #芸術 #itioshi
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
