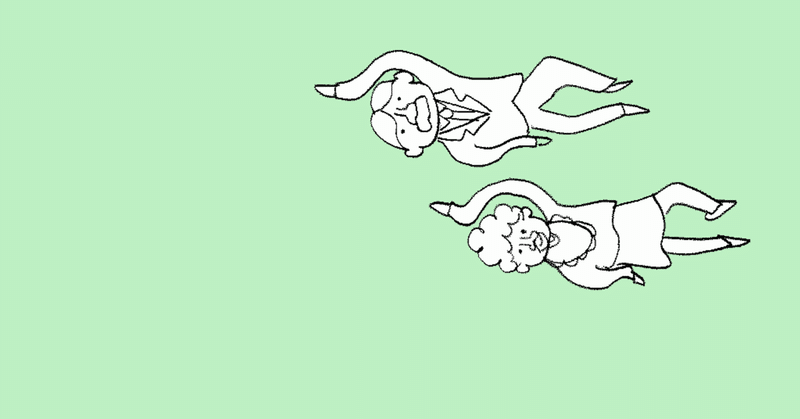
べき論ではなく、なにを目指すかを大切にしたい。
先日、20年NPO法人の代表理事を務めてきた大先輩と、話す機会をいただいた。その中で「NPOはこの20年で変わりましたか?」ということを聞いた。それに対する回答を聞いて、直接そう言われたわけではないけれど、「彼の中での『NPO』に大切なことは変わっていない」んだなと思った。その後いくつかの言葉を交わす中で、例えば海外の例を示された事とか、「ボランティア」を整理して語られたこととか、見る角度とか細部の積み上げ方は違うけれど、同じことを考えておられるんだな。考えてこられてきたんだなと思って、なんだか安心しました。
いろんな言葉には、その言葉の意味があり、特に名前にはその名前が示す「ある常識」とか「共通認識とされていること」がある。あることになっている。でも、言葉は時代と共に変化するし、名前に伴う共通認識や、「これはこうあるべき」ということも変化する。で、その変化することが大事で、さらに言うとその変化の中でも変わらないこと、それを僕は「物の理」と捉えていますが、それが僕は本当に大事だと思っています。
先の話で言えば、先輩は「ボランティアの存在が大事だ」なぜなら「そこで働いている人だけだと組織の保身に走りその組織がやるべきことよりもそれが優先される可能性があるからだ」ということを一例として話されました。僕はそれに対して「ボランティアの方々関わることで地域と組織の境界線があいまいに、ゆるやかになることが大事だ」なぜなら「地域に必要なことを支えるのが僕たちの役割だからだ」ということを話し、二人で「そうだ」「消費者ではなく当事者としてまちに関わる人が増えることが大事だ」という話になり、一致しているなと思いました。
僕らの組織のスローガンは「自然治癒力の高いまちの実現」で、それはまさしく「消費者ではなく当事者としてまちに関わる人が増える」で実現されるものだと思っています。先輩の言い方では「個の自立」であり「豊かな市民社会の実現」。
言葉は違うけれど話せば話すほど、目指していることは同じなんだなと思いました。
NPOとか、ボランティアという言葉は、その言葉に個々の頭の中で染みついてしまっているイメージがいろいろあり、それは関わりが深い人であればあるほど一文ではとても伝えられないように複雑になっていて、関りが薄い人には「無償で社会のために働く人とか組織」みたいにざっくり過ぎて実態と合っていないことになっている。そう感じます。
だから、できれば実際におこなっている行動で、その行動を一緒にしてくださる人を増やしていくことで、「自然治癒力の高いまち」が近づいてくれば、それが一番いいなと思っています。
自分なりの対談への振り返りとして。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
