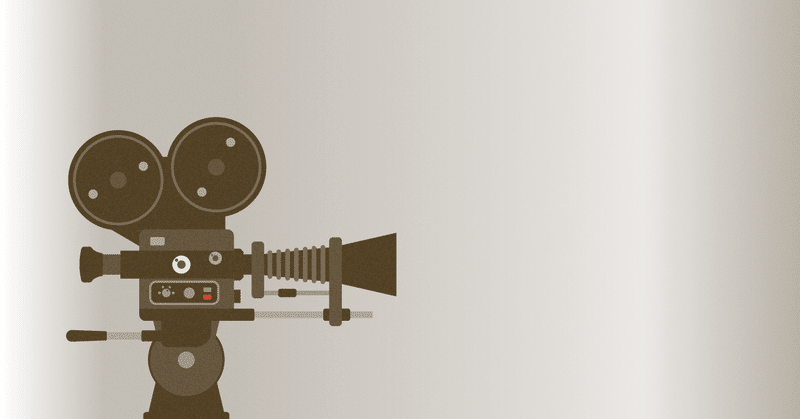
『幕末太陽傳』:1957、日本
文久2年、品川宿。攘夷の志士である志道聞多、伊藤春輔、大和弥八郎の3人が、馬を走らせる英国人たちを追い掛ける。大和は巾着袋を落とすが、気付かないまま走り去る。佐平次という男が巾着袋を拾い、中に入っている外国製の懐中時計を見つけて懐に入れた。
彼は仲間の新公、金坊、長ンまを連れて遊郭の相模屋へ赴き、酒や女郎を用意するよう頼む。おそめを始めとする4人の女郎が、すぐに部屋へ来る。攘夷の志士である高杉晋作が別の部屋で寝転んでいると、仲間の志道たちがやって来る。
相模屋楼主の伝兵衛は、義理の息子である徳三郎が戻らないことを気にする。岡っ引の平六が宿改めに来たので、若衆の喜助が案内を引き受ける。女郎・こはるに売り上げで負けているおそめは、やり手おくまから客の選り好みが過ぎることを注意される。こはるは高杉たちが平六を欺くための手伝いをした後、別の部屋へ向かう。
高杉は志道たちに、御殿山の異人館を焼き討ちしようと提案する。そこへ仲間の久坂玄瑞が現れ、廊下まで声が筒抜けになっていることを注意する。小平次は厠で志道たちと遭遇し、落とした時計を預かっていることを告げる。小平次が時計を分解して修理していると、志道が来て乱暴な態度を取る。高杉は志道を立ち去らせ、小平次に謝罪する。
翌朝、左平次は喜助から勘定を催促され、明日まで待つよう告げる。娘のおひさを女中として働かせている大工の長兵衛は、借金のカタである大工道具を持ち去ろうとする。そこへ伝兵衛の妻・お辰が現れ、娘を女郎として売る意思を確認される。こはるは仏壇屋の倉造と息子の清七を、それぞれ別の部屋で客として相手する。倉造と清七は互いに、相手が相模屋へ来ていることさえ知らない。
左平次は喜助から勘定を催促され、後から連れが来るので待つよう告げる。徳三郎が相模屋に戻り、吉原で遊んで来たので同行した附馬に勘定を払うよう番頭の善八に頼む。伝兵衛が支払いを拒否すると、徳三郎は銭箱を掴んで大声で騒ぎ始める。伝兵衛は激昂し、徳三郎と血の繋がっているお辰に彼の処分を任せる。
おそめは心中でもしようかと考え、貸本屋の金造を部屋に呼ぶ。2人は店の裏にある川へ行き、おそめが怯える金造を突き落す。だが、おくまが予備に来たので、おそめは心中せずに店へ戻ってしまう。浅瀬だったので金造は死なずに済み、おそめの身勝手に憤慨する。
翌朝、佐平次は喜助から勘定を催促され、一文も持っていないこと、連れの居場所も知らないことを悪びれずに白状する。伝兵衛は善八や喜助を叱責し、給金を半分にすると通達した。佐平次は行灯部屋を用意され、胸を病んでいるので咳き込んだ。
その夜、町を歩いていた志道たちは、どうやら女郎目当てで来たらしい長州藩江戸詰見廻役の鬼島又兵衛と遭遇した。佐平次は相模屋の手伝いを開始し、素早い動きで若衆たちの仕事を奪っては礼金を頂戴する。佐平次は高杉の部屋へ行き、時計の修理を請け負った。
彼は伝兵衛の元へ時計を持って行き、60両か70両になるのでツケが貯まっている高杉の部屋代にするよう促す。倉造と清七は店で鉢合わせし、こはるから両方とも起請文を貰っていたことを知った。佐平次は鬼島の部屋へ赴き、こはるから貰った起請文を見せられた。
こはるは倉造と清七に詰問され、窮地に陥った。佐平次はおそめから起請文を貰った客に成り済まし、部屋へ乗り込んで彼女を殺そうとする芝居を打つ。こはるを逃がした後、彼は倉造と清七に嘘の身の上話を語った。すっかり同情した親子は、こはるを諦めて店を後にした。
こはるから礼金を差し出された佐平次は、起請文の買い取りを要求した。こはるは佐平次に呆れるものの、その男っぷりに惚れ込んだ。佐平次は起請文を刷り、それで稼ぐようになった。
喜助と若衆仲間のかね次、忠助、三平たちは佐平次に憤慨し、暴力的な方法に出ようと目論んだ。おそめは金造の訪問を受け、「死んだけど生き返った」と言われる。おそめが中座して部屋へ戻ると彼の姿は消えており、後には位牌が残されていた。直後にガエン者の権太と玄平が棺桶を持って店へ現れ、中に入っている金造の遺体を見せた。
権太たちが責任を取るよう要求すると、善八が金を渡そうとする。金を奪い取った佐平次は、お湯を浴びせて金造たちの芝居を暴く。一味を追い払ったことで佐平次の株は上がり、喜助たちも計画を中止した。しかし全ては佐平次の仕組んだ芝居であり、後から金造たちと密会して小遣いを渡す。この一件で、おそめも佐平次に惚れた。
徳三郎は長兵衛がおひさを売ると決めたことを知り、思い直すよう説得する。しかし伝兵衛が金を渡すと、すぐに引き下がった。徳三郎は佐平次と花札で勝負し、大金を工面しておひさを買い戻そうと目論んだ。しかし佐平次に惨敗し、身ぐるみを剥がされた。
佐平次は彼に、高杉の時計を売れば大金になると教えた。しかし時計を盗み出した徳三郎は伝兵衛に見つかり、座敷牢に監禁された。おひさは食事を運び、女郎になりたくないので自分を女房にして駆け落ちしてほしいと持ち掛けた。
おひさは佐平次に、駆け落ちの手伝いを依頼した。彼女が1年に1両ずつで合計10両の支払いを約束すると、佐平次は承諾する。高杉たちは焼き玉を用意し、焼き討ちの準備を進める。そこへ佐平次が来ると、「たどんの減りが早いと思っていた」と言いながら焼き玉を持ち去ろうとする。
慌てて取り戻した久坂たちだが、隠密ではないかと疑いを抱く。そこで高杉は、自分が斬ると仲間に告げる。しかし高杉は佐平次の勇ましい態度を見て、刀を収めた。佐平次は高杉たちに協力し、志道が鬼島から百両をせしめるための芝居を打つ。さらに彼は、おひさと徳三郎を逃がすための作戦も着々と進める…。
監督は川島雄三、脚本は田中啓一&川島雄三&今村昌平、製作は山本武、風俗考証は木村荘八、撮影は高村倉太郎、照明は大西美津男、録音は橋本文雄、美術は中村公彦&千葉一彦、編集は中村正、助監督は今村昌平、所作指導は沢村門之助、音楽は黛敏郎。
出演はフランキー堺、左幸子、南田洋子、石原裕次郎、芦川いづみ、市村俊幸、金子信雄、山岡久乃、梅野泰靖、織田政雄、岡田眞澄、高原駿雄、青木富夫、峰三平、菅井きん、小沢昭一、植村謙二郎、河野秋武、西村晃、熊倉一雄、三島謙、殿山泰司、加藤博司、二谷英明、小林旭、関弘美、武藤章生、穗高渓介、秋津礼二、宮部昭夫ら。
―――――――――
『とんかつ大将』『洲崎パラダイス 赤信号』の川島雄三が監督を務めた作品。脚本は川島雄三と『ひばりの悲しき瞳』『俺は死なない』の田中啓一、『風船』の今村昌平による共同。
佐平次をフランキー堺、おそめを左幸子、こはるを南田洋子、高杉を石原裕次郎、おひさを芦川いづみ、こはるの客である杢兵衛大盡を市村俊幸、伝兵衛を金子信雄、お辰を山岡久乃、徳三郎を梅野泰靖、善八を織田政雄、喜助を岡田眞澄、かね次を高原駿雄、忠助を青木富夫、三平を峰三平、おくまを菅井きん、金造を小沢昭一、長兵衛を植村謙二郎、鬼島を河野秋武、志道を二谷英明が演じている。
この映画、冒頭に「製作再開三周年記念」と表示される。日活は戦時中の企業整備令により、大都映画や新興キネマと合併して「大映」という1つの会社にされていた。戦争が終わり、1954年に調布の日活撮影所が建設されて映画製作が再開されたので、そこから三周年を記念しての作品という意味だ。
つまり日活としても大きな意味を持つ作品だったわけだが、それなのに大作には似つかわしくない軽喜劇であること、しかも世間からの批判が強かった「太陽族」を連想させる題名であること、既にスターだった石原裕次郎や人気女優の芦川いづみを脇に回してフランキー堺を主役に起用したことなどから、川島監督は日活上層部から睨まれた。一方の川島監督も日活への不満が蓄積しており、この映画を最後に東京映画へと移籍した。
冒頭、佐平次が懐中時計を拾うシーンが描かれる。そこから彼が連れと共に相模屋へ入るシーンの間に、現在の品川を写し出すパートが挿入される。そして、もうすぐ閉鎖される赤線地帯があることをナレーションが説明した後、オープニング・クレジットがあってから、文久2年の本編へと突入する。
映画のストーリーだけを考えれば、現在の品川について説明するプロローグを付けておく必要性は全く無い。たぶん当時の日活の上層部からすると、そういう入り方にも不満があったんじゃないだろうか。時代劇映画なんだから、普通に時代劇として構築すれば良いわけであって。
しかも、最初は時代劇から入ったのに、カットを切り替えて、わざわざ現在の品川を写してから再び時代劇に戻るという面倒な手間を掛けることに何の意味があるのかと感じていた人もいたのではないだろうか。
しかし、そこには大きな意味があるのだ。いや、むしろ、それこそが監督の描きたかったテーマに直結していると言っても過言ではない。きっと監督は、売春防止法によって品川の赤線地帯が消えることに寂しさや憤りを感じていたのだ。そのことを、江戸の終わり頃にある遊郭を通じて表現したかったのだ。
だからこそ、この映画ではストーリーを進めることだけに意識を向けるのではなく、道草とも言えるような描写が多く含まれているのだろう。
普通に考えれば、佐平次が主人公なんだから、彼の絡む物語を進めて行けばいいはずだ。しかし、彼が登場しない時間帯ってのが随分と多くなっている。で、その時間で何を描いているというと、女郎たちや、遊郭で働く使用人、出入りする客や業者といった人々の様子だ。
貸本屋や呉服屋が来て女郎相手に商売をする様子なんてのは、ストーリー進行には全く必要性が無いが、そういう細かい遊郭の日常風景まで丁寧に描いている。
そういった描写を一言で表現するならば、「遊郭の賑わい」だ。もちろん、時には厄介な客が来たり、トラブルが起きたりすることもあるが、それも含めて遊郭の賑やかさであり、そして華やかさだ。きっと川島監督は、そういうモノを描きたかったのだ。
時代が移り変わって赤線地帯と呼ばれるようになっても、そういう活気のある場所ってのは引き継がれていたのだ。そして、そんな売春宿が持っている賑わいを無くしてしまうことに対する自身の気持ちを、この映画を通じて訴えたかったのだろう。個人的にも、ストーリーの部分よりも、遊郭の楽しさ、賑やかさという部分の方が、より興味をそそられた。
この映画は古典落語をモチーフとしており、「居残り佐平次」「品川心中」「三枚起請」「明烏」「芝浜」「船徳」「大工調べ」「文七元結」「五人廻し」「お見立て」などの要素が盛り込まれている。
元ネタの落語を知らなくても全く支障は無いが、知っていた方が楽しみが増すことは言うまでもないだろう。落語にはサゲってモノがあるが、そこを重要な要素として使っているわけではないので、ネタバレになっていて楽しめないということも無い。
「お調子者の佐平次が巧みな弁舌の機転の良さで上手に立ち回り、周囲のトラブルを解決して人々を魅了していく」という痛快で軽妙な物語を、小気味よいテンポで描き出した喜劇である。だから、基本的には深く考えずに、お気楽に楽しめる娯楽映画だ。
ただ、佐平次が金を払わず居残るのは別にいいんだけど、そのせいで善八や喜助たちが賃金を減らされるなどの迷惑を被っているのに全く罪悪感を示さず、罪滅ぼしもせずにヘラヘラしているのは、ちょっと不快感が残るなあ。
佐平次が品川へ来た理由を「胸を病んでいるので養生のために」と設定してあるのは、普通に考えれば全く要らない要素だ。それよりも「何だか分からないけど居残っている」という形の方が、キャラとしての面白味は出る。
しかも、単に明確な理由を用意しただけでなく、「病気の養生」ということにすると、それは笑いにするのが難しいモノになってしまうわけで。しかし、これが川島監督の作品ということや、そんな川島監督について深く知ってしまうと、そういう設定を肯定的に受け取れるようになる。
川島雄三監督は監督昇進の頃から筋萎縮性側索硬化症で呼吸筋に問題を抱えており、1963年に45歳で亡くなっている(死因は肺性心)。つまり監督は佐平次に自分を投影し、この映画で自分の思いを吐き出したのだ。
かなり私的な部分の多い作品ってことになるので、それは娯楽映画としてどうなのかという向きもあるのだが、でも娯楽映画として見ても充分すぎるぐらい面白いので、だから問題は何も無い。これで「自分の思いが強すぎてバランスを崩し、娯楽性が欠如している」ってことになったら、それは完全にアウトだけどね。
最初はバラバラに配置されていた複数の登場人物やエピソードが、そこに佐平次が関わることによって1つにまとまる。例えば、こはる&おそめは最初からライバル関係にあるが、そこの戦いに関しては、序盤はそんなにクローズアップされていない。そして、それぞれが全く別々のエピソードを受け持っている。
だが、どちらが抱えるトラブルも佐平次が解決することによって、「こはる&おそめが佐平次に好意を抱いて競い合う」という展開になり、そこが1つにまとまるわけだ。
終盤、高杉たちが異人館焼き討ちのために計画を進めるエピソードと、おひさ&徳三郎が駆け落ちしようとするエピソードが同時進行で描かれるが、ここの見せ方も上手い。しかも、ただ「両方に佐平次が関わって上手く事を運ぶ」という様子を単に並行して描くだけではなく、まるで無関係だった2つのエピソードを結び付ける辺りの手管も見事だ。
駆け落ちのエピソードは「佐平次が裏切ったと見せ掛けて、それも含めて作戦の内だった」という内容になっていて、なかなか憎いねえ。
完全ネタバレだが、この映画のラストでは、こはるを捜す杢兵衛に佐平次が「こはるは急死した」と嘘をつき、墓へ案内するよう要求され、騙されたと知った杢兵衛に「地獄も極楽もあるもんけえ。俺はまだまだ生きるんでえ」と告げて海沿いの道を逃走する。
それで終幕になっているのだが、この映画のラストが当初の予定と大きく異なる形になっているのは、かなり有名な話である。川島雄三監督は当初、「佐平次がセットの組んであるスタジオを飛び出し、現代の町を疾走する」というラストを考えていた。しかしスタッフとキャストから大反対されたため、演出を変更したのだ。
しかし、後になってフランキー堺が「監督に賛成すべきだった」と漏らしているように(最終的に川島監督がスタジオを飛び出す演出を断念したのは、主演である彼が反対したためだった)、やはり川島監督のプラン通りにしておいた方が、受ける印象は上だったと思う。そっちの方が、間違いなく解放感に満ち溢れている。
この映画だと、「墓場という陰気な場所からの逃走」という部分が弱くて、今一つ解き放たれた印象がしないのだ。やはり当初のプランの方が、「サヨナラだけが人生だ」の川島監督にふさわしい。
(観賞日:2016年5月26日)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
