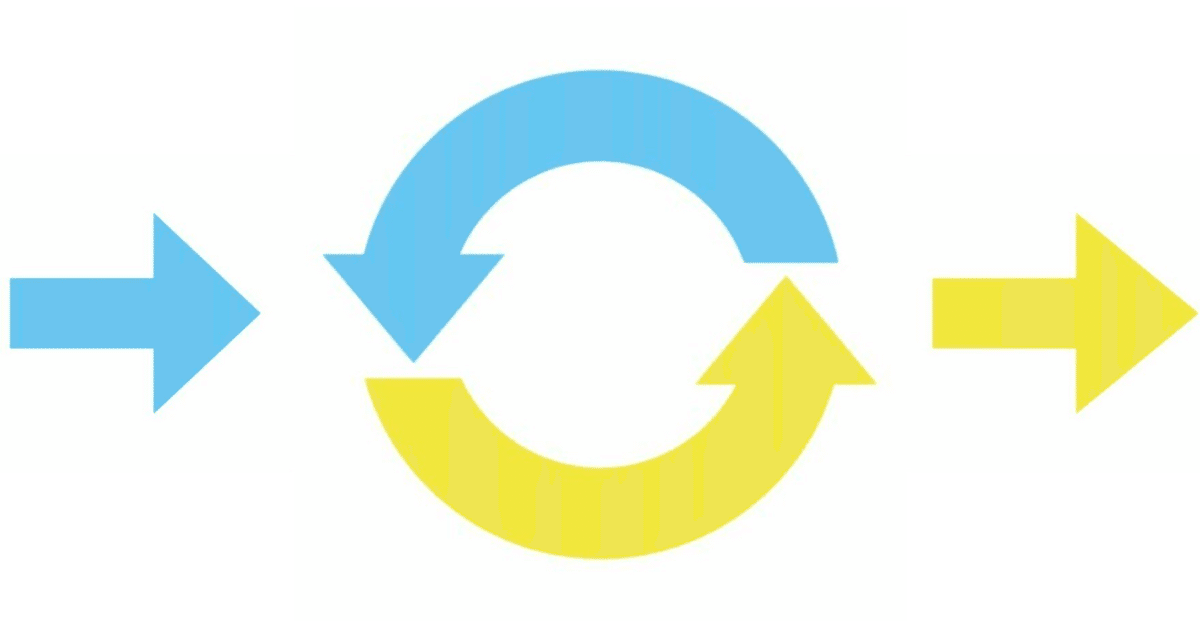
自分の発作が発生するプロセス 1/2
昨日自分の適応障害の発作が、"叫ぶ"ということを書いた。
この発作の症状については、自分自身それなりに向き合っていて、いつもいろいろな角度から考えているのだが(ダメージを受けながら)、今日はその中でわかったこと、気が付いたことを書いておこうと思う。
(昨日の記事↓)
元々僕は理詰めに物事を考えたがるタイプの人間で、この発作が起こるようになったときも、まずは原因と対策を考えるようになった。
原因はシンプルで、すぐにわかった。
「ストレスを感じた時」。
はじめは会社に関わるストレスだけであったが、次第に会社以外のストレス…たとえば、趣味でやっている草野球のことであったり、昔の黒歴史であったり、そういうものにでも反応するようになった。
問題は対策だ。
人間は過去に戻れない。
黒歴史をなくすことはできないし、趣味の草野球でしたエラーをなくすこともできない。
今後の人生、失敗しないで人生を送っていけるほど、器用な人間でもないのだ。
原因の根本を絶つことは不可能であるかに思われた。
対策のため、さらに分析をする中で、事象の粒感を細かくしたときに、自分の発作が発生するプロセスには2つの段階があることに気が付いた。
①発作の発生
発作の発生は、0→1のフェーズである。何らかの原因で自分の身体の中でストレスを起因としたシステムエラーが起き、それを理由に発作が発生する。
②発作の大小
発作の大小は、1→nのフェーズである。
①のプロセスを踏んで発生した発作が、大きい発作か小さい発作か。
要はデカい声で叫ぶのか小さい声で済んでいるのか。
本当に小さい声で済むときは、しゃっくりとか、咳とか、ゲップとか、そういう風に見えなくもないので、十分社会生活が可能であると感じられた。
逆流をすることはない。
必ず、①のプロセスを踏んで「発作の発生」が確定し、
そうすると②の判定に入って、発作の大小が決まる。
そして、最終的なアウトプット(発声)に行きつく。
この法則があることに気が付いた。
だから、おれは、ひとつひとつ丁寧に対策を打つことを考えた。
問題はここからだ。
どうしてもピースが足らなかった。
おれの主治医の先生は、割と信頼している先生で、出してくれている薬にも実際効き目は感じている。
ただ、薬の効き目は、"発作の大小"…すなわち②に限られる。
それでも、「投薬しても出て来る発作に関しては慣れるしかない」と、"発作の発生"、すわなち①に関しては、半ばこちらに解決策を丸投げする診断をされてしまっていた。
つまるところ、
「通院したところで、発作の大きさを抑えることは薬でできたが、発作の発生を防ぐことができなかった」
「病院で"②発作の大小"の解決策は見えたが、"①発作の発生"の解決策を見つけることはできなかった」
これは結構恐怖である。
何がきっかけでまた大声で叫びだすかわからない。
また何かの拍子に叫びだしてしまった時に、自制する手段がない。
薬で抑えられてはいるのだが、それがいつまで続くのか、どう続くのか、何が自分に起こるのか、何もわからない。
割と一か月くらい、途方に暮れていた。
おれはこのまま、一生虚空に向かって叫び続けるしかないのか。
(比喩表現ではなく、本当に虚空に向かって叫び続けていた)
もがき苦しむその中で、おれは、自分の"思考"に目を向けて見ることにした。
何かを考えているとき、発作が出ているのではないか。だとすれば、その"何か"はなんなのだろう。
…残念ながら、答えが出ることはなかった。
理由は簡単だ。漠然としすぎだ。対象が"何か"なのである。
おれが苦しんだ、ウルトラホワイト企業の曖昧な指示と何ら変わらない粒感なのであった。それが"何なのか"がわかるのであれば、すでに解決にかかっているはずだ。わからないから困っている。
こんな状態では解決するはずがない。
結果的に、別のルートで①についても、粒感を細かくし、解決策の糸口を見つけることになるのだが、
ちょっと長くなってきたのでも、それは次の機会に。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
