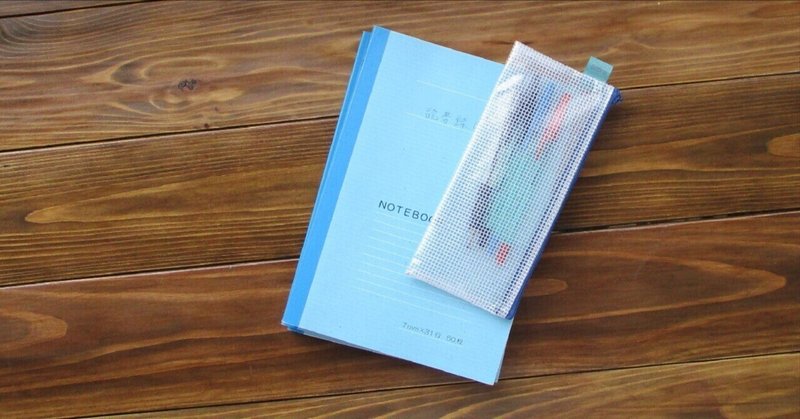
ユン・チアン「ワイルド・スワン 上」読書感想文
たしか「ブラック・スワン」という映画もあった。
「新宿スワン」という漫画だってある。
“ スワン ” がつくタイトルの作品は、なにかとおもしろい。
官本室で、この「ワイルド・スワン」の上下巻を目にしたときは、たぶんおもしろいだろうなとの予想があった。
どのような内容なのか?
様子見のため、手に取ってみた。
表紙裏には『世界の各紙で絶賛!』という見出しに、各国の新聞社の推薦文がいくつか載せられている。
それからすると、中華民国の建国から文化大革命を描いたノンフィクションの本らしい。
全世界で1000万部のベストセラーだという。
そんな本があるなど、まったく知らなかった。
文化大革命の前知識はないといっていい。
NHKの『映像の世紀』で見たことがあるくらい。
毛沢東が国民に呼びかけて、政敵の劉少奇を追い落とすという流れはわかる。
文化だの革命だのいっても、ただの難癖をつけてるだけで、なんやら大勢の中国人が、あにゃあにゃと甲高い声で騒いでいるイメージがあるだけで、イマイチよくわかってない。
この本を選んだ理由
ペラペラめくってみると、文字量が多い。
中国名の人物も多く登場しているようだ。
途中でこんがらがって、わけわからなくなるのでは。
官本を選ぶ時間は5分。
選本を失敗したくないと、1回は棚に戻した。
でも、ノンフィクションというのが気になる。
2度目に手に取ってみたのは、半年後だった。
その時代を生きた女性の3代記ともある。
ユン・チアンという著者も女性だという。
もしかすると、ありがちな愛憎劇が主かもしれない。
彼が好きとか嫌いとか、恋人がすべったのころんだの、家庭がどうだの夫がああだのという、すったもんだに終始するのかもしれない。
せっかくのノンフィクションが、謎の文化大革命が、すったもんだでそっちのけになる気配もする。
また棚に戻した。
で、3回目に手にとってみたときには、1年が経っていた。
どうして3回目があったのかというと、独居房での冬の読書には、単行本が扱いやすいというだけだった。
文庫本だと、開いたページを押さえつけたままにして読むのがちょっとキツイ。
冬になって、本も小机も冷たいので、指先は使いたくない。
手は足で挟んで温めないと、指の背にできかけたシモヤケが悪化する。
真冬になると、室温が8度を切るようになる。
暖房がない中で体の芯まで冷える。
そうなると、とたんに思考力が落ちて、読書も筆記もはかどらなくなるのも経験上わかってきていた。
人間、文化的な生活を送るのには、気温8度は必要だ。
もう少し経つと、防寒のために早々に布団を敷いて、くるまるだけの日が増える。
今のうちに、もっと読んでおきたい。
文字に触れておきたい。
そして筆記しておきたい。
読書で知識を得たい、知見を広めたい、教養をつけたい、考えを深めたい、そのような素晴らしい目的とはかけ離れた読書だった。

訳:土屋京子
原題:WILD SWANS Three Daughters of China
読感
おもしろい。
初めて知ることばかり。
近代中国の歴史というより、異文化を知るおもしろさが詰まっている。
いや、おもしろいは適切ではない。
ひらすら悲惨で残酷なノンフィクションとなっている。
いい方向に、期待を裏切られた。
止まらなくて、先を読みたくてたまらない。
時間となって本を閉じるのが惜しい。
日中から、続きを読みたくて仕方がない。
中国の建国期の混乱が、どんどんと伝わってくる。
共産党が政権をとった経緯も、前知識もなしで、難しい話はなしで、感覚として理解できる。
汚職や専制の政治が成立してしまう中国人の病理を、一般の生活目線で伝えている。
不思議な本だ。
リアルさが込められているからか。
ついさっき目にした出来事を、すぐに書いたような細かさがあって、読んでいて飽きさせない。
場面を想像させて、すいすいとページを進めさせる。
「自分のバカ」と頭を引っ叩きたい
女性作家だから、ありがちな恋愛や愛憎劇が・・・というのは、すべてゲスの勘ぐりだった。
一体どうして、女性作家にそんな先入観があるのだろう?
たぶん、湊かなえと角田光代の小説を読んでからだ。
女性作家を、つまらなそうに感じさせたままになってる。
とにもかくにも。
女性だから、というのは時代に沿わないのは重々と承知してはいるけど、女性作家にしか書けない繊細な文章ってある、と改めて発見したような本だった。
ざっくりした時代背景
要は「争いが絶えませんでした」ということである。
あにゃあにゃと、ごちゃごちゃしてるのである。
1921年 中国共産党(以下共産党)が結党
1927年 国民党と共産党の内戦、第一次国共内戦
1945年 国民党と大日本帝国とで日中戦争はじまる
1946年 国民党と共産党の内戦、第二次国共内戦
1949年 毛沢東が建国宣言して中華人民共和国が成立
1958年 毛沢東の主導で大躍進運動がはじまる
1966年 文化大革命がはじまる
大陸なのだ。
アメリカ支援の国民党が、軍事的に優勢という状況。
そこにソ連支援の中国共産党が、ゲリラ戦を仕掛ける。
さらに大日本帝国が絡んで深入りしてくる。
あとは “ 軍閥 ” という実力行使の民兵軍団も各地に居座る。
結局は、毛沢東率いる中国共産党が “ 農村から都市を包囲する ” ゲリラ戦で勝利する。
で、建国の父となった毛沢東だったが大躍進運動で大失敗。
国家主席を辞任。
で、その巻き返しで、文化大革命という名の権力闘争がはじまる。
登場人物
玉芳(ユイ・ファン)
著者の祖母。
1909年、満州義県生まれ。
16歳で軍閥の将軍の妾となり、著者の母・徳鴻を生む。
将軍の死後、39歳年上の医者と再婚する。
夏瑞堂(シャ・ロエイタン)
玉芳の再婚相手の医者。
著者の義理の祖父となる。
1870年、満州義県生まれ。
玉芳を診察したときに一目ぼれする。
お互いに再婚して生活をはじめるが、一族には猛反対され、長男は抗議の拳銃自殺をする。
夏瑞堂は、問題を解決するために、すべての財産を一族に譲り、玉芳と子の徳鴻を連れて家を出て錦州に移り住む。
65歳にして、貧しい新生活をイチからはじめる。
後に共産党高官となった家族に、四川省で呼び寄せられて暮らし、82歳で天寿を全うする。
夏徳鴻(シャ・トーホン)
著者の母。
1931年、錦州生まれ。
野生の白鳥という意味の「鴻」の字が名前につく。
「鴻」の英語の直訳が、ワイルド・スワンとなる。
国民党政権下の満州で、共産党に協力する活動をする。
ゲリラ隊の隊長として戦っていた夫と知り合い結婚する。
中華民国が建国となってからは、共産党の幹部となる。
この段階で、まだ20歳そこそこである。
21歳で著者を生む。
王愚(ワン・ユイ)
著者の父。
1921年、四川省・宜賓(イーピン)生まれ。
内戦時には、共産党ゲリラ隊の隊長を務める。
やがて張守愚(チャン・シオウェイ)と改名。
中華民国が建国となってからは共産党の高官となる。
共産党の教条を厳守して、公私混同や私利私欲はしないという人物。
この段階で、まだ30歳そこそこである。
夏二鴻(シャ・アルホン)
著者。
1952年、四川省・宜賓(イーピン)生まれ。
両親が共産党の幹部だったことから、特権で優遇された環境で育つ。
1966年に文化大革命がはじまってからは「二鴻」という名前の発音が、革命運動にそぐわないと思い「戎」(ユン)と改名する。
張戎でチャン・ユン。
英語表記が JUNG CHANG でユン・チアン。
内容と解説
祖母から母親から当人への3代の物語
上巻の3分の2は、著者の祖母から母への物語。
そこから、著者のユン・チアンの物語となる。
ノンフィクションとはいっても、当然として身内びいきだってあるだろうし、書ききれない感情だってあるだろうから、ある程度は美化されているのを見込んで読むのだけど、この本に限っては、それを一切させない。
登場する人物は、等身大に感じる。
客観的ともいうのか。
時代がこうだった、社会がこうだった、中国人とはこういうものだ、と補足して書かれているからかもしれない。
中国の動乱に目線がやさしい
書かれている内容のほとんどは、内戦や圧政による悲惨で残虐な日常でもある。
収奪による貧しい生活でもある。
胸がモヤッとする出来事ばかりが続いていく。
それでも、希望に似た、明色な気持ちが擦り減ることなく読み進めることができる。
なんでだろう?
そうさせるのは、それらの出来事を、著者がとりたてて非難することがないからではないか?
ヒステリックさがない。
淡々と書いている。
もちろん、悲しがったり、不安がったりはする。
だからなのか、小さな幸せが妙に心に響く。
たとえば以下である。
新しい生活は貧しかったが、ある日、仕事を終えた高齢の祖父が、ホカホカの焼き餅を買って帰ってきた。
寒い冬の夜だった。
一緒に食べたときには、祖父の目がキラキラしていた。
たったそれだけの、なんでもない一文である。
が、そこに平穏な小さな幸せが浮かび上がっていて、それだけでほのかに感動してしまう自分がいる。
今と比べるから悲惨に感じる
よくよく考えてみるに、著者は当時の気持ちに沿って丁寧に書いている。
今に生きる人が、今と比べてしまうから悲惨に感じる。
しかし当時を生きた人からしてみれば、周りがすべて悲惨だったら、それが通常というか、悲惨のハードルは高い。
わるくいえば、・・・わるくいう必要もないが、さほど不幸に悩んではない。
というより、そんな悩んでいる間がない。
今に生きる人が、今と比べて「悲惨でしたね」と「絶望でしょう」と「不幸でしょう」と「かわいそうですね」と感じてるだけで、当事者らは夢と希望を持って明日に挑む。
ありのままに今を生きているのが伝わるから、さほど絶望が感じられないのかもしれない。
全体的に怖さがあるのは当たり前だ。
真剣な人には怖さがある。
必死な人からは怖さが発揮される。
全員が全員、真剣に生きていて、必死に生きている。
だから、怖さがある。
女性の生きづらさが伝わる
著者の祖母は、毎朝、仏に祈る。
「来世は、犬か猫に生まれ変わらせてください。女だけには生まれ変わらせないでください」と毎日祈っている。
祖母は2歳で、中国伝統の纏足(てんそく)にするために足の甲の骨を砕かれている。
纏足のおかげで有力者の妻になるが、通常に歩くことができない。
その反動もあるのか。
母親は、女性を平等に扱う共産党に入り、個人を抑えつけて建国のための活動をする。
女性を平等というと聞こえがいいが、実態は配慮が一切ないだけだから負担は大きい。
毛沢東は「出産など歩きながらでもできる」と直前まで妊娠している女性兵士を行軍させている。
年頃となった著者は、文化大革命で恋愛どころではない。
恋愛は個人を優先させる行為となって、反革命だと批判されるからだ。
ノンフィクションは要約が難しい
この感想文を書きはじめて気がついたのは、いかに小説は要約がたやすいかということ。
万人受けするフィクションとして、ある程度は練りこまれて完成しているし、感動パターンも範囲が決まっているし、だからこうくるだろうという見当もつくし、割合と簡単にあらすじがつかめる。
省くことも短くすることもできる。
対して、ノンフィクションはむずかしい。
感想文は長くても4000文字、通常は31行のノートに米粒の字で2ページと決めているが、とてもそれだけには収まらない。
とくにこの「ワイルド・スワン」は収まらない。
人が生きたという事実に、あらすじなどない。
とくに女性が3人ともなると、簡単にはあらすじが書けない。
書く以前に手がつけられない。
1冊があらすじになっている。
それを知った読書だった。
