
ポイント・オブ・ビュー
ほらね、と思わず、言いたくなった。
すぐ下で紹介する文章を見つけて、ルネサンス期における思考の大きな転換を無視して、いまのビジネスシーンにおけるイノベーションの方法は語れないんだって、あらためて確認できたからだ。
「視点」という訳語で二流三流の売文家風情が自分の「方法」を語っている場面などのべつ見せられるこの頃、そのたびに19世紀末のヘンリー・ジェイムズの理論的苦闘を思いだす。「ポイント・オブ・ビュー」が元々はルネサンスの絵画アートの専門概念でしかなかったものを、そっくり小説アートの概念に切り換えたのがヘンリー・ジェイムズだった、ってご存知でしたか。「メソッド」という概念に心底こだわり続けたのはヴァレリー(『レオナルドの方法』)に劣らぬくらいジェイムズであったと喝破した先哲サイファーの『文学とテクノロジー』が全く読まれていないのにほとんど絶望して、最近とにかく復刊企画を通した。
高山宏さんの『アレハンドリア』に所収の「シャーロック・ホームズのマニエリスム」より引用。
いまのビジネスシーンにおけるイノベーション創出が目的の一部となったプロジェクトにおいてはこの引用中にもある「視点 point of view」を明らかにすることが大事だとされる(「メソッド」についても同様だが、「視点」のほうに話を絞る)。
視点が大事なのは、どんな立場からどういう風に現在やその先の未来の状況を見通して、その変革を提案するのかを明らかにすることなく、その提案の賛同者を得ることはむずかしいからだ(また、たとえ得られたとしても後に問題となりやすい)。
ようは意図を「見える化」した上で仲間を得ようという話だし、自分たちの依ってたつところを明らかにしておくということで、もちろん、いつも書いてるとおりでこれは大事なことだと僕自身も思っている。
僕らも画家たち同様に自分たちが見ているヴィジョンをほかの人にも示してあげる必要がある。その際、どこの位置からどういう眼で見て、その絵を描いているかを示す必要があり、そこではそれを一枚の絵の中で関係させた上でリアリティを感じさせる遠近法的作画は、ヴィジョンを明らかにする上でも参照すべきメソッドだと思う。
だが、同時に、この遠近法という「見える化」が単なるイリュージョン=見せかけであることも僕はよく知っている。その見せかけがもっともらしい思考の方法として用いられるようになった起源や経緯も知っている。
それが上の引用で、高山宏さんの指摘していることだ。

高山さんが名前をあげているワイリー・サイファーの『文学とテクノロジー』の中では、19世紀のヘンリー・ジェイムズの仕事がこのように評されている。
あるいは、『鳩の翼』(1902)の序文において彼が言っているように、小説家は「〈中心〉によってことを運ぶ」ようにしなければならない、観察のそれぞれの中心はそれ自らの遠近法を、その「独自な機会」を創造しなければならない。そして、1つの中心からのみ小説家は形式を達成しうるのであって、その形式の目ざすところは小説の経済にある。「1つの関連づけられた視点を採用することなしに、小説的処理の経済もまたないのである」。ジェイムズの比喩はアルベルティの遠近法理論に由来している。その淵源はルネサンスにあり、もともと絵画の方の比喩である。一定の固定した視点から、1つの測定可能な距離をおいて眺めたとき、絵画は一貫して観察された世界となり、一切の関係は可能なものとなる。
小説も視覚芸術における遠近法同様、1つの固定した視点をもつことで、小説の経済的システムを可能にする。キュビスムが複数視点を導入したのと同様、小説においても複数の視点を導入したメタ小説的なものも登場するが、それはあくまで「1つの関連づけられた視点を採用する」ことを導入したジェイムズ以降に成り立つことである。
同時に、この小説的な文章構築の方法がその後の日常的な文章の組み立て方にも影響を与え、思考そのものを遠近法的な視点によるものだとしたのだと考えられる。
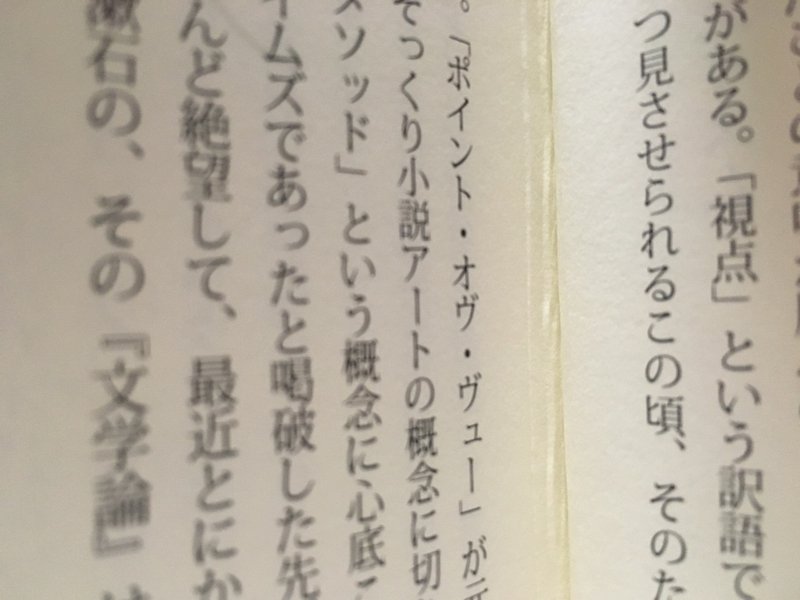
アルベルティが15世紀において視覚芸術に導入した遠近法的な視点は、19世紀において小説のような文学にも導入され、それがいまではビジネスシーンですら用いられるメソッドにも当たり前のように用いられる。だが、良い面ばかりでは当然ない。
この遠近法のもつ功罪両面の影響は、サイファーより30年弱前の1927年の『象徴形式としての遠近法』において、エルヴィン・パノフスキーが次のように指摘している。
遠近法はその本性からしていわば両刃の劍だからだ。つまり、遠近法は、物体が立体的に広がり、身ぶりをそなえて動きまわるような場をつくってもやるが、それはまた、光が空間のうちにいきわたり、物体が絵に解消してしまう可能性をも生じさせる。遠近法はまた、人間と物体とのあいだの隔たりを作り出しもする(「一つはそこで見ている眼であり、もう一つは見られている対象であり、第三のものはそれらのあいだの隔たりである」と、ピエロ・デッラ・フランチェスカにならってデューラーが述べている)が、しかしそれはまた、自立的に存在している人間に対峙している物の世界をいわば人間の眼のうちに引き入れることによって、やはりこの隔たりを廃棄してしまいもする。
そもそも扱いにくい現実の自然や人工物を、遠近法を用いることで、絵として解消し、人間の眼のうちに引き入れることで操作が可能になる。野生の事物を飼いならして使える素材へと加工する技が遠近法である。
「人間の思考の形は時代によって大きく異なる。 その思考の形を左右したのは、他でもない視覚技術の変遷」であるという考えのもとに「人間の見ることと考えることに関する歴史的な変遷を紹介」する連載noteのプロローグとしての「見ることと考えることの歴史 第1章」のなかの「1-6.正しい視点」ではまさにこの話題を扱っている。
遠近法はレオン・バッティスタ・アルベルティが1435年の『絵画論』の中ではじめて体系的にまとめたのだが、そこでアルベルティは遠近法を「正しい制作術(コンストルツィオーネ・レジティマ)」と呼んでいる。
それを確認した上でnoteでは、次のように書いている。
アルベルティはあくまで正しい画法を体系化したつもりだったと思うが、結果、それは絵を見るように世界そのものを見るという見方自体を合法化してしまった。その影響下にいまの僕らもある。街中に貼り出されたポスター、テレビの画面、スマートフォンの小さなディスプレイなど、私たちは四角く切り取られた二次元平面の中にある世界を真実だと思って疑わないからだ。コンテンツが描く内容が虚構(フィクション)かどうかを疑うことはあっても、それ自体、描かれた世界が実際の世界とさほど変わりないものと受け取られているからにすぎない。16世紀、17世紀のオランダを中心に大量に描かれた静物画が同時に空虚(ヴァニタス)を表現するものとされたのも、描かれた静物がリアルに感じられたからに他ならない。見かけにリアリティがあるからこそ、内実と見かけの構図が問題になる。その構図を用意したのが、「正しい制作術」である遠近法であったわけだ。
と。
「実際の世界と二次元平面上のリアリティある画像の間に境目を感じなくなり、その間をシームレスに思考を行き交いさせることができなければ、デザインなど成り立たないということを、ここでもう一度、認識しなおしておきたい」からだとも書いているのもそのnote中である。遠近法という「正しい制作術」は制作するもの自身を見せかけによって欺き、あたかも外界を相手にしているかのような自然さでまやかしの観念を操作できるようにすることで、デザインという外界にも影響を与えうる思考を可能にするのだ。

その遠近法の影響が視覚芸術やその応用としてのデザインの領域を超えて、小説というテキスト芸術にまで明確に入り込んだのが19世紀のヘンリー・ジェイムズの宣言によるタイミングだということができるのだろう。
サイファーはこうも書いている。
ジェイムズ以後、小説における視点の分析が、物語の限界内においてものごとをどういう角度から眺めるかという意識のみでなく、それが内在的に登場人物たちと共にする(一緒の)視覚であれ、彼らの背後にある(その蔭にある、あらかじめ決定し、予定する)視覚であれ、あるいは外的な(外部の、中立的、無関心の)視覚であれ、作者自身が自分の物語をいかなる角度から見るかという意識に移ってゆくにつれて、細微な測定はますます細微なものと化していった。
どこからどう見て描くとどうなるかを細微な違いも含めて理解しコントロールできるようになれば、より細微な表現も可能になる。かつ、この視点それぞれが生みだす見え方のアーカイブとその視点そのもののデータが残っていれば、組合せ=計算による創作の可能性が生じるというのは自然のことだ。
そこで自然をミメーシス=模倣するルネサンスから、自然にはないヴューを創作するマニエリスムへの変転は準備されていたのだといえる。
16世紀マニエリスムは曖昧や過剰に苦しみ、その逃げ場として無理矢理の単純さ、力まかせの整理術をうんだ。僕自身はこれをマニエリスム〈対〉近代という形ではとらえず、マニエリスムが内包する2段階とみて少し大掛かりなマニエリスム近代論を構想してきた。たとえばコンピュータ言語(0/1バイナリー、1667発明)はマニエリスムの綺想か、「近代」への突破口か。ルルス主義(最後はジョン・ケージ、一柳慧や松本潔にまで至る)を認めるなら、コンピュータ言語以上の組合せ術的マニエリスムはほかにない、ということになる。
と書くのは高山宏さんだ。
僕らはこの文章からいつでもAIによる創作、創造を連想することができるだろう。
僕にはいわゆるデザイン思考的なアプローチがルネサンス的で、その後訪れようとしているAIの使用に代表されるコンピューティングな創造にマニエリスム的に見え、後者には前者とは異なる面白みを感じる。
マニエリスムが16世紀の一時代の出来事ではなく、さまざまな時代に断続的にあらわれる常数だ、と言ったのはグスタフ・ルネ・ホッケだが、そのホッケに関連させて言えば、高山さんは別の本でこんなことも書いている。
宗教改革や「永遠のローマ」崩壊の危機を人々は過激に知性を使って生き延びようとする。そこでは理系も文系もない。絵だって完全に理系のものであり、遠近法もアナモルフォーズも技術者の計算の産物だった。そういう危機の生む新観念発明の頭脳の働き方をホッケの発見者エルネスト・グラッシはインゲニウム(ingenium)と称した。今でいうエンジニアの語源である。
『見て読んで書いて、死ぬ』からの引用だ。ルネサンスからマニエリスムへの移行のきっかけともなった、神聖ローマ皇帝カール5世の軍によるローマの破壊、殺戮、強奪が行われた1527年のローマ劫掠後の数々の危機が生んだ「発明のための頭脳の働き方」、インゲニウム。エンジンの語源であると同時に「生まれながらの才能」を意味したラテン語でもある、インゲニウムこそ、マニエリスムの画家たちが自らの創造性の根拠とみなしたものである。そのことに関しては「「見ることと考えることの歴史」プロローグ」で示している。「神は〈自然の〉事物を創造し、芸術家は〈人工の〉事物を創造する」(ホッケ)というのがマニエリスムの画家たちが遠近法というルネサンスの画家たちから受け継いだ遺産をより創造的に用いながら行おうとした仕事である。
外界の事物の複製的なイメージをしっかり頭の中に取り込んだ上で、それらの情報(データ)を自在に組合せながら創造的思考を行うことが求められる現代の僕らの思考はまさに、この一連の思考の流れにすっぽりと収まると思うのだ。
だからこそ、このあたりの思考史的なものを考え、理解していることの大事さを思う。
基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。
