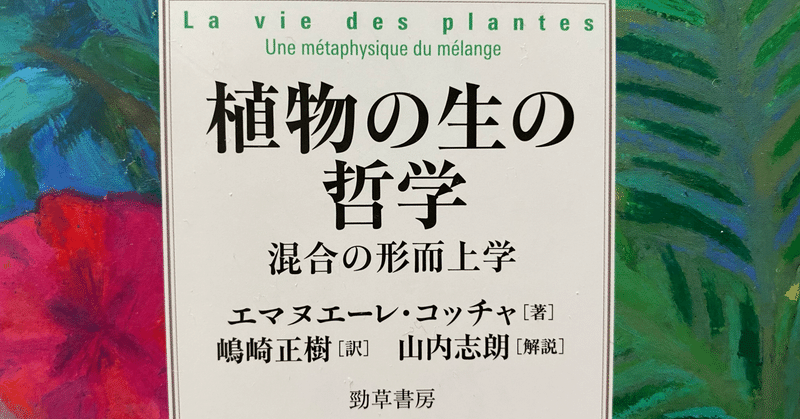
植物の生の哲学/エマヌエーレ・コッチャ
どうすれば良いか?を考える際、何を判断基準とするかが問われる。
何を信じて行動するか?という話だと思う。
その基準を再考することがここしばらくずっと問われているのだろうなと感じている。
根拠も乏しい思いこみであれこれ言うのももちろんどうかしているのだけど、科学的根拠や統計的エビデンスを持ちだしたところで、それも思いこみにすぎないことがわかってきているのではないか?
科学的にも統計的にも無理だと考えられることだって可能な場合はあるのだし、その逆だって十分ありえることを僕らはちゃんと認めたほうがいいし、そのこと自体を信じるべきこともあるのだということを最近嬉しい学びとともに実感もできた。
なんとかして欲しいではない。結局はそれぞれが何を信じるかだし、信じるためには自分が考え動くしかない。もちろん、それを他人に押しつけることは不要で、押しつける相手は自分だけでよい。
地球中心主義を越えて
人間中心主義の見直し、持続可能性という課題、AIが超知能化した際の未来に何を望むのか、など。更新すべき課題は、いま、たくさんある。
そもそも人類はその存在が生じて以来、自分たちが置かれた状況が大きく変わるたびに、常に何を信じて生きるか、行動するかを課題としてきたのだとも思う。
それがアニミズム的な原始宗教のこともあれば、多神教の時代もあり、さらにキリスト教や仏教、イスラム教のような世界宗教であることもあった。科学技術と資本主義経済と民主主義社会の3点セットがそれを担っていたのが直前までか。
その3セットの信頼性が著しく損なわれたいま、まさに「何を信じて生きるのか?」を見直す歴史的なタイミングの1つなのだろうと感じる。
信じるという点では、かつては天動説が信じられていた。地球が中心にあって太陽などの天体がその周りを回っているということを、コペルニクスがそれに異議を唱えるまで西洋の人々は信じていたわけだ。
しかし、いまも結局、その「地球中心主義」は変わらないと指摘するのが、フランス人哲学者で、『植物の生の哲学』の著者であるエマヌエーレ・コッチャだ。

持続可能性の観点から気候変動や環境破壊の問題を議論する際、人間中心主義的な思考を離れても、その離れた先に結局は、人間的な観点からみた「地球中心主義」を置いてしまう傾向があることが本書では指摘されるのだ。これはなかなか目から鱗だった。
「地球中心主義は、いわば偽りの内在性という罠だ」とコッチャはいう。「つまり、自律した大地などというものはないのである」と。
大地を知らず知らずのうちに、自律したものとして切り出してしまう僕ら人類はいまだ地球中心主義で、太陽、いやコズミックな力との関係性をあまく見てるし無視しすぎている。
こんな発想、いままで出会ったことないな、と思える視点が、このコッチャの本からはたくさん得られた。
というわけで、前置きが長くなってしまったが、すこし紹介してみたい。
植物の視点でみるコスモス
タイトルどおりと言えばそうなのだけど、タイトルだけからでは想像できないくらいの植物から世界を見つめ直すことの可能性が示されていてビックリした。
本を読んで、こんな風にびっくりする感覚はなかなかない。特に哲学書でこんな感じを受けたのは、いったいいつ以来だろうか?
のっけからコッチャが書く、こういう文章はそもそも好みだし、ここだけ読んで、すぐにこの本に惹きつけられた。
植物は、わたしたちの文化を定義づける、こういってよければ形而上学的な衒学趣味からすると、常に開いた傷口のようなものだ。抑圧されたものの回帰といってもよい。(中略)植物は、いわば人間中心主義の宇宙に生じた腫瘍、絶対的精神をもってしても廃絶できない廃棄物なのである。
人間中心主義的な見方でみると「廃絶できない廃棄物」なのかもしれないけれど、その廃棄物なしでは、人間も存在しえなかったし、もちろん人間中心主義なんか成り立たないことに気づくとすべてが反転する。
植物によって、また植物を通じて、わたしたちの地球は大気を産出するようになり、地表を覆う生物たちも呼吸ができるようになった。植物の生命とは現実世界のコスモゴニー[宇宙生成論]であり、わたしたちのコスモス[宇宙]を恒久的に生成しているものなのだ。
コッチャがすごいなと感じたのは、この大気や呼吸というものの認識を常識的な理解から大きく覆すような見方を提示してくるところである。
大気のなかで、僕ら人間や動物は呼吸をしていて、その酸素は植物から得て、吐き出した二酸化炭素は植物が光合成で用い、その過程でまた酸素が得られるという循環のうちにあるわけだが、コッチャはそのありようを、僕らも動物も植物も大気のなかに「浸っている」のだという。
大気は、呼吸を通じてそれぞれの存在が大気とともに互いに混ざりあう場だと見做される。僕らはいろんなものと混ざり合っている。混合こそがデフォルトの状態で、誰かや何かが常に僕のなかに入ってくるし、僕は常に何かや誰かのなかに混ざり合っていく。その混ざり合いが呼吸であり、それがなされる場が大気なのだ。
そんな場で、誰かのせいしたり、誰かが何かをしてくれることに期待したり、してくれなくて文句言ったり、してくれたらしてくれたで別の文句を言ったりとかっていったいなんなのだろうか?と思う。
「呼吸の原初的な属性、いっそう逆説的な属性はその非・実体性にこそある」のだ、とコッチャはいい、「呼吸は他から分離できるような対象ではなく、あくまで振動にすぎ」ず、「あらゆる事物が生命に開かれ、ほかの対象と混じり合うような揺れ動き、ほんの一瞬のあいだ、世界な原材料を活性化する振動」なのだという見方を提示してくれる。
そして、その振動の起点をつくる役割にあるのが植物だというわけだ。
植物を通じてコズミックな世界が大気に包まれ、互いに振動のなかに浸るのだ。
自分自身をかたちづくる
すこしでも植物を育てたことのある人なら、みな知っていることだが、植物の成長速度には驚くものがある。
朝と夜ではいったいどうしてこんなにもかたちを変えることができるのか?と思えるほど、あっという間に成長していたりする。僕らや動物は自由に動くことはできても、植物のようなすごい速度で自分のかたちを自由に変えたりすることはできない。
かたちを変える、かたちを作るという点では植物には天才的な才能がある。
植物にとってすべてのかたちは存在そのものの諸変化なのであって、行為や作用だけの変化ではない。かたちを造るとは、自身の存在のすべてをもってそのかたちを経験することなのだ。ちょうど人が年齢別・段階別におのれの実存を経験するように。
創作行為や技術は、変容のプロセスから創造者・産出者だけは排することを条件に、かたちを変容させることができる。その意味で行為や技術は間接的・抽象的なのだが、植物はその対極として、直接的な変容を突きつけてみせる。つまり植物が産出するとは、常に自分自身の変化を意味するということだ。
まったくもって植物に学ぶことは大いにある。この引用中にある、自分で自分自身をかたちづくれるということなどは、大いに見習わなくてはならない。
他人を変えること、状況を変えることばかり望んで、自分自身を自分自身によって変えようとしない人ばかりがいるなかで、「植物が産出するとは、常に自分自身の変化を意味する」というコッチャの指摘をどう読むか?
その植物自身の変化を支える光合成という彼らの呼吸が、世界そのもののかたちをもつくるのだ。そして、それがあるからこそ僕らもその世界創生に加わることも可能になる。植物とともにありさえすれば。
息をするとは世界を作ること、世界に溶け込むこと、そしてその永続的な営為の中で、自分のかたちを再び描き出すことをいう。世界を知り、世界に浸透し、世界とその精気によって浸透されることをいう。世界を横断し、つかの間、その同じ跳躍でもって、世界を個別に経験する場となること。この作用は決して終わりとなることはない。世界は生物と同様に、息吹の回帰、その可能性の回帰にほかならない。まさに精気である。
植物同様、僕らも息をしている以上、世界を作り、世界に溶けこんでいる。
それが人間の認識の方法だといえばそれはそうなのだが、傍観者的に世界を批判的にみる見方ばかりしていても、それで見落としてしまう部分がどれだけ多いかということに、この本は教えてくれる。
世界は僕らの息吹そのものにほかならない。
それなのになぜ傍観者気分になったり、被害者モードであれこれ言ったりができるのだろう。
すべてがすべての中にある
世界は場所ではない。
そう、コッチャは言う。
息を吸い込むとは、わたしたちの中に世界を到来させること、つまり世界がわたしたちの内にあるようにすること、息を吐くとは、わたしたち自身にほかならない世界に、自分自身を投げ出すことである。世界に在るとは、わたしたちが知覚し、生き、夢見ることのできるすべて、将来的にできるかもしれないすべてを含みもつ究極の地平の〈内部に〉、単純に身を置くことではない。わたしたちが、生き、考え、知覚し、夢想し、呼吸し始めるとにから、世界はその無限の細部にこいてわたしたちの内にあり、物質的・精神的にわたしたちの身体と魂に浸透して、わたしたちを成立させるかたち、内実、現実をもたらすのである。世界は場所ではない。それはすべてがすべての中にあるという浸りの状態、トポロジカルな内在性の関係など一瞬にして覆す混合の関係なのだ。
混合しているというのは、単に他のものと並んだ状態にあることを言うのではない。互いに自分の壁を越えて、相手の境界を侵犯して、影響しあう状態をいう。
また、混ざり合ったからといって、それぞれが自分を失うというのとも違う。混ざり合っても個々のアイデンティティは保たれる。他者からの影響を受けつつ、そのアイデンティティに変化を伴いながらも、自分は自分である状態は保ち続ける。
自分のなかに他者はあり、自分もさまざまな他者のなかにある。
誰もそれを拒むことはできない。
すべてがすべての中にあるというのは、世界においてはあらゆるものが循環でき、伝達でき、翻案できなくてはならないからだ。空間のパラダイムをなす形状としてときに人が想像する不可入性は、実は幻想にすぎない。伝達や相互浸透を妨げるものが存在するとされるその場所で、新たな局面が生まれ、それによって物体は、一方が他方に内在する関係を相互浸透の関係へと覆すことができるのだ。世界の中にあるすべては混合を産出し、その混合の内で自身を産出する。あらゆる場所ですべてが出入りするのである。
植物において循環は大気の中だけで起こるのではない。植物には大気に伸びる葉や枝や茎と同時に、地中に向かって同じように伸びる根茎がある。
根は隠されていて秘教的な、潜在する第二の身体のようだ。いわば解剖学できない反・身体、反・物質であり、もう1つの身体がなすことを鏡のように1対1で反転させ、地表面でのあらゆる努力が向かう先とちょうど正反対の方向へと植物を押しやるのだ。想像してみてほしい。あなたの身体のそれぞれの運動に、逆方向に向かう別の運動があったとしたらどうだろう。あなたの腕、口、目に、それぞれ正反対の対応物があり、あなたの世界の組成を定まる物質の、まさに鏡のごとく正反対の物質の中に位置していたとしたらどうだろう。根をもつということがどういうことか、これであなたはたとえぼんやりとでも思い浮かべることができるのではないだろうか。
人間や動物が地表面にしか身体を伸ばしていくことができないのとは違って、植物は地下の世界とも相互浸透が可能なのだ。
根は逆説的に太陽に向かう
地下においても「すべてはすべての中にある」ことを可能にするのが、植物である。
植物は地表においてだけだなく、地下の世界においても自らを世界に対して開き、呼吸することで世界と混合の関係をつくる。
すべてはすべてと接し、物質や液体がゆるやかに循環する。だからこそ、あらゆるものは自身の身体の限界を超えて生きることができる。すべてが「呼吸」するが、そのやり方は中空の世界とは異なっている。そもそもそうした身体の呼吸は、肺を通じてなされる必要がない。諸器官を経る必要もない。なぜならその身体はまるごと呼吸によって定義され、身体のすべてが物質の循環に開かれたポートであるからだ。自己の内部でも外部でも同様である。有機体とは世界と混合する新しいありよう、また内部での混合を可能にするやり方の発明にほかならない。
「有機体とは世界と混合する新しいありよう」の発明だとコッチャはいう。なによりもその発明を可能にしたのが植物にほかならない。
そして、植物が地表面に葉や枝を伸ばすだけでなく、地下にも根を伸ばすからこそ、地球とはただの大地ではなくなり、大地と天空との区別はなくなる。大地もまたコスモスとなり、地球中心主義的な見方は、すべてが混合し呼吸しあうコスモス的な見方にとって変わるはずである。
地球中心主義は、いわば偽りの内在性という罠だ。つまり、自律した大地などというものはないのである。大地は太陽から切り離せない。土に向かい、その内部に突き進んでいくとは、逆説的にひたすら太陽に向かって上昇することを意味するのだ。
そう。根が太陽に向かっていると見做せるなら、それが伸びる先の地中もまた天空と見做すことができる。「天空とは上空にあるもののことではない。それはいたるところにある」とコッチャはいう。
植物を介することで地中もまた天空、コスモスとなり、地球中心主義的な見方を越えて「あらゆる場所に天空だけがあり、わたしたちの惑星とそこに息づくものも含めたいっさいは、この無限で普遍的な天空という質量の、凝縮された一部分にすぎない」と考えることができるようになる。
すべてが天空だ
この本に描かれる視点のほとんどが画期的な発想すぎて、びっくりの連続である。
地球は天体だが、地球においてはすべてが天空だ。人間世界も、非・人間的な宇宙における例外ではない。わたしたちの存在、身振り、文化、言語、外見など、わたしたちはどこを取ってみても〈天空的〉である。(中略)天空を流体と影響力の空間として理解することが重要なのだ。生物学、地質学、神学は天体学の一部門でしかなくなるが、そればかりではない。天体学は加えて、偶然性、不測の事態、不規則な出来事の学ともなるだろう。天空は同一的なものが回帰する場所ではない。
僕たち自身が天空なのだ。コスモスなのだ。
そして、それは「同一的なものが回帰する場所ではない」。
であれば、科学的な根拠、統計的なエビデンスもどれほどのものだろうか?
天体学が「偶然性、不測の事態、不規則な出来事の学ともなる」とき、僕らは何を信じてる行動するべきだろうか?
コッチャの示す「呼吸」「混合」「浸り」という概念はその問いについて考えるときの大きなヒントになると感じた。
強烈に新しい視点を与えてくれる、本文170ページほどの小品。こういう本こそ、読む人がたくさんいるとうれしい。
基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。
