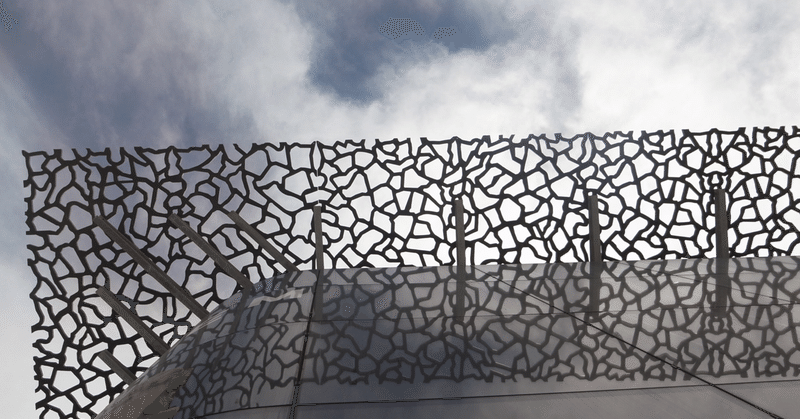
ヘルメスとアレッキーノと道化的汎用AIと
僕の道化熱はじつは終わっていない。
ウィリアム・ウィルフォードの『道化と笏杖』と読んだ後、何冊かはさんで、いまは山口昌男さんの『道化の民俗学』を読んでいる。
16世紀のイタリアを中心に流行した仮面即興劇コンメディア・デッラルテのなかの道化アルレッキーノを論じるところからはじまるこの本は、2章に入るとアルレッキーノの起源の考察をするのだが、そのなかでギリシア神話のトリックスター的な神ヘルメスとアルレッキーノの重なりを論じる過程でこんなふうにヘルメスという神格の特徴がリスト化されているのだけど、その内容がイノベーションという観点でみても面白い。
a)小にして大、幼にして成熟という相反するものの合一
b)盗み、詐術(トリック)による秩序の攪乱
c)至るところに姿を現わす迅速性
d)新しい組み合せによる(亀の甲と牛の腸のすじから琴を発明)未知のものの創出
e)旅行者、伝令、先達として異なる世界のつなぎをすること
f)交換という行為によって異質のものの間に伝達(コミュニケーション)を成立させる
g)常に動くこと、新しい局面を拓くこと、失敗を怖れぬこと、それを笑いに転化させることなどの行為、対談の結合
これ見て最初に思ったのは「こういう人で私はありたい」ということだ(まあ、リストの元になってるのは神の属性だけど)。こういう人物(神だけど)であれば、自分自身でイノベーションを起こせるか(神だから起こせて当たり前か?)は別にしても、イノベーションのための触媒には少なくともなれる。なるほど、僕が「道化」というものに惹かれるのはそういうわけか!とも思った。
新しいものが生まれるには……
相反するものの合一、秩序の攪乱、至るところに顔を出せる迅速性……。
どれも今までにない新しいものを創造するために必要な要素ではないだろうか。
従来2つ別のものとされていたものを合一させることができれば、これまでにない新しいものはできるだろう。見た目の小ささに反して容量は大きい入れ物、若いけど熟成された食べ物とか。
秩序の攪乱。盗みというとイメージが良くないが、通常別のところにあるものを拝借することで既存の秩序を壊して、そこから新たな可能性を引き出すことはできる。拝借することはそれを別のところに持っていってプラスにすることにもなれば、拝借された方に目を向ければ既存のものから何かがマイナスになるということでの撹乱にもなる。攪乱が起これば創造のきっかけになる。本当の創造は、混沌からはじまるはずだから。
そして、創造を起こすためには、相反するものを合一させることをはじめ、異なる領域同士をつなぎとめることが必要になる。それには至るところに顔を出せる迅速性は大事だと。
それは、世界のつなぎをするという要素とも重なってくる。伝令というヘルメスの役割は、生の世界と死の世界をつなぎ、秩序とカオスをつなぐ。領域横断、アンチ・ディシプリナリー。縦割り構造をヘルメスは易々と乗り越えていく。

笑いが創造の扉をひらく
ヘルメスを継いだアルレッキーノにもそうした相反するものをつなぎ、合一させ、そのことにより従来の秩序を攪乱する機能は受け継がれた。
アルレッキーノの笑いは、恐ろしい地獄さえも人間に役立つものへと変換させるのだという。
いうまでもなく、日常およびキリスト教的世界において、地獄は、あくまでも人間および神寵に敵対する世界であり、冷厳な、脅迫的な世界であったというのは変りなき事実であったろう。しかし、それ故に、そのような世界に自由に踏み入ったアルレッキーノのカーニヴァル的行為が、笑いを媒介として、静から動へ、地獄の諸力を転化し、人間に敵対するものを、人間のためのものへ変換させるということの意味は大きいのであり、それは民族的祭儀が「笑い」という行為において到るところで反復的に試みていることでもあったのである。
「笑い」という行為が、相反するものを合一させ、既存の秩序を攪乱する。異なる世界同士がつながれ、風穴が開き、「交換という行為によって異質のものの間に伝達(コミュニケーション)を成立させる」。亀の甲と牛の腸のすじから琴という楽器があたらしく創出されるのは、そういう動きが生み出されるからだ。イノベーションが本当の意味での創造だとするなら、基本的には同じ原理で生まれるのだのではないだろうか。
そこには道化的な笑いで、既存のシステム、既存の思考のありようを超えていくことが求められているはずだ。
笑いとイノベーションを導く創造との関係にピンとこないのだとしたら、それは頭に思い浮かべている「笑い」がここで言っているものとすこし違うのだと思う。この笑いは僕らの現代の笑いとはすこし異なるのかもしれない。
道化に対する笑いは、古代に発して、中世〜ルネサンス期まで続いた笑いだ。「フーリッシュな知性(前編)理解の外で」で、そのへんについて書いたが、その笑いはいまはもうほとんど、残ってはいないのではないか。
しかし、この古い笑いのもつ機能にこそ注目する必要があるはずだ。
笑いと豊穣儀礼という生成に関する儀礼との関係を、山口昌男さんは次のように論じている。
笑い、特に嘲笑が、何故豊穣儀礼に結びつくか。それは、笑いが、「静止」に対する「動く」状態に本質的に結びつくからではないか。笑いにおける動は、そのまま「移行」の観念につながる。儀礼が常に宇宙的な性格を持つこと、そして季節の変り目に集中することを考え併せるなら、笑いのコスモロジカルな意義もまた明らかである。即ちそれは「死すべきもの」を彼方に追いやり、「生成するもの」の出現を促進する。
笑いは、「死すべきもの」を彼方に追いやり、「生成するもの」の出現を促進する。
ここにおいて気づくことがある。ここまで述べてきた道化とその笑いの機能と、芸術との関係だ。
死との関係という意味では、芸術か深く死と関係していた時代のことを思い出す必要があるだろう。
たとえば「メディアには、死者崇拝という太古の範型が存在する」と『イメージ人類学』に書いたハンス・ベルティンクは、イメージ・メディアとしてのかつての芸術に、死とイメージの象徴交換機能があったことを告げる。
死者は失った身体を像と交換し、生者たちのあいだにとどまる。このような交換によって実現される死者の現前はただ像においてのみ可能であり、イメージ・メディアは死とイメージとの象徴的交換を遂行する生者たちの身体に対して存在していたばかりでなく、同時に死者たちの身体の代理も務めていたのである。
芸術もまた、道化の笑いと同様に、死と生の間に風穴を開ける。それゆえに芸術にはいまもスペキュラティブな創造の機能があるのだろう。

悲劇と喜劇が重なるとき
さて、笑いが「死すべきもの」を彼方に追いやって「生成するもの」の出現を促すことを考える際、ジョーゼフ・キャンベルが『千の顔をもつ英雄』(書評)において、英雄が倒すべき敵は「現状を守る怪物であり、過去の守護者」であるとしていたのを思い出す。
英雄と道化は裏腹なものだ。英雄は過去を倒すことで、やがて王になる。そのとき、英雄は王と王の影でもある道化に分裂する。ウィルフォードは『道化と笏杖』でこう書いている。
多くの豊穣の神(と女神)が、冬の不毛から春の新生という自然の変化に対応するような形で死に、また蘇るのと同様、中心の力の体現者たる王も同じ過程を演じてきた。そして不毛性は王の力に対する愚弄であるが故に、王は非常に早くから、自然の大災害の脅威を体現し、あまつさえ計算ずくで人々の愚弄の対象となる分身を持つようになったのである。短い期間のあいだ王の権威の幾ばくかを与えられた後、贖罪山羊として虐待され、殺されさえする身分低き者、すなわち偽王の制度こそが、1人の王が、重荷の下に滅び、超自然的に蘇るという、もっと古代の複合体内部の役割が分化したものである。
王は死に、そして、蘇る。そのことによって豊穣が約束されてきた。しかし、王が死を拒むとき、スケープゴート(贖罪山羊)としての道化が生まれる。それはかつての英雄だったものだ。
ここにおいて、悲劇と喜劇は重なってくる。悲しみと笑いが一体化する。
キャンベルもこう書いている。
おとぎ話や神話は、魂を表す神々の喜劇のハッピーエンドは、人類の普遍的な悲劇と矛盾するものとしてではなく、それを超越するものとして読むべきである。客観的な世界は過去の姿のままだが、主体の中で重要視するものが変わると、形を変えたように見えてくる。以前は生と死が争っていたのに、今では永続するものが顕在化する。鍋で煮立つ水が泡の運命に無関心だったり、宇宙が銀河の星々の出現や消滅に無関心だったりするのと同じように、時が起こすことに無関心になる。悲劇とは形のあるものを壊し、形あるものに対する私たちの固執を壊すことである。喜劇は荒々しく無頓着で無尽蔵の、自分ではどうにもならない人生の喜びである。したがって悲劇と喜劇は、両者を内包し両者によって区別される、ひとつの神話的主題と経験を表す言葉となる。
新たなるものの生成が、ここからしか生じないことを古代の人たちは知っていたのだと思う。
とはいえ、いまの時代に創造そのものの再創造、あるいは創造のあり方の非ヒューマン的なアップデートを考えるなら、古代の笑いを通じた生成にそのまま回帰しようという話にはならない。
むしろ、この笑いによる相反するものの合一をAIで実装するとどうなるか?という視点で考えたりする方が有効だろう。汎用的AIの知能のひとつとして、笑いがつなぐ異なるものの結合による創造というものが実装するとしたらどうしたら良いか?など。悲劇と喜劇を合わせたような新しい劇を汎用的AIが書き上げられるようになったら。
そんな非ヒューマニズム的なSF動画小説でも書いてみようかなどと夢想する。
そんな観点で、道化の笑いというテーマに引き続き着目したいと思っている。
基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。
