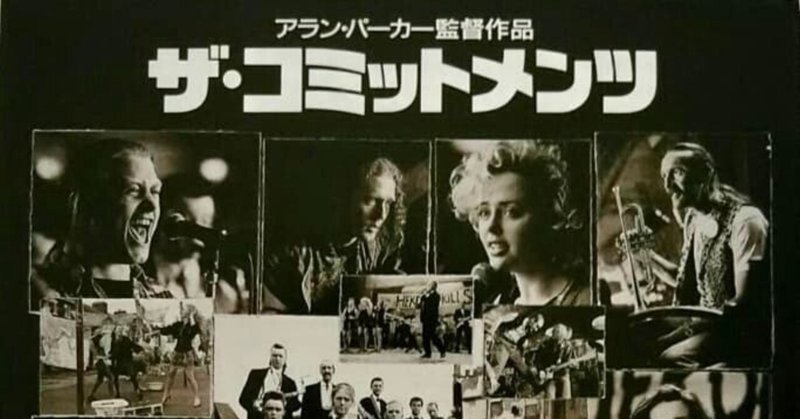2023年6月の記事一覧

「レオポルド美術館 エゴン・シーレ展 ウィーンが生んだ若き天才 」The Idiot/ Iggy PopHeroes/ David Bowie
東京美術館のエゴン・シーレ展。同時代のグスタフ・クリムトやオスカー・ココシュカの作品も展示され、第一次世界大戦の従軍後、スペイン風邪で夭折した彼の28年間を激動の時代背景と美術がより現代的色彩を帯びる流れと共に概観できます。 ちなみにシーレがウィーン美術アカデミーに入学した1906年の翌年と翌々年にはアドルフ・ヒトラーが同アカデミーを受験して不合格となっているそうで、その後ナチス・ドイツが近代美術や前衛芸術を、道徳的・人種的に堕落したもの=退廃芸術として禁止する流れと関連

HALLELUJAH: Leonard Cohen, A Journey, A Songハレルヤ:レナード・コーエン 人生の旅路と歌
2016年に亡くなったレナード・コーエンのドキュメンタリー。 ケベック州モントリオールの裕福な中流ユダヤ系家庭に生まれ。13歳でギターを弾き始め、地元のカフェでカントリー&ウエスタンの曲を演奏、大学在学中に初の詩集を出版。 歌手としては32歳という遅咲きの彼。 1960年代から禅に傾倒していた彼を知ったのは、1984年に発売された「哀しみのダンス」(Various Positions)でしたが、当初、アルバムは、アメリカでは売れないとレコード会社に発売を拒否されたと知りました
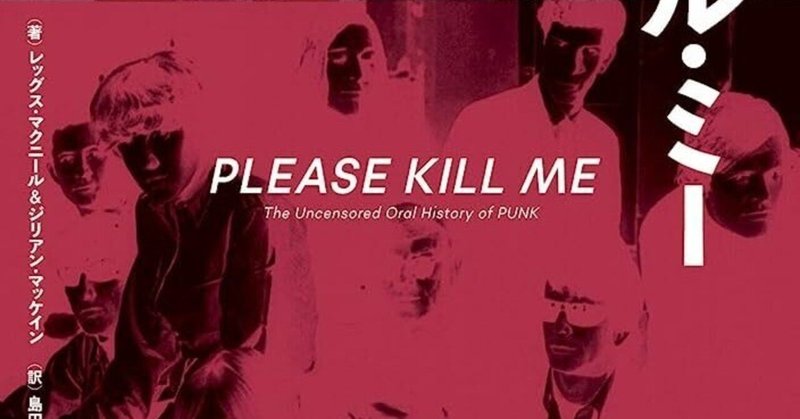
プリーズ・キル・ミー~アメリカン・パンク・ヒストリー無修正証言集Please Kill Me ~The Uncensored Oral History of Punk
~ この本で取り上げられた楽曲でSpotifyのリストも作ってみました。~ 日本版は、表紙にフィーチャーされたアンディ・ウォホール、ベルベット・アンダーグランドそしてニコの表紙のように、彼らから始まったアメリカ(ニューヨーク)でのパンクの話のような見え方ですが、これはニューヨークから始まり、一時期、ニューヨーク・ドールズのマネージャ―をしていたマルコム・マクラレンにより、イギリスで作られたパンクのお話。 本人やその身近な人たちの語りを組み合わせて、ものすごくリアルで面白く、そ

さよならアメリカ、さよならニッポン ~戦後、日本人はどのようにして独自のポピュラー音楽を成立させたか/マイケル・ボーダッシュ
ずっと読みたかったこの本。絶版でかなり高騰していますが、図書館で探してもらい読むことができました。 はっぴーえんどの楽曲をタイトルに冠した日本への留学経験のあるシカゴ大学近代日本文学准教授による著作で原題を邦訳すると「J Popの地政学的全史」 アメリカの占領が始まった1945年から90年代初頭のポストバブル期までの日本のポピュラー音楽史が、日本(アジア)のペンタトニック・スケール(五音階)を多用するメロディ、敗戦国特有の状況や心情からバブルを頂点とする経済発展と世界から