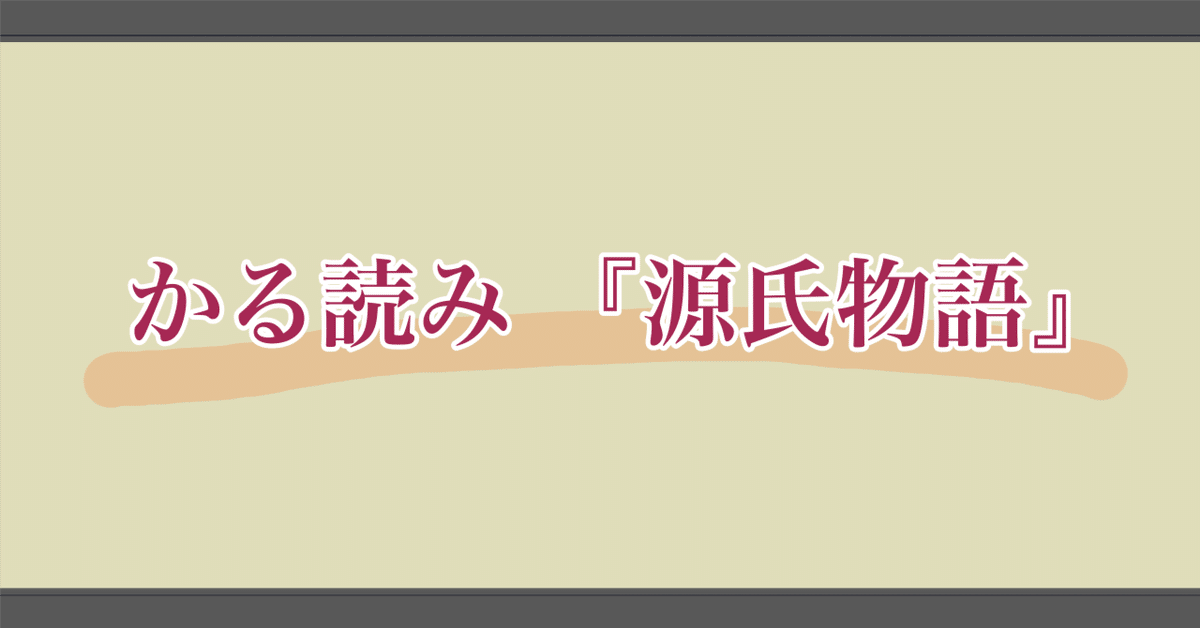
かる読み『源氏物語』 【夕霧】 悲劇は突き詰めると滑稽にもなるのかもしれない
どうも、流-ながる-です。
大河ドラマ「光る君へ」の制作発表を機に『源氏物語』をもう一度しっかり読んでみようとチャレンジしています。
今回は【夕霧】を読み、女二の宮(落葉の宮)の母・御息所の人生について思いを馳せようと思います。
読んだのは、岩波文庫 黄15-15『源氏物語』六 になります。【夕霧】だけを読んだ感想と思って頂ければと思います。専門家でもなく古文を読む力もないので、雰囲気読みですね。
女二の宮の結婚と御息所
朱雀院の更衣という立場
女二の宮(落葉の宮)の母である御息所は、もともと朱雀院の更衣であったと説明されています。さらっと朱雀院の妃たちについて思い出しますと、4名ひとまず確認できます。
朧月夜
今上帝の母
女三の宮の母
御息所
まず、朧月夜については物語においても別格扱いで、朱雀院の寵愛も深い妃として登場します。そうして、今上帝の母については、いわゆる国母で天皇の母という立場なので、これは政治的にも重んじられる存在です。女三の宮の母については故人ですが、身分が高く、娘の女三の宮は朱雀院から特に可愛がられています。
こうして並べてみますと、御息所は”更衣”という立場もあり、朱雀院の妃の中では軽く扱われていることがわかってきます。
御息所の考えのひとつとして、”皇女は未婚"というものが出てきていました。彼女のひとり娘の女二の宮は朱雀院の皇女であるので、御息所は娘については”未婚”であることを望んでいたことがはっきりしています。
単純に自身が更衣という低い身分であることのコンプレックスからなのか、というとそこはわかりません。娘の女二の宮は皇女であるが、母(自分)の身分が低いため軽く扱われるかもしれない、という危機感から、皇女としての矜持を求め、皇女の特徴とも言える”未婚”であることを欲したのかもしれません。
この御息所の考えについては、柏木との死後にも語られます。とにかく結婚そのものも反対であるし、相手がどうというより、皇女としての矜持のための”未婚”を守りたかったということだったと。
娘の皇女たる要素としての”未婚”に御息所はこだわっていた、と考えました。
柏木との結婚について屈辱までも感じていたかもしれない
これもまた振り返りになりますが、柏木はそもそも、女三の宮との結婚を望んでいました。女二の宮(落葉の宮)ではありません。はじめは無関係だったのです。
女三の宮の母はすでに亡くなっていて、朱雀院は自身の出家の前に女三の宮の結婚相手を探していました。ここでも女二の宮は無関係です。朱雀院はあくまで母のいない女三の宮を案じていて、母が健在である女二の宮については考えていません。御息所からしても、関係のない話ですね。
雲行きが怪しくなってきたのは、柏木が希望の通り女三の宮と結婚できず、女三の宮が源氏と結婚してしまってからです。
朱雀院
「朧月夜の親類でもある柏木には気の毒なことをしたなぁ」
柏木両親
「あんなに意気消沈してかわいそうだ。皇女との結婚をあんなに望んでいたのに」
こんなことを両者、考えたのでしょうか。
柏木と朱雀院の皇女である女二の宮との結婚を思いつきます。
この経緯については、御息所からしたら我慢ならない結果であったことは、【夕霧】まで読むに至ると、じわじわとわかってきます。
そもそも、なぜ柏木は女三の宮との結婚を許されなかったのか、朱雀院のお眼鏡に叶わなかったからです。彼の官位官職は低く、皇女と結婚するには不足と判断された。
その後、出世はしたものの、一度それが理由で女三の宮と結婚できなかった男との結婚を、女二の宮(落葉の宮)ならOKでは、皇女両者の扱いの違いが浮き彫りになってしまいます。御息所は思ったのではないか、"自分の身分が低いから、更衣腹の皇女だから、許された"と世間に思われた、これは屈辱だ、と。
朱雀院は、女三の宮の幼い点も包容力でカバーしてくれる大人の男性でなくては、という事情もあって源氏との結婚をと考えたのでは? という予測は、読者にしかわからないことでして、御息所からすれば、女三の宮と女二の宮(落葉の宮)の格差をまざまざと突きつけられた、ショッキングな出来事であったように思えてきます。
その後の結婚生活についても、朱雀院は女三の宮についてあれこれ考えるばかりで、柏木と結婚した女二の宮については、さほど気にしている様子はありませんでした。
悲劇はいきすぎると滑稽にも映る
【夕霧】の最大の悲劇といえば、御息所の死でしょうか。「源氏物語」ではさまざまな人々の死が描かれますが、この御息所の死については、悲しさと同時にそれに反する滑稽さを感じます。
死は回避できないですが、絶望と共に死を迎えることを回避できたかもしれないのに、人物のそれぞれの性質や動きに翻弄されるように事切れてしまいます。
女二の宮、あまりに不動
悲劇の大元になった事件というと、夕霧が女二の宮の居室に入り込んで、ひと晩滞在してしまった一件です。これについて、律師が誤解のうえで御息所に伝えてしまい、大問題に発展します。
夕霧と女二の宮の結婚の事実はないのですが、女二の宮は”そうと誤解されるようなことを招いてしまった自身の落ち度”を責めているので、何も言えません。侍女(女房)たちはカバーしようとしますが、女二の宮はそこから何かをするということはなく、事態は緩やかに悪化するだけでした。御息所の一番近くにいる人物が"何もしない"ので、読者としてはなんとももどかしい描写です。
とんでもない伏兵である夕霧の妻・雲居雁
雲居雁は見方によっては、何をしているんだ、と非難を浴びかねないことをしていますが、完全に巻き込まれている立場です。その点も元凶である夕霧は理解していて、文(手紙)を奪うという行動について強く責めるといったことはしていません。
御息所は例の一件を、結婚としてみなし、次の夜も通うはずだと思っていたところ、その思惑とは違い訪れない夕霧に、正式な結婚なら三日間連続で通うところ、訪れないとは何事か! という意図で文を書いたわけです。その重大な文を夕霧の妻の雲居雁が夕霧から奪ってしまう。夕霧は必死に取り返そうとしてしまうと、雲居雁がムキになってしまうと、頑張って懐柔しようとするも、失敗を繰り返し、隠された文をようやく見つけた時には、時すでに遅しという顛末です。夕霧の不器用さがここで発揮されるといったところ。
悲劇なのだけど、これがどこか滑稽にも感じるんですよね。夕霧も雲居雁も、もちろん御息所もマジなんです。マジなのに、展開が滑稽でならない。これが例えば、雲居雁が思ったように、夕霧の秘めた恋人からの文ならば、悲壮感はなかったかなという気さえします。
思い込みの中にいる御息所
病の中では冷静な判断ができないのは当然です。律師からズケズケとした物言いで女二の宮について伝えられ、ショックを受けてしまうのも哀れを誘います。人が弱っている時に、ストレス負荷をかけるようなことをする律師の行動にむしろ非難が集まってしかるべきだと思うわけですが、律師は言うだけ言って去ってしまいます。
御息所は、女二の宮を責めるような言い方はしませんが、悲嘆するといった印象です。案外これが堪えるのではないのか、という気もします。御息所は、女二の宮をとにかく皇女らしくと育ててきたという理想があったと考えると、その通りにならなかった落胆が滲んでいたのでしょうか。女二の宮の気持ちを考えると、つらくて何も言えないのもわからないでもないです。
病の身では最悪の想定や、後ろ向きな姿勢になってしまうのも仕方ありません。本来なら、御息所はこの事態をどうにかできる力もあったのかもしれないですが、命が尽きて、絶望の中で死を迎えてしまいます。
もう少しだけ、彼女に命があれば、という気持ちになってしまいました。あと少し時間があれば、誤解が解けていたのかもしれません。
そうしてこの顛末について、少し距離を置いてみると滑稽に見える悲劇だとも思えそうだと思いました。
ここまで読んでくださりありがとうございました。
参考文献
岩波文庫 黄15-15『源氏物語』(六)柏木ー幻
いただきましたサポートは、大切に資料費などに使わせていただきます。
