
我らmixi世代!
「mixi世代」なんて言葉があるのか分からないが、僕はたぶんその世代なのだと思う。
今のTwitterやInstagramと異なり、mixiはそう易々と入れないSNSだった。
すでに入会している登録ユーザーから招待を受けないと利用登録ができないのだ。
完全招待制という方式は、ユーザーそれぞれの素性が明らかになり、健全で安心感のあるコミュニティを維持するという目的だったそうだ。
たしかに今のSNSと違って一定の治安が守られた場所だった。
しかし当時SNSなんて呼び名はなかった。じゃあmixiとは何だったのだろうか。記憶を辿っていくほど意味が分からない。「閉鎖的インターネット」といった表現が近いのだろうか。
でも、あのコソコソしたところが好きだった。
僕にとっては防空壕だった。現実からの逃避として、社会からの隠れ家としての非常口だった。
そんな疎開先は日記を書くためだけのツールにしかならなかった。
どう考えても「暮らしに必要なもの」ではなくて「なかったとしても困らないもの」だった。mixiはあくまで「いらんけども」という領域を超えない何かだった。
しかもテキストの内容はほぼ山本直樹のマンガレビューだけだった。
あの頃、延々と山本直樹を読みふけっていた。しかしなかなか単行本が見つからなかった。見つけにくい本を見つけるために、あちこちの本屋を歩き回るのだ。
年上の恋人が「探し回らんでも、読みたい本がすぐ見つかるとええねんけどな」と言っていた。
その四年後、恋人の夢は叶った。
スティーブ・ジョブズの名プレゼンと共にiPadが発売され、電子書籍元年が訪れた。マニアックな漫画を探しまわる苦労は消えて、その替わりいくつもの書店が街から姿を消した。
そんな「山本直樹レビュー」の日記に誰かからのコメントがあると、「新着コメントが1件あります」と赤い文字がビカビカ光る。
僕たちmixi使用者はあのビカビカが表示される度にドーパミンの洪水に飲み込まれていた。
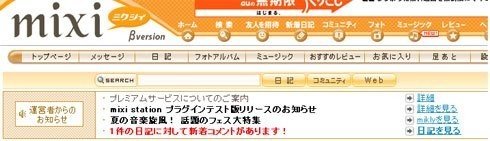
SNSというもの自体、真新しかったせいもあるだろうが、mixiにはよく分からない破壊力があった。
今のメインストリームのレスポンスはリツイートやファボ、いいねなどだ。mixiのビカビカはそれらの比ではなかった。あんなにドーパミンが出ることはない。
当時、「mixi中毒」という病理的な言葉まで誕生したが、その通りの依存性があった。
そしてmixiには「足あと」という訪れた人の痕跡が残るシステムがある。誰かが自分のページにアクセスしたら、その履歴を見られるのだ。
僕は恋人とお互いのページを「足あと」だらけにする不気味なコミュニケーションを繰り返していた。「いつも見てるよ」という言葉無き叫びだ。怖すぎる。
しかし恋人が僕の日記にコメントをすることはなかった。
僕も当然のようにしなかった。お互いのページを「足あと」だらけにするだけだ。気味の悪いコミュニケーションだし、振り返ると「いや、コメントしろよ」と思うのだが、当時はなんだか気恥ずかしくてできなかった。
でも赤いビカビカが光らなくても「見てもらっている」というだけで承認欲求が満たされた。
インターネットの中でコソコソしていた僕と当時の恋人は、オフラインでも笑えるぐらい隠れていた。
昼間に梅田やミナミのような盛り場を歩いたり、遠出もしなかった。誰かからの指示でもないのだが、自然とそうなった。
そんな腫れ物に触るような日々は細長く続いていた。でもそれも秋が始まる頃、夏の輝かしさが少し残るぐらいの季節までだった。
ある日、梅田でしこたま飲んだ後、十三大橋を歩いて帰ったことをよく覚えている。
夜霧がアスファルトまでおりていて、空がグラデーションで白くなっていた。夜が朝を迎えにいっているみたいだった。
真夜中の陸橋は川の音しか聞こえなかった。水音としてではなく、夜そのものから音を出しているような神秘的な響きだった。
「橋の上、歩いて帰るの好きなんすよね」
「あたしも」
その程度のくだらない対話しかなかった。そんな「なかったとしても困らないもの」ぐらいの会話をボソボソ交わしていた。
恋人が橋の真ん中で振り返り「梅田ちっさ……」とつぶやいた。
立ち止まって、来た道を振り返った。梅田は吸い込まれるように小さくなっていて、おもちゃの街みたいだった。
夜の淵がエンドロール後の映画館のように白くなりはじめ、睡眠薬とアルコールで頭がほぐれていた。あのまま死にたいぐらい気持ちよかった。
「あたしら、あした生きてるかなあ」
とか何とか言っていた。
「いきなり地震が来るかもしれんしなあ……」とも。
「もう地震は嫌ですね……阪神淡路のとき、家グチャグチャになりましたもん」
「エイズが大流行するかもしれへんし」
「それは地震より、なんか嫌ですね」
「震災やウイルスが地球を滅ぼす前に」
歌うように続けられた。
「屋久島とか、奄美とか、バリ島とか連れてってよ」
奇妙なものを見せ付けられたかのようだった。茫然とした。
恋人は両腕と背中を欄干に預けて、天空の星を眺めていた。
「行きたいなぁ、南の島」
「いや、何十万するんすか……何年かかるか……て言うか、俺じゃ一生かかっても無理ですよ」
「ええねん」
恋人は僕の言葉を遮って、改まった声で続けた。
「何年かかっても、無理かもしれんけど、『行きたい』ってだけで、それだけでええねん。問題なんて跳ね除けようとした時点で、半分は跳ね除けたようなもんやんか。分かった?行きたいねん」
あの日の僕には『行きたい』が『生きたい』に聞こえた。そんな気がした。
「でも、俺らが、そんな長くいられるわけないじゃないですか……」
「そら、そうやなぁ」
十九歳だった。水平線の青は、燃えつきた灰のように白くなっていた。夢の続きではないが、確かな現実とも思えない夜明けだった。
音楽を作って歌っています!文章も毎日書きます! サポートしてくれたら嬉しいです! がんばって生きます!
