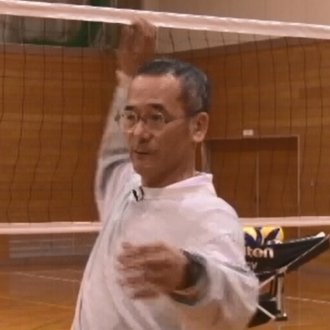#蹴球症候群
なぜサッカー選手は“挨拶”をするべきなのか? インタラクションとセンサーの欠如
サッカー選手や、サッカーに関わる人間は、挨拶をするべきだと思ってきた。挨拶をする、という行為は人によっては当たり前の行為であるが、ただ、中にはその感覚が抜けている選手などがいる。
ただこの“挨拶をする”という行為は、何も深くお辞儀をしろとか、目上の人にはペコペコしろとか、礼儀を守れとか、そういううるさいジジイみたいなことを言いたいわけではないことは、先に断っておかなければならない。
いわゆる、
ブラックボックスを省くな。
生きているだけで、人間は何かを入力し、出力し続けます。しかしある意味で自然に反して、意識的に入力し、その結果としての出力に期待をする場合があります。意識的に机に向かって勉強をするとき、などがその好例と言えるでしょう。もっと広く言えば、「学習」をするとき、あるいは何かしらの「向上」を求めるとき、私たちは「入力」と「出力」の関係を暴こうとします。
『このように「入力」したから「出力」がこうなった』と
プロットとしての勝利 vs 義務としての勝利
勝利とは何か。自分にとっての勝利と、他者にとっての勝利は何が違うのか。同じサッカーというスポーツに打ち込んでいる者の間でさえ、そこには何かしらの違いがあるような気がしていた。
どれくらい勝ちたいのか?とか、そういう「思いの強さ」みたいなものでは説明できないものがある気がしていて、今回はそれに書いていく。プロットとしての勝利と、義務としての勝利。
“理不尽”とは新興宗教である——。スポーツから暴力がなくならないメカニズム
減ってきていると信じたいですが、昭和と平成を経て、令和になってもなお、世代が変わろうがなんだろうが、スポーツ(体育)の世界から理解に苦しむ過度に制圧的な指導や、理不尽な訓練、または暴力がなくなりません。これは噂でも幻想でもなく、小さな子供たちのコーチが子供に対して制圧的になんちゃってサッカーコーチをしている現場は、いまだに見かけます。
これは、なぜなのか。
子供たち自身が、その指導に対して疑問