
ヒトラーは本当に戦争を計画していたのか? 『第二次世界大戦の起源』の文献紹介
1945年に第二次世界大戦が終結したとき、世界各国の研究者は戦争の原因を特定しようと大規模な調査に乗り出しました。当初、ドイツのアドルフ・ヒトラーが世界戦争に向けた計画を持っていたことを裏付ける史料があったので、ヒトラーに戦争の責任を帰する議論が優勢となっていました。
ところが、イギリスの歴史学者テイラーは『第二次世界大戦の起源(The Origins of the Second World War)』(1961)で第二次世界大戦の原因をヒトラーに帰す、まったく別の解釈を提示しました。
その解釈とはヒトラーが世界を相手にして主体的に戦争を仕掛ける計画を持っていたわけではなく、戦争が起こることを期待し、そのチャンスを利用しようとしていたにすぎないというものでした。
この記事ではこの著作の一部、特に第7章の内容を取り上げ、それに関連する批判を紹介してみたいと思います。今回は普通の文献紹介というよりも、論争紹介という性格が強い記事になることをあらかじめご了承ください。
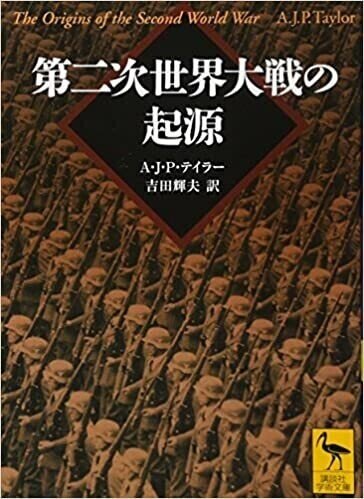
第1章 忘れられた問題
第2章 第一次大戦の遺産
第3章 大戦後の10年間
第4章 ヴェルサイユ体制の終焉
第5章 エチオピア戦争とロカルノ条約の終末
第6章 半ば武装せる平和、1936~1938年
第7章 独墺合併(アンシュルス)――オーストリアの最後
第8章 チェコスロヴァキア危機
第9章 6ヵ月の平和
第10章 神経戦
第11章 ダンツィヒのための戦争
ホスバッハ議事覚書の問題
第二次世界大戦は1939年9月1日にドイツがポーランドに侵攻したことに端を発しています。イギリスとフランスはその2日後の9月3日にドイツに宣戦を布告しており、それから1945年まで戦争状態が続きました。
第二次世界大戦の直接的な原因を明らかにするためには、ドイツ、イギリス、フランスの動きを探ることが必須であり、これに関連して他のヨーロッパの国々、例えばイタリア、ソ連、ポーランドなどの動きも視野に入れた複雑な外交史の研究が必要でした。しかし、特に注目されたのは、最初に軍事行動を起こしたドイツの対外政策でした。
ドイツの対外政策を解釈する上で避けて通れなかったのがヒトラーという要因です。ヒトラーは戦前から戦争計画を練り上げており、武力侵攻によってドイツの支配領域を拡大しようとしていたと考えられています。このことを示している史料が1937年11月10日に作成された「ホスバッハ議事覚書」でした。
この「ホスバッハ議事覚書」は陸軍参謀本部の中央課長を兼務していた首相付の上級副官フリードリヒ・ホスバッハが作成したもので、1937年11月5日、首相官邸で午後4時15分に始まり、8時30分まで続いた軍首脳会議(外務大臣も出席)の内容が記録されています。
それによれば、ヒトラーはドイツには「生存圏(レーベンスラウム)」の獲得が必要であるが、そのためには武力によらなければならず、具体的には「ドイツの問題は武力によってのみ解決できる」と述べていました(229頁)。この箇所は本書でも引用されています。
ヒトラーによれば、開戦の時期は1943年から1945年までの間とされています。しかし、これはシナリオの一つにすぎません。もしフランスで内乱が発生して能力を喪失した場合は、チェコスロバキアに軍事行動をとります。また、1938年にフランスとイタリアとの戦争が発生する可能性もあるため、これが起こればチェコスロバキアとオーストリアを攻撃することも計画していると述べられていました(229頁)。
ヒトラーは戦争を計画していなかった、という解釈
この会議でヒトラーが想定した事態は、いずれも非現実的なシナリオであるように見えるかもしれません。いずれも歴史的には起こらなかった事態だからです。そこで著者は、ヒトラー自身でさえも本気でそのような状況が起こるとは思っていなかったはずだと考えました。
著者の解釈は次のようなものです。ホスバッハ議事覚書に記録されたヒトラーの言葉は、戦争計画と呼べるには値しない内容でした。ヒトラーも本心では平和を維持しつつ、武力による威嚇で「生存圏」を拡大できるという見方を持っていたはずです。さらに、「ヒトラーは、1933年に奇跡が首相の座をもたらしたように、運命の転変が外交問題での成功をもたらすことに賭けたのである」という解釈を打ち出しています(230頁)。
この著作でヒトラーが自ら望んで戦争を行ったわけではなく、計画性がなかったという著者の主張はこのように展開されています。
著者の独自の解釈はそれだけにとどまりません。この会議の目的は戦争計画を話し合うことではなく、もっと別のところにあったという解釈も示しています。それによれば、当時、再軍備のさらなる拡大に財政運営の見地から反対していたヒャルマル・シャハト経済大臣兼中央銀行総裁を政治的に孤立させようと、ヒトラーは策を講じたのです。
「ヒトラーはシャハトを他の保守主義者から孤立させようとした。このためには軍備拡大計画で彼らを味方につけなくてはならない。彼の地政学的説明はほかならぬこのためであった。ホスバッハ覚書それ自身これを証明している。その最後の一節にいう――「この会議の後半では軍備の問題を取り扱った」疑いなくこれこそ会議の招集された理由であった」(231-2頁)
以上の解釈を読者に示すことで、著者は第二次世界大戦の原因をヒトラーの意図とは別のところに見出すことができることを主張していますが、それがどこにあるのかは必ずしも明白ではありません。
このような解釈は発表された当時、多くの読者の注目を集めました。しかし、少なくとも学界からは猛烈に批判を受けており、一部の研究者に至っては、この著作がいかに有害無益であるかを公然と批判しているほどです。一研究者の業績がこれほど多くの研究者に批判される事態はよくあることではありません。
ここから先は
¥ 100
調査研究をサポートして頂ける場合は、ご希望の研究領域をご指定ください。その分野の図書費として使わせて頂きます。
